観光
多文化共生
×
社会教育士
「縦割り」になっている各分野を「つなぐ」専門性
2007年、小平市役所に入庁。高齢者福祉課で働いたのち、2011年度に社会教育主事講習を受け、小平市中央公民館にて社会教育主事有資格者として5年間、まちづくりに誰もが関われる地域を目指して、市民と共に地域課題の解決に尽力した。 2015年に東京都オリンピック・パラリンピック準備局に出向。その後 小平市役所に戻り文化スポーツ課にて、オリンピック・パラリンピック、文化振興、多文化共生、観光まちづくり等の事業を担当。 2019年には公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会へ転職し、現在に至る。
Q. 萩元さんはどのような活動をされているのですか?
-
これまで、地域活動支援に取組んできましたが、現在は特に多文化共生と観光まちづくりを掛け合わせた活動が多いです。 両者の共通点は外国人の方と向き合うことです。 例えば、そこにいる外国人が訪日外国人なのか在住外国人なのかは分かりませんよね。訪日外国人に対しては観光分野から支援、在住外国人に対しては多文化共生分野から支援というような区別をするのはよくないことだと思います。
-
外国人にとって訪れやすい街を目指すなら、多文化共生の考えを持って観光おもてなしをする。そしてまた逆に、外国人にとって暮らしやすい街を目指すなら、観光おもてなしの考えを持って多文化共生のまちづくりをするということが効果的です。 私の講座では、在住外国人の方に協力いただきながら、地域の方々が在住外国人の方と交流する機会を設けています。そして、交流する際にはお互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築けるようにするといったことを意識しており、参加する地域の方々には外国人の方が暮らしやすい・訪れやすいまちづくりを考えていただいています。

Q. 具体的には、どのような講座をしているのですか?
-
例えば、ピンバッジづくりの講座というものをしています。オリンピック・パラリンピックには、ピンバッジ交換をする文化があります。講座の中で、受講者が話し合いながらその街の特徴を詰め込んだオリジナルバッジを作成し、オリンピック・パラリンピック開催時に日本に訪れた外国人の方と、自分たちで作ったピンバッジ交換をきっかけに、積極的に国際交流を行ってもらうことが目的です。
-
また、講座では、やさしい日本語と無料の多言語音声翻訳アプリの使い方を学びながら、地域の方が実際に留学生をはじめとする外国人の方と交流する機会を設けています。地域の方と外国人の方がお互いにコミュニケーションに難しさを抱えないよう配慮することで、講座終了後も地域の方が自ら国際交流をしたいと思えるようなきっかけづくりをしています。

Q. 観光において多文化共生と連携するメリットは何ですか?
-
観光を推進するとは、世界にその地域を注目してもらうということだと思います。その際重要となってくるのが、「地域の中の世界の目線」です。 日本人と外国人の捉え方は違うので、新たな魅力に気付ける可能性として観光分野における在住外国人との連携・協働は地域をより魅力的にすることに繋がります。
-
そのような観点から考えると、地域の中で内なる国際化を推進すること、つまり多文化共生のまちづくりを進めることが、観光の推進にもつながるのです。
観光業界からは萩元さんの活動はどのようにうつっていますか?
(ジャパンショッピングツーリズム協会 代表理事 新津 研一さん)

私はこれまで、観光を通じて様々な自治体のまちづくりをお手伝いしてきました。行政では、インフラ整備と産業振興につながることが観光において重要だとされていますが、これまで、私が地域の観光振興に携わってきて一番強く感じていることは、観光振興が進むと住民の方々が自分たちの街に誇りを持ったり、自信を取り戻したりする、そしてそれが、街の元気につながっているということです。 しかし、観光に興味が無かった人が観光に興味を持ったり、観光を通じて自分の街に興味を持ったりするようになるにはきっかけが必要です。色々なところで観光セミナーやインバウンドセミナーも実施されていますが、知識を学ぶだけだとなかなか自分の街の誇りにはつながりません。 一方で、萩元さんがやっていたのは、観光をきっかけに街の歴史や街の特徴に気が付くように仕掛けるなど、自分の街を再発見する「火を点ける」ということです。火さえ点いてしまえば、今まで観光ガイドをしていた方や、リタイアしたシニアの方をはじめとする住民の方々が、観光をきっかけに改めて自分の街を勉強し直す、見つめ直す、魅力を再発見するということが自発的に生まれていきます。 観光や多文化共生のプログラムを萩元さんとこれまで一緒にやってきましたが、最初は、萩元さんが一つ一つのプログラムをとても長い時間をかけて行うということに驚きました。しかし、振り返ってみると、従来の観光分野は時間をかけて地域に根差した取組をするというのが本来の姿であり、観光において短期的事業が現在増えているのは、近年のインバウンドブームの影響なのではないかと気が付きました。
Q. 多文化共生と観光を一体的に推進しようと思ったのはどのようなきっかけがあったのでしょうか?
-
もともと公民館で働いていた時に、1つの課題に対面した際は、その課題が「どのような分野なのか」と考えるのではなく、「どのような人が関係しているのか」という視点からものごとを考えていました。 公民館をはじめとした「社会教育」という分野は、「学びを通じたまちづくり」とも捉えることができます。社会教育では、1つの課題を「どのように解決するか」と考えるのではなく、「どのような関係者、資源をつなぎ解決するか」と考えます。そのため、1つの課題に対面した時に、一つのジャンルに限られるということがなく、常に関係者と協力する、関係者同士をつなげるということをしていました。
-
いろんな組織において「縦割り」はよくあることです。しかし、分野を超えて連携・協働し、より良いものを目指すというのは、現在、どの分野においても求められていることではないでしょうか。そういった中で、社会教育は縦割りになっている各分野をつなぎ、連携するための支援をする点に専門性があり、そしてそれが現在、社会教育に求められている役割だと考えています。

萩元さんが分野横断的に活躍できる理由について教えてください
(株式会社エンパブリック 代表取締役 広石 拓司さん)※萩元さんとまちづくり活動で連携・協働
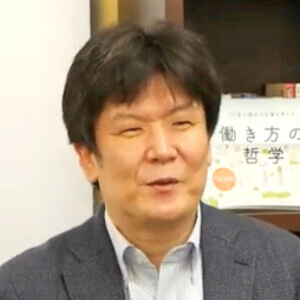
萩元さんは地域の持つ力や地域の方々がしたいことを形にしてきていました。観光も多文化共生も、様々な人の力をどう生かすかということがテーマです。例えば、観光は単にすごいものをPRするよりも、人と人のコミュニケーションの機会をどう広げるかということが、真に観光振興をしていく上でのポイントだと思います。 地域の人が集まって共に学びを作るプロセスを大事にしているということが、萩元さんが観光や多文化共生で活躍できている理由だと思います。
Q. 萩元さんの考え方の軸にある「社会教育」とは何かについて教えてください。
-
社会教育には「学習支援者」という言葉があります。学びの主役である市民を横や下から支える概念です。社会教育の分野では、主体となる市民が自ら学び合い、時には必要な人を招いて学び、活動の仕方や学習の仕方を身に着けることに主眼を置いています。そうでないと、一生その講座を続けなくてはならないですよね。学び合って、地域を良くして、課題を解決する。そういうコミュニティーを生み出すことを主眼として社会教育活動は展開されています。 そして、学んだことを人に伝え、その人がさらに誰かに伝える。学びの波及で活動が新たに生まれ、そこでも学びが必要となり、それを活かして活動する。そういう地域の中の「学びの循環」が、社会教育の中では生み出されます。
-
そのように、その場だけのつながり作りだけではない、その後、新たな価値を生み出し続けるつながりが多方面で構築されるのというのが、社会教育の成果だと考えています。 私は、社会教育を通して、学び合いを大切にし、多様性を理解し認め合い、高め合えるサスティナブルな地域社会をたくさん作りたいと考えています。
市民から見た萩元さんはどのような人ですか?
(小平市民 モハメド・シャミムさん)

私は日本に来てからずっと、友達を作りたいと考えていました。そして、祭りはみんなと仲良くなれる日本の文化だということを知り、友達を作るためにお祭りを開きたいと考えました。 しかし、どのようにお祭りをすれば良いのか分からなかったので、市役所に相談に行った時に萩元さんに出会いました。萩元さんは色々と教えてくれて、地域の中で様々なイベントを企画している出口さんを紹介してくれました。その後、萩元さんと出口さんのお陰で、その年のうちに、2回も公園でお祭りをすることができました。お祭りではいっぱい人が来てくれて、友達もたくさんできました。

(小平市民 出口 宙伯さん)

事を起こす時につながりや思いを持つ人と出会うのが大切だと考えています。イベントを開く際に、萩元さんにモハメドさんと繋げてもらえたのがとても嬉しかったです。

やさしい日本語を一緒に推進していた吉開さんから見た萩元さんはどのような人ですか?(やさしい日本語ツーリズム研究会 吉開 章さん)

長らくビジネスの世界にいる私は、やさしい日本語を萩元さんと推進していく中で初めて社会教育という領域があることを知りました。萩元さんはレガシーという言葉をよく使っていましたが、どんな小さな研修でも、例えどんな大きな事業でも、社会教育に関わる方はそれが終わった後に何を地域に残せるかを意識しているのだと思いました。 萩元さんは一流の社会プロデューサーだと思っています。社会で何かを残していきたいという信念を持った方が、予算はなくてもその人柄と人脈とで活動をしながら、少しずつ実績を積み上げていく。たとえ小さな実績でも地域のためになると確信を持って行動されてきた、ここが萩元さんの素晴らしいところだなと思っています。また、萩元さんはどんな小さな活動でも、「社会をこうしたい」という大きな社会ビジョンを常に持っているのですが、やさしい日本語を推進する際に、萩元さんのような行政や私のような民間企業、そして研究者など、多様な関係者が連携する上では、萩元さんが大きなビジョンを掲げてくれたことが連携するカギになりました。
Q. これからの社会教育士に向けて一言お願いします!
-
いろんな分野で注目されるワークショップやファシリテーション、コーディネート能力は元々、社会教育の専門性であり、得意とする分野でした。そのような専門性を持った社会教育士は、今後、色々な分野での活躍が期待されます。
-
「社会」という単語と「教育」という単語が掛け合わせっているところがみそだと思っています。簡単な言葉で言うと「学びを通じて社会をつくっていく」こと。これが社会教育の醍醐味であり、そのことを専門的に担える社会教育士は本当に素晴らしい仕事だと思います!

あらゆるシーンで活躍する社会敎育士の活動事例を紹介しています
-
福祉
×
社会教育士

[ 島根県 ]
浜田のまちの縁側 代表栗栖 真理さん
「健康づくりはまちづくり」地域福祉を支える社会教育
-
防災
×
社会教育士

[ 北海道 ]
恵庭市 総務部基地・防災課長藤野 真一郎さん
「共助」を本当の意味で理解するには「学び合い」が必要
-
教育行政
×
社会教育士

[ 東京都 ]
杉並区教育委員会事務局 学校支援課
社会教育主事中曽根 聡さん
住民自治を支える「学び」の伴走者
-
学校
×
社会教育士

[ 岡山県 ]
浅口市立寄島小学校 校長安田 隆人さん
これからの子どもたちの学びには、社会教育の視点が必要
-
公民館
×
社会教育士

[ 大阪府 ]
貝塚市立中央公民館 職員中川 知子さん
学ぶ権利を支え、人が変わる瞬間に立ち会える仕事

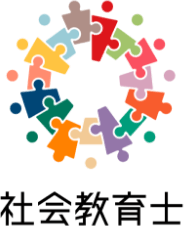
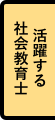
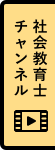
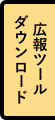


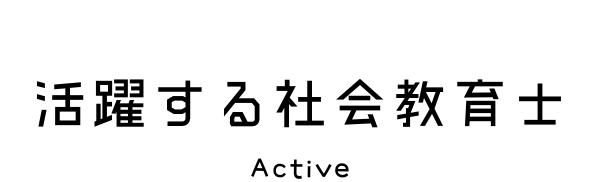
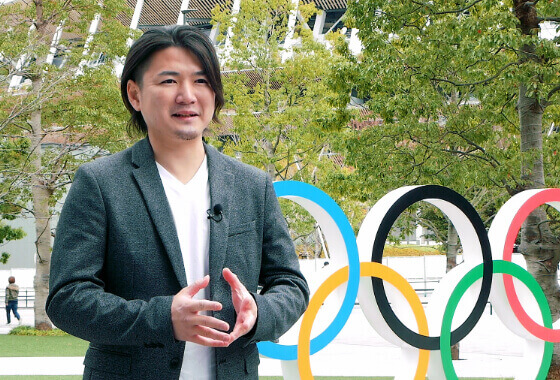
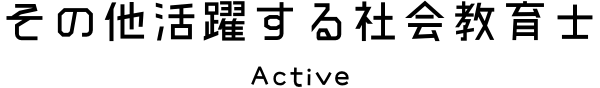



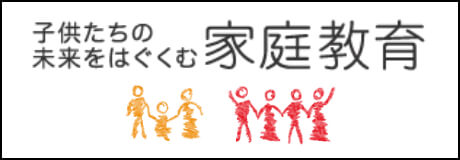

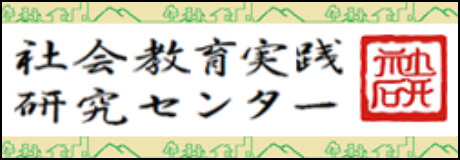
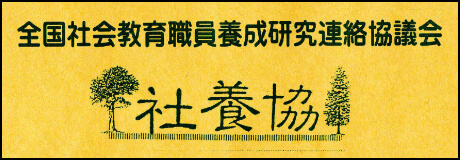

なぜ、萩元さんの講座を受講しようと思ったのですか?(多文化共生講座受講者)
「やさしい日本語」に惹かれました。ピンバッジづくりも興味がありましたが、実は、お嫁さんがカンボジアから来てくれていて、難しい文法が理解できないため、普段から家ではやさしい日本語を使うことを意識していました。そこで、改めてやさしい日本語について学んでみたいと思い受講しました。
やさしい日本語とは?(やさしい日本語ツーリズム研究会 吉開 章さん)
外国人の方のように、日本語を母語としない方々のために、日本語を母語としている者が、言葉や文法を調整する話し方です。外国の方だけでなく、聴覚障害や知的障害を持つ方とのコミュニケーションの中でも注目されています。国内にいる外国人に対して、一番通じる言葉は「やさしい日本語」です。ぜひ、観光や多文化共生に取組む行政や、NPO、民間企業の方には、積極的に「やさしい日本語」を使ってほしいと思います。
多文化共生に取組むNPO法人フィリピノナガイサの半場さんから見た、多文化共生と観光を一体的に推進するメリットは何ですか?
(NPO法人フィリビノナガイサ 理事・事務局長 半場 和美さん)
多文化共生や日本語教育の枠に入れると(在住外国人は)支援を受ける側に押し込まれてしまいます。そして、支援というとどうしても少し暗いイメージがついてしまいがちです。 しかし、観光と一体的に推進することで、多文化共生の取組が持つ、本来の意義に光が当たり、在住外国人も観光においては主体的に活躍でき、支援される側ではなくなります。 また、萩元さんみたいなコーディネート業をすごく専門的に、ストイックにやっている方にお会いしたのは初めてでした!