学生ベンチャー企業が大学と連携して九州広域で実施するブロックロボットプログラミング教室
- 学習活動の分類:
- 対象学年:
小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年
- 教材タイプ:
ビジュアル言語, ロボット
- 使用ツール:
- 実施主体:
株式会社ロジコモン
- 実施都道府県:
長崎県, 大分県
- 事業区分:
総務省事業
- 情報提供者:
管理者
- 実施場所:
学校
- コスト・環境:
端末はグループ使用、事業者持ち込み
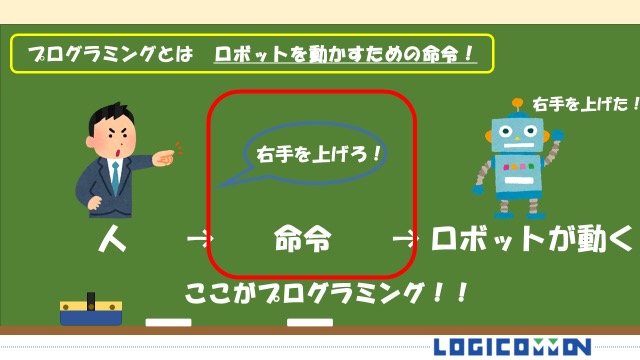
概要
●モデルの意義・目指そうとしていることや、特徴(特異性、利点)
今回の実証事業において大きな目的として、「九州でのプログラミング教育の普及」・「大学生をメインメンターとして起用」・「子供たちへのコーティング的支援を目的とした教職員や保護者等のサブメンターとしての起用」がある。
また、今回の実証事業においての特色としては、「1.大学生ベンチャー企業と大学の連携による実施」・「2.九州工業大学と連携しメインメンターの大学生には単位を付与」・「3.教職員や保護者などを子供たちの精神面のサポートを中心に行ってもらう」の3点がある。
この3つの利点に関して述べると、1つ目については、大学生ベンチャー企業である“ロジコモン”が実証事業を行い、成果を示すことで他の学生・大学間でも同様の活動を促していく目的があり、今後の国内でのプログラミング教育の普及に繋がっていくものであると考える。
2つ目については、メインメンターとして大学生を起用しさらに大学から単位を付与する(九州工業大学では前年度の実証でも同様の単位付与を実施済み)ことで、今後のプログラミング教育の教え手として、単位という学生のモチベーションを保てるとともに大学付近の小学校に出向くことで大学と小学校などとのつながりが強くなり、大学の地域貢献や大学の知名度向上なども目指せる。また、大学生が小学生に“教える”という活動を通して今まで教えられてきた学習について教える側に立つことで新たな目線で学ぶことを見直してもらう目的もある。
3つ目については、教職員や保護者をあえて「子どもたちの精神面のサポート」を主体としたサブメンターに起用し、技術的面ではない箇所のサポートに徹底することでプログラミング教育の教え手としてのハードルを下げるとともに、プログラミングが普及していない地域において少しずつプログラミング教育の普及を進めていける利点がある。また、保護者に子供との接し方(コーティングの活用)を指導することで、この活動を通じて家庭内での子供への教育方法の改善も目指した。
●なぜそのモデルを設計・採用するに至ったか
このモデルを採用したきっかけとしては、昨年度の同事業で、九州工業大学の一学生で参加し、その時に九州のでプログラミングの認知度が都心に比べ非常に低いということを知り、どうにかしてもっと九州で広めていきたいと思い株式会社ロジコモンを設立した。そこでプログラミング教室を何度か実施している際に、子供たちの楽しくプログラミングに触れ学ぶ姿を見て、プログラミング教育が既存の教育より考える力や自分の考えを仲間に伝える力を育成するうえで大きな可能性を感じたことと、見学に来ている保護者側がプログラミングに対して理解が進んでなく難しそうというイメージが独り歩きしていることを感じ、この経験から子供たちへのプログラミング教育と保護者などへの認知度の向上の両立を目指した本モデルを考案した。また、教育する人として大学の教授や教員が行うより、年齢的にも小学生と近い大学生が行った方が、話を聞く姿勢や質問をする回数等、生徒自身の積極性が高い傾向があるように見受けられたため前年同様大学生をメインメンターとして起用することで、さらなる小学生の自主的に学ぶ環境を提供できるようなモデルを採用した。
また今回の実証モデルでは、教育課程内での活用を意識し、図形問題や身近な信号機などを題材にした実証モデルとした。



