まちの魅力 PR大作戦
- 学習活動の分類:
- 対象学年:
小学校第3学年, 小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年
- 対象教科等:
総合的な学習の時間
- 教材タイプ:
ビジュアル言語
- 使用ツール:
- 実施主体:
文部科学省
- 実施都道府県:
東京都
- 事業区分:
文部科学省事業
- 情報提供者:
管理者
- コスト・環境:
学校所有のパソコン1人1台利用(モニタ利⽤時にはタッチパネル搭載のパソコンが必要)
- 実施事例の詳細:
まちの魅力 PR大作戦(PDF)
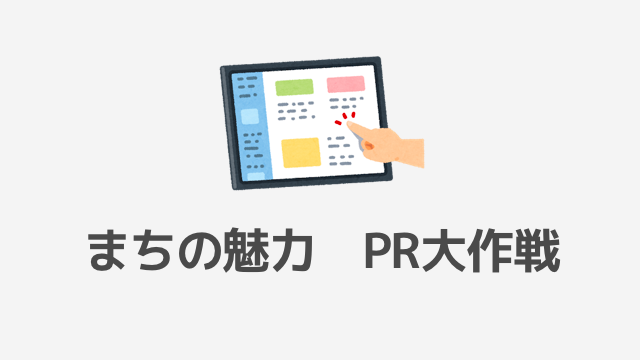
1) 単元や題材などの目標
近年,多くの観光客が訪れる状況をもとに,安心してまちの魅力に触れてもらうことができるための案内の方法を考えることで,まちの一員としての自覚をもって自分とまちとの関わりを深めていくことができるようにすることを目指している。
2) 単元や題材などの学習内容
本題材は、学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。
1次においては、子ども達が生活する「まち」に焦点をあて課題を設定し、「まち」の魅力を考え、自分たちがお勧めするスポットを整理し、プログラミングを活用した情報発信の方法を用いて、案内表示を作成する。
2次においては、駅に案内表示を設置するとともに、案内表示の利用状況について情報を収集する。収集した利用状況の情報に基づき、案内表示の効果について検証するとともに案内表示の改良を行う。
3次においては、1、2次において学習したプログラミングによる「まち」の魅力の発信方法を踏まえ、プログラミングに関わらず、観光案内において工夫している取組について、商業施設や駅等の担当者にインタビューを行い、子ども達自身が、まちの一員として魅力ある「まち」づくりに寄与できることをまとめ、発表する。
3) プログラミング体験の関連
総合的な学習の時間において、プログラミング体験を取り入れた学習活動を展開していく上では、探究的が学習の過程に適切に位置付けるとともに、探究的な学習において論理的思考力を育成し、コンピュータの動きをよりよい人生や社会づくりにいかそうとする態度を涵養することが重要である。
使用する学習ツールに関しても、プログラミングを学ぶために作られたものだけではなく、「課題の設定」や「情報の整理・分析」等、探究的な学習に活用可能なものであり、できるだけ操作の習得に時間がかからないものが望ましい。本時の学習では、「自分たちがお勧めするスポットをタッチパネル式の案内表示で魅力的に発信することができないか」という課題を設定し、「情報の収集」において、身近な生活にコンピュータやプログラミングが活用されていることに気付くとともに、「まち」の魅力を発信することに寄与していることに気付かせる。
その上で、「整理・分析」において、プログラミングによる情報発信の方法を体験しながら、子ども達自身が意図する情報発信の方法を写真や動画、説明文等の順序及び動作を組み立てて、プログラミングによる案内表示を作成する。このScratchを活用したプログラミングを体験する学習においては、具体的には、例えば、写真や動画、説明文等を自分が意図した順番やタイミング等で一連の動きとして表現するためには、一つ一つの個別の動きをつなげたものであることが分かることや、一つ一つの個別の動きには、それらに対応する命令が必要であることが分かる。また、例えば、外国人や高齢者、子どもなど、案内表示による情報発信の方法を対象によって変えるためには、条件を設定することで命令を分岐させる必要があることを理解させることができる。さらには、作成した案内表示を「まとめ・表現」において発表し、他の子ども達から良かった点や改善点を教えてもらうことで、改善すべき点を踏まえた案内表示を作成するには、コンピュータに意図した処理をどのように改善すれば、意図した一連の動きに近づくかを試行錯誤する学習にもつながる。
このように、「整理・分析」においてプログラミングを体験する学習を取り入れることにより、探究的な学習を深めるとともに、自分が意図する情報発信の方法を論理的に思考する学習となることが期待できる。
参考添付資料
実施事例の詳細(PDF)
関連教材情報
Scratch
| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |
|---|---|
| 動作環境: | ブラウザ Windows |



