地域主体による自走的・持続的な プログラミング教育人材の育成推進
- 学習活動の分類:
- 対象学年:
小学校第3学年, 小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年
- 教材タイプ:
ビジュアル言語
- 使用ツール:
- 実施主体:
株式会社サックル
- 実施都道府県:
宮城県, 山形県
- 事業区分:
総務省事業
- 情報提供者:
管理者
- 実施場所:
学校
- コスト・環境:
デスクトップPC1人1台(コンピュータ教室 ※実証校によっては事業者持ち込みあり)
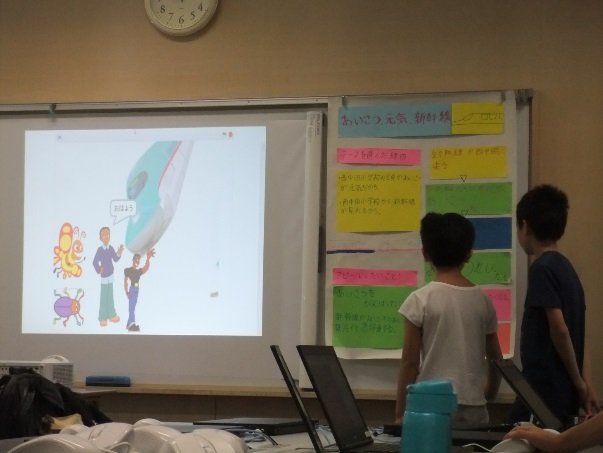
概要
モデルの意義・目指そうとしていることや、特徴(特異性、利点)
地域在住の高校生からシニアまで幅広い世代をメンターとして育成できる、地域主体の自走可能なプログラミング教育人材の育成環境構築を目指す。また、定量的・定性的な評価やインストラクショナルデザインを活用したSachool考案のカリキュラムにより、より効率的・効果的なメンター育成およびプログラミング教育方法を追求する。
なぜそのモデルを設計・採用するに至ったか/成り立ち
弊社は、仙台で子供向けのプログラミングスクールSachoolを開講している。以前より、小学校にてプログラミングのワークショップを行うことがあり、保護者と地域住民の方々を中心とした放課後教室の運営スタッフと連携を取りながら進めてきた。そのスタッフの方々は、他に仕事を持ちながらも、放課後の児童向けに企画を考え、実行に当たっていた。地域主体で小学生のために様々な取り組みを精力的に行う姿勢に刺激をうけ、そういったコミュニティをプログラミング教育の普及にも活かしていきたいということで今回地域主体の実証モデルを考えるに至った。
過去の実証は、学生を中心としたメンターで構成されていたが、今回はそれ以外の世代をメンターにすることも目的とした。これまでワークショップを行う際に連携してきた放課後教室の運営スタッフやNPO法人の仙台シニアネットクラブの協力を得て、今回は、地域在住の高校生からシニアまで幅広い世代をメンターとした実証を行った。なお、メンターに求めた条件は下記の3つである。
1. パソコン操作に興味がある
2. 子どもたちに教えることが好き
3. プログラミング/プログラミング教育に興味がある
独自の活動で得た強み/特長
弊社は、プログラミングスクールを運営しており、小学生を対象としたプログラミング教育に関する独自のノウハウを有している。実証においては、これらのノウハウやインストラクショナルデザインを活かしたカリキュラム構成となった。また、T-KNIT(後述参照)に協力してもらい、まちあるきプログラミングの要素も取り入れた。
さらに、事務局側からのアンケートの他にもこちらで用意したアンケートを実施し、データを集計/数値化することで「定量的・定性的な評価」も行うことを目的とした。
プログラミング教育に関する現状に対する課題意識等の観点
以前よりプログラミング教育に関する課題は、下記3点と認識していた。
1) 誰が教えるのか<リソース>
2) 何を教えるのか<カリキュラム・スキル>
3) いつ教えるのか<時間的制約>
そのため3点の課題の解決へつながる取り組みにすべく、下記の点に留意した。
1) その地域に住む幅広い世代でメンターとする
2) 教えるのに平易な内容である(アンプラグド~パソコン)
3) 幅広い世代をメンターとすることで教え手側の時間的制約を乗り越える
またそれに伴い、主に教育課程外で行われる講座として設計した。
参考添付資料
参考資料
関連教材情報
Scratch
| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |
|---|---|
| 動作環境: | ブラウザ Windows |



