- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 「学校教育におけるJSLカリキュラムの開発について」(最終報告)小学校編 > 6.「教科志向型」JSLカリキュラム「理科」
CLARINETへようこそ
6.「教科志向型」JSLカリキュラム「理科」
6.1 日本語を母語としない子どもたちにとっての理科
日本語を母語としない子どもたちにとって理科の学習には、次のような特徴があると考えられる。
(1)学習活動への参加の容易さ
理科の場合、観察、実験など具体的な現象を直接体験することから出発する学習活動が中心となり、また、グループ単位で学習活動が進められることも多い。このように直接体験、具体物による支え、他の子どもたちからのサポートが得やすいため、日本語を母語としない子どもたちにとっても理科の学習活動に参加することは比較的容易である。
(2)概念的な理解の困難
だが、こうした学習活動への参加によって得られた体験を、科学的なイメージや概念としてとらえ直し、事象の性質や規則性などの自然の特性を理解し、科学的な見方や考え方を構築することは難しい。例えば、豆電球が光っているという現象を体験として受け止めることは容易だが、それを「電気」という概念でとらえ直すことには困難が伴う。その結果、理科の学習活動への参加が自然の事物・現象についての理解に結びつかず、単なる「面白い体験」で終わってしまう危険性がある。
(3)日本語による概念的な理解の困難
体験を科学的な概念でとらえ直すことは、日本語を母語としない子どもたちに限らず理科を学習する子どもたちすべてに共通した課題である。この点で日本語を母語としない子どもたちとその他の子どもたちの間に本質的な違いは存在しない。しかし、日本語を母語としない子どもたちは、この作業を外国語である日本語で行わなければならない。このため、その他の子どもたちに比べて、より一層の困難が生じると考えられる。
6.2 「教科志向型」JSLカリキュラム「理科」のねらい
6.2.1 理科における「学ぶ力」
このように、日本語を母語としない子どもたちには、観察や実験などを行い、科学的なイメージや概念としてとらえ直し、自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な見方や考え方を構築していくための力(=「学ぶ力」)が必要であり、「教科志向型」JSLカリキュラム「理科」(以下、「JSL理科」とする)のねらいは、理科の学習活動に参加し、日本語で「学ぶ力」を獲得できるよう支援することである。
理科における「学ぶ力」は大きく二種類に区別できる。一つは、授業の流れに乗って他の子どもたちと協力しながら実験、観察など行い、それを通して様々な体験を生み出すことにかかわる「学ぶ力」である。もう一つは、そのようにして得られた体験を科学的な概念等としてとらえ直す活動にかかわる「学ぶ力」である。
上で述べたとおり、学習活動の流れに乗ることにかかわる「学ぶ力」の獲得については、理科の授業が直接体験をベースにしていること、グループワークなどによってその他の子どもたちからの支援も得やすいことなどから、日本語を母語としない子どもたちでもそれほど大きな困難はないと考えられる。これに対して、体験の科学的なとらえ直しにかかわる「学ぶ力」は、とりわけ日本語を母語としない子どもたちにとっては、その獲得、利用が非常に難しい。そこで、JSL理科では「学ぶ力」について以下の目標を設定する。
- (1)実験、観察、グループワークなど理科の授業がもつ直接体験のリソースを最大限に生かして、日本語を母語としない子どもたちが授業の流れに乗るための「学ぶ力」を活用し深める機会を提供する。
- (2)日本語を母語としない子どもたちが体験のとらえ直しにかかわる「学ぶ力」を獲得し、活用するための手厚い支援を提供する。
6.2.2 学習活動への参加を通した「学ぶ力」の獲得
「学ぶ力」の獲得に向けた支援は、学習活動の流れの中で得られる直接体験と一体となって提供される必要がある。「学ぶ力」をこのような体験と切り離して獲得させようとすることは、食材に触れることなく料理の技術を学ぶようなもので、極めて困難かつ非合理的である。繰り返し述べているように日本語を母語としない子どもたちであっても理科の授業における実験、観察活動への参加は比較的容易である。つまり、通常の理科の授業の中で子どもたちは、「学ぶ力」を獲得するための足場を得ることができるのである。そこで、JSL理科では日本語を母語としない子どもたちが通常の理科の授業に参加しつつ、その中で授業の流れに乗るための「学ぶ力」を深め、体験のとらえ直しにかかわる「学ぶ力」を獲得できるような支援を提供することを目指す。
6.2.3 共生志向のカリキュラム
このようにJSL理科では、教室での学習活動に参加するための「事前準備」として「学ぶ力」を獲得させておくという方法ではなく、学習活動に参加することを通して「学ぶ力」を獲得させることを目指す。しかし、もちろん日本語を母語としない子どもたちを通常の授業に参加させれば必要な「学ぶ力」が自然に獲得されるわけではない。子どもたちが授業の流れに乗り、また、日本語を用いて対象の科学的なとらえ直しをしていくためには学習活動面でも日本語面でも様々な支援が必要である。そこで、JSL理科では通常の授業にこのような支援を埋め込み、日本語を母語としない子どもたちが、その他の子どもたちと一緒に参加できる授業づくりを目指すことになる。通常の授業にJSL的な支援を重ね合わせて子どもたちに提供するのである。上で述べたように、体験を科学的な概念でとらえ直すことは日本語を母語としている子どもたちにとっても難しい課題である。JSL理科が通常の授業に重ね合わせる支援は、日本語を母語としている子どもたちにとっても有効な学習支援となり得る。この点でJSL理科は、日本語を母語としない子どもたちのためだけのカリキュラムではなく、日本語を母語としない子どもたちとその他の子どもたちが授業の中で共生していくことを志向したカリキュラムであるということができる。
6.2.4 多様な指導形態への対応
しかし、このことはJSL理科において取り出し、その他のタイプの指導を否定するものではない。取り出しの学級でも、理科の授業を行う十分な時間的余裕があり、また実験、観察、検討などを(可能であれば複数の)グループで進めることのできる条件があれば以下で示すような授業を行うことは可能である。また、例えば、実験や観察の実施については、他の子どもたちからの支えも得やすい在籍学級が担当し、日本語での体験のとらえ直しについては取り出し学級できめ細かな指導を行うといった分担も可能であると考えられる。しかし、このような場合、体験から概念的なとらえ直しまでの一連の活動の流れを分断せず、連続的なものにするための十分な配慮が必要となる。これを怠ると、結局、「食材なしで料理を学ぶ」タイプの「事前学習」と同じ問題を抱えることになる。
6.3 JSL理科の授業の構造
日本語を母語としない子どもたちを実際の学習活動に参加させ、その中で「学ぶ力」を獲得させる方法は「トピック型」JSLカリキュラムのアプローチと共通している。このため、JSL理科における授業の基本的な考え方、構成要素については、「トピック型」JSLカリキュラムにならい、(1)理科における学習活動の局面、(2)学習活動への参加を可能にする支援の構造、(3)授業づくりのツールの3点に整理して述べることにする。
6.3.1 学習活動の局面
6.3.1.1 「学習活動の局面」の位置づけ
JSL理科では、「トピック型」JSLカリキュラムと同様に、学習活動をいくつかの局面に区分し、それをこのカリキュラムにおける授業の基本構造とすることにした。子どもたちに提供される支援はこの基本構造に応じて整理されることになる。
「トピック型」JSLカリキュラムが採用した学習活動の局面「体験→探求→発信」は、子どもたちがトピックを追求する場合の典型的な学習活動の一つの可能性として提案されたものであった。これに対して、JSL理科では通常の理科の授業が持つ基本構造を整理し、それを学習活動の局面とした。 これは、JSL理科が、日本語を母語としない子どもたちが通常の授業における学習活動の展開の中で「学ぶ力」を獲得することを目指していることによる。JSL理科が提供する授業の基本構造は、日本語を母語としない子どもたちのために用意された特別のものではなく、日本の小学校で通常行われている授業の構造と同じである。したがって、理科の授業を担当した経験を持つ教師・指導者であれば、自分が通常行ってきた授業の展開を、以下に示すJSL理科における学習活動の各局面に対応させ、調整、組み替えを行うことで日本語を母語としない子どもたちが参加可能な授業の基本的な展開を比較的容易に作りだすことができる。
6.3.1.2 「学習活動の局面」の構造
JSL理科では、学習活動の局面の展開パターンを、「課題をつかむ」→「予想」→「観察・実験・調査」→「考察」→「発表」と整理する。通常、教室で行われている理科の授業の多くが基本的にはこの展開パターンにしたがっていると考えられる。
このパターンは、学習テーマや対象の違いによって大きく3つのバリエーションに分けられる。
| A.観察型 | 直接体験とその言語化を比較的長い期間にわたって繰り返すことにより、認識を深めるタイプの学習。(例:植物や動物の観察等) |
|---|---|
| B.実験型 | 構造化された実験場面のもとで行われる直接体験とその言語化により、認識が深められるタイプの学習。(例:電気、流水の働き、てこの働き、水溶液等) |
| C.調査型 | 直接体験が困難な対象について、調査等に基づき言語的(理論的)な体験を先行させるタイプの学習。(例:天体、人の誕生、土地のつくり等) |
基本的な展開パターンと3つのバリエーションをまとめた図を以下に示す。
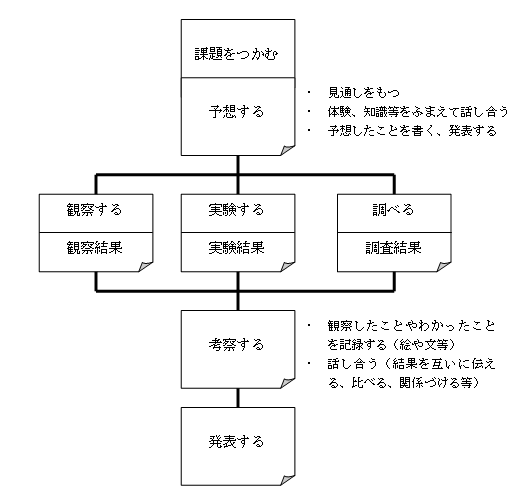
3つのバリエーションの内Aタイプでは、例えば比較的長期間にわたって植物や動物の観察を繰り返すといった方法で、「予想」→「観察・結果」→「考察」→「発表」という展開パターンの授業を何度も反復する。5学年の「発芽と養分」を例にしてみよう。ここではインゲンマメとトウモロコシの種をまいて、発芽の様子などを詳しく調べるが、授業は以下の5つの段階で進んでいく。
- 発芽には何が必要か(水曜日)
- 発芽のようす(発芽には適度な温度が必要)
- 種子のようす(子葉にはでんぷんがあり、発芽に使われる)
- 発芽と養分(でんぷんの確認、ヨウ素液)
- まとめ
これら、5つの段階の授業それぞれが「予想→観察・結果→考察→発表」という展開パターンによって組み立てられ完結することになる。これに対してBの場合、実験というよく準備されコントロールされた一度の観察が授業のベースになる。しかし、この場合も「予想→実験・結果→考察→発表」という学習活動の展開パターンがあり、基本的にはAタイプと同じ構造を持つ。Cタイプも同様である。
6.3.1.3 理科の3区分と「学習活動の局面」の関係
A、B、Cの各バリエーションは、おおまかには「生物とその環境」「物質とエネルギー」「地球と宇宙」という理科の3区分に対応している。しかし、例えば「生物とその環境」の区分での授業がすべてAタイプになるとは限らない。場合によっては、Bタイプ、Cタイプの授業も行われると考えられる。これらのバリエーションはあくまでも理科における典型的な学習活動の3つの展開パターンであり、学習内容、対象とは一応、独立のものと理解されたい。
6.3.2 支援の構造
6.3.2.1 学習活動における配慮
子どもたちが授業にスムーズに参加するためには、いま展開している活動が授業の一連の流れの中でどのような位置にあるのかを理解している必要がある。日本語を母語とする子どもたちの場合、日本語による年齢相応のコミュニケーション能力を有しているため、理科の授業における教師・指導者の指示や他の子どもたちとのやりとりの中で、このような展開を比較的容易に把握できる。例えば、今、観察している対象について自由にいろいろと印象や感想を述べる局面が、観察の結果を分析的に整理する局面に切り替わったことを自然に察知し、適切に対応するといったことが比較的容易なのである。これに対して、日本語を母語としない子どもたちは、このような局面の切り替わりについていけず、うまく授業の流れに乗ることができない場合も多い。そこで、日本語を母語としない子どもたちが参加している授業においては、この局面の切り替わりを明示し、それを子どもたちに意識させる必要がある。また、典型的な学習活動の展開パターンに繰り返しふれさせることで、子どもたちが自分で授業の展開に乗ることができるようにしていく必要もある。学習活動の局面の展開パターンに一定の共通した構造を持たせておき、そのパターンにしたがって個々の授業を組み立てておくことは、教師・指導者が支援を考える際の基本的な枠組みになると同時に、日本語を母語としない子どもたちが理科の学習活動にスムーズに参加していくための支援としても機能するのである。
以上のように、JSL理科では「予想→観察・実験・調査→考察→発表」という学習活動の展開パターンを持つ授業に日本語を母語としない子どもたちを参加させ、その中で「学ぶ力」を獲得させることを目指す。このために必要な支援として、「理解支援」「表現支援」「評価支援」という3種類の支援を用意する。
6.3.2.2 理解支援
子どもたちが学習活動の展開を理解し、局面に応じて意識を適切に方向づけ、学習に必要な体験を得ることができるようにするための支援である。つまり、授業の流れに乗ることにかかわる「学ぶ力」に対する支援である。これは、「トピック型」JSLカリキュラムにおける「学習支援」に対応するものであり、そこで提示された一連の支援も活用可能である。
6.3.2.3 表現支援
子どもたちが授業の展開の中で日本語を用いて体験を整理し、思考を展開し、それを他者に伝えていくための支援である。つまり、体験のとらえ直しにかかわる「学ぶ力」に対する支援である。これは、「トピック型」JSLカリキュラムにおける「日本語支援」に対応するものであり、そこで用いられていたAUをベースにした支援も有効である。
6.3.2.4 評価支援
授業の流れに乗れているか、体験の科学的なとらえ直しがうまくできているかを子どもたち自身に確認させるための支援。理科学習の展開パターンに応じた「フローチャート式ワークシート」によって行われる。学習活動の各局面に対応したワークシートへの書き込みが中心的な活動となるため、書き言葉のための表現支援の側面も持つ。また、ワークシートは教師・指導者にとっても子どもたちの思考や理解の状況を知ることのできる重要な手がかりとなる。さらに、グループワークにおいて他の子どもたちとのコミュニケーションを媒介するツールともなり得る。
6.3.3 授業づくりのツール
このような支援を組み込んだ授業を作るためのツールとして以下のものを用意した。これらのツールを用いた実際の授業づくりの方法については6.4で解説する。
6.3.3.1 理解支援のツール
教師・指導者による理解支援の具体的な方法を一覧表にした。教師・指導者は、指導案作成時に子どもたちの実態と授業の展開を考慮しながら、これらの支援を指導案に埋め込んでいくことになる。表中にあるA1、A2といった記号は、実際に指導案を作成する際に用いるものである。
| 種別 | 支援項目名 | 具体的方法 | |
|---|---|---|---|
| A 授業展開場面で | A1 | 典型的展開 | 毎回、理科特有の展開パターンに沿って授業を進めるようにすることで、授業の流れに乗れるようにする。→3つの型 |
| A2 | 情報収集 | 先行知識・経験などを有しているかどうか。観察・実験・調査などを進めるための日本語が分かっているかどうか。海外での授業の進め方(双方向対話型授業・一方的受信型授業/課題解決型授業・暗記型授業など)と大きく異ならないかなどをチェックする。 | |
| A3 | 簡潔な導入 | 本題に関係のない話は避け、なるべく単刀直入に導入する。 | |
| A4 | 展開の明示 | どのような授業展開をしていくのか、今、どの段階の学習をしているのかを、整理・明示しながら授業を進める。→ワークシート | |
| A5 | 要点の明示 | 子どもたちの力に応じた目標を定め、その要点は必ず明示する。(強調する・板書する・教科書にアンダーラインを引かせるなど) | |
| B 説明・発問場面で | B1 | 細分化 | 日本語力に応じ、複文や重文を単文に分けて話す。 先行知識や経験などに応じ、授業の流れを妨げない程度に内容を細かいステップに分けて話す。 |
| B2 | 具体化 | 実物・模型・写真・絵・ビデオ・図・グラフなど、言葉での理解を助けるための教材・教具を使ったり実演したりする。 | |
| B3 | 付加補足 | 付け加えて説明することで難しい表現の理解補助にする。 | |
| B4 | 言い換え | 難しい言葉は知っている言葉に言い換える。ただし、1、2度言い換えたあとは難しい言葉だけを使うようにする。 | |
| B5 | 例示 | 例を挙げて説明する。 | |
| B6 | 比喩 | 身近な事象にたとえたり、擬人化したりして話す。 | |
| B7 | 対比的説明 | 事象や特徴などを表に書かせ、対比させながら説明する。 | |
| B8 | 明瞭な説明 | 大切な箇所はゆっくり、はっきりと話す。初出語彙と思われる言葉は板書し、文字でも確認させておく。 | |
| C 思考させる場面で | C1 | 役割分担 | グループ活動では、その子にできそうな役割を教師・指導者が与えるか、班員に伝えて役割分担をさせる。 |
| C2 | 方法習得 | 観察・実験・調査の結果の記録法(何をどう記録したらよいか)を明瞭に示し、活動の途中でも声をかけて確認する。ワークシートや友達のものを参考にしながら記録させる。 | |
| C3 | 思考補助 | 「だから」「でも」「こうしたらこうなった」「このことからどんなことが言えるか」「 |
|
| C4 | 整理補助 | □や→を使い、考えたこと分かったことをワークシートに図解的にまとめさせる。 | |
6.3.3.2 表現支援のツール
表現支援のツールとして教師・指導者が留意すべき一般的な支援事項の一覧と、理科AUを用いた日本語表現支援を用意した。
A.一般的な表現支援項目
| 種別 | 支援項目名 | 具体的方法 | |
|---|---|---|---|
| D 語彙 | D1 | 一般語彙提示 | 記録や発表に使う一般的な言葉を表などで提示しておく。表を事前に渡し、母語訳をつけさせておく方法もある。子どもたちはその表から言葉を選んで記録していく。 |
| D2 | 重要語彙提示 | その単元で重要な語彙については、板書し説明するほか、耳に定着させるために、意識的に何度も口にする。 | |
| D3 | 学習時間確保 | 漢字表記の重要語彙については、時間内に指導する場を設ける。 他の子どもたちには「きれいに書く練習だ」と言って3回清書させたり、「この漢字がつく言葉を10個探しなさい(地面→地しん・地ばん・面積・表面…)」と言って作業を与えたりして、個別指導の時間を確保する。 |
|
| D4 | 許容とフォロー | 絵や動作による発表、代名詞(これ・こうする)による発表を許す。ただし、絵や動作、代名詞が表す日本語を後できちんと教えてやる。 | |
| E 理科的表現 | E1 | 例文提示 | 見本となる文を書き写す。先に他の子どもたちに答えさせておき、そのモデルを十分に聞かせてから、書かせたり、言わせたりする。複数の選択肢から自分の意見を選ばせる。空欄補充式で文を完成させるなど、見本となる文が手に入れられる環境を作る。 |
| E2 | 一文習熟 | 重要な文は、範読→斉読→数人を指名して読ませる→また斉読するといった時間を設け、何度も子どもたちの耳に入れ、重要な文を暗記させる。教科学習途中での「文型指導」は混乱するので避ける。 | |
| E3 | 見聞先行 | 表現するには、十分な蓄積が必要。見たり、聞いたりした文を読み、そして書くという経過をたどって、理科的な表現が身に付くようにする。 | |
| E4 | 場の提供 | 日本語力に応じた発表をする場を設けてやる。 | |
※ 表現支援項目D(語彙)についての補足説明
教科学習における語彙は、次の3つに大別できる。
- 一般的語彙 … 日常生活でよく使われる語彙
(変わる・空気・いつも・少し) - 教科的語彙 … 日常生活でも教科学習でも使われる語彙
(変化・酸素・たえず・少量) - 専門的語彙 … その教科学習以外にはあまり使われない語彙
(窒素・石灰水・気体検知器)
( )内は小6「ものの燃え方」における語例
日本で暮らしてきた子どもたちは、1.2.は既知と考えられ、授業では3を中心に新しい言葉を教えていけばよい。一方、日本語を母語としない子どもたちの場合は、1.2.のような語彙でも知らない言葉があるという気持ちで授業を進めなければいけない。しかし、一斉指導が行なわれている授業では、いちいち1.2.のような言葉を説明する時間はない。そこで、その対策として次のような方法をとるとよい。
| 1.2.の語について | 話しながら顔色を見る。様子によって図や絵などを板書する。 |
|---|---|
| 2.3.の語について | 「どう変化するかな。どう変わるかな。」のように言い換えてみる。 |
| 下表のように事前に語彙リストを渡して母語訳がつけられるようにしておく(母語でも知らない言葉という場合や母語訳を助ける人がいない場合もあるので注意)。 | |
| 重要語句ではないものは「これ」「それ」などの言葉で代用しておく。 |
<語彙リスト例>
今日のじゅぎょうでつかうたいせつなことば
| 1.知っているね | 2.知らないかもしれないね | 3.新しくおぼえることば |
|---|---|---|
以下略 |
以下略 |
以下略 |
B. AUを活用した表現支援
「トピック型」JSLカリキュラムで用いたAUカードは体験から出発し、探求を重ね、その成果を発信するという展開の中で用いられる日本語表現を整理したものであり、理科の学習活動における日本語表現支援のツールとしても有用である。
JSL理科では、これに加えて、理科の学習活動に固有の日本語表現に対応した理科AUも用意した。これは、「トピック型」AUと同様に、授業における子どもたちの学習活動を構成する一連の単位的な活動と、それに対応する日本語表現をセットにしたものであり、理科における「学ぶ力」の具体的な内容一覧でもある。その基本的な考え方、カリキュラムにおける位置づけ、実際の活用法は「トピック型」AUとまったく同じであるので、「トピック型」JSLカリキュラムの解説も参考にされたい。
理科AUは、学習活動の各局面に対応して次のような構造になっている(カッコ内の記号はAU番号)。「トピック型」JSLにおけるAUは、教師・指導者と子どもたちのコミュニケーションのみによって構成されていたが、理科においてはグループワークにおける子どもたち同士のコミュニケーションも重要である。そこで、理科AUではグループワークに関するAUも用意した(理科AU一覧は資料1として添付)。
- 理科AU‐1 課題をつかむ(R‐1~R‐57)
区分共通
問題提起の問い/生物とその環境
問題提起の問い/物質とエネルギー
問題提起の問い/地球と宇宙 - 理科AU‐2 予想する(R‐58~R‐72)
- 理科AU‐3 観察する・実験する・調べる(R‐73~R‐109)
- 理科AU‐4 考察する(R‐110~R‐129)
- 理科AU‐5 発表する(R‐130~R‐166)
- 理科AU‐6 グループワーク(R‐167~R‐205)
6.3.3.3 評価支援のツール
評価支援のツールとして以下のような機能を持ったワークシートを作成する。資料2として指導案作成例にある小3「地面の温かさをくらべよう」用のワークシートに作成上の留意事項を書き込んだものを示しておくので参考にされたい。
| 種別 | 支援項目名 | 具体的方法 | |
|---|---|---|---|
| F 評価 | F1 | 状況把握 | 今、課題把握→予想→観察・実験・調査→考察→発表のどの段階にいて、何をしているかが理解できているかをフローチャート式のワークシートに書き込ませる。 |
| F2 | 学習参加 | 自分の手でしたことは何か。どんな係を担当したか。いくつ仕事をこなしたかを記録させる。友達と協力して進められたかなどは子どもたちどうしで相互評価させてもよい。 | |
| F3 | 内容理解 | その単元の結論が理解できたか書き込ませる。 | |
| F4 | 日本語理解 | 重要な語句や表現を使って観察・実験・調査の結果、及び考察の結果をまとめさせる。 | |
6.4 授業の作り方
JSL理科における授業づくりは、子どもたちの実態を把握することからスタートし、基本的な学習活動の流れを構想し、それにAUなど具体的な支援を埋め込んでいくという点で基本的には「トピック型」JSLカリキュラムと同様である。ただし、「トピック型」JSLカリキュラムでは、興味関心など子どもたちの実態に応じてトピックを選択したのに対して、JSL理科では学習内容の選択は教科の構造によって決定される。したがって、JSL理科における授業づくりとは、理科の学習活動に日本語を母語としない子どもたちを参加させていくための支援プランづくりであるということになる。
JSL理科における典型的な授業づくりの流れを以下に示す。資料3に示した様式の指導案に必要事項を書き込んでいくことと、ワークシートを作成することが具体的な作業となる。JSL理科は多様な状況での授業づくりを想定しているが、ここでは在籍学級の授業に日本語を母語としない子どもたちが参加している場合を想定して説明をする。
- 子どもたちの実態を把握する
教科の理解、日本語力、興味・関心など、対象となる子どもたちの実態を把握すると同時に、その他の子どもたちの様子(サポートをしてくれるか等)についても把握しておく - 授業の基本計画を立案
課題把握→予想→観察・実験・調査→考察→発表という学習活動の局面を基本的な枠組みにして計画を立て、指導案の「学習活動と言語活動」欄に記入する - AUの選定
各段階の学習活動に特に必要な「トピック型」AU、理科AUを子どもたちの実態を踏まえながら選定し、指導案の「学習活動と言語活動」欄に記入する - 理解・表現困難箇所の抽出
日本語としての難しさだけでなく、概念として理解の難しいと思われる箇所をピックアップする - 理解支援の方法を考える
A1~C4のツールを参考にして必要な支援を選び、指導案の「支援」欄に記入する - 表現支援の方法を考える
D1~E4のツールを参考にして必要な支援を選び、指導案の「支援」欄に書き込む - ワークシートを作る
F1~F4のツールなどを参考にしながら、指導案の「ワークシート」欄にワークシートの基本構成を記入し、フローチャート式ワークシートを作成する - 授業を行う
理解支援・表現支援・ワークシートへの書き込み支援をしながら子どもたちを授業に参加させていく - 評価支援と評価を行う
書き込んだ内容・表現の間違いを正す
授業時の活動状況とワークシートへの書き込みを資料としてF1~F4の各項目を評価する
6.5 指導事例
JSL理科における支援を埋め込んだ典型的な指導案をサンプルとして提示する。具体的な内容は、以下のとおりである。
<指導案一覧を挿入>
指導案はそれぞれ小単元レベルで作成されている。各指導案は、資料3として添付する。
「トピック型」の場合と同様にこれらの指導案はあくまでもJSL理科における授業づくりの参考、ヒントであり、ここに掲載した授業のみでカリキュラムが完結しているわけではないことに注意されたい。
6.6 JSL理科資料
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
-- 登録:平成21年以前 --