- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 学校図書館 > 子どもの読書サポーターズ会議 > 子どもの読書サポーターズ会議 (第3回) 会議の概要 > 資料4 齋藤委員の発表資料
学校図書館
資料4 齋藤委員の発表資料
公共図書館と学校図書館-協働のパートナーとして-
平成19年10月23日
鳥取県自治研修所長
(元鳥取県立図書館長)
齋藤明彦
1.鳥取県立図書館の近年の取り組み
1.目標
- 公共図書館は持ちうる力を最大限に発揮し地域にどう貢献していくか
- 「役に立つ、役に立つと認められる図書館」
- 「教育機関の枠を超える情報提供機関」
- ~そのための理論「CUBE」…提供するメディア・内容、協働する相手
2.施策の柱(新規の内の主なもの)
- ア 暮らしや仕事に役に立つ情報提供
- ビジネス支援~ 講座・展示・相談会・出前図書館
書籍・雑誌・DB・パンフレット - 健康情報~ 闘病記文庫
- そのための双方にメリットがある協働の発掘:30+30=150
- 同じく情報提供の多様化
- ビジネス支援~ 講座・展示・相談会・出前図書館
- イ 高等学校等図書館の支援(平成14年司書配置開始・始動、平成15年本格稼働)
- 物流 ~毎日発送(2日以内到着)、月2回回収~購入希望図書の購入
- ~学期毎のセット貸出(テーマ別、25冊*20セット)
- ~大量貸出(展示用など)
- 学校支援担当司書等の訪問相談 年数回
- 研修(学校に出かけての生徒・一般教員向け研修を含む)
- 図書館プロデュースの展示・イベント・講座の提供&協力
- 物流 ~毎日発送(2日以内到着)、月2回回収~購入希望図書の購入
- ウ 図書館のアピール・・イメージ転換と周知
- エ その他
2.公共図書館と学校図書館の連携の現状と望まれる姿
目標を共有する大切な協働パートナーであること
- 公共図書館職員の認識・・お客さんの一人?
- 学校図書館の現状追認・・そこしか知らないorあきらめ・遠慮
- 図書館の対学校図書館「物流」について
- 現状は「毎日送受」から「なし」まで
- 望まれる物流システム
- 校内のニーズに対応できる、新たな利用を提案できる
- ◎ 毎日送受、横の物流あり、コスト(費用・時間・手間)が最少
- ○ 今あるもの、置かれた条件などでコストパフォーマンスの良い物流を
- 人の「連携」について
- 司書等の学校訪問・学校での講座
- 研修会・交流会
- レファレンス
- 望まれる連携体制に向けた人的整備のあり方
- 学校~司書・司書教諭・校内組織・生徒の活動(委員会・部活動)
- 公共図書館~学校に知見を持つ担当者(片手間でなく)
- 公共図書館プロデュース(または協力)の展示・イベント・講座
- 公共図書館が幅広のネットワークを作ることが前提
- 三者にとってすべてプラスになる仕組み
- 読み聞かせ活動、ブックスタート運動等地域ぐるみで行うべき取り組みにかかる連携
- 読書や学校図書館活動、図書館教育がどう子どもたちに影響を与えるか
- 教育委員会(文部科学省も?)縦に割らないこと
- 情報の共有と協働
3.地域ボランティアの「活用」について~ここは簡単に
- 館の(学校の)中でどう位置づけるか、どう「活用」するか
- 協働か、自己実現か
- 組み込むのか、場の提供か
- 地域一般か、保護者か
- 司書教諭、学校図書館司書(担当職員)とボランティアの「役割」分担
- 状況・目的による
新たな可能性を求めて~「CUBE」という考え方
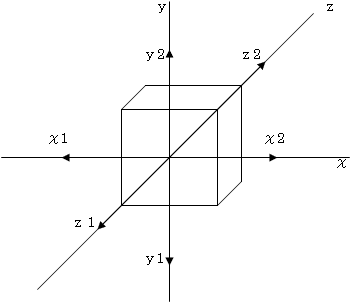
- 中心に、現在の施設、活字資料、職員を置き、「情報提供メディア」「提供する情報の内容」「協同できる個人団体」の3方向を同時に延ばすことにより、情報提供能力を飛躍的に拡大する。
- それにより、図書館のイメージを「趣味的」から「役に立ち必須のもの」に変える。
- バランスよく拡大することで、予算・人手のコストを抑えられる。
X軸=情報を提供するメディア
- X1=アナログ方向~講座、セミナー、相談会、ちらし、パンフ、展示会
- X2=デジタル方向~インターネット、データベース、既存資料のデジタル化
Y軸=提供する内容
- Y1=より柔らかいもの~ヤングアダルト
- Y2=専門的なもの~工学、自然科学、経営、法律、医療
Z軸=協働する相手
- Z1=個人~図書館ボランティア(整理、催し、IT)、個人講座
- Z2=団体、機関~行政各部局、商工団体、国・県の外郭団体、その他公的団体
質問は齋藤明彦saitoua@pref.tottori.jpへどうぞ
お問合せ先
総合教育政策局地域学習推進課
-- 登録:平成21年以前 --