- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成29年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成29年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(京都市)
平成29年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(京都市)
平成29年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
本市では,「日本語指導トータルサポートシステム」の体制により「特別の教育課程による日本語指導」をはじめとする指導や支援を実施している。担当課は人権教育担当であり,日本語指導に精通した指導主事を配置している。具体的な人員配置は下記の通りである。
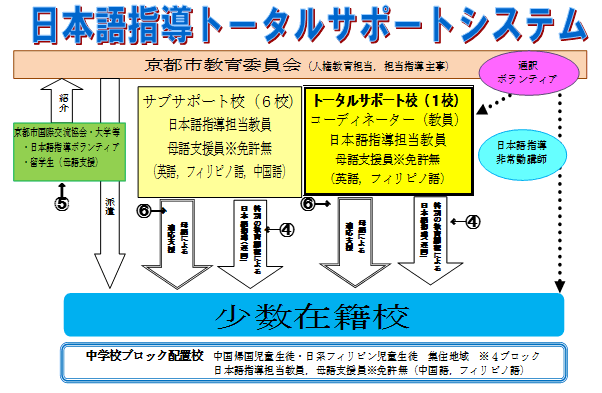
※ 図中の丸数字は,以下「2.具体の取組内容」の項目に対応
2.具体の取組内容
[2]拠点校等(トータルサポート校・サブサポート校)の設置
拠点的機能の整備(日本語指導トータルサポートシステム)
日本語指導トータルサポートシステム
京都市基本計画「はばたけ未来へ!京プラン実施計画第2ステージ」に,「『多文化が息づくまち』の実現に向けた学校教育の充実」として位置づけられている。日本語指導が必要な児童生徒及びその保護者に対する適切な指導・支援の実施を目指し,上記イメージ図の体制により,(公財)京都市国際交流協会や大学等とも連携して各取組を実施した。
- トータルサポート校
日本語指導コーディネーター,日本語指導担当教員(複数名)・母語支援員を配置し,担当地域内に日本語指導が必要な児童生徒の編入があった場合,コーディネーターと母語支援員又は通訳ボランティアが在籍校に出向き,面談や日本語能力を測るアセスメント等を実施している。その結果に応じて,コーディネーターが日本語指導担当教員や母語支援員等の派遣調整等を行った。 - サブサポート校
日本語指導担当教員や母語支援員を配置し,トータルサポート校の担当地域以外の地域に日本語指導が必要な児童生徒の編入があった場合,教育委員会の担当指導主事がコーディネーターとして,編入があった学校に出向き,面談やアセスメントを実施,サブサポート校からの日本語指導担当教員や母語支援員等の派遣調整を行った。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の実施
昨年度に引き続き,原則来日後1年以内の児童生徒を対象に週1~4時間の指導を実施した。
指導は,児童生徒が在籍する学校で実施している。(日本語指導担当教員が在籍校を巡回)
4月:日本語指導担当教員指導力向上セミナー<1>「個別の指導計画作成について」
4月~5月:各校で個別の指導計画作成,教育委員会担当課に提出。
前期終了時:日本語能力測定結果等を踏まえて指導計画の見直し。
9月・1月・2月:個別の指導計画に基づいた授業研究や指導内容の検討会(日本語指導担当教員指導力向上セミナー[4][6][7])
日本語指導指導者養成研修会(日本語指導コース)と東京学芸大学JLS研修会の伝達研修
3月:日本語能力測定結果等を活用した評価を個別の指導計画に記入し提出。次年度に申送り。
[6]日本語指導ができる支援員の派遣
- 日本語指導ボランティアの派遣
- 【ボランティアの募集】(公益財団法人)京都市国際交流協会や大学と連携して募集
- 【派遣対象】特別の教育課程による日本語指導を終了した児童生徒及び対象外の児童生徒
- 京都市立小・中・高等学校及び総合支援学校の児童生徒が対象
- 【派遣回数】児童生徒1人あたり年間52回上限※週1~2回,課外の時間に1時間程度
- 【派遣調整】教育委員会担当課で学校からの申請によりボランティアを決定。
平成28年度3月末:申請書提出
- 4月21日:日本語指導ボランティアガイダンス
講義「在籍校とつながる日本語指導」グループ交流 - 4月下旬から5月上旬:指導開始
※ 日本語指導担当教員指導力向上セミナー(講演や授業研究等)に参加可能
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
- 母語支援員の派遣
トータルサポート校,サブサポート校を拠点校として母語支援員を配置し,必要に応じて少数在籍校に派遣する。主な業務内容は,来日直後の児童生徒及び保護者への適応支援である。(上記イメージ図参照)
- 【勤務形態】京都市教育委員会非常勤嘱託職員
- 【言語・人数】英語・3名,中国語・3名,フィリピノ語・2名
- 【派遣対象校種】京都市立幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び総合支援学校
[3]日本語能力測定方法等を活用した実践研究の実施 (必須実施項目)
- 平成29年6月26日 日本語指導担当教員指導力向上セミナー[3]
- 講義「年少者の四技能の発達とDLA」 外部講師
- DLAの実施の様子から評価し模擬サポート会議を開催
- 平成29年9月15日 日本語指導担当教員指導力向上セミナー[4]
日本語指導担当教員がそれぞれ実施したDLA結果を持ちより,評価と今後の指導・支援についてグループで検討する。 - 平成30年1月12日 日本語指導担当教員指導力向上セミナー[6]
DLAをはじめとする日本語能力測定結果をもとにした授業の実際について検討
指導助言 外部講師 - 平成30年2月19日 日本語指導担当教員指導力向上セミナー[7]
DLAをはじめとする日本語能力測定結果をもとに,指導の振返りと今後の指導計画を考える。
前期・後期終了時に,DLAを実施し,教育委員会担当課に提出。
[9]成果の普及 (必須実施項目)
- 7月28日「多文化共生社会実現に向けた研修会」※全市全校種対象(希望制)
- 日本語指導が必要な児童生徒の現状と支援体制について講義
- 日本語指導指導者養成研修(管理職コース)参加者から伝達講義
- 少数在籍校での実践報告
- 市内各校・支部の研修会での発信:9校・2支部,京都教師塾での講義
- 市内大学等での発信:3回
- 他都市の研修会や学会等での発信:11回
- 京都市教育委員会のホームページに,本市の日本語指導等について掲載
3.成果と課題
[2]拠点校等(トータルサポート校・サブサポート校)の設置
拠点的機能の整備(日本語指導トータルサポートシステム)
日本語指導が必要な児童生徒は,ルーツをもつ国や来日背景,来日までの就学経験や今後の展望など,一人一人が異なっている。昨年度から,トータルサポート校を設置し,コーディネーターを配置したことにより,新規編入が重なる時期であっても,それぞれの現状を丁寧に把握し,必要な指導や支援を検討することができている。これにより,京都市内の全ての小中学校で,編入当日の母語による支援,早い段階からの日本語指導の開始が実現した。また,トータルサポート校,サブサポート校に,複数名の担当教員を配置したことにより,経験の浅い担当教員が相談しながら指導を進める様子が見られた。また,非常勤講師についても,トータルサポート校やサブサポート校の担当教員に相談したり,教材を活用したりできるシステムとしたことから,担当教員同士のつながりも深まった。
課題としては,新たに来日し,編入する日本語指導が必要な児童生徒数は,年々増え続けており,コーディネーター1名と担当指導主事1名でも,日本語指導担当教員や母語支援員の派遣調整が難しい状況となっていることがあげられる。特に,母語支援員は,新規来日数が増加するにつれて,1校当たりに派遣できる期間が短くなってきている。また,対象児童生徒の母語も多様化しており,来日直後から母語での支援ができないケースも出てきている。
このような状況が今後も続くと考えると,日本語指導が必要な児童生徒が編入した場合,受入れ校が支援に使える教材や情報を集め,いつでも活用できるようにウェブにアップするような方策も検討していきたい。トータルサポート校については,今後増設が必要であるが,そのための財源及び人材確保が課題である。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の実施
来日直後から,個別,または少人数の環境で日本語指導を受けられることから,日本語の習得が進むと共に,心の安定にもつながり,対象児童生徒が不適応を起こすことなく登校できた。また,日本語指導が必要な児童生徒の受入れ経験が少ない少数在籍校であっても,個別の指導計画作成や評価を通して,日本語指導担当教員と学級担任,教科担任等が連携して指導・支援にあたる体制がつくることができた。これにより,対象児童生徒に関わる全ての人が子どもの現状を共通理解し,よりよい指導や支援について考えることができた。
課題は日本語指導担当教員の負担が挙げられる。本市では,対象児童生徒が自校で指導が受けられるように,日本語指導担当教員が少数在籍校を巡回しているため,担当者1名が指導できる人数は限られており,学校間を移動する時間と費用,そして身体的な負担もある。
今後も,特別の教育課程による日本語指導は継続し,現在の原則来日後1年以内としている対象も,学習言語獲得を考えると伸ばす必要があると考えている。しかし,基礎定数化の基準である18名に1人の教員では,集住地域以外では実現が困難である。今後,指導時数や指導期間の再考も含めて,継続していける方策を考えていかなければならない。
更に,日本語指導が必要な児童生徒の中で,日本語指導だけではなく,特別な支援が必要だと思われる児童生徒は確実に増えてきている。このような児童生徒に対して,特別の教育課程をどのように編成し指導をしていくのか,特別支援教育の担当課と連携して個別の指導計画を作成し,指導を進める必要がある。
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
日本語指導ボランティアの派遣
今年度,高等学校についても派遣対象としたことから,学力保障をめざした,更に長期的な指導や支援が可能となった。また,日本語指導担当教員指導力向上セミナーを日本語指導ボランティアに開放したことから,毎回積極的に参加するボランティアが複数名あった。グループ交流で,違った立場からの意見を聞くことが可能となり,互いの理解が深まった。
課題は,日本語指導ボランティアに求められる指導内容にボランティア自身が対応しにくいことである。日本語指導ボランティアが指導する児童生徒は,「特別の教育課程による日本語指導」が終了した児童生徒,もしくはその対象外の児童生徒である。そのため,学習場面で必要な日本語力の習得をめざすと共に,進路実現を見据えた長期的な展望も必要となる。しかし,日本語指導ボランティアは教員免許の有無を問わないため,教科の学習内容とつなげる指導については実施が難しい現状がある。
今後は,教員経験がある方や,教員をめざす学生を日本語指導ボランティアとして活用していくことも考える必要がある。
[6]児童生徒の母語がわかる支援員の派遣
母語支援員の派遣
来日直後に母語がわかる支援員を派遣することにより,日本語指導が必要な児童生徒が安心して日本での学校生活をスタートすることができている。また,受入れ経験がない学級担任や学年担当教員の不安も解消されるとともに,教員や周りの児童生徒が,対象児童生徒の母国の文化や生活習慣等にふれる機会ともなっており,互いに理解し合える受入れ環境づくりにつながっている。
このように,来日直後に母語支援員を派遣することの成果は大きいが,その反面,対象児童生徒やその保護者,そして在籍校の教員が,母語支援に頼ってしまう状況も生まれやすく,派遣終了後の対応に苦慮する受入れ校もある。<2>でも述べているが,受け入れた学校の教員が支援に活用できるような教材や情報を提示することで,母語での支援がない状況でも何とかコミュニケーションがとれる環境づくりを進めていきたい。
[3]日本語能力測定方法等を活用した実践研究の実施 (必須実施項目)
昨年度に引き続き,DLAについての研修を実施したことで,日本語指導担当教員がDLAを活用した日本語能力測定について理解し,実施できた。また,実施結果の共有方法や,今後の指導・支援へのつなげ方について模擬サポート会議を体験したことにより,日本語指導担当教員が中心となって各学校で共通理解する場が設けられた。これにより,学級担任・学年教員・管理職・保護者との連携が深まると共に,よりよい指導・支援の実現につながった。
更に,DLAを活用した日本語能力測定方法について実施を義務付けたことにより,学期毎に指導者が客観的に対象児童生徒の力を把握し,自らの指導を振返る機会となり,指導力向上への意欲が高まった。更に,授業研究を実施したことから,日本語の力に応じた授業づくりについても認識が深まった。
課題は,DLAを実施する際に活用できる教材等である。DLAを活用した評価の実施について,提示されている教材は限りがある。指導経験が豊富な教員は同等レベルの教材を探して測定を実施しているが,経験が浅い教員については,その教材選定が難しい。今後,活用できる教材情報を持ち寄って検討し,四技能それぞれの測定に使える教材一覧作成などに取り組みたい。
[9]成果の普及 (必須実施項目)
「日本語指導トータルサポートシステム」について,市内の様々な研修会で発信したことにより,特別の教育課程による日本語指導をはじめとする指導や支援体制の周知が図れた。その結果,新規来日の場合については,編入連絡があったその日に担当課に相談が入るケースが多くなっている。また,就学時健康診断時に,日本語指導が必要な様子がみられると,その時点で連絡が入り,就学前に保護者との面談を実施し,入学後の指導や支援について決定することも多くなってきている。更に,日本語力に課題がみられる日本生れの児童や,児童生徒自身は日本語を獲得しているが,母語での支援が必要な保護者に関わる相談などが確実に増加している。このように,日本語指導が必要な児童生徒の教育についての認識をもつ教職員が確実に増えており,子どもの現状に応じた適切な指導や支援が実現している。
また,他都市での研修会や学会等で,本市の取組を発信し,多くの質問を受けたり,意見を得たりしたことから,現在の体制を客観的に振り返り,今後の実践に活かすことができると考えている。
課題としては,研修会で発信する機会には限りがあることが挙げられる。また,研修会に参加しない教職員は日本語指導が必要な児童生徒に対する取組について知る機会は少ないと考えられる。ホームページに情報を掲載はしているが,それらについても,実際に子どもを受け入れて初めて見るということが多い。
今後は,全市立学校に対して,定期的に発信できるような方法を考えるとともに,管理職を対象とした研修会や,参加人数が増えるような魅力的な研修会を企画・実施していきたい。
平成29年度の「日本語指導が必要な児童生徒」の数を把握していないため,「日本語指導が必要な児童生徒のうち、特別の教育課程で指導を受けた児童生徒の割合」は記載不可。
※ なお,目標が達成できなかった理由は,突然の帰国,指導開始直後,日本語面以外の要因など。
4.その他(今後の取組予定等)
就学前の子どもをもつ外国籍の保護者に対して,家庭での子どもとの具体的な関わり方や日本の小学校生活について紹介するようなリーフレットを作成する。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
