- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成29年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成29年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(長浜市)
平成29年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(長浜市)
平成29年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
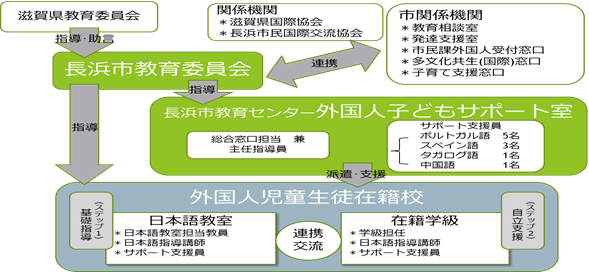
長浜市外国人児童生徒教育担当者連絡協議会の構成員:
外国人子どもサポート室長、日本語教育加配教員または学校の担当者、市主任指導員、各言語サポート支援員、市教育委員会事務局担当者
2.具体の取組内容
(1)運営協議会・連絡協議会の実施
- 年2回の「長浜市児童生徒の日本語指導にかかる担当者連絡協議会」を開催した。
- 11月24日:市内外国人児童生徒の現状把握と(3)(4)についての協議
- 2月27日:(3)(4)についての協議、今後の課題の整理(両日とも長浜市役所本庁にて開催)
(3)日本語能力測定方法等を活用した実践研究の実施
- 協議会にて、日本語能力測定方法などを活用した実践研究のための協議を行った。
- 1学期:日本語指導担当教員の在籍する小学校で、日本語能力測定方法等を活用した対象児童の実態把握。
- 11月:協議会にて、実態に応じた指導について情報交換。
- 2月:協議会にて、より効果的な実態把握の方法について情報交換。
(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施
- 協議会にて、「特別の教育課程」による日本語指導の実施のための協議を行った。
- 4月:各校にて「特別の教育課程」の編成
- 11月:協議会にて、個別の指導計画に基づいた指導実践の共有
個別の指導計画の見直し、指導の改善 - 2月 :協議会にて、達成目標の評価、来年度に向けて長浜共通の様式について検討
(6)児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
外国人サポート支援員を、9小学校・6中学校に定期的に派遣した。また、定期の家庭訪問や緊急の家庭訪問・保護者対応にも通訳として担任教員に同行した。学期末の個別懇談会や新入生説明会でも通訳を務めた。さらに、学校便りや保健便りといった、保護者配布文書の翻訳を行った。
(9)成果の普及
- 10月25日に湖南市立岩根小学校にて行われた県内の外国人児童生徒教育担当者配置校連絡会議にて、本市の取組について報告を行った。
- 12月9日に長浜市国際交流協会が行うスピーチ発表会「You 弁 In Nagahama」にて、市内外国籍中学生1名が日本語でスピーチを行い、日頃の日本語学習の成果を発表した。
3.成果と課題
(1)抽出した児童生徒の指導計画等を持ち寄り、情報交換をしたことで、「特別の教育課程」のより良い活用方法や、より効率的な支援の仕方・課題などを互いに共有でき、それらを各学校へ持ち帰り、その後の指導に活かすことができた。今後、今年度検討した「特別の教育課程」の長浜市様式を完成することにより、作成にかかる時間を短縮し、日本語指導担当教員の負担軽減を図る。
(3)日本語能力測定方法を行うためには児童生徒個別にかなりの測定時間と複数の人員が必要なため、在籍数の多い学校で行うことは難しい。今後も市内で情報交換しながら、より実効的な方法を模索していく。
(4)市内共通の様式を検討することで、各学校で一定の指導の在り方について共通認識することができた。今後も検討を進め、より効果的に日本語指導が実施できる体制を構築していく。
(6)学習指導、生活指導、教育相談を在籍校で適宜行うことができ、外国にルーツをもつ児童生徒の学校生活をより円滑にし、また生徒指導等の問題が起こったときにも迅速に対応し、早期に解決することができた。平成30年1月末現在で、緊急派遣は403時間に上った。
本市には、平成30年1月9日現在で、239名の日本語指導を必要とする児童生徒がいる。外国にルーツをもつ児童生徒は転入・転出が激しく、中でも今年度は海外から直接転入してくる児童生徒の増加が目立ち、それが市内の4小中学校に集中した。そういった学校では、現時点で雇用しているサポート支援員だけでは十分に支援に回り切れなかった。日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する学校において、日本語能力及び基礎的・基本的な学力を確実に向上させるためには、さらに人的な支援が必要である。
(9)スピーチ発表会については、市内の様々な立場の外国語の習得を目指す人との交流の場となり、児童生徒の日本語学習の意欲向上につながる。今後は、複数参加ができるよう働きかけをしていきたい。県内の外国籍児童生徒を抱える各市町と交流する中で、本市の大きな課題として感じたことは、初期指導教室の再開である。今後予算化に向けて関係機関と協議を続けていく。
4.その他(今後の取組予定等)
来年度は、日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する学校に、「外国人児童生徒学習指導員」(非常勤)を配置し、よりきめ細かな学習指導ができるよう体制を強化する。
また、「特別の教育課程」の長浜市様式を完成させ、活用できるようにしていく。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
