- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成28年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(姫路市)
平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(姫路市)
平成28年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
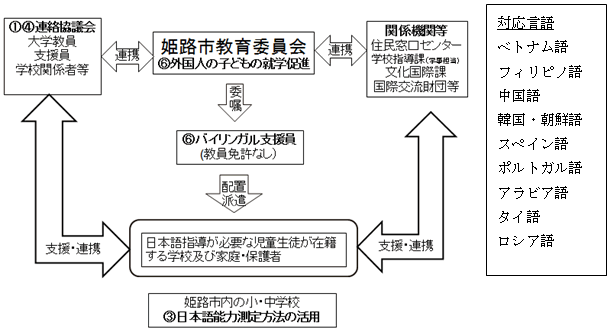
2.具体の取組内容
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[1]運営協議会・連絡協議会の実施
- 大学教員及び姫路市教育委員会指導主事・姫路市内各学校の日本語指導担当教員・支援員等で構成する連絡協議会を3回開催した。
(1)第1回姫路市帰国・外国人児童生徒受入促進事業連絡協議会 平成28年5月31日開催
- 【参加者】
- 大学教員1名 各校担当者等46名 支援員12名 指導主事等7名 文化国際交流財団国際交流担当3名 他町教育委員会主査1名
- 【内容】
- 事業説明
- 演習 「日本語能力測定方法を活用した日本語指導」
- 講演「日本語指導の要素を取り入れた在籍学級での学習支援について」
(2)第2回姫路市帰国・外国人児童生徒受入促進事業連絡協議会 平成28年11月4日開催
- 【参加者】
- 兵庫県教育委員会人権教育課副課長1名 各校担当者等31名 支援員4名 指導主事等5名
- 【内容】
- 授業公開 1年 理科 「物質のすがたとその変化」
- 講話 「国及び県の外国人児童生徒等教育について」
(3)第3回姫路市帰国・外国人児童生徒受入促進事業連絡協議会 平成29年3月23日開催
- 【参加者】
- 大学教員1名 各校担当者等38名 支援員7名 指導主事等6名
- 【内容】
- 授業公開 1年 理科 「力による現象」
- 指導助言
- 事後研修会及び各校の取組の交流
[3]日本語能力測定方法の活用 (必須実施項目)
- 5月に開催した第1回姫路市帰国・外国人児童生徒受入促進事業連絡協議会において、昨年度中央研修に参加した日本語指導担当教師を講師とした日本語能力測定方法(DLA)の演習を行い、日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校の先生方に日本語能力測定の方法を伝達した。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施(必須実施項目)
- 「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた説明会 平成28年5月31日開催
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
- バイリンガル支援員(スタディサポーター26(のべ46)名・通訳18名)の派遣
日本語指導が必要な児童生徒の在籍する幼・小・中・特別支援学校等に、母語と日本語が話せるバイリンガル支援員(スタディサポーター)・バイリンガル支援員(通訳)を派遣し、日本語指導の補助や学校との連絡調整を行った。
コミュニケーションの円滑化を図ることにより、児童生徒及び保護者の心の安定を図った。 - バイリンガル支援員(就学促進員)の派遣
平成18年度以降実施している就学状況調査の手法を踏襲し、学校や関係機関等と連携し、外国人の子どもの就学状況調査を行った。今年度は不就学の子どものいる家庭がなかったため、バイリンガル支援員(就学促進員)の派遣はなかった。
3.成果と課題
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[1]運営協議会・連絡協議会の実施
成果
- 第1回連絡協議会では、本市における日本語指導が必要な児童生徒の受入体制及び日本語能力測定方法(DLA)の概要及び活用方法について説明を行った。次に前年度の日本語指導研究推進校の日本語指導担当教師によるDLAの演習をしていただいた。さらに、大学教員から、日本語指導の要素を取り入れた在籍学級での学習支援について講義をしていただいた。在籍学級での学習支援を行うにあたり、「教科の目標」とは別に「日本語の目標」を設定することの必要性等を話していただいた。今年度、初めて日本語指導担当になった教員や日本語指導が必要な児童生徒の担任になった教員も多く、参加者の感想には「本市における支援体制や支援員の活用方法について理解することができた。」「DLAを活用し、児童の実態をより正確に理解し、指導へとつなげたい。」「担任に任せるだけでなく、校内の連携体制作りが大切であることが分かった。」「支援員との連携をもっと密にし、今後指導していく上で参考になった。」などがあり、指導・支援のポイント等数多く得ることができた協議会となった。
- 第2回連絡協議会では、理科室で中学1年生の理科「物質のすがたとその変化」の授業公開を行った。公開授業には多くの参観者があり、授業後の参加者の感想に「日本語指導の必要な生徒が分かる授業は、すべての生徒が分かる授業である」や「重要となる語句が強調されており、生徒の頭に残ると思う。持ち帰って授業に生かしていきたいと思う。」などがあり、これからの参観者の授業実践に役立つ公開授業となった。その後の兵庫県教育委員会人権教育課副課長の講話では、外国人児童生徒等教育についての国の方向性やそれを受けての県の考え方を教えていただいた。その後の感想には「文科省の最近の流れや考えを伝えていただいて、これからの日本語指導について先を見通すことができた。」や「日本で活躍できる人材育成等の話に共感した。」と、日本で学び、働くことを想定した指導支援のあり方に共感した感想が多くあり、今後の日本語指導を含めた外国人児童生徒の受入を再度考え直すきっかけができた協議会となった。
- 第3回連絡協議会では、中学1年生の教室で理科「力による現象」の授業公開を行った。公開授業には多くの参観者があり、授業後の参加者の感想に「自分のものさしで(生徒の日本語能力を)測らず、しっかりと実態を把握することが大切。」や「授業者の実践を交えながらの事後研修が参考になった。」、「日本語の目標の大切さやターゲットセンテンスや授業の組み立て方について意見を交えながら交流することができて勉強になった。」、大学教員の話から「日本語の目標の説明が分かりやすかった。」などがあり、児童生徒の実態把握や単元構成の大切を参加者に広げられる協議会となった。
課題
- 学校内での受入及び研修体制をより充実させ、日本語指導担当や担任のみならず、学校全体で日本語指導が必要な児童生徒に関わり、情報を共有する体制づくりが必要である。また、協議会等で各校担当者等の定期的な意見交換が不可欠であり、日本語指導が必要な児童生徒を長年受け入れている学校の取組を聞いたり、各校における悩みや課題を共有したりする機会を継続的に設定していきたい。さらに公開授業も取り入れながら、学校間での効果的な学習教材や指導・支援方法等の情報を共有できるような連携を視野にいれ今後も年3回程度の実施を行っていきたい。今年度は、講師を2回招聘し、公開授業後、「在籍学級における教科指導型日本語指導」についてお話をしていただいたが、参加者からは、「もっとお話が聞きたい」という感想が多かった。今年度もこれまで日本語指導を必要とする児童生徒が在籍していなかった学校に対象児童生徒が編入してきた学校が2校あり、来年度も新1年生として入学してくることが分かっている学校が数校ある。そのため、初めて日本語指導担当になる教員や日本語指導が必要な児童生徒の担任になる教員も多いことが予想される。来年度は、3回講師を招聘し研修を進め、姫路市内の帰国・外国人児童生徒教育の充実を図っていきたい。
また、初期指導など特別な日本語指導が必要な児童生徒には目が行きがちであるが、生活言語には不自由しないが家庭で言語が母語である等で学習言語が身についていない児童生徒を把握する必要性がある。そして、その児童生徒に対する在籍学級での日本語指導(教科指導型日本語指導)について、広く研修していく必要がある。
[3]日本語能力測定方法の活用 (必須実施項目)
成果
- 日本語能力測定方法(DLA)の演習を行うことで、伝達講習を受けた先生方の感想には、「やり方がよく分かり、すぐに実践できると思った。」「対象児童に必要なアセスメントを選び実施し、日本語能力を把握し、担任と今後の支援について計画したい。」「支援員と連携し計画的に実施し、支援生徒の支援に活かしたい。」「児童が話す・読む・書く・聴くに関して何が得意で何が不得意なのか、児童の学習到達度を理解し、個に応じた支援方法を模索したい。」などの意見があり、DLAの必要性を理解することができた。日本語指導に対する捉え方が曖昧であったが、DLAを活用することで、より焦点化して日本語指導の在り方を考えて対応することができた。
- 来日すぐに母語支援員と一緒に日本語能力測定を実施することで、対象児童生徒の母語に関する理解度を把握することができ、今後の日本語指導を行う上でたいへん参考になることが分かった。
課題
- 日本語能力測定方法(DLA)などを、多くの先生方に理解してもらうための研修が必要である。
- 測定する時間の確保が難しいため、どのように実施していくかが課題である。
- 全ての測定を実施するには、時間がかかりすぎるため、まず、どの測定を行うのが有効であるか、検討していくことが課題である。
- 日本語能力を測定した結果を、日本語指導に有効に活用していくことが重要である。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施(必須実施項目)
成果
- 「特別の教育課程」編成、個別の指導計画とも、文部科学省作成の様式及び記入例を提示したため、各校担当者とも記入例を参考に作成することができた。
- 昨年度作成の個別の指導計画を参考に今年度の指導計画を作成することができた。
- 個別の指導計画を作成しているため、学校内で日本語指導担当者や学級担任がかわっても、支援方法等について引き継ぎをしやすい。小学校から中学校、または他校へ転入する場合も、対象児童生徒の学習歴や支援状況を把握することができる等、「特別の教育課程」編成の意義を共通理解することができた。
課題
- 別室指導を行っている日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する学校では、個別の指導計画を児童生徒数分作成しなければならないため、教師の負担が大きい。
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
成果
- 渡日歴の浅い児童にとって支援員が心の拠り所になり、母語での会話を通して、心配なことや分からないこと、悩み等の相談に乗り、心の安定を図ることができた。
- 学校生活のきまりや、日本人の習慣、日本の文化についても教えてくださり、日本の理解が高まった。
- 日本語理解が十分でない児童生徒には、教科書や参考図書を翻訳し、児童生徒が理解できる言語で学習を進めることができた。また、難しい日本語の意味を母語で説明することで、学習への意欲が持続し日本語での理解が深まった。
- 休み時間も一緒に過ごし、遊びや他の児童と関わるときのルールを教え、当該児童は集団生活にずいぶん慣れることができた。
- 学習言語や学習内容の母語での支援により、授業内容が少しずつ理解できるようになり、それに伴って、自分から発表したり、家庭学習に積極的に取り組んだりできるようになった。
- 友達との関わりを支援してもらい、トラブルなく過ごすことができた。
- 周りの児童が対象児童の母国の生活や文化に興味をもった結果、本人の意欲の向上にもつながった。
- 支援員と児童との母語での会話が周りの児童へのよい刺激になった。
- 学年便りや学校行事、学校便りのプリント等、保護者に伝えることを翻訳したり、電話や家庭訪問などでの通訳をしたりして、学校と保護者をつなぐ重要な役割をした。
- 保護者会や進路相談時に、日本語の理解が十分でない保護者への通訳を行うことで担任と生徒及び保護者間の意思疎通に大いに役立った。
- 懇談時の通訳や通知表を含む配付物の翻訳等、必要に応じて細かなことまで伝えることができ、保護者は児童の様子を正しく理解でき、学校への不安を減らすことができ、信頼を深められた。
- 児童生徒の問題行動に対して、母語での対応や家庭への連絡がスムーズに行え、早期解決が図れた。
課題
- 対象児童生徒の編入が散在傾向にあるため、多くの学校に派遣する必要があり、現在の予算では、1校あたりの派遣回数が充分でないのが現状である。
- 支援回数が多いほど学習効果が高い。予算が限られているので、少ない回数で、いかに効果的な支援になるか工夫したり、計画を綿密に立てたりする必要がある。
4.その他(今後の取組等)
- 予算が限られている中で、母語による支援員を派遣できる回数は多く取れない状態である。また、特別の教育課程で組めるのは、年間280時間だと週8時間程度になる。そのため、児童は多くの時間を在籍学級で過ごすことになる。学級担任や教科担任が在籍学級で対象児童生徒を含めた全ての児童生徒にわかる授業である教科指導型日本語指導を推進していきたい。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
