- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成28年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(出雲市)
平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(出雲市)
平成28年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
出雲市日本語指導実施体制
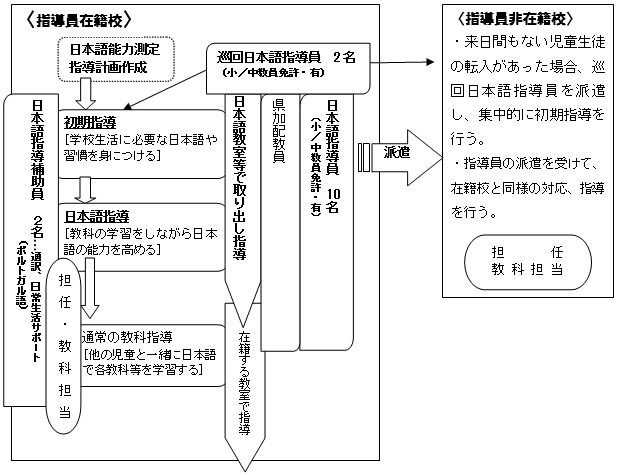
2.具体の取組内容
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[3]日本語能力測定方法の活用
- DLA等による測定(前期・後期)及び測定結果を活用した児童生徒の状況把握(在籍校)
- 測定結果を反映させた個別の指導計画の作成(在籍校)
- 対象児童生徒の日本語能力にもとづく必要指導時数の算出、指導員の配置・派遣計画の立案(市教委)
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
○日本語指導教職員研修会(1)【「特別の教育課程」及び「個別の指導計画」作成、実施に関する研修会】(平成28年8月1日)
- 「特別の教育課程」の概要と効果、指導計画の作成、指導プログラム例、DLAの実施
- 日本語指導担当者による実践例報告、情報交換
○東京学芸大学JSLサテライトセミナーinしまね【児童生徒の日本語力に配慮した授業、学校づくり】(平成28年10月26日)
- 校内体制づくり、JSLカリキュラムの基本的な考え方、授業づくりグループワーク
- 日本語指導担当者による情報交換
○日本語指導教職員研修会(2)【「特別の教育課程」及び「個別の指導計画」、DLAの実施について】(平成29年3月28日)[予定]
- 「特別の教育課程」の編成及び「個別の指導計画」作成に関する説明、DLAに関する研修
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
○出雲市日本語指導員(小学校8名、中学校2名)[出雲市臨時的任用職員]
- 対象児童生徒に対する日本語指導、学習支援
- 1日4時間×週5日勤務
○出雲市巡回日本語指導員(小学校1名、中学校1名)[出雲市臨時的任用職員]
- 来日間もない児童生徒に対する初期日本語指導、生活・学習支援
- (小学校)1日4時間×週4日、(中学校)1日4時間×週5日勤務
[6]児童生徒の母語ができる支援員の派遣
○日本語指導補助員(ポルトガル語対応、小学校2名)[出雲市臨時的任用職員]
- 対象児童に対する生活場面(休憩時間、給食、掃除等)及び学習時の入り込み支援
(教師の指示を通訳して伝える、児童の発言を通訳して教師に伝える、教師による面談や児童同士の会話のサポートなど) - 対象児童の保護者支援(電話連絡や来校時の通訳、連絡帳など簡単な内容の翻訳など)
- 1日4~6時間×週5日(週28時間)勤務
[8]その他(職員研修の実施)
○日本語指導担当教員(小学校1名)、在籍校管理職(小学校1名)、行政担当者(2名)による先進地視察
- 愛知県豊橋市:小学校1校、中学校1校、豊橋市教育委員会
- 静岡県浜松市:小学校1校、浜松市教育委員会
- 授業視察、質疑応答、資料閲覧
○在籍校への情報提供
3.成果と課題
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[3]日本語能力測定方法の活用
[成果]
- 測定結果の分析により、重点的に指導を行う教科や日本語技能を明確にすることができた。
- 測定結果等を示しながら、学級担任等と情報交換を行い、児童生徒の状況を把握したり、在籍学級での学習の際の支援に活かしたりすることができた。
- 測定結果を反映させた個別の指導計画を作成したり、1時間の授業の構成を工夫したりすることができた
[課題]
- 日々の生活・学習指導に時間を割いており、日本語能力測定のための時間の確保が難しい。
- DLAを実施できる指導者の人数が少ない。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
[成果]
- 研修会や情報交換を通して、「特別の教育課程」の概要や「個別の指導計画」の必要性の理解が進んだ。
- 先行して個別の指導計画を作成・実践している学校では、担任と連携して児童理解や指導を行うことができ、児童が学校に慣れ親しみ、学習内容の理解が進んだ。また、個別の指導計画の作成を通して、より詳細に児童の実態把握ができ、個に応じた教材を用意したり、わかりやすい授業を心掛けたりすることができた。
[課題]
- 「特別の教育課程」の編成や「個別の指導計画」の作成に関する周知や教職員の理解が進んでいない。
- 対象児童生徒の有無や人数の違いなどにより、学校間で校内体制等に温度差がある。
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
[成果]
- 出雲市日本語指導員の配置・派遣により、77名の児童生徒(小学校59名、中学校18名)に対し、7820時間(担任等との連絡、研修会参加を含む)の指導を行うことができた。
- 出雲市巡回日本語指導員の派遣により、来日間もない11名の児童生徒数(小学校6名、中学校5名)に対し、1503時間(担任等との連絡、研修会参加を含む)の初期指導を行うことができた。
- 対象児童生徒の在籍校に指導員を配置・派遣して日本語指導を行うことで、対象児童生徒が早く学校環境に慣れ、日本語の習得や学習内容の定着が進んだ。
- 年間で15名の児童生徒に、日本語ステージの向上が見られた。
[課題]
- できるだけ少人数(可能ならマンツーマン)での指導を実施したいが、指導員の人数の都合上、3人以上のグループになるところがある。
- 勤務時間のほとんどを指導に充てており、他の教職員との情報交換や研修、教材作成の時間が不足している。
[7]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
[成果]
- 低、中学年のステージ下位の児童を中心に23名に対応し、1531時間の支援を行った。
- 母語支援のおかげで、教師の指示が確実に伝わり、対象児童が他の児童とともに学習活動や学校行事に取り組むことができた。遠足や学習発表会などの行事に、対象児童が楽しみながら取り組むことができた。
- 対象児童が友達とトラブルになったり困ったことがあったりした時、母語で注意したり話を聞いたりすることで、子どもたちの困り感の解消につながった。
- 対象児童にとって母語で会話をする時間ができ、精神的な安定につながっている。
[課題]
- 担任や教科担当教員との相談、打合せの時間が不足している。
- 現在対応しているのは、ポルトガル語のみ。人数は少ないが他言語のニーズもある。
[8]その他(職員研修の実施)
- 日本語指導が必要な児童生徒に対する指導・支援体制、「特別の教育課程」の編成及び「個別の指導計画」作成、サバイバル日本語・日本語基礎・技能別日本語等のプログラムや教材、指導上参考となる資料などについて、具体物や情報を得ることができた。
- 視察で得た資料等を参考に、「特別の教育課程」による日本語指導実施のための計画づくりを進めることができた。
[課題]
- 視察した2市に比べ、指導計画やプログラムの内容、指導資料等の情報の提供が不足している。
4.その他(今後の取組等)
- 「特別の教育課程」の編成及び「個別の指導計画」の作成について、先進校の取組や参考となる資料を例示しながら周知を徹底していく。
- 特に対象児童生徒在籍校では、日本語指導員や巡回日本語指導員、日本語指導補助員の役割についても教職員の共通理解を図り、より効果的な日本語指導を行うための連携を進める必要がある。
- 日本語能力測定法については、校内の役割分担等による時間の確保を行うとともに、研修等を通して実施できる教員を増やし、児童生徒の日本語能力や必要な支援・指導に関する理解が進むようにする。
- 市教委が教職員研修や情報交換の場を設定し、有用な資料や情報を提供するとともに、市教委と学校あるいは学校同士が連携して指導にあたれるようにする。
- 現在対応できていない言語への対応も含め、他の行政機関や関係団体と連携し、対象児童生徒や保護者への支援を進めていく。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
