- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成28年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(茨木市)
平成28年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(茨木市)
平成28年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
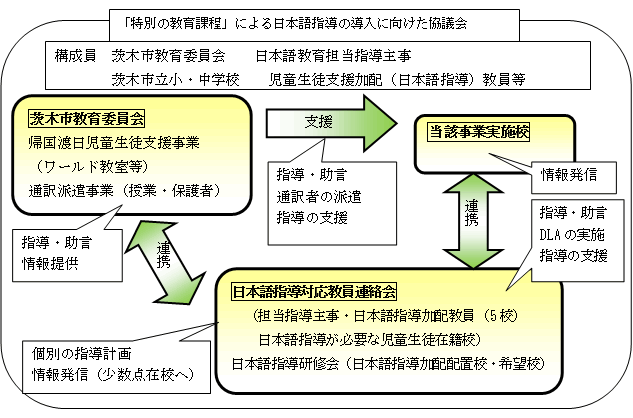
2.具体の取組内容
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[3]日本語能力測定方法の活用
- 市内の日本語指導教員が少数散在校の日本語指導が必要な児童生徒へのDLAを実施し、学校に対して指導を行った。
- 全てDLA実施のための日本語指導教員の派遣は、市教育委員会担当指導主事が日程調整、内容をコーディネートし、少数散在校へのアドバイスや継続した支援(通訳派遣等)を行った。
- 1年目の日本語指導教員については、2年目以上の日本語指導教員と一緒にDLAを実施し、共同でアセスメントを行うことで、スキルアップを図った。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会を「にほんごプロジェクト協議会」とし、市内の日本語指導教員を中心に、市内教職員への周知と、特別の教育課程による日本語指導が必要な児童生徒の把握に努めた。
- 4月…日本語指導教員連絡会
- 本事業による通訳者派遣対象校への支援と、市内の日本語指導が必要な児童生徒についての情報共有と方針決定。
- 特別の教育課程の実施方法と、個別の指導計画の作成方法についての研修・交流。
- 7月…第1回にほんごプロジェクト協議会
- 市内の日本語指導が必要な児童生徒の現状について
- 日本語指導教員の実践について(報告)
- 日本語指導が必要な児童生徒に対する府・市の支援体制について
- DLAについて
- 12月…第2回にほんごプロジェクト協議会
- 市内の日本語指導の内容とDLAの具体的な方法について
- 市内の日本語指導が必要な児童生徒の情報共有と課題について(交流)
- 3月…第3回にほんごプロジェクト協議会
- DLAの具体的な実践について(動画を用いて)
- 日本語指導が必要な児童生徒の支援について(次年度に向けて)
- DLAについて学校での周知と活用について(交流)
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
- 茨木市授業通訳者派遣要綱上、週2回、1回2時間の派遣が限度であるところを、本事業を活用して、毎日2時間派遣した。(全36回)
- 対象児童の母語、児童の家庭内における第2言語、日本語の3か国語を話せる通訳者を対象児童の通訳者として派遣した。
- 対象児童が小学1年生のため、入学式から通訳者を派遣し、小学校生活をスムーズに送れるよう支援した。
- 当初は対象児童の母語で小学校生活についての概要を説明することが多く、その後、母語で形成された概念を日本語に翻訳して理解を促した。 【例】絵カードや具体物を使って“What is this?”→”dog”→”In Japanese”→””いぬ”
- 主に抽出個別指導において、授業者と通訳者で日本語指導をすすめた。
3.成果と課題
※取り組んだ実施事項[1]~[8]について、それぞれ記入すること
[3]日本語能力測定方法の活用
成果
- 少数散在校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒に対し、DLAを実施することによって、個々の日本語能力の課題がわかり、具体的な支援・指導につなげることができた。
- DLAを通じて、児童生徒の生活を在籍校の教職員が深く理解することができ、言語面以外でも本人・保護者の支援につながった。
- 日本語指導教員が自校以外の児童生徒に対しDLAを行うことによって、茨木市全体として日本語指導を必要とする児童生徒の実態を把握することができ、研究を進めることができた。
課題
- 少数散在校においては、DLAの結果、特別の教育課程を編成すべきステージの児童生徒であっても、学校体制として日本語指導の個別指導が難しい場合があった。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
成果
- 日本語指導教員の実践を紹介することによって、特別の教育課程による日本語指導の成果について周知することができた。
- 市立小・中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の、課題解決に向けた情報交流や共有の充実を図ることができた。
- 外国にルーツのある児童生徒の学力の課題が、言語能力(日本語能力・母語能力)に起因することもあるということについて、教職員に広く周知することができた。
- 日本語指導教員が中心となって、学校組織や教職員全体で日本語指導が必要な児童生徒を支援していこうという意識が高まった。
課題
- 各学校の担当者の意識は向上したが、直接対応する教職員には周知・理解が不十分な点もあり、日本語能力に課題がある児童生徒への効果的な支援に至らない場合もあった。
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
成果
- 入学当初、対象児童とは英語でのみ意思疎通が可能で、簡単な日本語のあいさつも理解できず、児童自ら話しかけることも難しい状態だったが、本事業により、サバイバル日本語や生活言語の習得が進み、日本語の指示を理解し、簡単な日本語での会話ができるようになった。
- 派遣通訳者が英語と中国語を臨機応変に使い分け、母語力を向上させるとともに、学校生活を母語でサポートすることで、環境の変化や、初めての行事などの不安になる場面でも、対象児童が安心して過ごすことができた。
- 生活言語やコミュニケーションに必要な言語の習得が進むことで、学級の児童とコミュニケーションできるようになった。集団でのルールを少しずつ理解し、グループで行動できるようになり、自分から遊びに誘えるようにもなった。
課題
- 学校生活における言語習得が進むにつれ、発達的な課題による困難さも見られるようになった。言語的な課題と、発達的な課題を複合的に解決する必要があり、これは、本事業対象児童だけの課題ではなく、全市的な傾向として見られるものである。本市における特別支援教育の関係諸機関とも連携して、言語と発達の両側面で支援できる体制づくりを推進する必要がある。
4.その他(今後の取組等)
- 少数散在校への丁寧できめ細やかな個別指導のためには、日本語指導教員の巡回指導を活用し、在籍校教職員とも連携しながら、児童生徒の困り感に寄り添い、学校生活や一斉学習への適応を図っていきたい。
- 来年度も、本協議会を継続して開催し、担当者への情報提供と意識の向上に努め、各学校で支援を必要としている児童生徒を把握するとともに、日本語指導教員の巡回指導などを活用して、支援が必要な児童生徒の日本語能力の向上と、日本での生活適応を図っていきたい。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
