- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成27年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(八王子市)
CLARINETへようこそ
平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(八王子市)
平成27年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
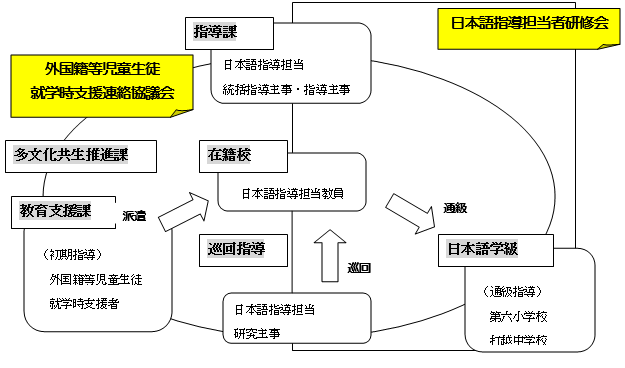
2.具体の取組内容
[1]関係者会議の実施
児童生徒の母語がわかる支援員(外国籍等児童生徒就学時支援者)、日本語学級教員、日本語指導担当教員、日本語指導統括指導主事、指導主事及び研究主事(日本語巡回指導員)、多文化共生推進課職員、教育支援課職員による連絡協議会、研修会における情報交換により、日本語指導が必要な児童生徒への共通理解、指導力の向上を図った。
[3]日本語能力測定方法の活用
今年度は日本語能力測定方法の具体的な活用に向けた準備期間と位置づけ、DLAの概要や測定方法について、関係者会議のなかで共通理解を図った。
日本語能力測定方法の具体的な活用に向けて、語彙カード等の補助教材を整備し、また、測定方法の研究等の準備を進めた。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施(必須実施項目)
「外国籍等児童生徒就学時支援連絡協議会」において、個別の指導計画の活用状況について関係者間で共通理解を図った。
[5]日本語巡回指導員の派遣
日本語の習得が充分でない児童生徒に対して、在籍する学校へ日本語巡回指導員が訪問して、基礎的な日本語の指導を行った。
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
就学手続きの時点で日本語に不安のある児童生徒を把握し、就学校と連携しながら、初期指導として一定期間(小学校上限40時間、中学校上限60時間)、児童生徒の母語が分かる外国籍等児童生徒就学時支援者を在籍校に派遣した。
3.成果と課題
[1]関係者会議の実施
日本語指導に関わる関係者での連絡協議会や研修会において、日本語指導の現状と課題についての意見交換を重ねることで、日本語指導が必要な児童生徒の受入体制、また、それぞれの実態に応じた日本語指導の支援体制の整備の必要性について、関係者間で共通理解を図ることができた。
様々な理由により来日している状況があり、それぞれの児童生徒、保護者との繋がりをもって、将来について問題意識をもって取り組んでいける体制づくりが必要である。
[3]日本語能力測定方法の活用
日本語能力測定方法を活用の可能性として他の検査と併用することで児童生徒の困りの原因が発達に関するものなのか、あるいは家庭環境等を背景とした日本語の習得に課題があるのかの判断への活用について調査、研究を行った。
今後の具体的な実施に向けて、来年度は外部講師を招いての学習会を開催し、測定方法について関係者が十分に理解し、的確に日本語能力を把握することができるよう取り組み、指導方法を決定する仕組みをつくる必要がある。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施(必須実施項目)
ひとりひとりの日本語能力に応じた日本語指導がより効果的に行われるよう、児童生徒の抱えている課題を記録し、引き継ぐことのできる個別の指導計画の様式や作成方法についての研修会を重ね、「外国籍等児童生徒就学時支援連絡協議会」において、引き続き協議・検討を重ねていく。
[5]日本語巡回指導員の派遣
児童生徒の在籍校と連携しながら、ひとりひとりの日本語能力を考慮した、個に応じた資料を活用した個別指導の充実を図った。
また、日本語の習得だけではなく、児童生徒の心理的な面でのサポートも行い、円滑に学校生活を送ることができるよう、在籍校との情報共有を図った。
引き続き、児童生徒の実態に応じた日本語指導により、児童生徒の適応力を育んでいく。
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
就学当初からの支援者派遣により、日本語の習得が充分でない児童・生徒の就学に対する不安を解消し、学校生活への円滑な適応を実現することができた。また、日本語に不安のある児童生徒が母語で支援者と話をすることで、日本語でのコミュニケーションがとれないというストレスの解消となり、心理的なフォローにもつながった。
今後は派遣上限時間数を拡大し、従来の学校生活への適応指導のみならず、あいさつ等の日本語初期指導も含めた支援の充実を図っていく。
4.その他(今後の取組等)
- 日本語初期指導教室の設置へ向けた調査・研究。
- 日本語指導の教材集及び実践事例集の開発と活用の推進。
- 日本語指導が必要な児童を、就学時健康診断や保護者説明会の段階で把握できる仕組みづくり。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
-- 登録:平成29年02月 --