- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成27年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(神戸市)
CLARINETへようこそ
平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(神戸市)
平成27年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
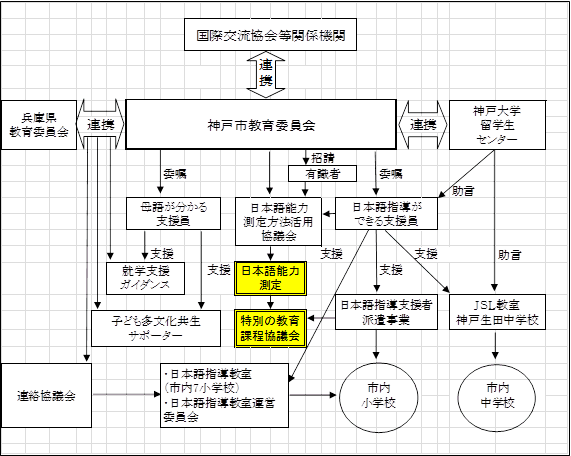
連絡協議会構成員
- 日本語指導教室実施校担当教員7人、日本語指導教室支援員6人、教育委員会事務局指導主事3人
支援員
- 日本語指導ができる支援員:8人
- 母語の分かる支援員:対応言語
中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピノ語、スペイン・語、ウルドゥー語、ロシア語、モンゴル語、ネパール語、ベンガル語、ヒンディー語、タイ語、インドネシア語、13言語
2.具体の取組内容
[1]運営協議会・連絡協議会の実施
日本語指導に係わる連絡協議会を神戸市総合教育センターで3回開催し、帰国・外国人児童生徒の受入体制の現状と課題の把握や、受入にあたっての指導・支援のあり方を協議した。
第1回 6月 4日 日本語教室の年間活動計画と実施状況の情報共有
第2回 10月22日 日本語教室の実施状況報告、日本語能力測定方法についての学習会
昨年度の中央研修参加者による報告と実践発表
第3回 2月 4日 日本語教室の年間活動報告
[2]初期指導教室やセンター校等の設置
- JSL教室を神戸生田中学校に開設
神戸生田中学校をセンター校として、日本語で学習指導を行う日本語指導者(日本語教師)を派遣し、センター校以外に在籍する市立中学校生も対象に、市内各校から生徒が集まりやすいよう放課後に日本語指導を実施した。
初めて日本語を習う初級指導クラスと、中学校での5教科指導に当たる移行期指導クラスに分け、生徒の日本語習得の状況に応じた指導を展開した。 - 市立小学校7校を拠点校として日本語指導教室を開設
拠点校は、本庄小学校、本山第二小学校、こうべ小学校、港島小学校、真陽小学校、御蔵小、神陵台小学校の7校とした。
各校年間32回程度の日本語教室を実施し、生活適応を図る指導、生活言語から学習言語へと日本語習得を図る指導等を行った。(計216回)
[3]日本語能力測定方法の活用
- 10月22日(木曜日)
「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」
測定方法についての学習会実施
(参加者)- センター校担当教員
- 日本語指導支援員
- 教育委員会事務局指導主事
- 2月4日(木曜日)
DLAの実践と効果の報告
(参加者)- センター校担当教員
- 日本語指導支援員
- 教育委員会事務局指導主事
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
- 第1回協議会開催(4月27日)
- 「特別の教育課程」による日本語指導を行う場合の年間スケジュール例検討
- 義務教育諸学校における日本語指導の新たな体制整備について
- 学校における日本語指導の流れ
- 日本語指導の研究の方向性について
- 参加者 センター校担当教員
- 日本語指導支援員
- 教育委員会事務局指導主事
- 第2回協議会開催(11月25日)
- JSLカリキュラムを活用した日本語指導のあり方
- 「特別の教育課程」実施のための課題と体制整備について
- 参加者 センター校担当教員
- 日本語指導支援員
- 教育委員会事務局指導主事
- 第3回協議会開催(2月25日)
- 日本語能力測定方法を活用した日本語指導について
- 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA研修
- 来年度の取り組み方検討
- 参加者 センター校担当教員
- 日本語指導支援員
- 教育委員会事務局指導主事
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
- JSL教室
JSL教室に日本語指導員を派遣し、日本語指導を行った。
年間実施 計543回(初級・移行期1年生・移行期2年生・移行期3年生) - 日本語指導教室(日本語の初期指導)
拠点校7校に日本語指導ができる支援員を派遣した。
年間実施 計216回 - 日本語指導支援者派遣事業(学習言語の指導)
日本語指導ができる支援員者を派遣し、日本語指導を行った。
事業対象校:本庄小、中央小、山の手小、兵庫大開小、駒ヶ林小、東灘小、
年間実施 計2,522時間
[6]日本語指導を要する児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
- 神戸市子ども多文化共生サポーター(派遣回数799回)
日本語指導を要する外国人児童生徒の支援のために、児童生徒の母語を話せる「子ども多文化共生サポーター」を小中学校に派遣し、支援対象の児童生徒と教員等とコミュニケーションの円滑化を促すとともに、生活適応や学習支援、心の安定を図るなど、学校生活への早期適応を促進している。
3.成果と課題
[1]運営協議会・連絡協議会の実施
- 各教室での支援者の工夫等、情報の共有が図れた。個人差への対応と小学校における学習言語習得支援が課題である。
- 関係機関と連携し、日本語指導ができる人材の確保に努めることが必要である。
[2]初期指導教室やセンター校等の設置
- 小学校ではセンター校での支援により、児童の心の安定に成果が見られた。中学校では、JSL教室での学習言語習得に成果が見られた。センター校の受入拡大に伴う支援者の充実と、小学校での学習言語習得に向けた取組が課題である。
[3]日本語能力測定方法の活用
- 日本語指導教室の拠点小学校の担当教員と支援員へは「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」の活用方法を周知し、活用の研修ができた。より多くの教員や支援者への周知と実践の広がりが今後の課題である。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
- 日本語支援員がいる学校で作成している個人カルテをもとに、「特別の教育課程」のひな形の例を作成した。しかし、また検討をしていかなければいけない部分は多い。
- 「特別の教育課程」について、今後も周知徹底をしていく必要がある。
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
- 母語を介した生活言語の獲得支援から、学習言語レベルでの日本語指導への接続に課題がある。
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
- 新渡日の児童生徒には、母語が分かる支援員を配置することでカウンセリング機能も発揮され、落ち着いた学校生活に結び付けることが出来た。
- 高校進学に向けた具体的な教育相談ができた。NPO等の支援団体や学校関係者との連携を継続させることが課題である。
4.その他(今後の取組等)
- 「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」の活用による児童生徒の日本語能力の把握と日本語指導を行う。
- 関係機関と連携し、日本語による日本語指導のできる人材の確保に努める。
- 支援を要する児童の在籍数や地域の特性等から、小学校拠点校については毎年見直しを行う。
- 母語を介した生活言語の獲得支援から、学習言語レベルでの日本語指導への接続を見据えた日本語指導支援システムの構築に向け研究していく。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
-- 登録:平成29年02月 --