- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成27年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(愛知県)
CLARINETへようこそ
平成27年度 「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(愛知県)
平成27年度に実施した取組の内容及び成果と課題
1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)
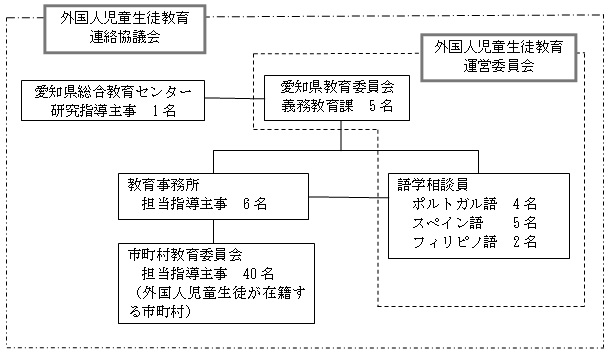
2.具体の取組内容
[1]運営協議会・連絡協議会の実施
(1)外国人児童生徒教育運営委員会(4月・2月)
- 目的
- 学校における日本語教育の状況の把握と課題の分析を行う。
- 語学相談員派遣計画および成果の検証を行う。
- 構成員
- 義務教育課(5名)
- 語学相談員(11名:ポルトガル語4名、スペイン語5名、フィリピノ語2名)
(2)外国人児童生徒教育連絡協議会(8月)
- 目的
- 「『特別の教育課程』による日本語指導の在り方」というテーマでのパネルディスカッションを通して、外国人児童生徒教育の専門家、外国人児童生徒教育を推進している市町教育委員会、語学相談員、教員という様々な立場からの意見を聞きながら、DLAの活用と個別の指導計画の作成を中心に、児童生徒への日本語指導の在り方について検討する。
- グループ協議では、テーマごとにグループを編成し、各市町が抱えている共通の課題や取組について協議をすることで、県内全域における「特別の教育課程」による日本語指導の推進を図る。
- 構成員(62名)
- 外国人児童生徒が在籍する市町村教育委員会の担当指導主事(40名)
- 各教育事務所の担当指導主事(6名)
- 愛知県総合教育センターの担当研究指導主事(1名)
- 愛知県教育委員会語学相談員(10名:ポルトガル語4名、スペイン語5名、フィリピノ語1名)
- 愛知県教育委員会義務教育課(5名)
- 平成27年度の内容
- パネルディスカッション「『特別の教育課程』による日本語指導の在り方」
- グループ協議
[テーマ]- ア DLAを活用した個別の指導計画の作成について
- イ 初期指導教室の運営とそれに関わる課題について
- ウ 日本語指導を支援する人材の確保と環境整備について
[3]日本語能力測定方法の活用
(1)児童生徒の日本語能力の活用(4月~12月)
- 語学相談員が訪問校の日本語指導担当教員とともに、児童生徒の日本語能力を測定
- 訪問校のうち40校で児童生徒の日本語能力を測定し、その後の指導に反映
(2)日本語能力測定方法及びその活用についての研修
- ア 外国人児童生徒教育講座(6月)
- 対象 日本語指導担当教員(53名)
- 内容 日本語能力測定方法の概要説明及び語彙カードを使用した演習、質疑応答
- イ 教育課程研究集会(8月)
- 対象 各地区の外国人児童生徒教育の中核となる教員(32名)
- 日本語能力測定方法を活用した支援の在り方についての研究協議
- ウ 外国人児童生徒教育連絡協議会(8月)
- 参加者
- 外国人児童生徒が在籍する市町村教育委員会の担当指導主事(40名)
- 各教育事務所の担当指導主事(6名)
- 愛知県総合教育センターの担当研究指導主事(1名)
- 愛知県教育委員会語学相談員(10名)
- 愛知県教育委員会義務教育課(5名)
- 内容
「DLAを活用した個別の指導計画の作成について」をテーマに、3グループで協議を行った。
- 参加者
- エ 語学相談員研修会(8月)
- 目的
- 学校から語学相談員へのDLA実施の要望が高まっている中、DLAの趣旨の理解を図り、演習を通して実施方法などを習得する。
- DLAを用いて把握した児童生徒の日本語能力を踏まえた支援の在り方について理解を深め今後の支援に生かす。
- 参加者 語学相談員(10名)
- 内容
- 講義「DLA はじめの一歩 ~DLAを活用した効果的な学習指導について~」
- DLAの演習
「はじめの一歩」、「話す」の演習
- 目的
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
(1)外国人児童生徒教育連絡協議会(8月)
- 目的
- 「『特別の教育課程』による日本語指導の在り方」というテーマでのパネルディスカッションを通して、外国人児童生徒教育の専門家、外国人児童生徒教育を推進している市教育委員会、語学相談員、教員という様々な立場での意見をいただきながら、DLAの活用と個別の指導計画の作成を中心に、児童生徒への日本語指導の在り方について検討した。
- グループ協議では、テーマごとにグループを編成し、各市町が抱えている共通の課題や取組について協議をすることで、県内全域における「特別の教育課程」による日本語指導の推進を図った。
- 構成員(62名)
- 外国人児童生徒が在籍する市町村教育委員会の担当指導主事(40人)
- 各教育事務所の担当指導主事(6人)
- 愛知県総合教育センターの担当研究指導主事(1人)
- 愛知県教育委員会語学相談員(10人:ポルトガル語4名、スペイン語5名、フィリピノ語1名)
- 愛知県教育委員会義務教育課(5人)
- 平成27年度の内容
- パネルディスカッション「『特別の教育課程』による日本語指導の在り方」
- グループ協議
- [テーマ]
- ア DLAを活用した個別の指導計画の作成について
- イ 初期指導教室の運営とそれに関わる課題について
- ウ 日本語指導を支援する人材の確保と環境整備について
- [テーマ]
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
6 児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
(1)目的
語学相談員を公立小・中学校へ派遣し、ポルトガル語、スペイン語及びフィリピノ語を母語とする外国人児童生徒の就学者に語学指導や生活適応指導等を行うことにより、本県の外国人児童生徒教育の充実に資する。
(2)語学相談員の言語と人数
- ポルトガル語の語学相談員 4名
- スペイン語の語学相談員 5名
- フィリピノ語の語学相談員 2名
(3)業務の内容
- 外国人児童生徒に対する日本語及びポルトガル語、スペイン語又はフィリピノ語指導の補助
- 外国人児童生徒に対する生活適応相談
- 保護者に対する教育相談及び親子交流会に関する援助
- 手引き書等資料作成への援助
- 教職員研修会における語学指導等
(4)訪問の実績
- 訪問校数
- 小学校148校 中学校60校 特別支援学校1校 計209校
- 支援した児童生徒数
- ポルトガル語613名 スペイン語226名 フィリピノ語216名 計1,055名
[7]その他
- 語学相談員研修会(4月、5月、6月、8月、10月、12月、2月)
- 目的
訪問校において、外国人児童生徒一人一人の日本語能力に応じた日本語指導をするため、支援の在り方について協議をし、さらに充実した支援を図る。 - 参加者
語学相談員11名、担当指導主事 - 内容
- ア 外国人児童生徒への日本語指導や生活的応相談等の支援の在り方の検討
- イ 各学校の児童生徒についての情報交換
- ウ 外国人児童生徒教育講座の準備
3.成果と課題
[1]運営委員会・連絡協議会の実施
(1)外国人児童生徒教育運営委員会
- 事業を推進する上での県としての考え方を語学相談員に伝えるとともに、学校や児童生徒の状況を語学相談員から直接聞くことができ、取り組むべき課題の共通理解を図り、今後の外国人児童生徒教育の在り方を検討することができた。
(2)外国人児童生徒教育連絡協議会
- パネルディスカッションを通して、個別の指導計画作成の意義やDLAを用いて児童生徒個々の日本語能力を把握する重要性を市町村教育委員会に伝えることができた。
- 各市町村が課題と捉えている共通のテーマについてグループ協議することで、課題解決に向けてどのような手立てをうつ必要があるのかを検討することができた。
[3]日本語能力測定方法の活用
○ 様々な研修でDLA及びその活用方法について扱うことで、DLAの実施方法やその趣旨、活用の仕方などを、日本語指導担当教員、市町村教育委員会担当指導主事、語学相談員に伝えることができ、外国人児童生徒の支援に携わる人たちの意識の高揚、力量の向上を図ることができた。
○ 語学相談員については、研修でDLAのノウハウを身につけることで実施回数が増加し、それに伴って個別の指導計画の作成も少しずつ進んでいる。
△ 今年度の研修で一定の成果は見られたものの、まだまだ十分であるとは言えない。今後もDLAの趣旨、実施方法、活用方法などを広く知らせる機会が必要である。
△ DLAを実施すればいいわけではなく、DLAの結果を日々の指導にどのように活用していくかが重要になってくる。今後は、効果的な指導にするためには、DLAの結果をどのように活用すべきかに重点をおいて、研修を行っていく必要がある。
[4]「特別の教育課程」による日本語指導の導入に向けた協議会の実施
○ パネルディスカッションを通して様々な立場の方からの意見を聞くことで、生徒一人一人の日本語能力に合わせた指導をしていくことの必要性や、日本語指導の担当教員や担任が見通しを持って児童生徒に指導していくことの大切さを、会に出席している各市町村教育委員会の担当指導主事等に伝えることができた。
○ 平成27年度当初は、「個別の指導計画」の作成を始めている市町村は全体の半数以下で、地域によって取組に差がある状況であった。そこで、外国人児童生徒教育連絡協議会のグループ協議において、先進的に取り組んでいる市町村の状況をはじめとした情報交換を行い、参加者に県内の各地域での取組状況について知ってもらうことができた。この協議会で得られた情報から、各市町村での取組が更に進んでいくことを期待している。
△ 日本語指導担当教員が短い期間で替わってしまう場合があり、また経験年数の浅い担当教員も多いことから、各地区における外国人児童生徒教育のリーダーとなる人材が不足しているという問題が挙げられた。県としては、「教育課程研究集会 外国人児童生徒教育部会」及び「外国人児童生徒教育講座」等で、日本語指導担当教員の育成及び力量向上のための研修を引き続き行っていく。
△ 語学相談員や支援員等、日本語指導に携わる人材の不足も、グループ協議の中で問題として挙げられた。県内には、大学生のボランティアを活用したり、NPOとの連携を図ったりしている地区もあるので、来年度の連絡協議会では、ボランティアの活用や他機関との連携を図っている地区の取組の紹介等も検討していきたい。
[5]日本語指導ができる支援員の派遣
[6]児童生徒の母語が分かる支援員の派遣
(1)成果(学校への調査から)
- 通訳や翻訳を通し、保護者の協力が得られるようになった。
- 外国人児童生徒の教科等の学習理解が向上した。
- 外国人児童生徒の日本語能力が向上した。
- 児童生徒の日本語能力が把握でき、「個別の指導計画」の作成または見直しが図られた。
- 児童生徒の精神的安定、不安の軽減が図られた。
- 進学について必要な情報が得られた。
- 児童が母国への関心を高め、ルーツに自信を持つことができた。
- 児童生徒の母語力が向上した。
(2)課題
△ 県内の広い地域で活動をしているため、先進的に外国人児童生徒教育を行っている学校での支援状況をはじめ、語学相談員は様々な情報を持っている。そのため、教材や指導方法等、具体的な助言がほしいという学校からのニーズがある。また、語学相談員の活動内容として、文書の翻訳や保護者会での通訳も大きな割合を占めており、学校の意図がきちんと伝えられるような翻訳や通訳の力が学校側から期待されている。こういった要望に応えられるよう、語学相談員研修会等でのさらなる力量向上が必要である。
△ 平成27年度は、独自に語学相談員を設置していない市町村の学校への訪問を優先的に計画し学校訪問を実施したが、年度末の調査で各語学相談員の訪問地域にやや偏りがあることが判明した。そのため、平成28年度は訪問地域を見直し、独自に語学相談員を設置していない市町村の学校へ定期訪問ができるように調整する。
[7]その他
○ 今年度5名増員し、新規採用者が増えた。初めて学校現場で児童生徒の支援をする語学相談員もおり、新しい語学相談員を育てていくという意味において、様々な情報交換が可能な語学相談員研修会はたいへん貴重な機会となった。
○ 語学相談員は、児童生徒への支援についてそれぞれに課題を抱えている。研修会ではその課題について皆で検討し、解決策を探ることで、各語学相談員のその後の支援の充実を図ることができている。
△ 語学相談員のような支援員を配置している市町村の増加に伴い、特にフィリピノ語において人材を確保するのが困難である。また、語学相談員の力量を向上させるため、どんな研修を行っていくのか見直す必要がある。
4.その他(今後の取組等)
(1)語学相談員の配置
- ポルトガル語4名、スペイン語5名、フィリピノ語2名の語学相談員を、平成28年度も県内の小中学校に派遣する。
- 独自に語学相談員を設置していない市町村の小中学校に、定期的に訪問ができるようにする。
- 外国人児童生徒への日本語指導の補助、生活適応指導、保護者会での通訳、連絡文書の翻訳等を行う。
- 日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実を図るため、合同で教材開発・作成を行う。
(2)研修の充実
[1]外国人児童生徒教育講座(6月・10月)
- 外国人児童生徒教育を担当する小中学校教員を対象に、外国人児童生徒教育に必要な技能を習得し、資質の向上を図るための研修を行う。
[2]外国人児童生徒教育連絡協議会(8月)
- 外国人児童が在籍する市町村教育委員会の担当指導主事、各教育事務所の担当指導主事、語学相談員等が参加し、各市町村の取組状況等の情報の共有、今後のよりよい在り方についての協議を行い、県全体の外国人児童生徒教育の推進を図る。
[3]教育課程研究集会 外国人児童生徒教育部会(8月)
- 外国人児童生徒教育を担当する各市町村の中核教員を対象に、日本語指導が必要な児童生徒の学力を向上させるための取組等を協議・情報交換し、効果的な外国人児童生徒教育の在り方について研究を深める。
(3)関係部局との連携
- 県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室との連携
- 外国人児童生徒等による多文化共生スピーチコンテスト
- あいち外国人の日本語教育推進会議
- (公財)愛知県国際交流協会との連携
- 学校とNPO等との連携による外国人児童生徒指導関係者共同研修
- 外国人児童生徒日本語指導員養成講座
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
電話番号:03-6734-2035
-- 登録:平成29年02月 --