- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 「学校教育におけるJSLカリキュラムの開発について」(最終報告)小学校編 > 3.「教科志向型」JSLカリキュラム「国語科」
CLARINETへようこそ
3.「教科志向型」JSLカリキュラム「国語科」
3.1 日本語を母語としない子どもたちにとっての国語科
3.1.1 「伝え合う力」をめぐる困難
日本語を母語としない子どもたちが、国語科学習のどのようなところに困難を感じて、学びに入っていけないのだろうか。
こうした子どもたちの抱える問題は多岐に渡り、すべては列挙できないが、国語教育での実状と照らし合わせてみると、概ね以下のようなことが考えられる。
- 相手に自らの考えや意見、気持ちなどを分かりやすく順序立てて訴え、表現することができない。
- 相手の考えや意見、気持ちなどを十分に理解することができない。
- 相手の問題や疑問を受けとめ、自らの考えや意見を見直したり、向上・改善させたりすることができない。
- 認知力の発達途上における概念形成の段階で、自らの問題点や疑問点を表現できない。
3.1.2 困難の背景
日本語を母語としない子どもたちが抱えるこのような困難の背景には、日本語力と学習内容理解と認知力の相互関係の中で生じる以下のような問題が関係しているといわれている。
- 生活場面を中心とした話し言葉による「聞く」「話す」から、書き言葉による「読む」「書く」を含む言語能力が求められていること。
- 認知的能力の発達が、教科学習には十分でないこと。
- 抽象的・概念的な命題の理解がむずかしく、国語科で使用される知的な言葉や記号になじめないこと。
- 具象から抽象へ、また、抽象から具象へという学習形態や思考過程になじめないこと。
国語科では、学習指導要領の改訂の基本方針を受けて、目的や相手、場面や状況に応じて効果的に言語を運用する力を育成することを目指し、これを基礎に互いの立場や考えを尊重しながら言語で伝え合う能力の育成を重視している。日本語を母語としない子どもたちも含めたすべての子どもたちに対して、この力を伸ばすことが学習指導要領の趣旨の実現のための鍵といえよう。
上で述べたとおり、日本語を母語としない子どもたちの国語科における困難は、基本的にこの「伝え合う力」をめぐる困難であるといえる。日常生活に支障のない程度に日本語を習得した子どもたちでもこのような困難を感じることが少なくない。母語同様に日本語が流ちょうに感じられても、国語科の授業において日本語を用いた「伝え合う力」が求められる学習活動には十分対応できないという状況が多々ある。
国語教育は、日本語を母語とし、コミュニケーションに特段支障をきたさない子どもたちを主な対象としているため、日本語力と認知力等にかかわるこのような問題が強く意識されることはなかった。しかし、日本語を母語としない子どもたちに対しては、このような問題点も視野に入れ「伝え合う力」をめぐる様々な点において橋渡し的支援が必要となる。ここに「教科志向型」JSLカリキュラム「国語科」(以下、「JSL国語科」とする)が取り組むべき課題がある。
3.2 「教科志向型」JSLカリキュラム「国語科」のねらい
国語科の目標は、言語の教育として言語能力を育成するとともに、国語を尊重する態度を育てていくことであり、これらの能力や態度を、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」それぞれの領域の特性を生かした言語活動を通して育成することを基本としている。したがって、JSL国語科のねらいは、国語科の言語活動に参加し、日本語で「学ぶ力」を獲得できるよう支援することである。
国語科の言語活動は、国語による言語能力の育成を目的としたものであり、言語活動に参加するためには、文字や表記などの習熟が重要な要素となる。また、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」それぞれの言語活動に参加する中でも、日本語を母語としない子どもたちにとっては、「伝え合う力」の育成に特に困難を伴うため、このための支援が重要である。このため、JSL国語科のねらいとする「学ぶ力」では、1.言語活動に参加するための言語事項や語彙にかかわる「学ぶ力」、2.「伝え合う力」を身に付けるための「学ぶ力」の獲得を重視している。
日本語を用いた「伝え合う力」の向上は、子どもたちが明るく生活できるための力となる。単なる言葉の伝達ではなく、単なる文字の読み書きではない部分に子どもたちは悩んでいる。このような状況を踏まえ、JSL国語科の目指すものは、言語そのものの伝授や習熟を目的とするものではなく、むしろ、子どもたちの「生きる力」としての言語力を育てることを最大のねらいとしている。「伝えたい」という意志と、「伝わる」という自信をもつこと、「相手が理解できる」「理解したい」という気持ちをもち、少しでも他者と豊かな言語活動を行い、言語を手がかりとして論理的に思考する力や豊かに想像する力を育成し、言語に対する感性を養っていけるようにするところにJSL国語科の意義とねらいがあると考える。それゆえJSL国語科では、日本語を母語としない子どもたちの日本語をより豊かに洗練されたものにすることと同時に、人間として現在発達途上にある子どもたちの情緒面や人間性の面での成長を支援することが目指されることになる。「伝え合う力」の獲得を通して子どもたちの豊かな人格形成の面での育成を支援することもJSL国語科の目標なのである。
3.3 JSL国語科の授業の構造
3.3.1 言語活動
国語科においては、目的や相手、場面や状況が具体的に設定された場における言語運用の学習を通して、実際の生活の場において生きて働く力としての言語能力を身に付け、それを豊かな言語生活の営みや創造に生かしていくことが大切である。このため、国語科においては、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」それぞれに示す内容の指導を、具体的な言語活動を通して行うものとし、学習指導要領では言語活動例を示している。国語科教科書は、そうした言語活動が十分に行われるよう単元を構成している。国語科がその指導内容において他教科と大きく異なる点は、この部分にあるといってよいだろう。このような単元構成の背景にある考え方は、言語運用力を身に付けさせようとする日本語指導の方針や目的と部分的に重なりあっており、国語指導と日本語指導の共通性が見出される理由ともなっている。
JSL国語科では、この「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」それぞれの指導のために行われる言語活動を基本的な授業の構造ととらえた。
3.3.2 支援の構造
3.3.2.1 言語活動の支援
国語科では、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導のために言語活動が位置づけられており、その活動の内容は領域それぞれに示される内容(=(イコール)学習スキル)により異なる。JSL国語科では、互いの立場や考えを尊重しながら言葉で「伝え合う力」などを高めていくための「学ぶ力」獲得のための支援を、それぞれの領域の学習スキルを身に付けるための言語活動を基本単位として整理することにした。これが、国語科AU(Activity Unit)である。国語科AUは基本的には、小学校学習指導要領の国語科の各領域の指導事項に基づく内容になっており、それは、国語科における指導の着眼点・ねらい、また目標としての到達点ともいえるもので、国語科の概念知識の獲得や抽象的学習の基盤形成に不可欠なものである。
トピック型JSLカリキュラムにおけるAUは、「体験-探求-発信」という学習活動の時間的な展開パターンにしたがって整理されていた。「教科志向型」JSLカリキュラムにおける他の教科も基本的にはこのような時間的な展開パターンに基づいて学習活動を整理している。しかし、国語科においては学習活動の時間的な展開は多様であり、それをパターン化することは教科の特性としてなじまない。このため、上で示したような言語能力別の分類を行うことにした。
また、トピック型JSLカリキュラムにおけるAUは、学習活動を構成している下位活動を最小単位にまで分割したものであったが、国語科AUでは、例えば「目的に応じた『伝え方のパターン』が分かる」といったより大きな単位となっている。これも、国語科の教科としての特性によるものである。この単位に言語活動を具現化させるための題材や素材、テーマ・話題、それらに対する子どもたちの認識や思考、想像などが組み込まれることで具体的な学習活動が構成されることになる。
以下に、国語科AUの形式で整理された学習スキルの一部を例として示しておく。学習スキル一覧は資料1として添付するので参照されたい。また、国語科AUの具体的な活用方法については「3.4授業の作り方」で述べる。
<話すこと・聞くこと>
- より具体的な相手意識をもち、伝えたいことを、順序や筋道を立てて、相手に伝わるように話す。
- 目的や相手に応じた「伝え方のパターン」が分かる。
- 相手の伝えたいこと、大事なことを落とさないように聞く。
- 聞く際に、話し手が伝えたいこと、話の中心、意見などを述べる時のパターンが分かる。
- メモをとりながら聞きとることができる。
- 「話し合いのパターン」が分かる(意見に理由をつけて話す。事実と意見を分けて話す等)。
<書くこと>
- 具体的な目的や相手を明確にし、どうしたら伝えたいことが伝わるか(「何を」「どう」書けば相手に伝わるか)を考えて書く。
- 目的や相手に応じた「伝え方のパターン」が分かる。
- 「伝えたくなる」ような気持ちをもつ(「伝えたくなる」ような目的、相手を設定する)。
- 書く題材に必要な事柄を集める方法が分かる。
- 人に尋ねるときのパターン(言い回しや言葉)、記述の仕方のパターンが分かる。
- 本などから情報収集をする方法が分かる。
- どう文章を組み立てれば、相手に自分の考えを正しく伝えられるかを考える。
- 自分の考え、思い、気持ち、意見、伝えたいことを表現するための言葉、言い方が分かる。
- 文や語と語のつながりを表す言葉が分かる。
- 目的に応じて、簡単に書いたり詳しく書いたりできる。
- 文章の間違い(細かい部分ではなく、正しく相手に伝えることができない間違い)を見つけることができる。
- 表現の効果などについて工夫する方法が分かる。
<読むこと>
- 自分から進んで本を読める。
- 学校図書館を利用して本を読める。
- 時間や事柄などの順序に着目し、内容を大筋でつかむことができる。
- 中心や要旨をさす言葉、時間を表す言葉などが分かる。
- 場面の様子、場面の移り変わり、情景などについて想像できる。
- 場面の移り変わりや情景を表す言葉が分かる。
- 挿絵や写真などから、物語・説明文の内容を推察できる。
- 登場人物の心情や、考え方を表す言葉が分かる。
- 読みとった内容について、自分の考えを持てる。
- 疑問に思ったことに基づいて、必要な情報を得るために、細かい点に注意して読むなど、効果的な読み方ができる。
- 文章の区切り目や大事な言葉を、明瞭に声を出して読める。
- 情景描写や会話など、その表現の着目して声に出して読める。
3.3.2.2 言語事項指導の支援
日本語を母語としない子どもたちが言語活動を通して「伝え合う力」を身に付けていくためには、言語活動にただ参加させるだけではなく、同時に正しく理解し(聞く・読む)、正しく表現(話す・書く)するための「言語事項」の習熟を図ることが必要となる。このような言語事項の指導は、話し言葉から書き言葉への移行を体験させ、共通性と相違性に気づかせること、及び、漢字仮名交じり文による理解力を身に付けさせ、漢字仮名交じり文による表現力を育成することに結びついていく。具体的には、次のような項目について指導を行うことになる。
- 発音・発生:母音、子音、イントネーション、アクセント、抑揚
- 文字:平仮名、片仮名、漢字、ローマ字
- 表記:仮名遣い、送り仮名、句読点、改行、符号
- 語句:語句の性質、語句の意味、辞書利用、語感、
- 文構造:主述関係、語句のかかわり、意味の切れ目と続き方
- 言葉遣い:敬体・常体、敬語、共通語、地域語
- 文語調:文語文
- 言語認識:言語の役割、国語の特質、話し言葉と書き言葉
JSL国語科では、これらの言語事項の習熟を支援する観点から、具体的な活動に即して国語AUによる整理を行っている。言語事項にかかわる学習スキルについても、言語活動と同様に資料1「学習スキル一覧」に示しているので参照されたい。
3.3.2.3 教科固有語彙
教科固有の学習基本語彙の指導も不可欠である。学習上の基本語彙・概念が理解できていないために、学習に困難を感じている子どもたちが少なくないからである。そこでJSL国語科では、教科固有の基本的な語彙・表現を「教科固有語彙」と名付け抽出することとした。語彙の選定に際しては、主に「国語科学習基本語彙一覧表」(井上一郎『語彙力の発達とその育成-国語科学習基本語彙選定の視座から-』明治図書、2001年)、「小学校国語科学習用語表」(297ページ以下)を参考にしている。資料1「学習スキル一覧」にその一部を抜粋して掲載しておく。詳細な一覧に関しては、本冊を参照されたい。
「教科固有語彙」について特に留意すべき点は、それが「指導すべき語彙、覚えるべき語彙」ではなく、「JSL国語科で扱う際に必要な学習語彙参考例」であるということである。語彙の学習自体が目的なのではなく、JSL国語科の主要な機能である国語科の言語活動への橋渡しの一環として必要な語彙を習得させることを明確に意識していただきたい。
ここまで説明してきたJSL国語科の枠組みをまとめると下図のようになる。この図では、JSL国語科の学習活動の基盤が、「学習スキル(話す・聞く、書く、読む)」「言語事項」「教科固有語彙」から構成されていることが示されている。
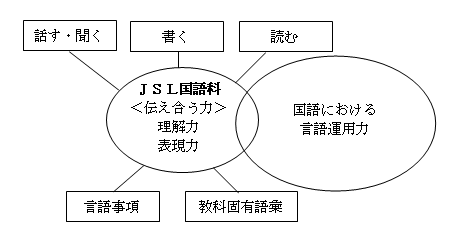
3.4 授業の作り方
3.4.1 基本的な考え方
JSL国語科に授業づくりは、「目標・ねらいと場の設定」「学習スキル・国語科AUの選択と具体化」「実際の指導とフィードバック」という三段階で展開する。以下に、その基本的な流れを示す。
第1段階:目標・ねらいと場の設定
まず、具体的な学習の場の設定を行う。この作業は、学習指導要領の学習内容を視野に入れながら、学習目標とねらいに基づいて進めることになる。ここで大切な点は、日本語を母語としない子どもたちに「伝え合う力」のどのような側面を身に付けさせたいのかを明確にしておくことである。より具体的にいえば、「場面の様子や移り変わりが読みとれていない」「『本を読んで内容が分かった。おもしろかった。』という喜びを味合わせたい」といった国語科の授業における子どもたちの問題点や目標にかかわる「教師・指導者の視点」をはっきりとさせておかなければならないということである。このためには日本語力、興味・関心など「子どもたちの実態」を配慮する必要がある。
第2段階:学習スキル・国語AUの選択と具体化
第一段階で明確化した「教師・指導者の視点」に基づいて、子どもたちに身に付けさせる学習スキルを決定する。具体的には、学習スキル一覧にある国語科AUから適切なものを選択することになる。あわせて言語事項、教科固有語彙の選択も行う。
続いて選択した国語科AUに具体的な題材、テーマ、活動を組み込み、指導計画・授業内容を決定する。題材の選択などにおいては、在籍学級における授業の進み方なども視野に入れておく必要がある。また、実際にどのような活動を行うのかという点については、国語科AU一覧にある活動例を参考にするとよい。言語事項、教科固有語彙の取り扱い方もここで決定する。
さらにこの段階では、日本語を母語としない子どもたちが抵抗感なく意欲的・能動的に学習が進められるような学習材(リソース)を用意し、支援の在り方、学習指導のバリエーションなどの検討も行う。
第3段階:実際の指導とフィードバック
日本語力が限定的な子どもたちへの学習指導を、分かりやすく示すことを心掛け、子どもたちの反応に留意しながら、授業を進行することになる。これは、教師・指導者の指導の方法や技術的な部分にかかわることである。
授業後、在籍学級における子どもたちの活動の様子を観察し、それを今後の指導にフィードバックすることも重要である。
3.4.2 授業づくりの実際:「読むこと(物語文)」領域を例に
次に、JSL国語科における実際の授業づくりの流れを「読むこと(物語文)」領域を例に示していく。授業づくりの流れは3段階8局面からなる。具体的には、次のとおりである。
| 第1段階 | 1.子どもたちの実態 |
|---|---|
| 2.教師・指導者の視点 | |
| 第2段階 | 3.学習スキル・教科固有語彙の決定 |
| 4.在籍学級での授業の調査 | |
| 5.指導計画、授業内容の決定 | |
| 第3段階 | 6.JSL国語科の授業 |
| 7.在籍学級の授業 | |
| 8.取り出しでの補習授業 |
では、各局面における教師の判断や考慮する内容を具体的に想定しながら、授業づくりの全体的な流れを示していこう。次頁で示す授業づくりの流れは、読むこと(物語文)に限らず、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」そして言語事項の領域においても同様であって、日本語を母語としない子どもたちへの指導を念頭において、国語科の学習指導をどのように具体化するかを示していると理解していただきたい。
| <第一段階> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
 |
|
 |
|||||||||||||
 |
<第二段階> |
 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
以下では、授業づくりの流れにおける各局面ごとに、教師・指導者の判断すべきことや行うべきことを解説する。
- 子どもたちの実態/教師・指導者の視点
子どもたちの実態を把握し、どんな力を身に付けさせたいのかを明確にする。 - 学習スキルや教科固有語彙の決定
子どもたちの実態と在籍学級での授業の調査をもとに、学習スキル一覧、教科固有語彙一覧を参照して、授業で具体的に身に付けさせたい学習スキル、国語科AUや教科固有語彙を決定する。 - 在籍学級での授業の調査
国語科学習指導要領では、「指導内容」を具体的に示すものではないために、何をどう指導していけば日本語を母語としない子どもたちに力を付けていくことになるのか、ということを、教師・指導者が見極めていかなければならない。したがって、「在籍学級の授業参加にすぐに生かせる」授業づくりのためにJSL国語科では「在籍学級の国語科の授業では、どんな授業・活動を行うのか。それによって、どんな力の育成をねらっているのか」を把握する作業が、非常に大切な手続きとなってくる。在籍学級で行われる授業を十分に調査し、その授業に参加するのに必要な学習スキル、国語科AUや教科固有語彙を子どもたちの実態に合わせることで、JSL国語科としての授業が構想され具体化してくる。 - 指導計画、授業内容の決定
その授業で具体的に身に付けさせたい学習スキル、国語科AUや教科固有語彙を決定した後で、その学習スキルを育成し、教科固有語彙を習得させるための学習指導計画、学習内容、学習活動を決める。 - JSL国語科の授業
授業計画をもとに、「支援」「学習指導のバリエーション」に留意しながら、授業を展開する。学習スキルの習得をより確実なものにするため、子どもたちの実態に合わせた支援、バリエーションを持たせた活動を仕組んでいく。 - 在籍学級の授業
子どもたちは、JSL国語科の授業後に在籍学級での授業に参加する。JSL国語科で身に付けられた力が在籍学級の授業で生かされているかを検証すると同時に、在籍学級で身に付けられなかったことを洗い出す。 - 取り出しでの補習授業
在籍学級での授業で身に付けられなかった学習スキル、国語科AUや教科固有語彙、あるいはその他のつまずきなどを整理して、取り出し指導にフィードバックし、補習授業を行う。
3.4.3 指導案のフォーマット
JSL国語科における授業づくりは、以上のような3段階8局面の流れで行われる。このうち第2段階までの作業は、具体的には指導案の作成というかたちをとることになる。以下で、JSL国語科における指導案のフォーマットについて説明する。もちろん、このフォーマットは個々の教師・指導者による授業づくりを縛るものではない。一つの参考例として理解されたい。
次頁に実際のフォーマットを示す。
〈指導案フォーマット〉
単元名「○○○○○(丸丸)」 ‐活動の具体化や学習のねらいを具体化した副題‐
- 領域
- 対象学年
- 指導時間数
- 指導形態(取り出し・在籍学級)
- 単元の設定理由とねらい
国語科の単元設定の理由やねらいとともに、JSL国語科としての単元設定の理由やねらいを示す。これに加えて日本語を母語としない子どもたちへのサポートに関しては、国語科の学習への橋渡しとしてのポイントなども単元のねらいに応じて示すようにする。 - 学習活動過程(各局面における伸ばすべき国語力・日本語力、学習支援・指導と学習材)
単元の指導計画、及びその学習過程が具体的に分かり、各局面における学習活動によって伸ばすべき学習スキル(国語科AU)を明示するとともに、その局面における学習支援・指導やそれに必要な学習材を示すようにする。なお、学習活動過程は以下のような枠組みで示す。
学習活動(具体的な言語活動) 次・時間
各局面における伸ばす学習スキル(国語科AU)
学習支援・指導と学習材 - 単元の指導目標
指導の目標を示す。国語科の目標だけではなく、「言語事項」「語彙」など日本語指導にかかわる目標も示すようにする。「5単元の設定理由とねらい」「6学習活動過程」に示したものを簡潔に整理して示すようにする。 - 支援・指導と学習材(リソース)
主に日本語指導にかかわるところの学習支援・指導の在り方とこの単元を行うに当たって必要となる学習材やその使い方を、簡潔にかつ具体的に説明するようにする。
学習材は、読む対象としての学習材以外に、学習過程において支援・指導が必要になる局面ごとに、子どもたちを支援するのに必要な学習材(教科書教材、他の図書資料、手引き、ワークシート、AUカード、語彙リスト、教具、人など)を示す。 - 学習指導のバリエーション
以下のような項目について取り上げて、想定される可能性を示す。- 日本語学習歴や学年、母語、出身国の違いへの対応の可能性
- 指導形態(学習集団が取り出しか在籍学級か)の異なる場合
- 学習活動の難易や広がりの変化、発展
- 学習指導形態の変化
指導案フォーマットの項目ごとに授業構想の視点を解説する。
1.領域
JSL国語科における学習活動は、学習指導要領国語科の3領域1事項(「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」「言語事項」)の分類に基づいている。教師・指導者は、国語科の学習を行うに当たって、3領域1事項の中で、どの力が身に付き、あるいは不足しているのかを判断し、その上でどのような力を身に付けさせたいかを初めに決定する。子どもたちの言語知識や言語能力を観察し、その能力に応じて子どもたちに身に付けさせようとする国語科の学習スキル及び国語科AUを、資料1「学習スキル一覧」を参考にしながら決定して欲しい。
2.対象学年
ここでいう「対象学年」は、「トピック型」JSLカリキュラムと同じく、「授業で取り扱う学習内容がどの学年の学ぶ力に相当した力を必要とするか、どの内容に関連があるかを示すもの」である。トピック型と同様に教科志向型においても子どもたちの知的レベルや知的好奇心からはずれないような配慮が必要である。特に、高学年の子どもたちに対しては、活動は同じだが話題や題材を高学年向きにするというような配慮が必要になってくる。さらに、高学年では読み物教材の語彙や漢字への指導が難しくなるので、それに応じた充分な学習材研究が求められる。
3.指導時間数
指導時間は、単元や指導形態に応じて変わってくる。在籍学級において行われる単元自体の指導時間を示す場合もあれば、その単元に必要となる基礎的な言語学習を行う取り出しの授業に要する指導時間を示すこともある。単元設定のねらいや指導形態を工夫しながら、柔軟な時間運用をすることが望まれる。なお、ここで示しているのは、想定している指導形態におけるおよその時間であって、取り出しの授業時間数が少なく、2時間扱いの授業でも2週間かかるような場合もあるので、あまり活動が間延びしてしまわないような配慮が必要である。
4.指導形態
指導形態では「取り出し指導」や「在籍学級」など、子どもたちがその活動で学ぶのに適した指導形態を示している。
5.単元設定の理由とねらい
現在の学習指導要領では、言語活動例が示されていることからしても一まとまりの活動が組織され、その活動を通して「伝え合う力」を身に付けさせようとしている。それは、子どもたちに意欲的で能動的な学習を成立させることにもなり、指導方法として効果的ではある。しかし、一方で活動が行われていれば、学習は成立しているとどうしても見られがちになってしまう。教師・指導者の方に明確なねらいや支援・指導を行う局面が明確でなければ、活動があっても学習が成立していないこともあるという点に注意されたい。このようなこともあり「単元設定の理由とねらい」では、単元中の活動によってどのような言語活動を組織し、どのような言語知識や言語能力を身に付けさせようとするかを明示している。JSL国語科においても同様であって、そのような言語活動を組織することによって、学習のねらいや視点、さらに国語科の学習への橋渡しとしての意味づけを意図的に示していくことが大切であると考えられる。
6.学習活動過程
本単元を行うに当たって、学習活動過程の局面ごとに「伸ばすべき国語力・日本語力」「学習支援・指導と学習材(資料)」を学習過程に沿って示している。各局面ごとに、どんな学習スキルや言語事項、語彙をねらうのか、そしてその場合、どのような支援・指導上の注意が必要か、支援・指導に必要な学習材はどのようなものかなどを考慮しながら学習計画を立てている。
7.単元の指導目標
「単元設定の理由とねらい」で構想している学習指導の目標を簡潔に示している。学習指導要領を一方で視野に入れながら、日本語を母語としない子どもたちを対象としたJSL国語科として重視する「伝え合う力」に関する目標も具体的に示すことによって、単元での学習内容が絞り込まれてくる。そして、学習活動過程を構想するときに、この目標を達成するためにどのような学習スキルの習得や学習語彙の指導が必要なのかを考えていく。
8.支援・指導と学習材(リソース)
本単元で扱う学習材の留意点や、他の学習材を与えるなど支援・指導などをしていく上での留意点を示している。教科固有語彙に関しては、「本単元に関わりのある学習語彙」として、主に「国語科学習基本語彙一覧表」(井上一郎『語彙力の発達とその育成-国語科学習基本語彙選定の視座から-』明治図書、2001年、334ページ以下。これに加えて「小学校国語科学習用語表」〈同書、297ページ以下〉を参照している。資料1「学習スキル一覧」における各領域ごとに示されている教科固有語彙もこの資料によっている)から抜粋して載せている。これは「指導すべき語彙、覚えるべき語彙」ではなく、「この単元を扱う際に扱うことが可能な学習語彙」「その語彙を学ぶ機会として本単元を使える」ということでとらえてもらうことと同時に、この語彙を意識することがJSL国語科における課題の一つである国語科学習への橋渡しの視点を意識することになるからである。
9.学習指導のバリエーション
本単元を扱う上で、子どもたちの実態などに合わせた指導上のバリエーション、国語科で具体的に付けたい学習スキルや教科固有語彙の習得のための別アプローチなどを示してある。子どもたちの実態や学級・授業の状況に応じた、柔軟な支援・指導が望まれる。
お問合せ先
総合教育政策局国際教育課
-- 登録:平成21年以前 --




