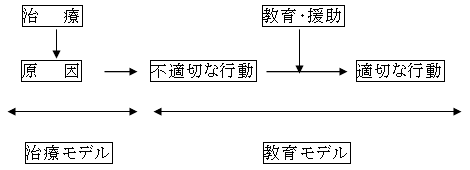- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 海外子女教育情報 > 施策の概要 > 在外教育施設安全対策資料【心のケア編】 > 第3章 スクールカウンセリング
CLARINETへようこそ
第3章 スクールカウンセリング
| 1. | スクールカウンセリングとは |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクールカウンセリングは、児童生徒の心理的な発達を援助する活動であり、「心の教育」や「生きる力を育てる」などの学校教育目標と同じ目的を持つ活動である。米国などでは、スクールカウンセリングは専門的資格を持つカウンセラーの業務として扱われているが、在外教育施設においては、学校カウンセリングを、カウンセリングマインドを持った教員が、全ての児童生徒を対象とし、児童生徒の人間形成に関わる諸問題に対して援助していく総合的な教育活動と位置づけている。 カウンセリングは、人間の心理や発達の理論に基づく対人援助活動であり、個人の成長を促進し対人関係の改善や社会的適応性を向上させることから、様々な領域の対人援助サービスの専門家がそれぞれの場面で活用している。学校教育においても、カウンセリング心理学に基づくアプローチが児童生徒の人格形成や様々な問題解決に有効であることから、教員を中心としたスクールカウンセリング活動が実施されている。 海外で暮らす子供達とその家族は、日本国内とは異なる文化、生活習慣、言語環境で生活しており、言語取得、学習、健康、進路、対人関係などの多様な問題を抱えている。また、治安の問題や自然災害などにより危機的な事態に遭遇する可能性も高く、国内以上に地域・家庭での教育的な経験が不足する傾向があり、子供達の「生きる力」を育てることが重要な課題となっている。これらの諸課題に対処するために、在外教育施設においては、スクールカウンセリング活動に積極的に取り組むことが必要といえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | スクールカウンセリングの特徴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクールカウンセリングには、次のような特徴がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 開発的カウンセリング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発的カウンセリングは、児童生徒の心理的な発達を促進し、社会生活で必要なライフスキルを育て、困難な問題に対処する力やストレス耐性を高める活動である。活動の視点として、「人権教育」「ライフスキル教育」「キャリア教育」などがある。これらは、生涯にわたる発達課題達成の支援であり、全ての児童生徒が対象となる。教科学習や特別活動、総合的な学習などの学級、学校全体の教育活動を通して実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <人権教育> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人権教育では、全ての国々のひとり一人が、人として生きる権利を平等に持っていること、個人は自らの人生を主体的に生きる自由があるが他人の権利を奪ってはならないこと、その為に話し合いが必要であり、その結果、お互いの権利を守るために約束、ルール、法律、憲法などが決められていることなどを理解させる。 【基本的人権の児童生徒への説明例】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ライフスキル教育> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHO(世界保健機関)は、どの時代、どの文化社会においても、人間として生きていくために必要な力があるとし、それをライフスキルと定義した。 「ライフスキルとは、日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するために必要な能力である。」(World Health Organization;Life Skills Education in Schools 1994より引用) ライフスキルには、次の10のスキルがある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <キャリア教育> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア教育とは、児童生徒が、自己の将来の夢、目標、希望を持ち、その実現に向け、必要な知識や技能を学び、社会人として自らの人生を主体的に生きる力を育てることである。 在外教育施設において、国際結婚による子供達の比率が高まっており、日本に帰国することを前提とする進路選択だけでなく、現地の学校に進学あるいは就職するケースも増えてきている。このようなケースでは、中学卒業後の進路を選択することが、国際人としてどのように生きていくかという人生の岐路であることがある。一方、治安や環境上の制約から生活の基本的な体験が少なく、社会体験や職業についての理解がほとんど育っていない児童生徒もいる。 キャリア教育では、
在外教育施設で培われた国際的な経験は、将来大きな成長の糧になると考えられるが、日本社会は異文化や個性を尊重する精神が育っていないため、これらの体験を否定的にとらえる傾向がある。このような国際的な環境で育つ児童生徒のキャリア教育は、派遣教員自身が国際理解・現地理解を深めるとともに、キャリア意識を持ち実施していく必要がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <対話のある教育> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対話は、自立した個人と個人の対等な相互尊重、相互理解による協働活動である。対話を通じて、自己理解、他者理解が深まる。話を聞くことは、相手の存在を認め尊重することであり、理解することは、自分とは異なる考えを受容することである。話すことは、自己を尊重する行為であり、話を傾聴し受容してもらう体験は、自己信頼感・他者信頼感を育てる。対話により、意識のレベリングが行われ、協働作業が可能となる。また、相互尊重の対話により創造的な思考が活性化する。 教育における対話には、次の種類がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 予防的カウンセリング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「対処できないと予想される生活環境ストレッサーがある」「緊張や不安が強い」「不登校傾向がある」「不定主訴がある」などそのまま放置しておくと問題の発生が予測される場合には、個別的な配慮が必要となる。予防的カウンセリングは、児童生徒の話を良く聴き、児童生徒の気持ちを理解するとともに、児童生徒を取り巻く環境・状況を正しく把握し、適切なアドバイスやスキル教育、環境(学級や家庭など)調整などを行い、問題の発生を未然に防いでいく。ラポールの形成と情緒的な支えが重要であり、スモールステップでスキルアップを行い、自己肯定感を高めていく。 問題点や原因を指摘するのではなく、どのように解決したいのか、解決に役立つリソースは何か、具体的にできる行動は何かを共に考え、実践する中で、自信を育てていくことが問題の発生を未然に防ぐことになる。第2章「 個人の対処能力や解決法で対処できない課題に直面した場合に、一人で問題を抱え込まないよう気軽に相談できる体制を事前に作ることが大切である。その為には、日常的な関わりの中で信頼関係を構築することが基本となるが、担任には相談できない問題もあり、相談箱の設置、相談日の設定など、気軽に相談できるシステムを考えることが必要である。また日常から児童生徒を良く観察し、授業時間以外の時間帯(休憩時間、放課後、家庭や休日など)で起きていることも把握するように心がけることが大切である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 問題解決的カウンセリング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題が発生した場合は、 問題解決には、個人に対するアプローチだけでなく学級や家族などの本人を取り巻く環境へのアプローチも重要である。その環境づくりのためにも、チームによる教育相談の体制を構築することが望ましい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <チームによるケース会議> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童生徒の全体像や取り巻く環境について正しく理解するためには、児童生徒にかかわる人達の情報を総合的・多面的に検討する必要がある。 また、その問題解決についても、一人での発想には限度があるが、チームによるケース会議を行うことにより、集団の知により、より良い解決策を見出すことができる。また、学校・教職員全員の一貫性のある関わりは、児童生徒の心理的混乱を低減させ、相乗的な効果を生み出す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ストレスマネジメントの活用> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題の予防やその解決に、ストレスマネジメントのアプローチは効果的である。ストレスマネジメント教育により当事者が問題とその影響を理解できる考え方を持つことで、セルフケアが可能になる。多様な問題や複合的な要因の影響について客観的に検討し、日常の生活、教育活動の中で実践可能な方法を見出し、実践していく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <専門機関との連携> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部機関・専門機関との連携、地域や保護者会などの協力者の依頼など、問題解決のためのネットワークを構築しておくことが必要である。情報インフラ整備の進んだ地域では、インターネット、E-mailや国際電話を利用して日本国内の専門機関との連携も可能である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | カウンセリングのプロセス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウンセリングのプロセスは、対話や関わりを通じて進展していく。この目に見える対話や出来事と平行して、本人の心の中には内的な作業のプロセスが存在する。カウンセリングのアプローチは、この本人の内的プロセスの変化に焦点をあてた対話を行っていく。本人自身が、自分自身のことを振り返り、自己理解を深め、問題解決に主体的に取り組み、自己成長へと向かう内的変化を促進することが、カウンセリングの本質ともいえる。カウンセリングでは、おおよそ次のようなプロセスが展開されていく。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --