- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 海外子女教育情報 > 施策の概要 > 在外教育施設安全対策資料【心のケア編】 > 第2章 心のケア 各論
CLARINETへようこそ
第2章 心のケア 各論
| 1. | ストレス対処の基本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレスに対処するためには、ストレス反応の発生メカニズムの各要因である「ストレッサー」「認知的評価・対処能力」「ストレス反応」に、それぞれ働きかけることが必要である。各要因への対処法として11の方法を取り上げる。 これらのストレス対処法を図8に示す。 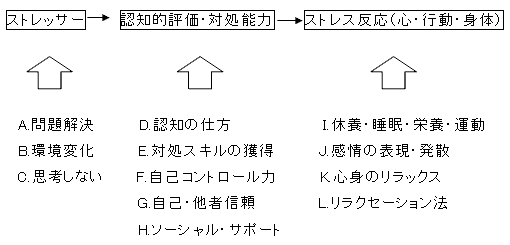 図8 ストレスへの対処法
また、ストレス対処法の児童生徒への説明図を図9に示す。 ストレス理論を理解することで、今まで自己コントロールできなかったストレス反応が対処可能であることを理解(認知的評価が変化)することになる。 ストレッサーには、生活環境ストレッサー、外傷性ストレッサー、心理的ストレッサーがあるが、心身の防御システムは一つである。従って、ストレッサーの種類に関わらず、対処の基本的な原理は同じである。外傷性ストレッサーに対しては、人によってはストレス反応とは異なるトラウマ反応が生じ、PTSDが発症することがあるので、第2章 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ストレッサーへのアプローチ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因となるストレッサーを取り除くことができれば、ストレス反応をなくすことができる。これはストレス対処法の最も基本になるアプローチである。ストレッサーは複合して作用するので、それぞれのストレッサーのレベルを低減し、その総和を下げることも重要である。原因となるストレッサーへのアプローチとしては次のような方法がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 認知・対処能力へのアプローチ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知的評価とは、ストレッサーが、どの程度の脅威であるのか判断することである。あるストレッサーがどの程度の脅威かという判断は、人によって異なる。それは、その判断に個人の性格や自己能力の評価、自信、信念などが関わっているからである。たとえば、自信がない人、物事を否定的に捉える人は、ストレッサーをより高い脅威と認知するが、自信がある人、物事を楽観的に捉える人は、同じストレッサーに対し、それほど脅威には感じない。このような、物事の捉え方や自信などの自己の能力の評価などの認知的評価は、ストレス反応に大きな影響を及ぼしている。従って、このような認知的評価を修正することが、ストレス状態を克服する有効な方法になる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ストレス反応へのアプローチ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 心身のリラックス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレス反応は、脅威であるストレッサーに対する心身の防御反応の結果であるが、本来機能すべき「休息の機能」が十分に活動していない状態にある。リラックス反応は、環境や刺激が、安全・安心で、脅威でないと判断したときに起きる反応であり、副交感神経系の活動が優位な状態にある。リラックス反応は、ストレス反応とは相容れない関係にある。従って、リラックスできる環境や刺激を積極的に確保し、リラックスすることで心身の回復機能を活性化させることが、ストレスによる様々な問題を解消することになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | リラクセーション法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リラクセーション法は、リラックス反応を誘導し、ストレス反応を低減させ、心身の回復機能を向上させる方法である。多くの文化圏で古来より様々なリラクセーション法が実施されてきたが、近年、医学的にもその有効性が確認され、ストレスマネジメントの方法として活用されている。リラクセーション法は、ストレス反応の軽減において即効性があり、訓練を続けることで心身の自律機能が回復し、ストレス反応が起きにくい体へと変化させる。 リラクセーション法には様々な方法があるが、セルフ・ケア法として行うことができる簡便な5つの方法を紹介する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 統合リラクセーション法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合リラクセーション法は、すでに効果の確認されているリラクセーション法を有機的に組み合わせ、その相乗効果により、より深いリラックスを簡便に誘導するリラクセーション法である。各種のリラクセーション法は、それぞれに特徴がある。筋弛緩法や呼吸法は身体のリラックス効果が高く、瞑想法や受動的音楽療法は精神的なリラックス効果が高い。一方、ストレス反応にも個人差があり、身体的緊張の高い人には、身体的緊張に効果の高いリラクセーション法を指導することが望ましい。震災などの場合に、大勢の人たちに個人にあった指導を実施することは大変な時間を必要とする。統合リラクセーション法は、このような個人差があっても、総合されたリラクセーション法のいずれかの要素が作用するため、集団での指導が可能である。また、誘導が平易であり、児童生徒がセルフケアとして実施できる特徴がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
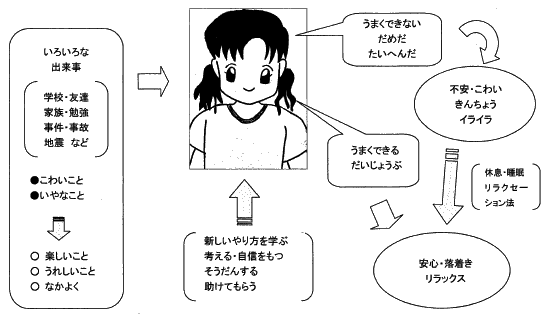 図9 ストレス対処法 説明図 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --