- 現在位置
- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 海外子女教育情報 > 施策の概要 > 在外教育施設安全対策資料【心のケア編】 > 第2章 心のケア 各論
CLARINETへようこそ
第2章 心のケア 各論
| 1. | 心のケアとストレス・マネジメント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危機管理において、「安全と安心の確保」が重要であると述べたが、安全確保のために避難する場合において、もし、大人達が恐怖と不安から混乱した状態で避難したとすると、子供達は「大人も対処できない異常な事態である」と受け止め、子供達も大きな不安と恐怖に怯えることになる。逆に大人たちが落ち着いて行動するなら、子供達は「大人達が対処可能な範囲の出来事である」と受け止め、大きな混乱を示さない可能性が高くなる。このように、子供の安心を配慮した行動や対処を取ることが、心のケアにおいては重要である。 心のケア活動を行うためには、人間の心身のメカニズムを理解し、援助する方法を学習する必要がある。また、人間の心身のメカニズムを理解することにより、多様な事態や様々な個人の症状に対して柔軟に対処することが可能となる。 人間の心身のメカニズムを理解し、援助に役立てるためには、「ストレス理論」に基づいて考えると理解しやすく、様々な場面で応用できる。 ストレスの概念は、一般に広く使用されており、保護者や児童生徒も理解しやすく、セルフケアの指導にも使用できるため、本編では、ストレス理論に基づいて心のケアの解説を行う。ストレス理論は、医学と心理学に共通する理論であり、多くの精神的症状や身体的疾患とストレスの関係及びその対処法が研究されている。ストレッサーに対する人間の心身のメカニズムや反応を理解し、ストレス反応を軽減あるいはストレス障害の予防や回復を行うことを「ストレスマネジメント」と呼ぶ。 子供達に「ストレスマネジメント」教育をすることは、ストレスについての正しい知識や対処方法を身につけ、セルフ・ケアができる力を育てることであり、困難な状況を乗り越える「生きる力」を育てる学校教育本来の目標と一致する活動といえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ストレスとは |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレス理論では、いろいろな出来事と、人間の行動や心身の反応との関係を、次のように説明している。その関係を図1に示す。 人間は、人生の中で様々な出来事(ストレッサー)に遭遇するが、その遭遇した出来事が自分の対処能力を超えた脅威であると感じる時に、ストレス反応と呼ばれる症状や行動を生じさせる。 図1 ストレスが起きるメカニズム
このストレス理論は、「自分の意思でコントロールできないものと理解していた情動や身体の症状が、自己コントロール可能である」という新たなパラダイムを提供することになる。この新たなパラダイムを受け入れるならば、自分を支配していた問題や症状がコントロール可能な対象へと変化することになる。 特に、被災者の心のケアにおいては、被災者にみられる情動反応の多くが「異常な状態に対する正常な反応」であることをしっかり伝え、理解を得ることが、混乱した心理状態から抜け出す大切なプロセスとなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ストレッサー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ストレッサー」には、日常生活で遭遇する様々な出来事や刺激が該当する。これらの「ストレッサー」には強さがあり、強いストレッサーは大きなストレス反応を引き起こす。 ストレッサーを、暑さ、寒さ、騒音、不快な刺激臭など物理的なものと対人関係のトラブルや別離などの心理社会的なものに区別するなどいろいろな分類が可能であるが、本編では「ストレッサー」の種類を大きく次の3つに大別する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ストレッサーに対する心身の防衛反応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生体にとって有害な出来事に出会った時は、危険から身を守るための心身の防御反応が生じる。天敵と出会った動物は、身を守るために、闘うか逃げるか、どちらかの行動をとる必要がある。どちらの行動をとるにしても、心身は、活動するための戦闘態勢を整えることになる。 このような戦闘態勢を整えるために、交感神経系と呼ばれる自律神経や副腎皮質ホルモンなどを分泌する内分泌系の活動が活発になる。 交感神経系の働きを、図3に示す。 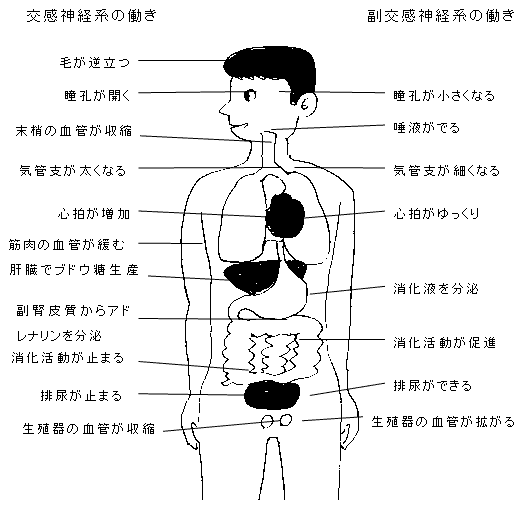 図3 自律神経系の働き
警戒するために、覚醒水準は高まり、敵が来るかもしれないという不安感情が起きる。目(瞳孔)は見開き、毛が逆立つ。活動エネルギーを全身に供給するために、肝臓ではブドウ糖が生産され、酸素を取り入れるために気管支が太くなり呼吸は速くなる。栄養と酸素を含んだ血液を全身に多量に送り出すために心拍(動悸)が速くなる。戦いで傷を負った場合の出血を防ぐために抹消の血管が収縮し、手足は冷たくなる。この様な戦闘の状況では、消化器系の活動が不要なため、その活動を停止し、食欲がなくなり、排尿や生殖器の活動も停止する。このような一連の身体の反応は、生体防御のための自然な反応と考えられている。 ストレッサーが加えられた後の心身の防御反応は、時間の経過とともに、大きく変化する。図4は、動物実験の結果をもとにストレスへの抵抗力が普段の正常値に対し、どのような変化をするか図示したものである。 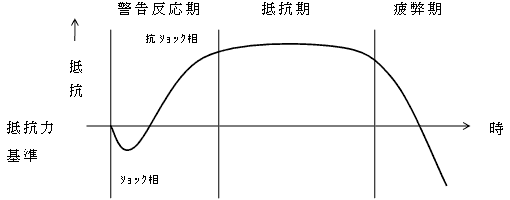 図4 ストレス反応の3相期の変化
(ハンス・セリエ 現代社会とストレス 法政大学出版局 1988) 警告反応期は、ストレッサーが加えられた直後の時期で、最初に抵抗力が低下するショック相を経て、抵抗力が高まる抗ショック相へと移行する。シヨック相では、身体的活動が低下し、抵抗力は正常値より大きく低下する。このような状態に対し生体は防御のために「闘うか逃げるか」の戦闘態勢を整え、抗ショック相に移行する。抗ショック相では、アドレナリンが分泌され、交感神経系の活動が活発になり、覚醒、活動水準が高くなる。時に過覚醒や過活動になることもある。このショック相、抗ショック相からなる警告反応期を経て、抵抗期へと移行していく。 抵抗期では、副腎皮質ホルモンなどが分泌され、身体の抵抗力が高まる。ストレッサーに対し活動性を高めてバランスを保っている状態である。この抵抗期は、心身の活動が活発になるため、休息とのバランスが崩れやすくなる。しかし、身体の防御機能にも限界があり、適応エネルギーが枯渇し、再び抵抗力が正常値以下に低下する疲弊期に移行し、ストレス反応が現れる。人間の場合、この抵抗期は約1週間から10日ぐらいといわれているが、様々な心理的・生活環境的ストレッサーの影響を受けるため、実際は複雑な過程をたどることになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ストレス反応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレス反応は、長時間ストレッサーの刺激を受けた場合や、強いストレッサーを受けた時に生じる生体反応であり、ストレッサーに対する生体の自然な適応反応と考えられている。ストレッサーの種類に関係なく、心身に同じ反応が起きること、また、その症状が全身に及ぶことから、「汎適応症候群」とも呼ばれる。人間の場合、ストレス反応は、心理的、行動的、身体的反応として現れる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ストレス状態が続くと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレス状況において、適切な対処行動がとれない時や、それが効果的でない場合、ストレス反応が生じるが、さらにこの状態が継続すると、ストレス障害と呼ばれる様々な障害や疾病へと進んでいく。 図5に、ストレスにより身体に現れる症状や心身症を示す。 また、ストレスによる障害や疾病には、次のようなものがある。
図5 ストレスによって身体に現れる症状
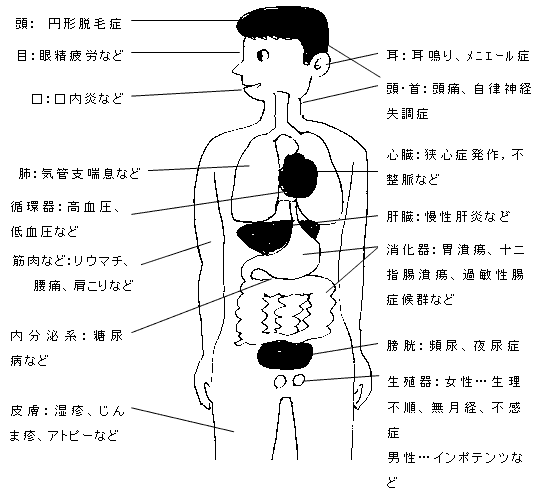 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | リラックス反応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッサーに対する戦闘態勢の継続によりストレス反応が生じるが、心身には非戦闘のときに、疲労を回復させるために休息をし、新たなエネルギーを取り入れるメカニズムがある。このような休息のための反応をリラックス反応と呼ぶ。リラックス反応は、安全・安心できる環境や刺激により、脅威でないと判断したときに起きる休息のための自然な反応である。 このリラックス反応のメカニズムを図6に示す。
図6 リラックスが起きるメカニズム
リラックス反応では、副交感神経系とよばれる自律神経系が活動する。 副交感神経系の働きを、図3に示す。心臓や肺を休ませるために、鼓動も呼吸もゆっくりとした速さになる。あらたなエネルギーを吸収するために、消化器系の活動は活発になり、食欲が増進する。排尿や生殖器の活動も元に戻る。睡眠は心身の疲労を回復させる最も休息した状態と考えることができる。私達は、昼間、活動しているときは、交感神経系の活動が優位であり、夜、睡眠している間は、副交感神経系の活動が優位になっている。 一日のサイクルの中で活動と休息のバランスが取れているときが健康な状態である。しかし、人間は、たとえ休息できる状態にあっても、頭の中で考える否定的な思考が心理的ストレッサーとなり、交感神経系の働きが継続してしまう傾向がある。このため、夜眠れない、休息できない状態が続き、ストレス反応やストレスによる障害が生じやすくなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 心のケアとリラックス反応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心のケアは、ストレス反応を取り除き心身を健康な状態に回復させること、あるいは予防することである。ストレス反応は、脅威であるストレッサーに対する心身の防御反応の結果であるが、本来機能すべき休息の機能が十分に活動していない状態と考えることができる。 従って、リラックスできる状態をつくり、心身の回復機能を活性化することが、ストレスによる様々な問題を解消・予防することになる。
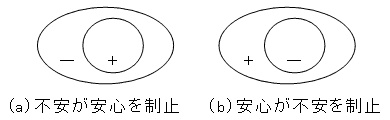 図7 逆制止の原理
心のケアを必要とする場合は、不安が安心を制止している状態といえる。心のケアでは、より大きな安心・リラックスを導くことにより不安を制止することが基本原理といえる。また、リラックス状態は、ストレス状態から開放された状態であり、心身の回復をもたらす副交感神経系の働きが優位なエネルギー充足の状態といえる。従って、心のケアでは、積極的にリラックス反応を導き、安心できる環境を整えていくことが大切である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --