|
資料2 サービス・サイエンスを巡る動向等について科学技術・学術政策局 1.サービス・サイエンスとは?社会科学やビジネスへの自然科学、工学の応用ないし、融合であるとされることが多い。 例えば、
本年6月に議員立法として成立した研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(研究開発力強化法)第47条において、 2.サービス・サイエンス振興の必要性等(1)日本におけるサービスの位置づけ我が国をはじめ主要先進国における産業構造の変化の中で、年々、雇用面を含め、経済に占める第3次産業の割合が増加し続けている。実際、第3次産業は我が国のGDPの約7割を占め、雇用の約3分の2を占めている。また、製造業においてもIT技術を利用した設計システム、製品のサポートなど事業におけるサービス部分が大きくなっていることが指摘されている。 (2)現状の課題 我が国経済が引き続き活力を維持していくためには、サービスを担う第3次産業を製造業とともに経済を支える「双発のエンジン」としていく必要があるが、現在、世界各国、特にアメリカにおいて、IT技術、数学を活用した新たなサービスが爆発的に伸張しているところであるが、我が国においてはサービス産業の国際的な展開が乏しいのではないか、また、アメリカ等に比べサービスのイノベーションが乏しいのではないかなどの疑問がある。 図 我が国の産業構造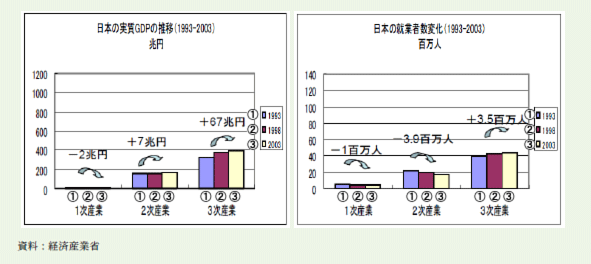 図 主要国における製造業とサービス産業の労働生産性上昇率の比較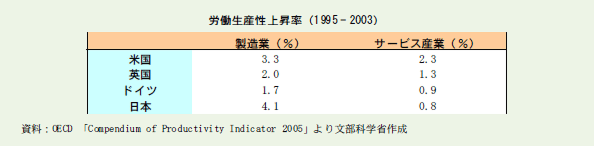 図 日米のサービス・セクターにおける研究開発費の推移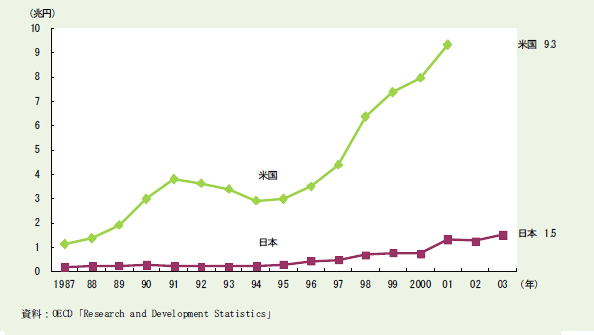 (3)サービス・サイエンス振興の必要性 サービス・サイエンスは、サービスが経済に占める割合の大きさ及びその成長率の大きさなどから、90年代以降、興隆を見たIT技術、バイオ技術などいわゆる「サイエンス型産業」に係る技術に匹敵、あるいははるかに上回る大きなインパクトを世界の経済に与える可能性がある。 3.世界各国におけるサービス・サイエンス振興の動き近年、米国を始めとして、世界の主要国がサービス・サイエンス振興の取組を開始。 (1)米国
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
