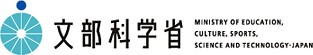ここからサイトの主なメニューです
|
| 1、 | 私的録音・録画問題の経緯等 |
| 「古くて新しい」という文言は、このためにあるのではないかと思わせるのが、著作物等の私的録音・録画の問題である。それは、情報伝達技術の開発普及によって生じる問題であり、将来また時を経て議論される問題になること必定であろう。 録音・録画技術がまだ開花してない明治32(1899)年施行の旧著作権法では、著作物の複製については、「器械的又ハ化学的方法ニ依ラ」ないで行うときのみ適法とされていた(第30条第1項第1)のであり、厳密にいえば、手写による複製が許されるだけであって、それ以外の、例えばいわゆるガリ版による複製も違法とされていたのであった。ガリ版による複製はひろく行われていたが、その複製部数が社会的問題になるだけのものには至らず、事実上、これを違法視することなく時は推移していたのである。 著作物の録音・録画による私的複製が、わが国でようやく問題視されるようになるのは、昭和40年代に入ってからといっても間違いではないであろう。昭和45年に現行著作権法が制定され、その第30条には、「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる。」と規定されている。著作物の種類を問わず、また、複製手段を問わず、それが個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における複製であれば、それは自由に合法的な複製とみられたのである。 しかし、現行著作権法制定にあたり、その衝にあった衆議院文教委員会は、昭和45年4月に法案に対する附帯決議を寄せているが、そこには、「今日の著作物利用の手段の開発は、いよいよ急速なものがあり、すでに早急に検討すべきいくつかの新たな課題が予想されるところである。よって、今回改正される著作権制度についても、時宜を失することなく、著作権審議会における検討を経て、このような課題に対処しうる措置をさらに講ずるよう配慮すべきである。」と述べられている。参議院文教委員会も同旨の決議を付しており、その後、衆参両院文教委員会からは、昭和53年,59年,60年,61年,63年,平成元年,3年の著作権法改正の都度、重ねて同旨の附帯決議が寄せられている。平成4年には、私的録音・録画補償金制度が導入されたことに伴い、「私的録音・録画問題に関する補償金制度が、ユーザー等の信頼を得て円滑に運営されるため、指定管理団体が行う権利者への補償金の分配、私的録音・録画以外の用に供するための特定機器及び特定記録媒体を購入する者への補償金の返還及び著作権等の保護に関する事業等のための支出が適切に行われるよう努めること。」という附帯決議が衆議院文教委員会から寄せられており、参議院文教委員会からも同旨の附帯決議が寄せられている。 これらの附帯決議に応えるためにも、著作権審議会が設置した第3小委員会、第5小委員会、第10小委員会で、著作物の私的録音・録画による複製問題解決のために鋭意努力したことは、著作権法施行100年を記念して発行された「著作権法百年史」に述べられている。 |
|
| 2、 | 西ドイツの課金制度とわが国の補償金制度−製造業者等の協力義務− |
| 著作権法百年史には、わが国の著作権にかかわる諸問題について網羅的に述べられている。ここでは、そこに詳しくは触れられていない問題点の若干を述べることにしたい。著作物等の私的録音・録画問題と密接に係わる問題であることはいうまでもない。 著作権審議会第5小委員会の結論を受け、文化庁は、著作物等の私的録音・録画問題の解決を希望して、社団法人著作権資料協会(現社団法人著作権情報センター)に対し、「著作権問題に関する懇談会」を設立して、著作物等の私的複製について利害の衝突する関係者間の合意形成にむけての努力を期待する旨を要望した。懇談会は、関係権利者代表、関係メーカー代表、学識経験者の3者によって形成され、35回にわたる審議の結果、その審議の「まとめ」を昭和62(1987)年4月に公にしている。文化庁に提出されたこの「まとめ」は、その中で著作権審議会に第10小委員会を設置することを勧告しており、かくして設置された第10小委員会に、その後、提出された日本音楽著作権協会芥川也寸志理事長の「私的録音録画問題と報酬請求権制度の導入について」(昭和63年8月)という著作権者側の意見,メーカー側を代表する社団法人日本磁気メディア工業会会長,社団法人日本電子機械工業会会長連名の「私的録音・録画と報酬請求権制度問題に関する意見書( 第10小委員会は、昭和62年8月に発足しているが、その第12回会議(平成元年11月)で、作業を効率的に進めるために、学識経験者5名をもって構成するワーキング・グループを発足せしめている。 懇談会の発足時から、その審議を悩ませたことのひとつは、無批判的に「西ドイツ方式」を日本で採用せよという声であった。西ドイツで課金(報酬請求権)制度が採られたのは1965年の改正著作権法によってであり、世界で初めてこの制度を採用したことは周知のとおりである。それまでは、1901年の「文芸・音楽著作物に関する著作権法」(LUG)や、1907年の「美術・写真著作物に関する著作権法」(KUG)が施行されていたのである。 LUG第15条は、著作権者の複製権を明記するのに続いて、「尤も個人的使用の為に著作物を複製することは認められるが、その複製が財産的利益を目的としないことを要件とする。」と規定し、KUG第18条は、「個人的使用を目的とし、かつ、無償で行われた複製は適法とする。」と規定していた。著作物等の録音による私的複製にもこの自由使用の規定が適用されることの可否をめぐって議論されることになったのである。1901年や1907年当時は、著作物の録音・録画に供される機器や記録媒体は存在しなかったためであり、当時に存在もしくは存在が予想される機器や記録媒体を用いる私的複製についてのみこの規定は適用されるという権利者側と、そのような制約は規定上存在しないので自由な複製は許されるというメーカー側の見解の衝突である。 両者の見解は、形式的にはともに成立するため、その何れを採るべきかについて論争が続き、紆余曲折を経て1955年に、画期的な判決が連邦通常裁判所(BGH−事実上の民刑事上の最高裁判所)から出されている。それは、著作権は立法者により初めて与えられるものではなく、事物の本性(Natur der Sache)から、すなわち、精神的所有権(Geistiges Eigentum)の概念から導き出されるものであり、1901年著作権法第15条のただし書は、この著作権の基本的思想の例外をなすものであって、著作権に対する制限は、その本来の意味及び目的を超えて拡張されてはならないとするものであった。つまり、著作物の私的使用のためにする録音による複製は、1901年法の予想するところではなく、それは著作権者の権限に服するものであり、許可なき複製は違法行為であると捉えたのである。その後、若干の経緯の後、録音のための機器や記録媒体の購入者による著作物等の許可なき録音は著作権侵害、すなわち違法行為であり、その違法行為に用いる機器や記録媒体を提供するメーカーは、その違法行為に寄与する者として、機器等を使用し許可なく著作物等を複製する使用者と共同でその責を負うと考えられ、著作権者等に報酬を支払う義務をメーカーに課すことが可能とまで考えは進むのである。その結果として、1965年の著作権法第53条(5)[現行第54条]は、録音・録画用の機器につき、その製造業者及び輸入業者はその機器の販売価格の5パーセントの範囲内で、著作権者に報酬を支払うべき義務があるとまで進んだのである(現在は5パーセントの文言は削除され、相応な報酬という文言に置き換えられている)。 1965年の西ドイツ著作権法が成立した当時、ベルヌ条約第9条第2項を新設したベルヌ条約ストックホルム条約(1967年)が、まだ存在しなかったことに留意すべきであろう。西ドイツ方式をそのままわが国の著作権法に導入せよという主張は、この間の事情をどこまで理解していたかはわからない。1965年当時、西ドイツでは、私的使用のために供される録音・録画用の機器や記録媒体を提供するメーカーや輸入業者は、著作権侵害に寄与するものであり、直接の侵害者であるユーザーとともに、その侵害につき連帯債務を負うべきものとされていたのである。 これに対し、わが国では、1967年のストックホルム改正会議に参加し、そこで新設された第9条の趣旨を充分に理解して1970年のわが国の著作権法は第30条を規定したのであり、しかも、いわゆるスリーステップスの存在を充分に認識して著作権の制限規定を設けているのである。このような事情の下に制定された第30条からは、メーカー等が録音・録画用の機器や記録媒体をユーザーに提供しても、ユーザーに違法行為がない以上、メーカー等が違法行為の寄与者になることはない。 このことは、前述の大歳・谷井両委員が第10小委員会に提出した意見書にもあらわれている。すなわち、両委員は、検討される事項として、「私権の行使が困難であるという理由で、私的録音・録画の当事者のいない私企業に特定の義務を課す法的根拠と、権利者等の報酬取得の実現にメーカーが「助力」するという義務の法的性格を解明すること」を求めたのである。 日本著作権法では、ユーザーの著作物等の私的録音・録画行為が適法である以上、これを西ドイツのように違法とし、この違法行為にそれを実現するための機器や記録媒体を提供することはその幇助にあたるということはできないし、それを根拠にメーカーに対し直接に報酬支払義務を課すことはできない。ベルヌ条約第9条第2項ただし書に該当する場合、すなわち、ユーザーの複製行為がその著作物の通常の利用(normal exploitation)を妨げ、著作者の正当な利益を不当に害するときは別であるが、その有無を知るためには、わが国における著作物等の私的録音・録画の実態を知らなければならない。 わが国における録音・録画機器の普及状況、家庭内での著作物等の録音・録画の実態等については、昭和53年11月の「総理府調査」,昭和59年3月のJASRAC(ジャスラック),芸団協,レコード協会のいわゆる「権利者3団体調査」,昭和60年10月の日本電子機械工業会及び磁気テープ工業会のいわゆる「メーカー2団体調査」,更に昭和60年11月の「内閣官房広報室調査」があり、平成3年には、権利者前記3団体にビデオ協会を加えた権利者4団体とメーカーの前記2団体が合同して「私的録音・録画に関する実態調査」が行われ、これらを検討してみると、録音・録画機器の普及は著しく、著作権者等の正当な利益を不当に害するおそれがあるという見解に到達し、更に、情報伝達手段のデジタル化を考慮すると、なんらかの制度的対応を採るべきであるという結論になったのである。 制度的対応を採るとき、権利者が如何に補償金を取得することができるかが、最初の、かつ、最も大きな問題となる。個々の権利者が自ら著作物の使用者を探し求めてそれを得ることは、ほとんど不可能であり、それは、権利者の集団を作っても容易ではない。諸外国ではメーカーに直接負担せしめる方策が採られるが、わが国では、そうするにはわが国としての法的根拠を求めなければならない。録音・録画用の機器や記録媒体の発達普及に伴い、ユーザーが著作物等を享受する機会が増大した反面、それは著作物の私的録音・録画の増大を意味するので、権利の保護と著作物の利用との間の調整の必要が生じてくることから、これらの機器や記録媒体を提供するメーカーは、この調整に協力することが公平ではないかと考えられた。ここでいう公平とは、不法行為法上で論ぜられる「利益を受ける者は危険を負う」という、いわゆる報償責任の考え方を借用したものであって、経済的行為として録音・録画のための機器や記録媒体を生産販売することにより損失を蒙る結果を受けざるを得ない権利者に対し、その損失を填補するための協力行為が要求されてもよいであろうという理論を考え、それをメーカーの協力義務という形で表現することによって、メーカー悪者論を嫌うメーカー側からの協力を得ることができたのである。 現象的に似ているにしても、メーカーに寄与侵害の責があるという考えから、メーカーに対し権利者に報酬を支払う義務があるという西ドイツ流の考えとは区別されなければならないのである。報償責任の考え方を借用したといっても、メーカーを不法行為に加担した者とみているものではないことは、いうまでもあるまい。 |
| 次のページへ |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology