福井県立藤島高等学校は2004年度から20年以上継続してスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されており、課題探究に取り組んでいます。2024年度に本事業に新設された文理融合基礎枠において、同校では第Ⅴ期(先導的改革Ⅰ期)より「文理融合のための共通基盤と専門知を備えた科学技術・イノベーション人材の育成システム確立と普及」を研究開発課題とし、「教養」を深めること、「志」をもつことを「研究力」と結びつけ、文理融合で未来に向かう価値創造に着手。本取組には第Ⅱ期から文系分野でも開始した課題探究の取組が活かされています。
お話を伺った先生
- 鈴木 聡史(すずき さとし)
-
理科(物理)教諭。図書・研究部部長。2019年度に同校着任。着任時からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業にかかわり、前任(福井県立武生高等学校、福井県教育庁高校教育課)から通算15年、スーパーサイエンスハイスクール事業にかかわっている。
- 青木 建一郎(あおき けんいちろう)
-
地歴公民科教諭(公民)。2004年度に同校に着任し、同校勤務21年目。第Ⅱ期(2009~2013年度)からスーパーサイエンスハイスクール事業にかかわる。同校独自制作の教養テキスト『近代とは何か―学生のための基礎教養第1集―』『私たちはなぜ科学するのか―学生のための基礎教養第2集―』を発案・編纂。
約20年の取組が「文理融合の課題探究」に活かされている
本校では、第Ⅴ期(先導的改革Ⅰ期、2024~2026年度)からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業に新設された文理融合基礎枠において「文理融合のための共通基盤と専門知を備えた科学技術・イノベーション人材の育成システム確立と普及」を研究開発課題としています。本取組では、理系分野のみではなく、人文・社会科学など文系分野でも研究開発を行い、両者を融合させた新たな「学力」(総合知)を生み出すことを目標としています。第Ⅴ期には、これまでの本校の取組の成果が活かされています。
第Ⅱ期(2009~2013年度)では、文系分野でも課題探究が必要であると考え、スーパーサイエンスハイスクール事業と並行して取り組みました。当時、文系分野には本事業予算が利用できなかったので、外部の助成金などを利用し、専門家に助言をもらう機会を徐々に増やしていきました。
第Ⅲ期(2014~2018年度)からは、文系・理系の共通基盤が必要であると考え、スペシャリストの育成に特化するのではなく、ジェネラル(総合的)に学ぶことも目標に加えました。スペシャルに探究することと同時に、ジェネラルに学ぶ「教養」が重要であると考えました。本校では教養を「断片的な知識・経験をつなぎ、高校で習得する知の全体像を俯瞰的に把握する力」と定義しています。知識や経験をつなげるハブとして、本校独自の教養テキスト『近代とは何か―学生のための基礎教養第1集―』『私たちはなぜ科学するのか―学生のための基礎教養第2集―』(後述)を作成しました。
第Ⅳ期(2019~2023年度)は、校内に図書・研究部を新規で設置して、図書館と課題探究のリンクを深めました。文系分野の課題研究は文献が重要であるためです。本校の図書館の専門書所有率は高校としてはかなり高いものとなっています。
また、教員ができることには限りがあると考え、地域企業や大学連携の仕組み「藤島プラットフォーム」を構築。福井大学や県立大学など県内の大学のほか、本校の卒業生には研究者が多く、そのネットワークが役立ちました。

第Ⅴ期「文理融合のための共通基盤と専門知を備えた科学技術・イノベーション人材の育成システム確立と普及」(提供:福井県立藤島高等学校)
第Ⅴ期は新たに「志」を追加
第Ⅴ期で新たな柱として加えたものが「志」です。知識や経験をよりよい未来の創造につなげるために必要であると考えたためです。この志を育むため、「研究Ⅲ」(3年で履修)を大幅にリニューアルしました。
「研究Ⅰ」(1年で履修)では2学期までに研究基礎スキルを習得し、3学期からそれぞれのテーマで課題探究を始めます。12月に13社の先端的な取組を行っている企業を招き、企業の問題意識と課題解決の方策、公的な志について各社が講演を行います。生徒は当日、2企業を選択して聞き、次年度に取り組む課題探究の課題の見つけ方や解決方法、社会における自らの役割を考えるヒントにします。
「研究Ⅱ」(2年で履修)は、学問領域に分かれて課題探究を行うことを通して「専門知」を形成します。生徒は自由な課題を設定して楽しみながら取り組んでいます。研究が進んでいない段階で文理交流会を設け、生徒同士が意見し合うことで総合知の重要性に気付かせることをめざしています。大学からの助言を受ける機会も設け、3学期に研究発表会を行い、その後、論文集としてまとめます。
「一番強い乳酸菌」を調べるため複数種類の乳酸菌を同じシャーレで育成している。(研究Ⅱ)
耐震構造を研究。筋交いの入れ方による倒れ方の変化についてモデル実験をしている。(研究Ⅱ)

白、黒、縞々でショウジョウバエの活動量の変化を比較するため公園で実験した。(研究Ⅱ)(提供:福井県立藤島高等学校)
文理混合チームで課題探究
リニューアルした「研究Ⅲ」はこれまでにない新しい取組で、試行錯誤しているところです。文理混合チームで多様な分野の専門知をもちより、協働して未来社会を創造する力を養うことを目標としており、第1クールは過去、第2クールは現在、第3クールは未来をテーマとしてグループワークを進めています。
第1クールでは、テキスト『近代とは何か―学生のための基礎教養第1集―』『私たちはなぜ科学するのか―学生のための基礎教養第2集―』の「科学と近代についての議論」などの文章を読み、科学技術とイノベーションの歴史に対する理解を深め、2年までに得た知識・体験をつなぎ、再構成していきます。
第2クールでは、「デザイナーベビー」や「ビッグデータ」などをテーマに科学技術が現代社会にどのような変革をもたらし得るのかを学び、光の部分だけでなく、影の部分を考え、今後の社会でどのように科学技術を活用していけばよいのかを検討し、話し合います。
第3クールでは、社会課題を解決し未来社会を変える、と考えられる先端科学技術を各グループで1つ選択。核融合や、薄型太陽光パネル、生成AI、DNA操作など、生徒は開発中や進化中のさまざまな技術を自ら見つけ、それが現代社会をどう変革していくのかを検討します。さらに各グループで選択した先端科学技術により生じる倫理的・法的・社会的課題の解決策について考え、明るい未来につながるような社会デザインを検討していきます。
本活動では、理系生徒が技術について文系生徒に説明し、文系生徒が社会的問題や倫理的問題を考えるなどのゆるやかな役割分担ができています。1クールごとに校外の専門家を招へいして講演会も行い、知見や視野を広げる機会を設けています。
研究Ⅲ第3クールの課題研究をグループごとに発表し合う。(提供:福井県立藤島高等学校)
個別の知識をつなげるための教養テキストを作成
研究Ⅲのグループワークで利用している『近代とは何か―学生のための基礎教養第1集―』(人文・社会科学分野が中心)、『私たちはなぜ科学するのか―学生のための基礎教養第2集―』(科学技術分野)は、福井県内の高校教員と大学教員に編集委員を依頼して古今東西の名文を集めて刊行したアンソロジーです。
高校で学ぶ個別の知識や経験がネットワークとしてつながった状態を教養と定義すると、知識をつなげるためには、近代社会の基本構造を学ぶ必要があります。現在の科学技術の発展やそれによる課題、そしてポストモダン(脱近代)など現代思想の出発点は近代にあるためです。しかし、それを明確につなげた教材がなかったため、第Ⅲ期にテキストの作成に着手しました。
当初はスーパーサイエンスハイスクールの予算を使った無償テキストでしたが、好評だったことから版元も決まり、現在は教材として販売しており、県内で採用している高校もあります。本校以外では、把握しているだけで全国の高校142校、大学12校、小中学校7校、行政機関12の教育関係者に購入されています。1学年全員が購入している高校もあります。初版は2016年で8600部を完売し、2023年に第1・2集計1万部を増刷しました。
これまで本テキストは、入学時に生徒に渡し、通常授業で使うこともありますが、基本的には朝読書の時間に読むなど自主性に委ねた活用をしてきました。3年になって読むと、これまで学んできたことがつながる、という生徒もいます。大学進学後、本テキストを大学の仲間や教授に紹介している生徒もいます。今期より文理融合基礎枠に取り組むこともあり、積極的な活用を進めていく予定です。
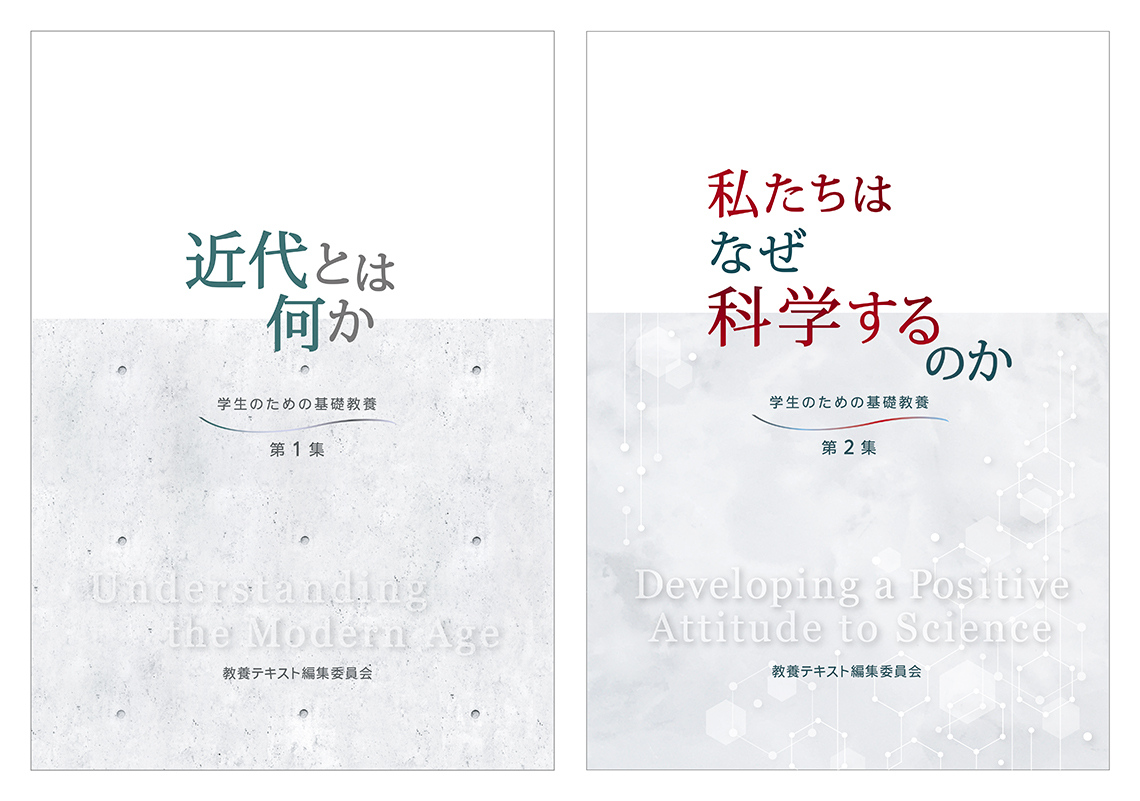
知識をつなげるためオリジナルのテキスト『近代とは何か―学生のための基礎教養第1集―』(人文・社会科学分野中心)、『私たちはなぜ科学するのか―学生のための基礎教養第2集―』(科学技術分野)を作成(提供:福井県立藤島高等学校)

テキストの内容は、福井県内教員と大学教員に編集委員を依頼し古今東西の名文を集めて刊行したアンソロジー(提供:福井県立藤島高等学校)
文系の課題探究の目的やゴール設定が難しかった
長年の取組を振り返り、課題であったと感じることは、まず文系の課題探究の目的やゴール設定です。最初は関心のあることから自由に問いを設定していました。ところが生徒が自分の主張を証明するために都合のよい資料ばかりを集めることもあるなど、課題探究につながっていない場合がありました。そこで第Ⅱ期の3年目から、課題解決型ではなく、アカデミックリサーチ(学術調査)型の探究とし、学問への接続を重視することとしました。大学教員に助言を依頼して、質問会を行うようにしたのもこの解決の一環で始めたことです。また、第Ⅲ期に、教養という概念を明確化するために、前述の教養テキストを自作しました。
教員の共通理解や協力体制の構築も課題でした。新しい取組に喜んで参加する生徒が多い一方で、当初、教員からは「文系で課題研究をする必要があるのか」「受験勉強にさしさわるのでは」などの疑問の声もあがっていました。課題探究発表会で生徒の発表を聞いた際には、教員から「高校生でもこんな発表ができるのか」という感想があり、生徒の可能性が広がる感覚を教員間で共有するきっかけになりました。しかしこれですべて解決するわけではなく、共通理解には時間がかかりました。
専門家が本事業にかかわるようになり、生徒への支援のようすを見たり、講演を聞いているうちに、教員もともに育っていったり、企業連携など外部の協力を得られたことで教員の役割分担が明確になったりするなど、実践の積み重ねにより解決してきている部分もあります。2021年から内閣府が「総合知」(人文・社会科学と自然科学を含むあらゆる 「知」の融合)の重要性について発信を始めたことも、本校の過去の実践と方向性を同じくしていて取組が進むきっかけになりました。
研究水準が確実に向上 GIGAスクール環境で調査効率も上がる
この20年で生徒の研究水準は確実に上がりました。過去の論文集と比較すると、問題意識や課題解決の手法が違います。本校の卒業生が大学院生や研究者として、高校生のアドバイザーを務めることもあるのですが「自分のやっていた頃と水準が違う」と驚いています。特に文系分野の研究水準の向上を感じています。
新カリキュラムがスタートし、総合的な探究の時間の充実が重要になるなか、文理横断・文理融合教育の推進が大学教育に求められるなど、時代の変化を感じます。GIGAスクール構想による1人1台端末配備の影響も大きいと感じます。初期のころは1台のPCに数人が群がっていましたが、現在は調査効率が格段に上がっています。
文理融合アカデミックデイで普及・連携を強化
第Ⅴ期の本事業では、成果の普及を求められています。また、大学・産業界や地域連携の強化をさらに図りたいという思いもあり、2025年2月11日、文理融合アカデミックデイを初開催します。研究発表会とともに研究者や本校のOBなどさまざまな方と交流する場として計画しています。
さらに、昨今は本をあまり読まない生徒が増えていることから、新入生向けに、教養の入り口となる内容をまとめた教養テキスト第0集の作成に着手しています。2025年度中には完成したいと考えています。
※本記事の情報は取材時点(2024年12月)のものです。
福井県立藤島高等学校
1855年(安政2年)、福井藩16代藩主の松平春嶽公により設立された藩校「明道館」が前身。卒業生として、旧制福井中学時代の岡田啓介首相、石田和外最高裁長官、南部陽一郎博士(ノーベル物理学賞受賞者)ら、新制藤島高等学校の野路國夫元コマツ会長、荒川洋治(詩人)、平井良典AGC社長、俵万智(歌人)らが知られ、多数の研究者を輩出している。2004年4月からスーパーサイエンスハイスクール指定校。現在第Ⅴ期。






