アメリカは連邦国家であり、教育行政は基本的に州に委ねられている。
アメリカでは、憲法第1条第8節第10修正(1791年12月)により、連邦の権限が規定され、規定されている以外の権限は、州および市民に留保されている。教育についても憲法に規定されていないことから、州の専管事項とされ、基本的に連邦は教育に関する権限を有しない。州が州憲法や州教育法に基づいて、州内の教育全般を統括している。
連邦レベルの教育行政機関は連邦教育省であり、その使命は、「教育機会の均等化」と「優れた教育の振興」である。これらの達成のための主たる事業は、各種補助金事業・奨学金事業、教育情報の収集・提供や研究開発となっており、国家教育費に占める連邦の負担率は10パーセントである。
アメリカの場合、上記のような教育行政システムにあるため、連邦レベルでの包括的な「教育基本計画」は存在していない。
連邦法の推移をみると、1960年代の公民権法の成立後、経済的に恵まれない児童生徒の多い地域に対する補助金の交付などを規定する初等中等教育法(Elementary and Secondary Education Act (ESEA) of 1965)や、連邦奨学金制度や教員養成に対する援助を規定した高等教育法(Higher Education Act of 1965)が制定された。1990年代には、![]() 就学前における学習準備の徹底、
就学前における学習準備の徹底、![]() ハイスクール卒業率の引き上げ、
ハイスクール卒業率の引き上げ、![]() 基礎的教科の達成度評価(学力測定)の実施、
基礎的教科の達成度評価(学力測定)の実施、![]() 教員の資質向上に向けた条件整備等の全国的な教育目標を内容とする「全国共通教育目標」を含めた「2000年の目標:アメリカ教育法(Goal 2000:Educate America Act)」や「学校改善法(Improving America's School Act (IASA) of 1994)」が制定され、州の施策を支援する補助金の交付を定めるようになった。2002年には、初等中等教育を対象にした「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法(No Child Left Behind Act of 2001)」(以下、NCLBという。)が制定された。同法は、教育改革に関する施策が包括的に規定されており、教育は州の専管事項であるが、同法が連邦補助金事業に関する授権法であることから、連邦政府の関与が一層深まる内容となっている。連邦政府が動きだした背景には、アメリカの学力の底上げを目的とし、教育水準が国際的にみて低いことや、国内での多くの施策が効果的に実施されていないといった問題があった。
教員の資質向上に向けた条件整備等の全国的な教育目標を内容とする「全国共通教育目標」を含めた「2000年の目標:アメリカ教育法(Goal 2000:Educate America Act)」や「学校改善法(Improving America's School Act (IASA) of 1994)」が制定され、州の施策を支援する補助金の交付を定めるようになった。2002年には、初等中等教育を対象にした「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法(No Child Left Behind Act of 2001)」(以下、NCLBという。)が制定された。同法は、教育改革に関する施策が包括的に規定されており、教育は州の専管事項であるが、同法が連邦補助金事業に関する授権法であることから、連邦政府の関与が一層深まる内容となっている。連邦政府が動きだした背景には、アメリカの学力の底上げを目的とし、教育水準が国際的にみて低いことや、国内での多くの施策が効果的に実施されていないといった問題があった。
NCLBに規定された施策の策定・導入は州の任意であるものの、ほとんどの州が導入していることから各州共通の枠組みとしてみなすことができ、国の「基本計画」に近い性質をもつものとして、本節では、NCLBを初等中等教育分野の「教育基本計画」として取り上げることとする。
なお、他の教育分野においてはNCLBと同様の法はないものの、高等教育分野でも連邦政府の関与が強まる方向にある。2006年9月に、「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会」が最終答申となる報告書を提出している。それを受けて、連邦教育省は、連邦政府による施策として高等教育改革に向けた行動計画「高等教育改革アクションプラン:アクセスの向上、学費負担の軽減およびアカウンタビリティの改善に向けて」を発表した。ただし、この計画は大綱的な政策方針を示したものであり,今後導入が検討される諸施策も,その実現可能性については不明な点が多いことから,今回は調査対象に含めないこととした。
連邦は、2002年1月、各州の教育改革を支援することを目的とするNCLB法を制定した。同法は学力の底上げを目標とし、同法に基づく補助金を受給する州に対して、カリキュラムの基準及び到達目標となる教育スタンダード策定、学力テストの実施と結果公表等を内容とする初等中等教育段階の施策の策定を要請している。NCLB前の教育法はいくつかの特定の事項を連邦補助金の交付条件とするなど限定的であったのに対し、NCLBでは、連邦補助金交付の範囲が公的教育に関わる広い分野となっていることが異なる。
教育は州の専管事項であり、また同法が連邦補助金に関する授権法であることから、連邦補助金を受ける条件として規定されている施策を策定するか否かは、州の任意となっている。しかし、すべての州が、施策の数や進捗度に差はあるものの、同法に沿った施策を策定、実施している。
NCLBは、アメリカ全土の教育水準の維持には連邦政府の支援が必要との意識が高まるなかで制定された。元来,教育に関する権限を持たない連邦政府が学力向上という目標に向けて積極的な動きを見せるようになった嚆矢は、1989年のブッシュ前大統領による「教育サミット」の開催で、合衆国レベルで初めて全国共通教育目標の設定が合意され、翌年、目標が発表された。その後、これらの目標は、クリントン政権にひきつがれ、1994年にクリントン政権時にアメリカ教育改善法(IASA)が制定された。同法は1965年に制定された初等中等教育法(ESEA)を部分的に改正したもので、補助金の交付条件として英語と数学の学力評価の実施等が規定されている。
2000年に就任したブッシュ大統領は、教育を国内政策の最重要課題と位置づけ、公的教育における新しい連邦の役割を作り上げた。それがNCLBであり、IASAの成果と大統領自身のテキサス州知事時代の経験がもとになっている。NCLBは、IASAとは異なり、初等中等教育法(ESEA)では基本的な枠組みが全面的に改正されている。
同法は2001〜2002年度(2001年度)の年度途中,2002年1月に制定された。法律としての効力の期限についての明記はないが,規定によると、2013〜2014年度(2013年度)終了時点までに、すべての児童生徒が、自分が住む州が決めた学力水準に達することとなっているため、2001年度から2013年年度の12年間を計画期間とみなすことができる。
NCLBはブッシュ大統領が提唱したものであり、同大統領が2001年1月に行った教育改革指針演説「教育における連邦政府の新たな役割−落ちこぼれを作らないために−」は、NCLBの基本であるととらえることができる。同演説において提示されているNCLBの指針の概要は次のとおりである。
NCLBは、6部からなり、第2部に初等中等教育向上に関する様々な規定が、10編に分かれて明記されている。また、各編の下には、部、補部、条項がある。10編ならびに部と補部は以下のとおりである。
| 編 | 編(Title) | 部(Part)および補部(Subpart) |
|---|---|---|
| 不利な状況にある児童生徒の学力の向上 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 高い資格を有する教員と校長の養成、訓練、雇用 |
|
|
|
||
|
||
|
||
| 英語能力が不足している児童生徒や移民の児童生徒のための語学教育 |
|
|
|
||
| 21世紀型学校 |
|
|
|
||
|
||
| 親に対する情報提供と学校選択の拡大、革新的プログラムの推進 |
|
|
|
||
|
||
|
||
| 裁量拡大とアカウンタビリティ |
|
|
|
||
| インディアン、ネイティブハワイアン、アラスカネイティブの教育 |
|
|
|
||
|
||
| インパクト・エイド | ||
| 一般条項 | ||
| 他の法令の廃止、修正 |
(資料)“No Child Left Behind Act of 2001”
連邦教育省によると、NCLBには、結果責任の重視、州や地方の裁量拡大、効率的な教育方法の適用、教育機会の拡大の4つの重点分野がある。概要は以下のとおりである。
| 重点分野 | 概要 |
|---|---|
| 結果責任の重視 (Stronger Accountability for Results) |
|
| 州やコミュニティの裁量拡大 (More Freedom for States and Communities) |
|
| 研究に裏づけされた教育方法の適用 (Proven Education Methods) |
|
| 教育機会の拡大 (More Choices for Parents) |
|
(資料)Department of Education
NCLBは全米児童生徒の学力の底上げおよび地域や学校間の格差是正のため、規定された施策を州レベルで実施させることとなっている。主要な施策は、![]() 州内統一学力テストの実施と結果公表、
州内統一学力テストの実施と結果公表、![]() 学力向上のための年次目標設定、
学力向上のための年次目標設定、![]() 学校の質の向上と教育機会の拡大、
学校の質の向上と教育機会の拡大、![]() 実績通知表の導入、
実績通知表の導入、![]() 高い資格を有する教員の育成・確保、
高い資格を有する教員の育成・確保、![]() 基礎学力(読解力)の向上のための集中投資となっている。
基礎学力(読解力)の向上のための集中投資となっている。
これらの施策は、NCLB法令の関連各編に規定されているものの、ほとんどが第![]() 編(不利な状況にある児童生徒の学力の向上)の第A部(地方の教育機関によって運営される基本プログラムの整備)にまとめられている。
編(不利な状況にある児童生徒の学力の向上)の第A部(地方の教育機関によって運営される基本プログラムの整備)にまとめられている。
同法が各州に策定を求める計画の主要の施策の内容は次のとおりである。
NCLB法第![]() 編において連邦資金を授与している学校のなかで、AYPの目標を達成できず「実績低迷校」と認定されると、以下のような改善策を実施しなくてはならない。そのなかには児童・生徒および親に対する連邦政府の援助も含まれる。
編において連邦資金を授与している学校のなかで、AYPの目標を達成できず「実績低迷校」と認定されると、以下のような改善策を実施しなくてはならない。そのなかには児童・生徒および親に対する連邦政府の援助も含まれる。
2002〜2003年度から、州は、年次レポートカードを準備し発表する。レポートカードに記載される情報は、読解力や算数の州全体の成績や評価、サブグループ別児童生徒の学習到達度、学区の実績などである。各学区は学校単位で類似の実績通知表を作成しなくてはならない。
NCLBでは、各州がそれぞれの施策の数値目標を設定することになっている。連邦としての数値目標は、ほとんどが達成年度でしか表されていない(注1)。数値目標を見るにあたり、諸州政府教育協議会(Education Commission of the States(ECS))がまとめた情報に基づき、補助金を受給する条件の具体的内容を以下のとおり挙げた。数値目標を含む内容はイタリックで表示した。
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 読解の教育スタンダード | 州は、第3学年(小学校3年)〜第8学年(中学校2年)において読解(reading)に関する学力標準を設定する(ESEAによる)。 |
| 算数の教育スタンダード | 州は、第3学年〜第8学年において算数(mathematics)に関する教育スタンダードを設定する(ESEAによる)。 |
| 理科の教育スタンダード | 州は、2005〜2006年度までに第3学年〜第5学年、第6学年〜第9学年、第10学年〜第12学年のそれぞれ1学年において理科(science)の教育スタンダードを設定する。 |
| 読解の州内統一の学力テスト | 州は、2005〜2006年度までに第3学年〜第8学年および高校を対象とする読解力の教育スタンダードに基づく評価システムを導入する。 |
| 算数の州内統一の学力テスト | 州は、2005〜2006年度までに第3学年〜第8学年および高校を対象とする算数の教育スタンダードに基づく評価システムを導入する。 |
| 理科の州内統一の学力テスト | 州は、2005〜2006年度までに第3学年〜第5学年、第6学年〜第9学年、第10学年〜第12学年のそれぞれ1学年において理科(science)の教育スタンダードに基づく評価システムを導入する。 |
| 英語の習熟度の評価 | 州は、2002〜2003年度までに、地方教育機関が英語の習熟度が低いすべての児童生徒の英語習熟度に関し年次評価を行うようにする。 |
| 地方教育機関の児童生徒の参加 | 州は、地方教育機関に通う児童生徒の100パーセントが、読解力、算数、理科の学力評価に各教科によって決められた年度までに参加する施策を実施する。 |
| 障害を持つ児童生徒の参加 | 州は、障害をもつ児童生徒の100パーセントが、読解力、算数、理科の学力評価に各教科によって決められた年度までに参加する施策を実施する。 |
| 移民の児童生徒の参加 | 州は、移民の児童生徒の100パーセントが、読解力、算数、理科学力評価にの各教科によって決められた年度までに参加する施策を実施する。 |
| 結果の分析 | 結果は、州、地方教育機関および学校レベルをサブグループに分けて分析する |
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 1州1アカウンタビリティシステム | ひとつの州で統一されたアカウンタビリティシステムが全ての公立学校と地方教育機関に適用される(ESEAによる)。 |
| 全ての学校がアカウンタビリティに参加 | 全ての公立学校の全ての児童生徒は州のアカウンタビリティシステムに参加する(ESEAによる)。 |
| 習熟度目標達成100パーセントを目指す | AYPの内容は、2013〜2014年度までに州の全ての児童生徒が読解力と算数において十分習熟するように、児童生徒が学力を向上させることを目指すものである。 |
| AYPの年次確認 | 州は、全ての公立学校や地方教育機関がAYPを作成したか否かについて毎年確認する。 |
| 全てのサブグループに対する責任 | 全ての公立学校および地方教育機関は各サブグループの成績に責任を持つ。(サブグループとは、経済的に恵まれない児童生徒、人種・エスニックグループ、障害を持つ児童生徒、英語の習熟度が不足している児童生徒をいう) |
| 基本は学力 | 州のAYPの内容は、主として各州の学力評価に基づく。 |
| 卒業率などを含む | 州のAYPの内容は、高校の卒業率(修了率)、および小中学校に関する指標を含む。 |
| 別々の読解力と算数の目標に基づく | AYPは別々の読解力と算数の学業目標に基づく。 |
| サブグループの95パーセントの児童生徒を評価 | ひとつの学校がAYPを作成するにあたり、州は全てのサブグループの95パーセントの児童生徒が評価に参加するようにする。 |
州は、次の施策を適切に策定しなければならない。AYPの達成の有無に基づき、学校や地方教育機関に対し制裁や報奨金が適用される。
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 適切な認識 | 州は新学期が始まる前に、学校改善の必要な学校、改善策または再建策を特定し、地方教育機関が親に適切な時期に連絡する。 |
| 技術支援 | 州は、科学的研究に基づく技術的支援を、学校改善、改善策または再建策が必要とされた学校に対し適切に提供する制度を持つ。 |
| 公立学校の選択 | 改善が必要とされた学校に通う児童生徒は同じ学区内の改善が必要と認識されていない学校に転校することができることを州の法律で規定する。 |
| 報奨金と制裁 | 州は、AYPに基づき、すべての学校(タイトル |
| 学校の認識 | 州は、学力格差を著しく縮小、AYPを達成した学校を認識するために、優秀学校の任命や財政支援などを行う施策を策定する。 |
| 学校の再建 | 州法は、学校統治に関し、次の4つのうち少なくともひとつの方法を承認する。
|
| 地方教育機関の改善策 | 州法が改善策を実施している地方教育機関に対し少なくとも次の対策をとることを承認し、州の教育機関が適切に実施する。
|
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 安全でない学校の基準 | 州は、2003〜2004年度の始めまでに継続して危険な学校を特定する基準を作成する。 |
| 安全でない学校の児童生徒の転校 | 州は、継続的に危険と特定された学校に通う児童生徒を学区内の他の公立学校へ転向すること認可する政策を制定し導入する。 |
| 暴力の犠牲となった児童生徒の転校 | 州は、暴力の犠牲となった児童生徒を学区内の他の公立学校へ転校すること認可する政策を制定し導入する。 |
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 補助教育サービスの基準 | 州は、2003〜2004年度の始めまでに効果的な補助教育サービス提供者を特定する基準を作成する。 |
| 認可された補助教育サービス提供者のリスト | 州は、2003〜2004年度の始めまでに学区内の認可されたサービス提供者のリストを整備する。 |
| 補助教育サービス提供者のモニタリング | 州は、補助教育サービス提供者の品質をモニターする基準を作成する。 |
| 補助教育サービスの導入 | 州は、適切な地方教育機関が、児童生徒の親によって選ばれた提供者による補助教育サービスの支給を調整するようにする。 |
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 州のレポートカード | 州は2003〜2004年度の始めまでに、全ての必要事項を含む州の年次レポートカードを準備し発表する。 必要掲載事項は次のとおりである。
|
| 施策(条件) | 内容 |
|---|---|
| 高い資格を有する教員の定義 | 州は2002〜2003年度の始めまでに、NCLBの条件に合う高い資格を有する教員の定義を適用する。 |
| 重要な能力 | 州は、小学校および中学校の教員が重要な学科において主要な能力を示す制度を創設する。タイトル |
| 新しい小学生教員テスト | 州は、新しい小学校の教員を適所に配置するためのテストを行う。 |
| 各学級に優秀な教員を配置 | 州は、各学級に高い資格を有する教員をおくという目標を地方教育機関が達成するために年次数値目標を設置する。タイトル |
| 高い資格を有する教員の育成 | 州は、高い専門的資格を持つ教員の割合を増やすために年次数値目標を設置する。数値目標は州の総合計画に含まれなければならない。 |
本節では、連邦政府全体の教育資金、連邦教育省による教育資金、NCLBの施策に対する資金について概観する。
連邦政府による教育および教育関連プログラムの資金(初等中等教育,高等教育及び研究開発に関する経費)は、教育省だけでなく、農務省、商務省、国防総省、エネルギー省、保健福祉省、国土安全保障省、住宅都市開発省、内務省、司法省、労働省、国務省、運輸省、財務省、退役軍人省に対して配分される。2005年の数字をみると、教育省に710億ドル、その他省庁に合計で613億ドル、その他機関に95億ドル配分され,その多くが高等教育や研究開発に充てられた。これらの合計は1,418億ドルとなり、名目GDPに占める割合は、1.1パーセント、連邦資金全体に占める割合は5.7パーセントである(図表2-1-3および図表2-1-4)。
初等中等教育への支出をみると(図表2-1-5)、連邦政府の資金は8.9パーセントに過ぎず、州や地方政府の資金が連邦資金の約10倍となっている。
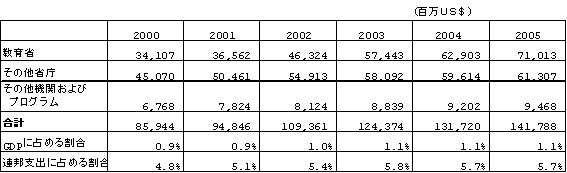
(資料)Department of Education"Fiscal Year 2008 Budget Summary"
US National Center for Education Statistics"Digest of Education Statistics, annual"
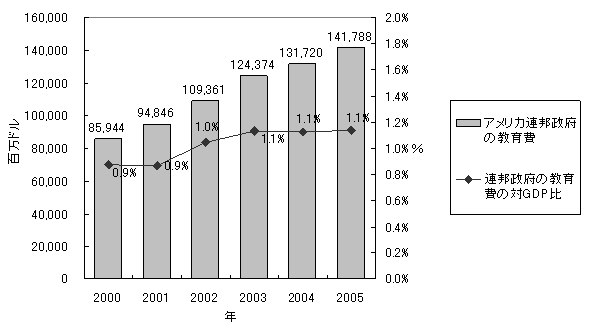
(資料)Department of Education"Fiscal Year 2008 Budget Summary"
US National Center for Education Statistics"Digest of Education Statistics, annual"
(10億USドル)
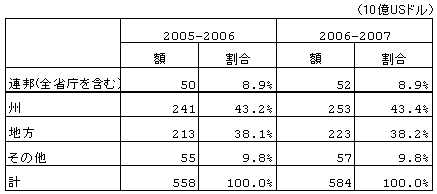
(資料)Department of Education"Fiscal Year 2008 Budget Summary"
大統領予算教書に示された連邦政府の予算(初等中等教育,高等教育及び省運営費を含む)をみると、2006年度は566億ドル(裁量経費分)であった。2001年度から2006年度にかけては、年平均増加率は約6パーセントと、経済成長率を上回る増加率で推移した。2007年度は560億ドルと推計され、2008年度は560億ドルの予算を申請中で、2006年からは若干減少傾向にある。
教育関連予算の内訳をみると(2008年)、NCLBが245億ドルと最も大きく、41.6パーセントを占めた。初等中等教育全体では64.9パーセントとなり、連邦教育省予算において初等中等教育に重点が置かれていることが示されている。2008年度の同省予算案の内訳をみると、効果が上がっていない、優先順位が低いと判断された事業の事業が淘汰され、これによって捻出された予算が重要施策に配分されている。
(百万USドル)
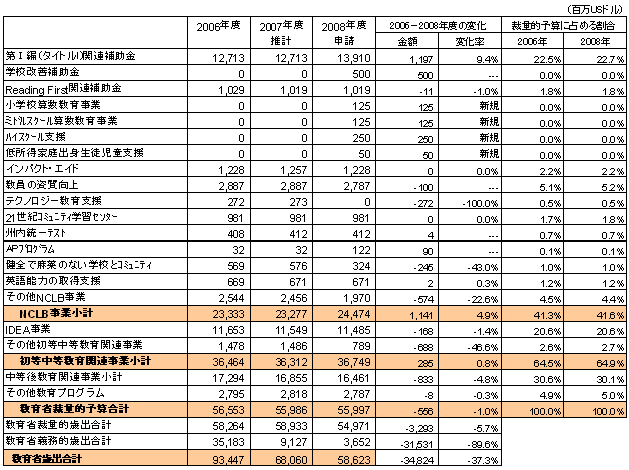
(資料)Department of Education"Fiscal Year 2008 Budget Summary"
OMB, The Budget for Fiscal Year 2008, Department of Education
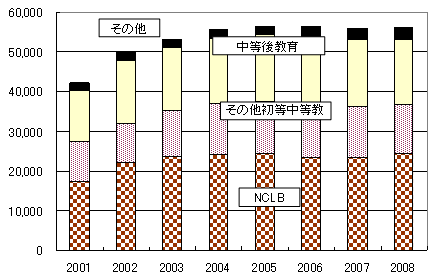
(資料)Department of Education
NCLBのなかで連邦政府の投資の内訳(2008年)をみると、NCLBの中核をなす第一編(タイトル![]() )、すなわち、不利な条件にある児童生徒の教育を保障するために州や地方を支援する補助金が56.8パーセントを占め圧倒的に大きい。前年度比9.4パーセント増の139億ドルを計上した。2001年からは59パーセント増加している。
)、すなわち、不利な条件にある児童生徒の教育を保障するために州や地方を支援する補助金が56.8パーセントを占め圧倒的に大きい。前年度比9.4パーセント増の139億ドルを計上した。2001年からは59パーセント増加している。
次いで、教員の資質の向上が11.4パーセントとなっている。英語習得支援は6.71億ドルを計上し2001年から50パーセント増加した。これは英語の習熟度が不足している児童生徒に対する英語および他の教科の学習支援に充当される。読解力向上に10億ドルが充当される。
ただし、州に対して提供された連邦資金が当初の承認された額の半分程度になっており、連邦政府の資金不足が指摘されている。
(百万USドル)
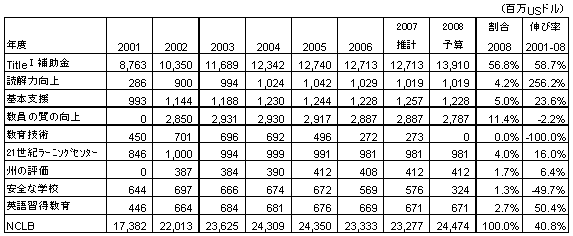
(資料)Department of Education
NCLBの目的は、全米の児童生徒の学力の底上げ、および地域や学校間の格差是正であるが、施策の主体となるのは州である。各州は、それぞれ教育スタンダードを設定し、学力テストを実施する。また、毎年、その年の学力向上の目標(年間向上目標:AYP)を決め、各学校がその目標に達したか否かについて評価を行い、目標に達していない学校については改善策を求めている。さらに、毎年、生徒児童の学力や施策の実績に関する通知書を作成する。このように、各州が州の生徒児童の学力を向上させることで、全米の底上げを図る仕組みになっている。
NCLBの施行から4年が過ぎ、各州のレポートカードのほか、教育省などから学力評価の状況や、研究機関から評価報告書が発表されている。
連邦政府が実施する全米学力調査(NAEP)の2005年度の結果によると、1992年から2005年の間に、第4学年と第8学年の読解力と算数は学力が向上した。しかし、12学年の読解力では、若干減少がみられた。数学では、基礎標準以上が60パーセントに達し、全米の平均得点において,第4学年の場合,1992年から2005年の間に500点満点で18.5点,第8学年でも10.7点の伸びであった。英語においてはほとんど変化は見られなかった。
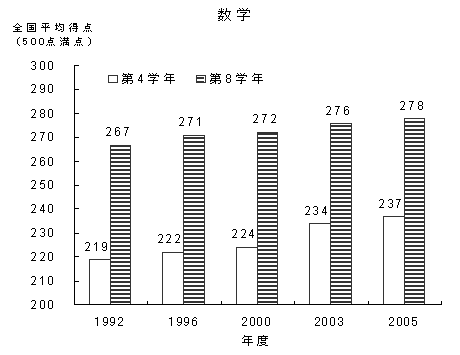
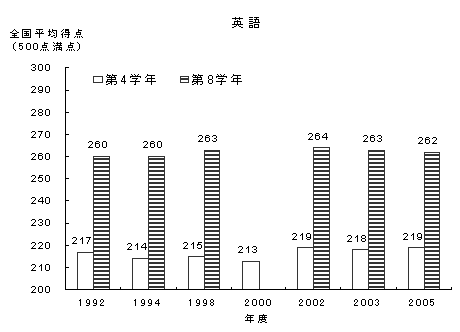
また、NAEPの結果を受けた分析が、2006年1月、教育専門紙「Education Week」に発表された。それによると、1996年度から2005年度の10年間で、アメリカにおいて、教育標準を設定し、それに対応した州内統一学力テストを導入、実施する州は増加し、人種間の学力格差が縮小する傾向にあるとされている。
以下の表は,「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法(NCLB法)」で示された考え方に基づく教育改革の取組の導入状況(2006年1月時点)について,教育専門紙(Education Week)が独自の調査によりまとめたもの。一部,NCLB法で求められていない取組を含む。
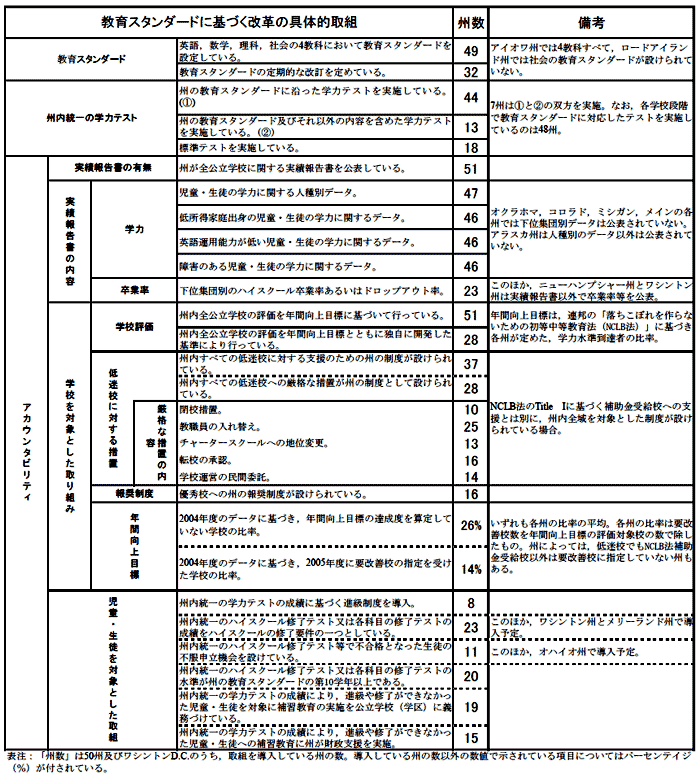
(出典)Quality Counts:A Decade of Standards-based Education At 10(Education Week Jan.5, 2006)
しかし、課題も多いとされる。たとえば、資金面をみると、連邦政府は、連邦資金から補助金を各州の施策に配分することになっており、州は補助金を受け取る条件として施策を実施する。しかし、連邦資金は各州の承認額の半額しか充当されてないのが現状である。現在の連邦資金の規模では、施策を効果的に実施するには十分ではないことが指摘されている。
また、合衆国憲法によって、教育は州に権限があるにもかかわらず、連邦が介入しすぎるといった批判もある。NCLBの施策実施には補助金交付が条件であるが、NCLBには、補助金の裏づけがない義務を州に課する規定がある。これを根拠に州によってはNCLBの適用を回避する動きも見られる。
文部科学省「諸外国の教育の動き2005」2006年
文部省「諸外国の教育行財政制度」2000年
土屋恵司「2001年初等中等教育改正法(NCLB法)の施行状況と問題点」2006年