平成18年12月、改正教育基本法が第165回臨時国会において成立、施行された。
戦後まもなく教育基本法が制定されてから約60年が経過し、わが国はその間、高度経済成長やバブル崩壊といった経済状況の変化や科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化、核家族化など、教育をとりまく社会経済環境は大きく変化してきた。
改正教育基本法はこうした社会環境の変化を踏まえ、これまでの教育基本法の普遍的な理念を守りつつも、今日求められる教育の基本理念を定めるとともに、教育における国と地方公共団体の責務についても明らかにしている。中でも特筆すべきは、同法第17条に基づき、国が「教育振興基本計画」を定めることについての規定が新たに加えられた点である。
この教育振興基本計画について、改正教育基本法では、「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。」としている。
従来、わが国には教育基本法に基づく基本計画は存在していなかったが、他の分野においては、図表1-1に示すように基本法に対応するようなかたちで基本計画が定められている。今回の法改正によって、教育分野においても、同様に基本法に対応した基本計画の制定が定められることとなった。
わが国の教育振興基本計画を定める場合、他分野の基本計画あるいは教育分野における一部先行自治体の基本計画等を参考に内容等について検討することのほかに、同時に教育分野において世界的な競争力をもった海外諸国における基本計画あるいは類似の教育目標を参考にすることも有効と考えられる。
しかしながら、教育基本計画の策定に関して海外諸国に目を転じた場合、わが国の教育基本法ならびに教育振興基本計画に該当する法制度体系が整備されているのかということについて、これまで十分な把握がなされておらず、また、これら基本的法体系と教育施策の基本計画の関係についての整理も十分ではない。
このため、本調査では、今後の教育施策の検討に向けた基礎的資料とするため、欧州、北米、アジアの海外主要各国の教育施策について実態を把握することを目的とした。
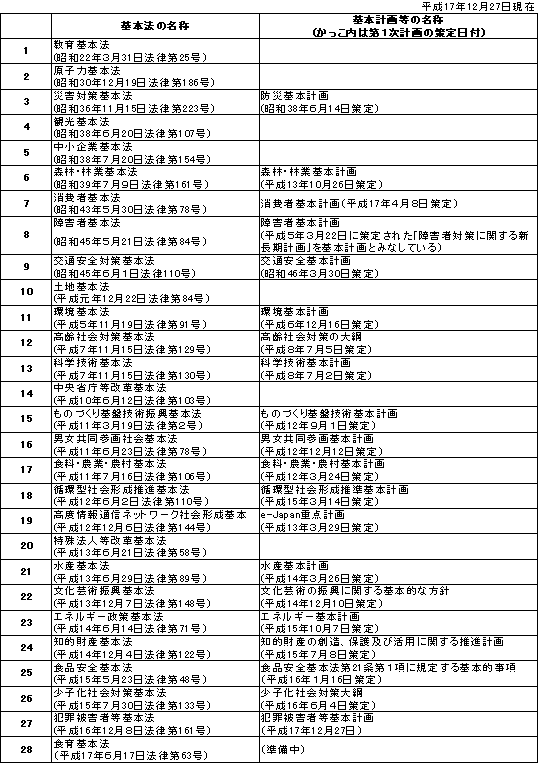
本調査においては、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国、フィンランドの6ヵ国を重点調査国とした。重点対象国の教育基本法ならびに基本計画に相当する法律の制定状況、概要は以下のようになっている。
アメリカでは、教育は基本的に州の管轄となっているため、連邦レベルではわが国の「教育基本法」に相当するものはないが、全米の教育目標を定めた法律がある。各州においては、教育行政の仕組みや学校教育の基本的枠組みを定める州教育法を定めている(ただし、教育の理念などを定めた規定はない)。
イギリスには教育の理念などを定めた「教育基本法」に相当するものはないが、教育制度の総合的な枠組みを定めた法律がある。
フランスでは、教育基本法に相当する法律が度々制定されているが、主要なものは1989年の教育基本法(ジョスパン法)と、2005年の教育基本法(フィヨン法)である。ジョスパン法は、教育を国の最優先課題とすることを公約した社会党政権下で成立した法律であり、主な内容としては、![]() 教育水準向上のための目標、
教育水準向上のための目標、![]() 就学前教育の促進、
就学前教育の促進、![]() 進路指導における生徒の主体性の重視、
進路指導における生徒の主体性の重視、![]() 学校運営に対する生徒の参加の促進、
学校運営に対する生徒の参加の促進、![]() 教員養成制度の改革、
教員養成制度の改革、![]() 教員・父母・学生・地方公共団体の代表からなる審議会の設置、等の規定がある。
教員・父母・学生・地方公共団体の代表からなる審議会の設置、等の規定がある。
ドイツでは、アメリカ同様、教育は基本的に州の管轄とされており、連邦レベルでは「教育基本法」に相当するものはない。ただし、高等教育に限り、「高等教育大綱法」が定められている。各州においては、初等中等教育法、高等教育法など個別の法律を制定しているが、教育基本法に相当する法律はない。
韓国では、教育の基本的事項を規定した「教育法」が1949年に制定され、度重なる改正が行われてきたが、1997年に全面的に改正された「教育基本法」が制定された。同法の主な内容としては、![]() 教育理念、
教育理念、![]() 学習権の保障、
学習権の保障、![]() 教育の機会均等、
教育の機会均等、![]() 教育の自主性・専門性の保障、
教育の自主性・専門性の保障、![]() 教育の中立性、
教育の中立性、![]() 義務教育、学校教育、
義務教育、学校教育、![]() 社会教育の奨励、
社会教育の奨励、![]() 英才教育、科学技術教育、教育の情報化など特別な教育への支援、等の規定がある。
英才教育、科学技術教育、教育の情報化など特別な教育への支援、等の規定がある。
フィンランドでは、1999年から施行されている「基礎教育法」がわが国の教育基本法に相当する。同法の主な内容としては、教育目的、教育行政の主体としての地方自治体の役割のほか、学区、教育期間、教育言語、教育内容、支援教育、教育評価、授業時間、学校組織等に至るまで細かく規定している。
本調査では、重点調査国のほか、経済成長著しいBRICsのうち、インド、ロシア、中国の3ヵ国に加え、オランダ、カナダ、イタリアについても調査を行った。これらの国のうち、ロシアと中国の教育基本法類似法の制定状況は以下のようになっている。
中国では、1980年代以降、教育に関する法律制度の整備が進められる中で、1995年に「教育法」が制定された。内容については、従来の教育政策を踏襲し、教育を社会主義現代化建設の基礎として、国家が教育事業の優先的発展を保障するという基本原則が明確に規定されている。
ロシアでは、ソ連邦崩壊以降、市場経済体制への移行にあわせた教育改革が進められ、1992年に「ロシア連邦教育法」が制定された。同法の主な内容としては、![]() 教育政策の原則、
教育政策の原則、![]() 就学前教育から成人教育までの学校制度、
就学前教育から成人教育までの学校制度、![]() 教育行財政、
教育行財政、![]() 教職員の待遇、等の規定がある。
教職員の待遇、等の規定がある。
わが国の教育基本法は、学校教育のほか、生涯学習や教育行政に至るまで幅広く規定が存在する。このため、教育振興基本計画の検討に際しても、教育分野全般について包括的・総合的に捉える必要がある。教育振興基本計画の検討に資する資料を提供することを目的とする本調査では、各国の教育分野全般についての包括的・総合的な計画の有無と内容を調査した。
具体的に、本調査においては、「学校教育分野(就学前教育、初等中等教育、高等教育)」、「生涯学習関連分野(職業教育、社会教育、家庭教育等)」、「教育基盤整備分野(教員、文教施設、教材、教育財政等)」の3分野における教育施策をまとめた基本計画等を収集し、国別・分野別に整理した。基本的に上記3分野にまたがる包括的・総合的な計画を調査対象とするが、総合的な計画が存在しない場合は、「学校教育分野(就学前教育、初等中等教育、高等教育)」における計画を中心に調査を実施した。
| 国名 | 分野 | 基本計画 |
|---|---|---|
| A国 (総合的計画あり) |
生涯学習関連分野 | 名称:「教育基本計画」 →調査対象 |
| 学校教育分野 | ||
| 教育基盤整備分野 | ||
| B国 (総合的計画なし、分野別計画あり) |
生涯学習関連分野 | なし→調査対象外 |
| 学校教育分野 | あり(名称:「学校教育基本計画」) →調査対象 |
|
| 教育基盤整備分野 | あり(名称:「教育基盤整備基本計画」) →調査の実施について検討 |
本調査の前段階として重点調査国以外の国を含め、総合的な基本計画の有無について把握し、一覧表に整理・分類することを最優先課題として調査した。各国の総合的な基本計画の有無とその教育分野の基本的法律(基本法)の関係について確認した後、重点調査国については極力、以下の![]() 〜
〜![]() の調査項目について把握に努めた(図表1-3参照)。その結果、今回調査国における教育の基本的法律と基本計画の関係はおおむね図表1-4のように表すことができると考えられる。
の調査項目について把握に努めた(図表1-3参照)。その結果、今回調査国における教育の基本的法律と基本計画の関係はおおむね図表1-4のように表すことができると考えられる。
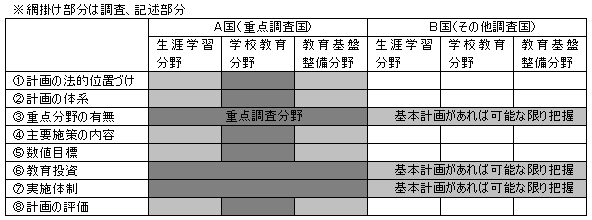
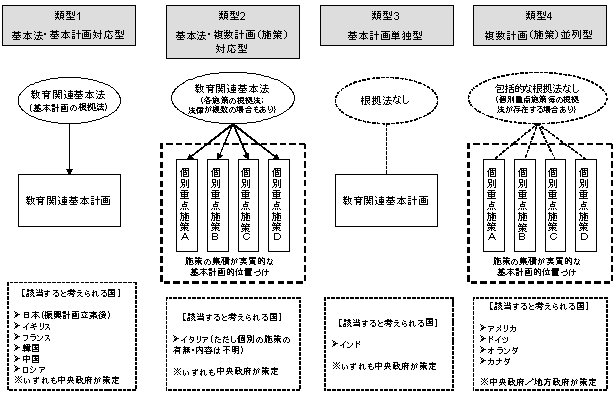
調査対象3分野を包括的・総合的に規定する基本法(わが国の教育基本法に相当する法)の有無についてまず確認を行い、基本計画との関連性(基本計画の上位概念としての基本法であるか否か)について確認した。基本計画が各分野別に分かれる場合は、それぞれの分野における基本法の有無と基本計画の関係について把握した。基本法と基本計画が一体化している場合はその旨、記載した。このほか、基本計画の策定プロセス(策定関与者、所管庁等)、計画期間についても可能な限り把握した。
計画の体系について、まず教育分野においてどのような政策目標が設定されており、かかる政策目標を実現するための具体的施策がどのように策定されているかについて、政策目標と施策の関係を軸に計画の体系を整理した。
基本計画において、国としてどのような分野に重点を置いているのか、どのような人材を育成しようとしているのかについて調査した。特に、重点分野の設定がある場合には、重点分野設定の考え方(国としてなぜ当該分野に重点を置くことにしたのか)について可能な限り把握した。かかる重点分野の捉え方は各国の教育、人材育成に対する考え方が顕著に現れる部分であると思われることから、当該項目については本調査における重点調査項目として捉え、重点調査国以外の国についても基本計画がある場合、可能な限り調査・把握に努めた。
各国に共通する施策、あるいはその国において特徴的な施策の整理を行った。また、科学技術の進歩や少子高齢化、国際化等の現代的課題について、基本計画ではどのような施策を行うことにより対応しようとしているのかについても整理した。
基本計画において、具体的な数値目標(指標)の設定があるかどうか把握した。数値目標がある場合、目標達成に向けてどのような教育施策が実施されたか、また数値目標の達成状況がどのようになっているかについて調査、把握した。
調査対象国においては、どのような教育分野に重点投資しているか(しようとしているか)について把握した。かかる重点投資分野の捉え方は各国の教育、人材育成に対する考え方が顕著に現れる部分であると思われることから、当該項目については本調査における重点調査項目として捉え、重点調査国以外の国についても基本計画がある場合には可能な限り調査・把握に努めた。具体的には、財政投資目標(重点投資分野)の有無および目標設定における基本的な考え方、投資予算規模、財源構成(税、家計負担、その他負担、国債等の別で把握)といった項目について把握を試みるほか、国民に対して教育分野への投資を促進する仕組み(税控除、寄附等)があるかどうかについても可能な限り調査した。
基本計画における教育担当官庁ならびに教育担当官庁以外の役割(法的根拠についても把握)、教育担当省と他省の連携体制、行政以外の主体の役割等について調査、把握した。実施体制の内容把握は、今後わが国において教育振興基本計画を策定する場合に極めて重要な情報となると考えられることから、当該項目については本調査における重点調査項目として捉え、重点調査国以外の国についても基本計画がある場合には可能な限り調査・把握に努めた。
計画の評価体制についても調査・把握を行う。具体的には評価についての法制度、評価の頻度・方法、評価結果と予算との関連、計画の見直しへの反映状況等について把握した。
本調査では、先行する既存調査のほか、日本国内で入手可能な日本語あるいは英語の文献、ウェブサイトを中心に調査を行った。今回、重点調査国のうち、ドイツ、フランス、韓国の3ヵ国に限り、可能な限り各国語の文献についても調査した。その他調査国については日本語、英語文献調査を中心とし、中国語、ロシア語、イタリア語等の文献調査は基本的に行わなかった。
また、今回調査では、現地でのヒアリング調査は行なっていないが、国内外の有識者へのヒアリング・照会は適宜実施した。
| 国名 | 文献例 | 調査対象言語 |
|---|---|---|
| アメリカ |
|
日本語・英語 |
| イギリス |
|
日本語・英語 |
| フランス |
|
日本語・英語・フランス語 |
| ドイツ |
|
日本語・英語・ドイツ語 |
| 韓国 |
|
日本語・韓国語 |
| フィンランド |
|
日本語・英語 |
| インド |
|
日本語・英語 |
| ロシア |
|
日本語・英語 |
| 中国 |
|
日本語・英語 |
| オランダ |
|
日本語・英語 |
| カナダ |
|
日本語・英語 |
| イタリア |
|
日本語・英語 |