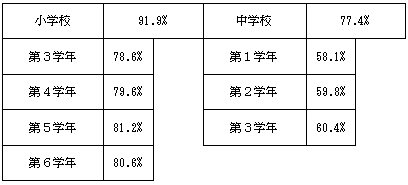| 資料 3 |
「総合的な学習の時間」の概要について
| ○ | 平成8年の中央教育審議会第一次答申においては、
(資料4:中央教育審議会 第一次答申(平成8年7月19日)参照) |
|||||
| ○ | これを受けて、平成10年教育課程審議会答申では、自ら学び自ら考える力などの[生きる力]をはぐくむことを目指す教育課程の基準の改善の趣旨を実現する極めて重要な役割を担うものとして「総合的な学習の時間」の創設が提言された。創設の趣旨は、以下のとおりである。(資料4:教育課程審議会答申(平成10年7月29日)参照)
|
|||||
| ○ | 「総合的な学習の時間」は、平成10年に改訂された学習指導要領に位置付けられ、平成14年から順次本格実施されているところである。 |
| ○ | 「総合的な学習の時間」は、学校教育法施行規則及び学習指導要領総則に各教科、道徳、特別活動とともに教育課程を編成するものとして位置付けられ、年間授業時数、各学校において教育課程上必置とすること、ねらい、具体的な学習活動の例、学習活動を行うにあたっての配慮事項等が示されている。 | ||||||||||||||||||
| ○ | 他方、この時間は、各学校における創意工夫を生かした学習活動を行うものであること、学習活動が各教科等の枠を越えたものであること等から、各教科等のように学習指導要領に内容を規定していない。 | ||||||||||||||||||
| ○ | なお、具体的な学習活動の例として、小・中学校においては、 (資料5参照) 【参考】年間授業時数(学校教育法施行規則(小・中学校)、学習指導要領(高校))
|
| ○ | 平成12年の教育課程審議会答申において、「総合的な学習の時間」の評価の在り方については、各学校において学習活動を定め、学校や児童生徒の実態に応じた特色ある教育活動が展開されるという趣旨から、学習の状況や成果などについて、児童生徒のよい点、学習に対する意欲や態度、進歩の状況などを踏まえて評価することが適当であり、数値的な評価をすることは適当ではないとされた。 |
| ○ | また、学習指導要領に示す「総合的な学習の時間」のねらいなどを踏まえ、各学校において定める具体的な目標や指導内容に基づき、観点を定めて「総合的な学習の時間」の評価を行うことが必要であるとされた。 |
| ○ | 以上を踏まえ、小・中学校の指導要録については、「総合的な学習の時間」に行った「学習活動」を記述した上で、指導の目標や内容に基づいて定めた「観点」を記載し、それらの「観点」のうち、児童生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記載するなど、どのような力が身に付いたかを文章で記述する「評価」の欄を設けることが適当であるとされた。(高等学校については、各教科の学習の評価と同様に、欄としては「学習活動」と「評価」から構成しつつも、各学校において定められた観点を踏まえて評価を行う) (資料4:教育課程審議会答申(平成12年12月4日)参照) |
| ○ | 平成14年度の「総合的な学習の時間」の実施状況は、本年2月にまとめられた「平成14年度公立小・中学校における教育課程の編成状況等の調査結果」によれば、以下のとおりである。 なお、平成15年度の計画状況については、現在、平成15年度の公立小・中学校における教育課程の編成状況等について調査中であり、近々公表する予定である。また、高等学校については、新学習指導要領が今年度から学年進行で本格実施されたところであり、今年度中に公立高等学校における教育課程の編成状況等について、調査を実施する予定である。
|