| (1) |
実態調査の実施
本専門部会では、大学施設のコストマネジメントについて、全ての国立大学と、私立大学のうち省エネ法の第一種及び第二種特定事業者に該当する62校を対象に実態調査を実施した。調査はアンケート方式で行い、平成16年12月に調査票を送付し、国立大学の全校(89校)と私立大学54校から回答を得た。
大学施設の管理運営に関する本格的な調査は先例が少なく、特に国立と私立に同じ内容の調査を行うのは初めてである。この調査により大学の取組状況及び国立と私立の対応の違いや解決すべき課題が明らかになった。
|
| (2) |
施設運営コストの実態 |
| |
| ・ |
経常的経費に占める施設運営コストの割合
施設運営コスト(点検保守費、修繕費、緑地管理費、清掃費及び光熱水費の合計)が人件費を除く経常的経費に占める割合は私立大学のほうが高く、国立大学では10〜15パーセントが最も多く全体平均が14.3パーセントであったのに対し、私立大学は15〜20パーセントが最も多く全体平均は19.5パーセントであった。
|
| |
図1-1 経常的経費に占める施設運営コストの割合 |
| |
| 国立大学(86大学) |
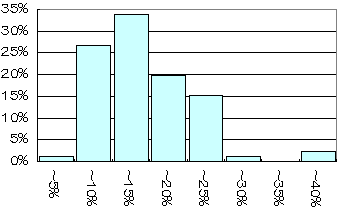
|
| 私立大学(49大学) |
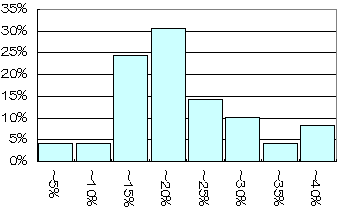 |
| ※未記入の大学は除いて集計した。 |
|
| ・ |
施設運営コストの増減傾向
施設運営コストは、国立大学で増加傾向にあると答えたところが多く、中でも修繕費や光熱水費の増加傾向が目立った。私立大学ではほぼ横ばいのところが多く、特に点検保守、緑地管理、清掃費は7割程度が横ばいであった。
国立大学の修繕費の増大は老朽施設の増加の影響と考えられ、今後もこの傾向が続くと予想される。光熱水費の増加は、施設保有面積の増加に加え、空調や照明等の室内環境水準の向上、パソコンや各種サーバなど情報通信機器の増加、実験内容の高度化等が重なったためと考えられる。
|
| |
図1-2 施設運営コストの増減傾向 |
| |
|
| ・ |
電力使用のパターン
大学等の電力使用パターンの特徴は、ピーク時に対するベース電力(休日や夜間でも使い続けている電力)の割合が高いことで、オフィスや工場で夜間や休業時の使用量が極端に少なくなるのに対し、大学等は4〜5割程度である。この要因としては、研究活動の24時間化、恒温恒湿室やクリーンルームなど連続運転が必要な設備の増加、各種サーバの増加等が考えられる。 |
|
| (3) |
施設マネジメント推進組織の実態 |
| |
| ・ |
業務担当部署の集約と分散
学内で施設運営業務を担当する部署については、集約型と分散型の考え方がある。図1-3は複数のキャンパスを持つ大学の実態で、国立大学は私立大学に比べて担当部署が分散する傾向があった。
それぞれのメリットに関する質問では、集約型で施設関連業務全体の整合がとれ無駄が省ける点や全学方針に基づく重点的経費配分を指摘する意見が多かった。分散型のメリットとして利用者の要望に敏速に対応できる点が予想されるが、国立大学の回答からはそれを裏付けるはっきりとした傾向は見られなかった。
|
| |
図1-3 施設業務担当部署の形態(主要キャンパスが複数の大学) |
| |
|
| |
図1-4 集約型と分散型のメリット比較(主要キャンパスが複数の大学) |
| |
|
| ・ |
外部委託の状況
米国の有力大学では、日本の大学に比べて施設担当部署に多数の職員を雇用している例が多い。米国では修繕や緑地管理等を大学職員が行っているのに対し、日本では外部委託が多いことが職員数の違いに表れている。日本でも過去には多数の職員が施設管理を行っていた時期があるが、職員数の削減と併せて外部委託が増加する傾向が定着した。
外部委託は、民間ノウハウの活用による業務効率の向上等のメリットがある反面、契約業務や監督業務が必要なことや、業務の硬直化や迅速な対応の点で課題もある。法人への移行を機に再度施設管理専門の職員雇用を検討している大学もあり、パートタイマーの雇用が効果を上げる場合も考えられる。各大学等が自らの実態にあった方法を検討し、最も効率的で利用者の満足が得られる体制づくりが望まれる。 |
|
| |
参考 施設業務担当職員数の例 |
| |
| マサチューセッツ工科大学(M.I.T)【MIT Facts 2005、MIT Department of Facilities FY2004より】 |
| |
学生数 |
10,317名 |
| |
教職員数 |
9,400名(Academic Staff:2,177) |
| |
|
内 施設系職員 559名 |
| |
|
| ・ |
Planning,Design,Construction&Administration |
:80.5 |
| ・ |
Trades Maintenance&Daily Services |
:478.5 |
|
| |
敷地面積 |
62万6千 |
| |
建物床面積 |
101万 |
|
| カリフォルニア大学バークレー校【University of California office of the President Homepageより】 |
| |
学生数 |
約3万名 |
| |
教職員数 |
(Full-Time) 11,679名 |
| |
|
| ・ |
Academic Staff:2,709 Professional and Support Staff |
:5,519 |
|
| |
|
内 施設系職員(Full Time) 約944名 |
| |
|
| ・ |
Architecture,Engineering&Applied Servides |
:150 |
| ・ |
Maintenance,Fabrication&Operations |
:794 |
|
| |
敷地面積 |
522万 |
| |
建物床面積 |
80万 |
|
| 東京大学(平成17年5月1日現在) |
| |
学生数 |
28,926名 |
| |
教職員数 |
7,520名 内 施設部 74名 |
| |
敷地面積 |
105万4千 (本郷、駒場、柏団地の計) (本郷、駒場、柏団地の計) |
| |
建物床面積 |
113万6千 |
|
|
|
|
| (4) |
施設運営コストの効率化に関する取組状況 |
| |
| ・ |
保有施設の実態把握
施設マネジメントの基礎は保有施設の実態把握であるが、現状では十分と言えず、私立大学に比べ国立大学の取組が遅れている。要修繕箇所、研究室等の使用実態、重要設備の更新時期等の把握は半数以上で行われているが、光熱水使用量を利用者ごとに把握できるのは、私立大学で44パーセント、国立大学で38パーセントに留まった。最も違いが大きいのは工事履歴を記録した管理用図面の有無で、私立大学の54パーセントに対し国立大学ではわずか21パーセントであった。これは一般企業に比べ極めて低い状況であり、正確な実態把握なしでは対策の検討すら不可能である。
|
| |
| 図1-5 基礎資料の把握状況 |
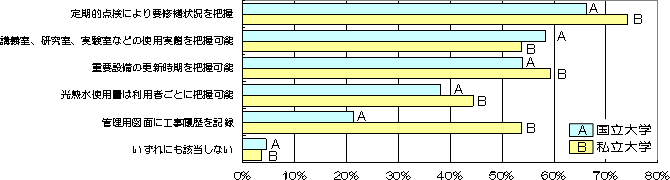
|
|
| ・ |
エネルギー使用量の将来予測
施設保有面積の増加、空調や照明等の室内水準の向上、実験内容の高度化等は施設運営コストを増加させる要因であり、今後の大学運営や施設整備を検討する際には、将来のシミュレーションを行い中長期的な予測を行う必要がある。この点でも国立大学の取組は私立大学と比較して低調で、実施しているところも新築、大規模改修、設備機器更新等のハード面の変化に伴う変動推計がほとんどで、研究内容等のソフト面の変化を予測した事例は少なかった。
|
| |
| 図1-6 エネルギー使用量の将来予測 |
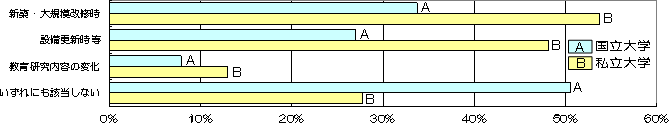
|
|
| ・ |
施設運営コストの縮減への取組状況
施設運営コストの縮減への取組の中で最も多いのが、教職員や学生に対する電力使用量のピーク抑制への協力要請で、8割の大学で実施され効果をあげているが、削減結果を積極的に公表しているのは約3割に留まる。
学内の体制づくりでは、全ての国立大学で施設の点検評価に関する委員会が設置されている一方、施設運営コストや省エネルギーに関する委員会を設置し、学内総意に基づく基本方針を策定している国立大学は半数に満たない。施設担当職員のスキルアップトレーニングの実施は約半数程度である。
今後の計画では、新築や大規模改修時の省エネルギー対応や、既存施設に対する照明制御等の機能付加を計画中の大学が多い一方、予防保全の実施、省エネルギー診断 の活用、ESCO事業(20ページ参照)の活用等を計画中の大学はまだ少ない。総じて私立大学の取組が進んでおり、国立大学はまだ一部に留まっている。 の活用、ESCO事業(20ページ参照)の活用等を計画中の大学はまだ少ない。総じて私立大学の取組が進んでおり、国立大学はまだ一部に留まっている。 |
| |
 |
省エネルギー診断
省エネルギーの観点から、施設の使用や設備システム及び現状のエネルギー使用量等について調査、分析し、各施設にあった省エネルギー手法を提案するサービス |
|
|
|
| |
| 図1-7 施設運営コスト効率化への取組状況 |
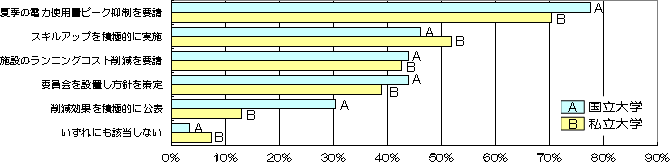
|
|
| |
| 図1-8 施設運営コスト効率化についての具体的計画 |
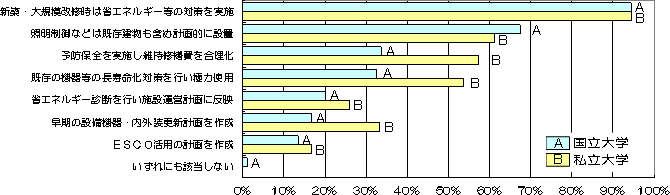
|
|
| ・ |
高効率機器等の導入状況
省エネルギー効果が高いとされている高効率型照明(Hf等)、空調のインバータ制御、複層ガラスや断熱材等の採用等については、新築や大規模改修事業での導入率が高いものの既存施設への導入はまだ少ない。保有施設の過半で導入されている大学の割合は、高効率型照明器具が3割程度で他は概ね1割程度に留まる。
これは、既存施設の改善余地が大きく、今後の対応次第では省エネルギーの可能性が高いことを表しているが、現状では省エネルギーを主目的とした改修工事は少なく、改築及び大規模改修を待つのが一般的である。
|
| |
| 図1-9 新築・大規模改修時の高効率機器導入状況 |
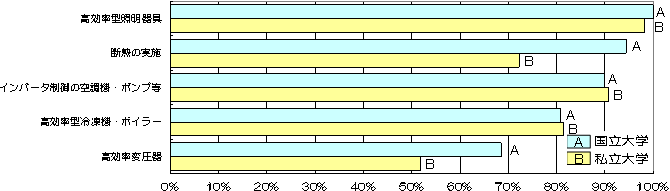
|
| 図1-10 既存施設への高効率機器導入状況 |
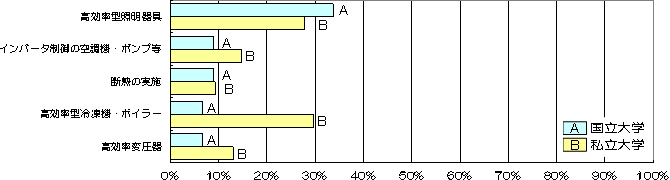 |
|
|
| (5) |
調査結果から読みとれる傾向とその要因 |
| |
| ・ |
国立大学と私立大学の傾向の違い
全体としては、私立大学の方が国立大学に比べて、施設運営に対し積極的に取り組んでいる傾向が読みとれる。特に、基礎資料の把握状況、エネルギー使用量の将来予測、施設運営コスト縮減の具体的計画では両者の違いがはっきりと現れた。経常経費に占める施設運営コストの割合も相対的に私立大学の水準が高く、施設の維持管理に応分の経費をかける意識が実践に反映されている。
もちろん国立大学と私立大学では、組織形態、財務制度、意志決定プロセス等様々な相違点があり単純な比較は難しいが、このような相違が生まれる背景を考えることが、今後の課題を解決する上で多くの示唆を与えてくれる。
|
| ・ |
国立大学のコストマネジメントが低調な要因
相対的に国立大学の取組が低調な理由としては、文部科学省がアンケート調査に先立って行った国立大学へのヒヤリングの結果、次のような要因が複合的かつ長期にわたり継続されてきたためと考えられる。 |
| |
 |
学内で施設運営業務と関係予算配分に関わる部署が財務、施設、各部局など多岐にわたり、各々が独自の方針や慣習に従って実行するため、大学全体としての方針がなく、関係者間の共通認識も不足していること。 |
 |
施設運営費は本部から各部局に配分され、部局の裁量で執行する方式が多いため、例えば全学の光熱水費を調べるにも部局照会が必要になるなど、大学全体の実状把握が不十分だったこと。 |
 |
法人化以前の会計制度では、予算は項目毎に計上され他の項目への流用は原則認められなかったため、項目毎の予算額に沿った執行が多かったこと。 |
 |
部局への経費配分は定員や前年度実績が根拠となるため、経費縮減の成果が当事者に還元されるとは限らず、モチベーションが働かないこと。 |
 |
業務委託が増加傾向にあるが、必ずしも業務内容の検証や契約方法、単位の改善による縮減効果を積極的に求める意識に乏しいこと。 |
|
|