 |
国際展開手法のバリエーション拡大 |
|
|
| 日本コンテンツの国際展開は1970年代にアニメが米国へ、1980年代には「おしん」の世界的なヒット、1990年代には「東京ラブストーリー」がアジアでヒットするなどの実績を持っているが、かつては翻訳や編集は施されるにしても、基本的にはコンテンツをそのまま販売するという形が一般的であった。 |
| しかし、現在ではバラエティ番組のフォーマット販売やドラマ、映画のリメイク権販売、複数市場を視野に入れた国際共同制作、キャラクターのライセンス輸出、プロダクト・プレイスメントなど国際展開の手法は多岐にわたっている。 |
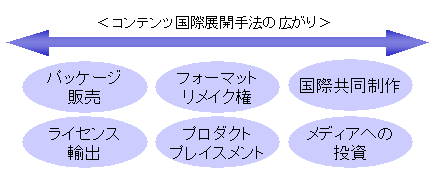 |
 |
メディアへの投資 |
|
|
最近では、メディアそのものへの投資を行うことによって作品を露出できるチャンネルを確保する動きも現れている。例えば、アニメの人気が高い韓国において、複数の日系事業者がアニメーション専門チャンネルの運営事業者に出資することにより、多数の日本作品を放送することに成功している。
|
 |
中国のWTO加盟を契機とした規制緩和 |
|
|
| 中国では、WTO加盟を契機として、外国映画輸入枠が拡大している他、中国国産映画に限定した外資系による配給事業も認められつつある。さらに、中国の都市部では映画館のデジタル化とシネコン化が急務となっており、外資系事業者に対する映画館運営事業の出資も認められつつあり、外資規制についての緩和が進んでいる。 |
こうした規制緩和動向は大きなビジネスチャンスにつながる可能性があるため、常に注目しておく必要がある。
|
 |
現地流通への多角的な参入 |
|
|
| コンテンツの国際展開手法のバリエーションは既に幅広いものになっているが、個別コンテンツベースの輸出のみではなく、現地におけるコンテンツ流通により積極的に参入していく必要がある。 |
| 外国コンテンツに対して設けられている流入規制については、国際共同制作やリメーク権・フォーマット権の販売等によって回避できるため、既存の手法を現地流通参入の視点からもっと活用すべきである。また、アジアにおいてもコンテンツ産業分野に関する規制緩和、市場開放が進展する可能性があり、こうした動向を活用して現地のコンテンツ流通に対する参入を積極的に図っていくべきである。 |
(2)提言 |
−提言 現地流通への積極的参入− 現地流通への積極的参入−
| ○ |
コンテンツ国際展開を推進するには、パッケージ販売に加え、国際共同制作、リメーク権・フォーマット権販売、海外メディアに対する投資といった多角的な手法を活用することにより、現地流通への積極的参入を図るべきである。 |
| ○ |
コンテンツのアイデア盗用を防ぐよう、所要の環境整備を図る必要がある。 |
| ○ |
アジア各地におけるコンテンツ産業に関連した規制緩和動向を踏まえることにより、多角的手法による効果の最大化を図るべきである。 |
| 例) |
| ・ |
テレビ番組の年間包括契約による海外販売の展開 |
| ・ |
海外パートナーとの共同事業展開による複数市場におけるコンテンツ輸出 |
| ・ |
現地の専門チャンネルに対する日系各事業者による出資 |
|
|
|