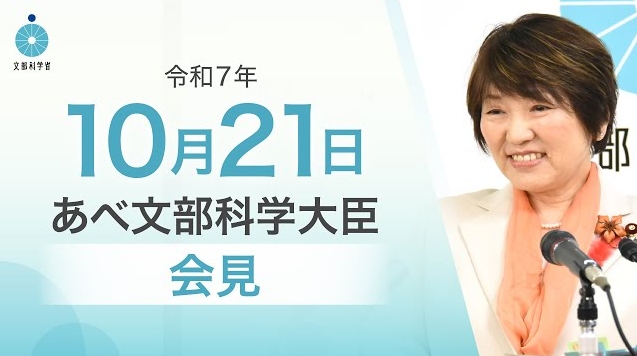- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年10月21日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年10月21日)
令和7年10月21日(火曜日)
教育、科学技術・学術、その他
キーワード
内閣総辞職,大臣在任中の成果と課題、次期大臣への期待,理系人材の増加に向けた取組,性に関する指導の在り方,「科学の再興」に向けた今後の期待,大臣在任中の出張・視察,参政党による街頭演説,今後の文部科学行政への関わり方
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年10月21日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年10月21日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から1件でございます。先ほどの閣議におきまして、総理に辞表を提出いたしました。新しい大臣が任命されるまでは大臣としての職務を継続することになるところでございますが、令和5年12月の副大臣就任に引き続きまして、令和6年10月からは文部科学大臣に就任させていただきまして、この間、記者の皆様も含め多くの皆様に大変お世話になりましたことに御礼申し上げます。本当にありがとうございました。私からは以上です。
記者)
これまでを振り返ってというところですけれども、昨年10月の就任会見では誰も取り残さないことが大事だとした上で、教師を取り巻く環境整備や研究力向上、スポーツ、文化芸術立国の実現を掲げられました。1年間、各分野でそれぞれ様々な政策がございましたけれども、これまでを振り返り特に印象に残ったこと、または後任の大臣に期待したいことをそれぞれお願いいたします。
大臣)
令和6年10月1日、文部科学大臣に着任をいたしましたけれども、副大臣の期間と合わせますと本日で通算678日目となりました。この間、「誰1人取り残されない社会」の実現を目指しまして全力で取り組んでまいりました。特に、先の通常国会におきましては与野党の委員の皆様と活発な議論を経まして、また約50年ぶりとなる教職調整額の引き上げ、また高等教育費の負担軽減など重要な政策を実現するとともに、中学校35人学級への道筋をつけることができたことは大臣としての役割を一定程度果たせたものというふうに考えているところでございます。やはり通常国会のときに文部科学省の官僚の皆さんがしっかりと私をお支えくださったことは誠に大きいことだというふうに考えています。そのときに大臣をさせていただきましたこと、本当にしっかりと頑張らなければいけないと日々努力をさせていただいておりました。また、この他、印象深いことはたくさんございましたけれども、例えば地域産業を支える人材の育成に向けまして関係省庁と連携しながら「産業人材育成プラン」を策定させていただきましたこと、また専門高校を拠点といたしました地方創生支援など取り組んだことも今後につながる成果であったというふうに考えているところでございます。また、私自身の国際経験も生かさせていただきながらTICAD9を通じましてアフリカ諸国との関係強化の取組、教育分野における国際貢献と関連施策の充実も努力をさせていただいたところでございます。我が国の研究力の向上に向けまして、基礎研究への支援等にも努めてまいりました。先日はノーベル生理学、また医学賞、化学賞を日本人2人が受賞したこと、国民にとって大きな誇りと励みとなったところでございます。もちろん文部科学行政におきましてはまだまだ課題が山積しているところでございますし、今後も様々な課題に直面することになるというふうに思います。新しい大臣には文部科学省職員の先頭に立って文部科学行政の推進に尽力をしていただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
記者)
文部科学行政に関われて通算678日ということなのですが、成果が出たと先ほどおっしゃっていただきましたが、一方で道半ばという政策もあると思います。心残りであるということがありましたら教えてください。また、次の大臣に向けてメッセージや託したいことがありましたら教えていただけますでしょうか。
大臣)
先ほど申し上げましたように、教職調整額の引き上げでございますけれども、実現いたしましたけれども、学校における働き方改革、ここは改革のいわゆる途上でございまして、今後さらに加速していく必要がございますし、またいわゆる高校の無償化、ここの部分と合わせまして国公私立の枠を超えた高校の在り方ということの見直しも含めまして高校改革に向けた議論も早急に進める必要があるというふうに思っているところでございます。また、ノーベル賞の坂口先生と北川先生と直接御意見いただきましたけれども、何と言っても基礎研究への支援と、また「科学の再興」の部分の実現も最重要課題でございまして、このままでは本当に次のノーベル賞の候補の方々をしっかりお支えできるような体制になっているとは思えないので、そこはまた閣外に出てからもしっかり応援をしてまいりたいというふうに思います。この他、挙げればき切りはございませんが、各分野ともまた結論に至っていないものも多くございまして、今後とも文部科学省一丸となって議論を深めてもらい、またそれぞれの政策を前に進めていただきたいというふうに考えているところでございます。私自身、立場は次どうなるかまだ全く分かりませんけれども、文部科学大臣経験者として今後もしっかりと状況を注視していきながらいわゆる側面支援、場合によっては叱咤激励をしていきたいというふうに思っているところでございます。
記者)
先ほど、振り返りの中でもノーベル賞の受賞について触れられて、今も基礎研究が大事だということで触れられていましたけれども、副大臣、大臣それぞれの在任中にDXハイスクールの導入、拡充について尽力されてきたと思うのですが、理系人材の底上げという意味でも底上げとか裾野の拡大という狙いが恐らくあるのだと思うのですが、そこら辺、御自身で振り返って理系人材をいかに育てるかというところ、これまでどんな取組、DXハイスクールについてはどんなふうに振りかえられますでしょうか。
大臣)
現在、大学教育段階におきましてはデジタル、理数分野のいわゆる学部転換の取組が進む中でございますけれども、この政策効果、実は最大限に発揮していくためにも高校段階、もっと早くても大切だと思いますが、デジタル等の成長分野を支える人材育成の抜本的強化が必要だというふうに考えているところでございます。このため、本事業を通じまして全国の高等学校の最新のICT環境、また整備、また専門的な外部人材、やはり教える方が大切なのでその活用をした形の実践的な取組を推進して現場の教師の指導力の向上、これを図ってきたところでもございます。文部科学省としていたしましては、引き続きこの本事業を推進していきながらデジタルと成長分野の人材育成の強化に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
記者)
大臣在任中に教員の盗撮事案が発覚するなど、子供たちが性暴力性被害の被害者になる事案が相次いで発覚しました。これらの事件については防犯カメラの設置とか、スマホ持込ルールなどの対策が議論されていますけれども、この対策の一つの論点として子供たちに対する教育の充実が必要という意見があります。学習指導要領の改定に向けた議論も進んでいますけれども、性に関する指導について今後どうあるべきと考えるか、あべ大臣はこういった運営について関心を持っていらっしゃると思うので議員としてお考えを伺えばと思います。
大臣)
性教育に関しては、私はずっと当選以来取り組んできた部分でございます。そうした中で、性に関する指導も含めて学習指導要領については現在、中央教育審議会におきまして改定に向けた具体的な議論が行われているところでございまして、現時点で大臣としての立場でこうあるべきといったコメントをすることは控えたいというふうに思います。その上で、本日が最後の会見となりますのであえて個人的な期待を申し上げますと、やはり生命(いのち)の安全教育であれ、性に関する指導であれ、最も大切なことは子供たちを守ることでございまして、そのために何が必要なのかという観点からぜひ活発な議論をお願いしたいというふうに思っているところでございます。また、本件につきましては私自身、大臣就任前から議員としても、先ほど申し上げましたようにまさに力をずっと入れてきた部分でございまして、今後も引き続き子供たちを性暴力からしっかりと守るという、守り抜くというために最大限努力をしてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
大臣、先ほども科学の再興についてお話があったのですけれども、具体的に次の大臣にこれだけは実現してほしいというようなことがあれば教えてください。
大臣)
次の大臣がまだよく分からないので、現在、文部科学省におきましては「科学の再興」に向けまして具体的な対応策を検討すべく有識者の会議を立ち上げて今議論を進めているところでございます。また、先日のノーベル賞を受賞した坂口先生、北川先生の御意見にもあったとおり、基礎研究を重視すること、また若手研究者の研究時間をしっかり確保していくこと、また研究支援人材、やはり研究者が全てのことをやらなければいけないというところをしっかりと支援人材を入れていき、研究者が真に研究ができる環境を作っていくことに対する施策等が必要であるというふうに考えているところでございまして、それは文科省の担当省庁が、担当の人たちが今一生懸命やっているところでございまして、また今後も我が国から優れた科学技術・イノベーションの成果が創出されるように次の大臣にも引き続き、文科省の担当者は今一生懸命やっておりますが、しっかりそれを支えて独創的で多様な基礎研究の支援と研究支援人材の育成、先ほど申し上げました研究環境の改善、これにつきますので、改善に向けました施策を一層進めていきながら必要な予算の確保、また全力で取り組んでいただきたいと思いまして、これも閣外に出てもしっかりとこの部分も応援させていただきたいと思います。
記者)
大臣、在任中に国内外問わず大学ですとか研究機関とかいろいろなところに視察に行かれていたかと思います。この中で印象に残っている視察先があったら教えてください。それと合わせまして、そこで得た知見が文部科学省でのどんな政策に生きたいとお考えになるかも教えてください。
大臣)
大臣の就任以降、現場の声を聞き、また文部科学行政に活かすという観点から学校、文化・スポーツ施設、研究機関、国内外の様々な場所を訪問いたしました。数えてくれたら国内出張が64回あったようでございまして、ちょっと多かったのかどうかは分からない。大体1人でもしょっちゅう動いていますから。やはり現場の声が私はまさに大切だと思っておりまして今回も、また海外出張は6カ国、5回行かせていただいたそうでございます。それぞれの訪問先で大変勉強させていただきました。特に印象に残ったもの、例えばガーナ・エジプト、これはTICADに向けた出張でございましたが、特に世界銀行と連携をして、連携をしていく観点からも訪問したところでございますが、関係閣僚との会談、また学校現場を視察させていただきまして、その後、TICAD9に合わせて両国の教育相と意向表明書、LOIでございますが、これを世界銀行とJICAとの署名を実現できました。このときにやはり感じたのは、日本の教育が海外に行ったら本当に評価がされているということでございました。また、国内外の多くの大学、いわゆる研究機関と意見交換もさせていただきまして、例えば「グローバル卓越人材招へい研究大学強化」、EXPERT-Jでございますが、この取組を、迅速に開始をいたしまして国際頭脳循環の強化を図ることができました。やはり日本だけで頑張っていくのではない、やはり海外の方と一緒に頭脳循環をしていくという環境整備が少しは皆さんと一緒に頑張れたかなと思っておりまして、それを加速していくことがまさにもっと次の課題となるのかなと。これ以外も出張を通じまして多くの知見をいただきまして関連施策を図ってまいりました。関係者の皆様に大変感謝をするとともに、一番最後に行きましたのが奈良県の五條というところに行きまして、市立の農業高校、それで4年制のいわゆる農業者になりたいという子たちが東京やいろいろなところからそこに住んでいろいろなことを手伝っている、やはり地方創生を考えたときにこういう地域密着型の教育というのもまさに人を呼び込む、また関係人口を増やしていくという観点から、また地域産業を守るという観点からはまさに重要だというふうに感じたところでございます。また文部科学大臣という職責は、職は離れますけれども、この経験を踏まえまして文部科学行政、文部科学省の取組をしっかり応援してまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
少し逸れた質問で恐縮ですけれども、19日の参政党の街頭演説で国立大学の学生がお金のために外資系企業の就職を希望していて、外資系企業が潤うと国民の所得が減る、そして国はその大学に税金を交付してその流れを助長しているというような主張がありました。大臣も国としてもこの場で国立大の支援には取り組んでこられたと思いますけれども、こうした考えについてお聞かせください。
大臣)
御指摘の神谷代表の発言につきましては報道で承知をしておりますけれども、国立大学は我が国の将来を担う有為な人材を育成し輩出する役割を担うべきという御主張だったのかもしれないというふうに考えております。他方で、国公私を問わず大学の卒業生はそれぞれ様々な職業につき、また社会で活躍をされているところでございますので、卒業生の就職先が外資系企業かどうか否かであるということを国からの支援の在り方と一律に結びつけることは難しいというふうに考えています。ただ、先ほど申し上げたように報道でしか承知しておらず、どういった場面でどういった趣旨の発言なのか詳細を把握しておりませんので、これ以上のコメントは控えさせていただきます。
記者)
先ほどから少し話も出ていますけれども、これからも大臣という立場ではなくなるけれども、文科行政には関わっていくであろうというところでお話しされていますけれども、特にこのテーマでこういうことをしたいみたいなことがございましたら教えてください。
大臣)
先ほど申し上げましたが、文部科学行政は様々な課題が山積をしておりまして、1つ1つの課題を解決して文部科学行政を前に進めていくためには、まず文部科学省だけではなくて関係省庁、ここがまさに大切でございまして、立法府をはじめとして幅広い主体の力を動員していく必要があります。それは省庁横断だけでなく、地域がやはりどのように考えていくかということがやはり大切でございますので、そこからもやはりしっかり声を上げていきながらどういうふうに主体的にそれぞれが関わっていくかということがまさに重要だというふうに思っております。特に産業界は本当に人材不足に悩む中、産業界の考える人材育成とは何であるかということを意見だけではなく、財源も人材も含めてトータルでやっていかないと、文部科学行政だけで成り立つ話ではないというふうに私は考えておりまして、そのためには大臣にしかできないこともございますが、逆に閣外にいるからこそできることもたくさんございますのでしっかり応援をしていきたいというふうに思っております。私といたしましては、大臣を離れた後も、また大臣経験者、すなわち文部科学行政の当事者の1人といたしまして今後も文部科学省におきまして重要政策が実行されるよう、あらゆる立場で責任を持って取り組んでいきたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室