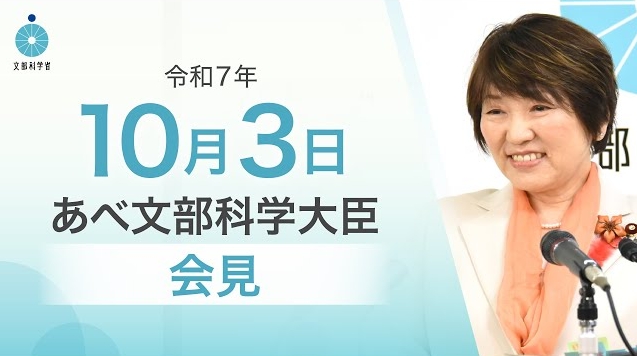- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年10月3日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年10月3日)
令和7年10月3日(金曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
第22回STSフォーラム年次総会への参加、全国学生調査の結果と学問分野ごとの学習時間差の分析、外国人の子供の就学状況等調査の結果、全国学力・学習状況調査における結果公表方法の見直しと学力の底上げに向けた取組の具体化
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年10月3日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年10月3日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございます。10月5日日曜日でございますが、京都市で開催されます第22回科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム(STSフォーラム)の年次総会に参加をさせていただきます。午後に予定されております「基礎研究、イノベーションと政策」をテーマといたしますセッションに登壇させていただくとともに、この機会に各国要人との間で科学技術分野での協力等につきまして会談を行う予定でございます。本総会の出席を通じまして我が国の科学技術分野の国際協力を前に進め、我が国における研究力の強化に努めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
先週発表されました全国学生調査に関してなのですけれども、専攻する分野によって学生さんのいわゆる勉強に充てる時間が結構大幅に違うということで、理系の特に医学の方とかはすごく長くてというような傾向がありましたけれども、これだけ差が出ているということに関して大臣はどう思いますでしょうか。
大臣)
文部科学省におきましては、学生目線からの大学教育、また学びの実態を把握することを目的といたしまして「全国学生調査」を実施しているところでございまして、第4回の施工実施の結果を先日、30日でございますが、発表、公表させていただいたところでございます。その中におきましては、学部学生の最終学年におきまして医学・獣医学系の学生は実習などの授業への出席とその予習・復習等に関する学習時間、また国家試験の勉強などの自主的な学習時間が多い一方で、人文・社会学系の学生は学習時間が全般的に少ないことが明らかになりました。少子化が進展する中にありましても、「知の総和」向上を目指すために個々の学生の学習の質と量を充実させていくことは不可欠でございまして、そのためにも学習時間の確保は大きな課題というふうに私どもも認識をしているところでございます。また、人文・社会学系の学生につきましては数理・統計・データサイエンスに関する知識が身についている割合が、理・工・農分野に比べて低いという結果も出ているところでございます。これらの結果も踏まえまして、各大学におきまして学生の主体的・自律的な学習を促す環境が構築されるとともに、理系的素養を身につける教育の推進など、社会の変化に対応した学習が行われるよう、文部科学省といたしましても引き続き各大学の取組を、支援してまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
昨日、令和6年度の外国人の子供の就学状況調査の結果が公表されまして、学齢相当の外国人の子供の人数が大きく増加していることが判明しました。こうした結果を受けて大臣の受け止め、そして外国人児童生徒の就学における課題は何か、そしてその課題に向けてどのような対応が必要と考えているか教えてください。
大臣)
今回の調査結果でございますが、学齢相当の外国人の子供の人数は約16万人となりまして、前回調査よりも1万人以上の増加というふうになったところでございます。外国人の児童生徒の増加に伴う支援の充実が求められているということから、これまでも就学促進に取り組む自治体への支援とともに日本語指導に必要な教員定数の安定的な確保、また補助者の活用などによる受入れ、また支援体制の整備に努めてきたところでございます。また現在、外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議を設置いたしまして、今後の取り組むべき施策等について議論をいただいているところでございまして、同会議での議論も踏まえながらさらなる教育の充実方策についてしっかりと検討してまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
全国学力・学習状況調査について質問させてください。今年度から公表方法が3段階に改められ、先日、最後の都道府県政令市別の結果が公表されました。平均正答率は地域差ばかりが注目されがちな状況を変えることが目的だったかと思いますが、今回の公表方法の見直しの成果を現時点でどう受け止めていらっしゃるのかということをお伺いしたいです。
大臣)
全国の学力学習・状況調査(注)の結果につきましては、今年度から学校への結果返却時期の早期化、さらには分析結果の丁寧かつ効果的な発信等のためにおっしゃるように3段階に分けて公表をいたしました。この学校現場の要望に答えまして、夏休み前に結果を提出し1人1人の学習指導の改善の取組を支援できたこと、また学びの改善につながるデータを丁寧に分析しながら、例えば箱ひげ図や、またチャート等も加えまして公表内容を充実させることができたことなどは、今回公表方法を見直した成果であるというふうに私ども考えているところでございます。文部科学省としては、本調査をより良い形で実施できるよう、引き続き教育委員会また学校等の様々な関係者の意見を丁寧に聞かせていただきながら進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
(注)「全国の学力学習・状況調査」は、正しくは「全国学力・学習状況調査」です
記者)
全国学力・学習状況調査について引き続き伺います。先日、都道府県政令市別のデータが公表されました。各教科の正答数を成績段階別に見ると、特に成績下位層について差が挙げられたという分析がされていたと思います。それについて大臣の見解を伺います。また、学力の底上げをどう図るかという点について、特に社会経済的背景が厳しいSES層へのアプローチを含めて国として取り組むこと、また自治体に求めること、それぞれお伺いします。
大臣)
先日公表いたしました全国学力・学習状況調査の結果におきまして、全ての教科で各都道府県、指定都市の平均正答率とIRTバンドの層の分布は全国的なばらつきの傾向と大きな差は見られないと判断しているところでございますが、一部の都道府県・指定都市におきましては全国と比べて下位層の割合が10ポイント以上多いなどの状況も見られたところでございます。本調査の重要な目的は、児童生徒一人一人の学習の改善にあります。文部科学省におきましては、今回初めて都道府県・指定都市別の結果を、整理をいたしまして、特徴を文書で説明いたしました「都道府県・指定都市別ノート」を作成いたしましてお示しをしたところでございます。各都道府県等におきましては、このノートを含め今回の分析結果を活用いただきながら分布また習熟度に一層着目をしていきながら学力の下位層の児童生徒を、下支えをしていくという、この取組の具体化をさらに進めていただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室