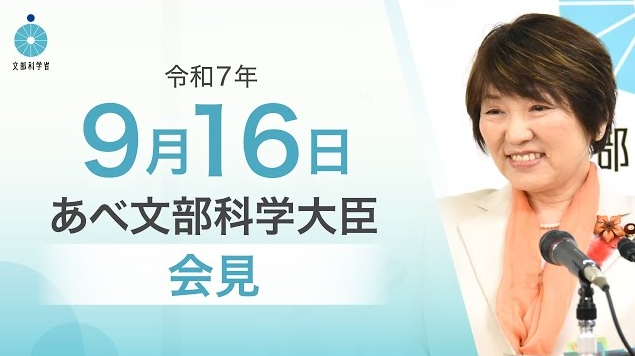- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年9月16日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年9月16日)
令和7年9月16日(火曜日)
教育、科学技術・学術、文化
キーワード
「ながさきピース文化祭2025」開会式への出席,長崎大学、長崎純心大学、国立諫早青少年自然の家への視察,大学入学共通テストWeb出願開始,JAXAの火星衛星探査計画「MMX」,文部科学省におけるAIの開発、活用推進のための施策、マテリアル分野の研究開発でのAIの活用,「こども性暴力防止法」に基づく教員の性犯罪歴の確認、学校現場における防犯カメラの設置,学校における働き方改革のための事務職員、支援スタッフの充実,不登校児童生徒の健康診断の受診率と健康管理,北海道札幌ろう学校「日本手話」訴訟,「科学の再興」の検討スケジュール
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年9月16日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年9月16日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは2件でございます。週末、長崎県に出張してまいりました。14日は、天皇皇后両陛下御臨席のもとに第40回国民文化祭「ながさきピース文化祭2025」開会式に出席をさせていただきました。長崎の文化、平和への思いを表現するステージを拝見いたしまして、全ての関係者の熱い思いを感じました。15日は、長崎大学を訪問させていただきまして、地域医療において重要な役割を担っている長崎大学病院や日本有数の感染症教育・研究拠点でございます熱帯医学研究所を視察いたしまして、学長や職員と意見交換を行いました。次に、長崎純心大学を訪問いたしまして保育士、社会福祉士といった地域に不可欠な人材の育成、また地方私立の大学の経営についての説明を受けまして、理事長、学長と意見交換を行わせていただきました。最後に、国立諫早青少年自然の家を訪問いたしまして、豊かな自然に囲まれた野外教育施設、また県内の民間団体から寄付を受けたスポーツ施設などを視察させていただきまして、理事長や施設職員と施設の計画的な維持管理や今後のあり方についての意見交換を行わせていただきました。今回の出張を通じまして得た知見、これを踏まえまして、関連施策の充実に取り組んでまいりたいというふうに思います。
2件目でございます。本日16日から令和8年1月実施の大学入学共通テストの出願が開始されます。出願期間は10月3日まででございます。今回の共通テストからWeb出願となりまして、現役の高校生を含めまして全ての志願者が個人でパソコンやスマートフォンなどを利用して出願します。このことにつきまして、本日、教育委員会等を通じまして改めて高校生一人ひとりへ周知をいたします。各学校の先生方におかれましても、引き続き生徒の出願について丁寧なフォローをお願いいたします。文部科学省といたしましても、大学入試センターと連携をしていきながら、SNSなどあらゆる手段を通じまして周知活動を行ってまいります。また、報道関係者の皆様にも改めまして広く周知する観点から御協力をお願いしたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
先日、NASAの無人探査車が回収した岩石から生命の痕跡の可能性のある物質が発見されました。日本でも、JAXAのほうで26年度から火星の衛星から土壌を持ち帰る計画を始める予定ですが、計画への影響というのをどのように考えているでしょうか。
大臣)
NASAの火星無人探査車の「パーシビアランス」による火星における生命の痕跡の可能性につながる発見があったということは承知をしているところでございます。一方、JAXAにおきましては2026年度に打ち上げる予定の火星衛星探査計画の「MMX」におきまして、火星の衛星「フォボス」から世界初となる火星圏からのサンプルを直接持ち帰ることを目指す計画を進めているところでございます。今回のNASAの研究成果、また今後の「MMX」から創出される成果を通じまして、火星の起源また構造に関する理解が飛躍的に発展することを期待しているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き「MMX」の2026年の打ち上げに向けて着実な開発を進めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
先週金曜日12日に政府のAI戦略本部が立ち上がりました。今後、文科省としてどのような役割を果たしていくかお聞かせください。
大臣)
先週の12日金曜日でございますが、開催されました「第1回AI戦略本部」におきまして基本計画骨子が示されたところでございまして、石破総理からも政府一丸となって同計画の年内の決定に向けまして検討を加速させるよう指示がございました。文科省といたしましても、AIスキルの獲得、またAIリテラシー向上などを含めまして幅広いAI関連人材の育成・確保、またAI研究開発力の強化、科学研究の在り方を変革する「AI for Science」の推進などを通じまして、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」、この実現に貢献してまいりたいというふうに思っております。また、我が国の強みでございますマテリアル分野等におきまして、AIの活用によりまして国際競争力を引き上げていくことはまさに重要だというふうに考えておりまして、文科省といたしましては科学研究向けAI基盤モデルの開発及びデータ基盤の充実・強化、先日、物質・材料研究機構でも視察をさせていただきましたAIやロボットを活用いたしました自動・自律実験システムの開発導入などを通じまして、マテリアル分野の研究開発の変革をしっかりと目指してまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
9月12日の先週金曜日ですが、こども家庭庁の有識者検討会でこども性暴力防止法の運用指針に関する中間取りまとめが示されました。そちらについて2点お伺いします。まず、国公私立を問わず小中高校、幼稚園などが義務対象事業者として現職者、新規採用者の犯罪履歴の確認が必要となります。こちらに伴う犯罪歴の取り扱いのリスクだったり、解雇に伴う訴訟リスクが膨大な事務作業が求められるなど、現場に負担感があると思いますが、確実に制度を利用してもらうために文部科学省してどう対応されますか。もう1点が、防犯カメラというのが有効と示されて、学校現場などで導入に向けた検討を推奨するよう方針が示されましたが、文部科学省として検討を進めるよう求めますか。
大臣)
御指摘のとおり、「こども性暴力防止法」におきましては、子供たちを性暴力等から守り抜くために現職の教員、また新規採用者に等につきましても性犯罪歴の確認を行うこととされております。この仕組みを確実に運用していくためには、やはり確認の対象となるものが相当数になることを踏まえまして、無理なく関係する事務を行うことができるよう、現場の負担をしっかりと考慮する必要があるというふうに私どもも考えております。この点、現在、こども家庭庁におきまして現場の負担軽減を図るべく犯罪歴を確認するためのシステムの構築に取り組んでいるところでまさにございまして、文部科学省といたしましても例えば確認の時期を分散するなど、必要な対応を協議しております。また、防犯カメラの設置につきましてでございますが、以前の会見でも申し上げたというふうに思いますが、複数の人の目が届きにくい場所など、設置が有効な場合もあるものと考えておりまして、その際には保護者や、また児童生徒等に理解を得ながら実施をすることが必要であることから、また今回の「中間取りまとめ」におきましてもそのように留意点が記載されたものというふうに承知をしているところでございます。引き続きこども家庭庁と連携をしていきながら、教育委員会等に対しましてこうした留意点等も周知しながら、子供たちを性暴力等から守り抜くための取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
学校の働き方改革で一つお伺いいたします。今現在、学校と教師の3分類という形で中教審の教師を取り巻く環境整備特別部会の中で議論されていると思いますけれども、これについて教師以外が積極的に参画すべき業務というふうに分類されたものについて、特別部会の委員の方や学校事務職員の方などから学校事務職員に実質的な業務の付け替えが起こって負担が増えてしまうのではないかという懸念の声が上がっています。こうした指摘に対する文部科学省の見解について教えてください。それから、学校事務職員さんをはじめ教師以外の専門職を今後どうやって増やしていくのかという、財政措置の観点もあると思うのですけれども、こちらについても計画について併せて教えていただければと思います。
大臣)
学校・教師が担う業務に関わる「3分類」に関しましては、中央教育審議会におきまして(注1)御審議を踏まえまして、その内容のアップデートを行った上で給特法に基づく「指針」に位置づけることにしております。こうした中でございまして、御指摘のとおり先日8月19日の中央教育審議会の特別部会におきましては、事務職員の過度に業務が集中すること、また業務を全てお任せするという姿勢にならないよう注意が必要であるといった御意見があったところでもございます。「指針」につきましては、こうした御意見も踏まえた上で、また秋ごろを目途に公表する予定でございますが、業務の分類を示すだけではなくて業務そのものの精選や、また効率化などが必要であるという旨もしっかりと明記する方向で検討したいというふうに考えているところでございます。こうした学校における働き方改革の加速化のためには事務職員が専門性を生かしまして校務の運営に一層参画していただくことがまさに重要でございまして、文部科学省におきましては令和8年度概算要求におきまして事務職員を含む教職員定数の改善を要求しているところでございます。さらに、事務職員のみならず支援スタッフ、また保護者、地域住民等と教師が(注2)連携・協働を促進するためにも、教員業務支援員などの支援スタッフの配置、充実などの予算を要求しているところでもございます。文部科学省におきましては、引き続き学校における働き方改革の推進に必要な予算の確保に向けてしっかりと取り組んでまいります。
(注1)「おきまして」は、正しくは「おける」です
(注2)「地域住民と教師が」は、正しくは「地域住民と教師の」です。
記者)
学校の健康診断について伺います。総務省が不登校の子供の学校の健康診断の受診状況について、初の調査に乗り出す方針だということが示されています。そこで、健康診断の現在の受診率とそれに対する大臣の御所感、受診率を上げるための今後の対策についてお考えをお伺いします。特に不登校の子供に対してどのように取り組んでいくのか、お考えを聞かせください。
大臣)
不登校児童を含めた健康診断の受診率については把握を行っていないところでございますが、健康診断を受けることができなかった児童生徒に対しましても受診の機会を確保していくことはまさに重要だというふうに考えております。このため、文部科学省におきましては個別の事情などによりまして健康診断を受けることができなかった場合の対応につきましては、保護者に事前に周知するなど、また適切に対応できるよう、様々な機会を通じまして各教育委員会等に求めてきたところでございます。また、学校における保健管理のあり方につきましてでございますが、本年の5月に有識者会議を設置しているところでございまして、健康診断を受けることができなかった児童生徒の健康管理についても必要に応じてしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。
記者)
手話の教育についてお尋ねします。北海道の札幌聾学校の児童が担任の教諭が日本手話が堪能でないために学習の権利を侵害されたとして北海道に損害賠償を求めた訴訟で、先週11日に札幌高裁が一審札幌地裁判決を支持して請求を棄却しました。そこで、この判決について大臣の所感をお伺いしたいのと、もう1点、判決の中で教育する側は障害児に対して適切な配慮を尽くし学習意欲を持続させるよう一層の努力を続けると望むと付言がありました。これに関してどのような配慮が必要だと思うか、大臣の考えをお聞かせください。
大臣)
御指摘の事案につきましては、報道等によりまして承知しているところでございますが、個別の判決については文部科学省としてのコメントは控えさせていただきたいというふうに思います。文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導、また必要な支援が行われることが重要であるというふうに考えているところでございまして、引き続き特別支援教育の充実に向けまして学校や教育委員会における取組の支援に努めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
「科学の再興」委員会についてお聞きしたいのですけれども、これまでの科学技術基本計画では文科省からの政策的インプットは今よりずいぶん前にやっていたかと思うのですけれども、今回、第7期基本計画を作る最後のタイミングで「科学の再興」委員会ができた、その意味について教えてください。
大臣)
次期の「科学技術・イノベーション基本計画」についてでございますが、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIでございますが、基本計画専門調査会におきまして検討が進められておりまして、本年6月の論点整理案におきまして基礎研究力の抜本的強化を目指した「科学の再興」が示されたところでございます。これを受けまして、基礎研究力強化を担う文部科学省といたしまして、「科学の再興」の具体的な対応策を検討すべく先般、有識者会議を立ち上げたところでございます。この「科学の再興」による相対的に失われつつある我が国の研究力の国際的な優位性を取り戻すべく、年度末に決定予定の次期基本計画に反映いただけるよう、しっかりと議論を進めたいというふうに思っているところでございます。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室