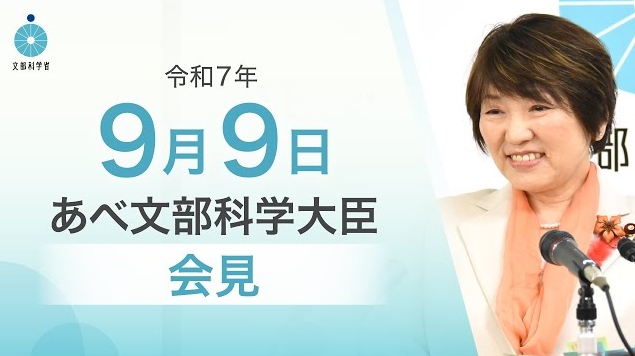- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年9月9日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年9月9日)
令和7年9月9日(火曜日)
教育、その他
キーワード
ユネスコ世界ジオパーク・カウンシンルにおける認定勧告・再認定決定、石破総理の辞任表明、「調整授業時数制度」導入に向けた事例創出、教育課程特別部会「論点整理(素案)」における教科等の内容の精選及び教師の負担軽減の考え方、高等学校授業料無償化の検討状況、教師の業務の持ち帰りと学校における働き方改革
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年9月9日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年9月9日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から1件ございます。5日金曜日から6日土曜日にかけまして、チリで開催されました第10回ユネスコ世界ジオパーク・カウンシルにおきまして、我が国から申請をしておりました山口県の「Mine 秋吉台」の認定勧告が出されたところでございます。令和8年春の開催予定のユネスコ執行委員会での承認を経まして、ユネスコ世界ジオパークとして正式に認定されることになります。また、ユネスコ世界ジオパークについては原則4年前(注)に再認定審査が行われることになっておりまして、この度、我が国から申請をしておりました糸魚川、また島原半島、隠岐、伊豆半島の4地域の再認定が決定されました。地元関係者の皆様に対しまして心から祝意を表すとともに、長年にわたる御尽力に敬意を表するところでございます。ユネスコ世界ジオパークに世界中の多くの人々が訪れ、またその魅力に触れることができるよう、文部科学省といたしましても地方自治体の取組にしっかりと協力をしてまいります。以上です。
(注)「原則4年前」は、正しくは「原則4年毎」です
記者)
先日、石破総理が退陣を表明されました。参院選で与党が惨敗をしてからの約50日間、政治空白ができたのではないかという批判の声もありますが、今回の決断について大臣の評価をお願いします。
大臣)
石破総理が辞任を表明されたことにつきましては、個人的には大変残念に思っておりますが、総理のお考えを尊重したいというふうに思います。私といたしましては、石破内閣の文部科学大臣の職にある最後の瞬間まで総理を全力でお支えをいたしまして、大臣としての職責を果たしてまいります。以上です。
記者)
次期学習指導要領について一つお尋ねいたします。5日の中教審教育課程企画特別部会で示されました論点整理素案で、「調整授業時数制度」の創設が提言されまして、その運用に向けた知見の蓄積ということで今年度、研究開発学校では9都道府県46校で柔軟な教育課程を編成、実施し、更に来年度からは全ての都道府県・政令市で更に事例創出の加速を図るべきだというふうにしています。文科省として具体的にどのような取組を検討しているのか、またそうした事例創出への期待も合わせて教えていただければと思います。
大臣)
中教審で議論中の調整授業時数の制度につきましては、制度導入後、各学校が創意工夫ある教育課程の編成、具体的なイメージを持って速やかに取り組むことができるよう、全国の教育委員会・学校による知見や事例の蓄積が不可欠というふうに私ども考えております。このため、制度導入に先立ちまして来年度から研究開発学校の取組などを参考としていきながら、全ての都道府県・指定都市、一定数の学校で教育課程の柔軟化を施行できるまで(注)新たな仕組みの創設を今検討しているところでございまして、来月までに周知をする予定でございます。こうした取組を迅速に進めながら全国各地で調整授業時数制度の導入に向けた準備を加速することを通じまして、制度導入時には多様な個性また特性、背景を有する子供たちを包摂していく柔軟な教育課程編成に円滑に取り組める環境をしっかりと整備をしてまいりたいというふうに思っております。以上です。
(注)「施行できるまで」は、正しくは「試行できる」です。
記者)
関連しての質問ですけれども、同じ次期学習指導要領の論点整理素案、調整授業時数制度の関連です。柔軟な教育編成を可能にすることということが盛り込まれておりますけれども、年間の総授業時間数自体は維持するという枠組みが今のところ示されております。そういった前提で、学校現場から負担が更に増えるのではないかという不安の声も上がっております。素案の中では教科書の内容について精選していくという方向も示されておりますけれども、詳細については今後の議論になるかもしれませんけれども、改定の大きな方向性と教員の負担軽減というところをどうやって両立させていくか、現時点での大臣のお考えがあればお聞かせいただければと思います。
大臣)
今回の論点整理(素案)におきましては、学校指導要領(注)につきまして各教科等の本質的理解の獲得に重点を置いた内容の構造化と必要に応じた精選を行うことを示しているところでございます。合わせまして教科書の内容、また分量、この方向性も踏まえつつ精選していくことを示しているところでございます。次回の特別部会で論点整理が取りまとまりました後に、また各教科等のワーキンググループにおきまして学校段階また教科等の特性を踏まえていきながら丁寧な議論をお願いしたいというふうに考えているところでございます。また、今般の論点整理素案におきましては今後の検討にあたっての基本的な考え方として「実現可能性の確保」を掲げているところでございます。教育課程の実施に伴いまして、教師に過度な負担、また負担感が生じにくい在り方を追求いたしまして、教師と子供の双方に「余白」を創出することでしっかりと豊かな学びにつなげられるよう、引き続き丁寧な検討を進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
(注)「学校指導要領」は、正しくは「学習指導要領」です
記者)
1点目の幹事社さんからの質問に関連してなのですけれども、政治的空白が50日間ぐらいできたということで、この間、高校無償化に関する議論がなかなか進んでいたようには見えなくて、一方で中学生、中学校3年生にとってはそろそろ進路を絞っていく時期にもなってくるのではないかと。今後早急に高校無償化の議論を進められることが期待されるのだと思うのですけれども、その点について大臣のお考えを教えていただけますでしょうか。
大臣)
いわゆる高校無償化についてでございますけれども、令和8年度予算編成過程におきまして成案を得まして実現するものとされておりまして、鋭意、3党の実務担当者による協議が行われているというふうに承知をしているところでございますが、来年度、高校等へ進学する生徒が安心して進路選択ができるよう検討を進めていただくことがまさに重要だというふうに考えているところでございます。文部科学省といたしましては、3党における協議結果を踏まえて速やかに対応ができるよう、必要な準備はしっかりと進めてまいります。
記者)
先ほど一つ前の質問で教師に対するという話がありましたけれども、昨日、この場で全日本教育組合の方々が会見されまして依然としてやはり残業が多いですとか、家に持ち帰る仕事があるですとか、土日に仕事をしなければいけないというようなことを訴えられていました。これらのことは、大臣もしくは文科省としても課題だというふうに感じておられるのかということと、あとそれを解消するためにはどのようなことが必要で、それを時間的目処として何年後にはこうしていたいみたいなものがあれば教えてください。
大臣)
御指摘の調査に関してでございますが、その詳細を把握しているところではございませんのでコメントは差し控えさせていただきます。また、学校における働き方改革でございますが、この推進に向けましては本年6月に成立をいたしました改正給特法におきまして全ての教育委員会に対しまして教師の業務量の管理、また健康を確保するための計画の策定などを行っていただくこととしているところでございます。加えまして、文科省におきましてもいわゆる「3分類」、この徹底に加えまして業務の適正化と、また教職員の定数の改善、さらには支援スタッフの充実も取り組むことというふうにしているところでございます。また、業務の持ち帰りにつきましては文部科学大臣が定める「指針」におきましても、本来行わないことが原則である旨を示しているところでございまして、引き続きその趣旨を徹底してまいりたいというふうに思っております。こうした取組を通じまして各教育委員会、学校における業務の精選と適正化、これに向けた取組の支援、私どもしっかりと支援に努めてまいりまして学校における働き方改革、しっかり推進をしてまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室