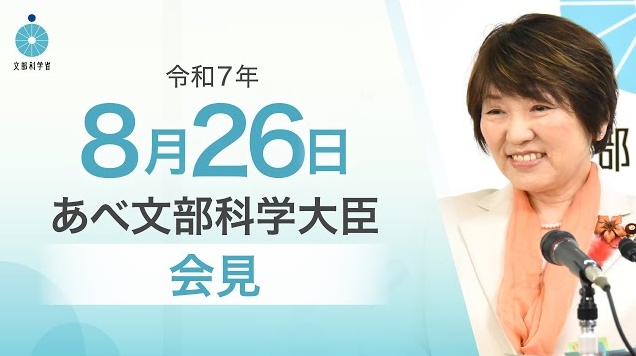- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月26日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月26日)
令和7年8月26日(火曜日)
教育
キーワード
TICAD9の成果報告について、大臣の韓国出張について、「医学系研究支援プログラム」採択課題の決定、教員による性犯罪の抜本的対策を求める署名に対しての見解と今後の対策、今後の学校教育におけるローマ字の綴り方に対する見解、北海道釧路市教育委員会が提出したメガソーラ開発事業に対する意見書への見解、TICAD9にて表明された今後の我が国の人材育成に向けた文科省の取組、学校現場における熊対策への対応について、夏休み明けの児童の自殺増加に対する見解と自殺予防の取組について
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年8月26日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年8月26日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から3件ございます。先週20日水曜日から22日金曜日に横浜におきまして、第9回アフリカ開発会議、TICAD9でございますが、開催されまして、「TICAD9横浜宣言」が採択されたところでございます。文部科学省におきましては、「TICAD9」の開催に向けまして7月末にガーナ教育省と関係強化のための意向表明書、LOIでございますが、を署名するとともに、また今月19日にはエジプト教育・技術教育省ともLOIを署名するなど、取組を進めてまいりました。また、会議の初日の20日におきましては世界銀行及びJICAとアフリカにおける高等教育支援に関するLOIの署名を行うとともに、南アフリカのンジマンデ科学技術イノベーション大臣と意見交換を行わせていただきました。この他、会期期間中には教育・科学技術・文化・スポーツ、各分野におけるテーマ別イベント、またブース展示なども行ったところでございます。これらの「TICAD9」における成果を生かしていきながら、また引き続き若者・女性を中心といたしました学生交流、また科学技術協力、文化・スポーツ交流の促進など、アフリカ諸国との更なる連携強化を図ってまいります。
2点目でございます。本日26日から28日水曜日(注1)まで、大韓民国を訪問させていただきます。今般の出張におきましては、APECで初開催となる閣僚級会合「APEC文化ハイレベル対話」に出席をいたしまして、文化・クリエイティブ産業の構築をテーマに議論を行う予定でございます。併せまして、ソウル日本人学校、またソウル大学半導体研究所の視察なども行う予定でございます。今回の出張を通じまして、文化分野におけるAPEC各国との更なる連携強化を図るとともに、教育・科学技術分野における大韓民国との一層の連携を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
3件目でございます。令和6年度補正予算で創設をいたしました「医学系研究支援プログラム」採択課題が決定されましたので御報告をいたします。本事業、研究者の研究活動と大学病院・医学部における研究時間の確保、処遇の改善など、研究循環改善(注2)に関わる取組を一体的な支援を通じましてその自走を促すことで、医学系の研究力を抜本的に強化することを目的としているところでございます。大学病院・医学部を置く全国の大学を対象に公募いたしまして、日本医療研究開発機構、AMEDでございますが、での審査の結果、単独大学の総合力の向上を目指す総合型が6課題、また複数大学の連携による特色ある取組を支援する特色型が計20大学からなる6課題、採択をされました。今後、本事業が大学病院・医学部を取り巻く研究環境の改善の契機となり、また我が国の医学系研究全般の研究力の躍進につながることを期待しているところでございます。以上でございます。
(注1)「水曜日」は、正しくは「木曜日」です
(注2)「研究循環改善」は、正しくは「研究環境改善」です
記者)
昨日、教員による性課題の抜本的対策を求める署名や教職員らによる性暴力防止法見直しに関する要望書が文科省に提出されました。今後の文科省としての対応をお願いいたします。
大臣)
当該団体より要望書の提出があったことは報告を受けているところでございます。児童生徒性暴力等への対応に対しまして、多くの署名とともに具体的な要望をいただいたところでございまして、改めて教員による児童生徒性暴力等は決してあってはならないという共通認識を持ち、国、教育委員会、さらには学校が一丸となって徹底的に取り組むことが必要であるというふうに私どもも考えているところでございます。文部科学省といたしましては、こうした事案を根絶していくため先般、全国の都道府県・指定都市教育委員会の教育長に対しまして、児童生徒性暴力等への対策について指導を行ったところでございますが、引き続き教員性暴力等防止法の趣旨も適切に踏まえつつ、さまざまな観点から取組を強力に進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
8月20日に文化審議会がローマ字のつづり方について、これまでの訓令式からヘボン式に則ったものへの改訂を更新いたしました。小学校では国語の時間、授業では訓令式を基本としたローマ文を習う一方で、外国語ですと自分の名前をヘボン式に書き直すようにというふうな、両方のつづり方の指導が行われているようです。今後、この背景に合わせて学校教育におけるローマ字のつづり方の指導、こちらも統一されるのでしょうか。そのタイミングはいつになるのでしょうか。それから、ヘボン式に改定となった場合であったとしても訓令式のつづり方が誤りというわけではないというふうに考えますが、例えば英語のテストの場面などで富士山の富士を「huzi」と訓令式で書いた場合などに、これがテストで間違い、減点にはならないというふうな理解でよろしいでしょうか。
大臣)
現行の学習指導要領の解説におきましては、昭和29年の内閣告示を踏まえまして、ローマ字のつづり方は訓令式を主として、ヘボン式も併せて指導することとしているところでございます。今後予定されている内閣告示の改定でございますが、ヘボン式が主になりますが、一方でタイピングなどではこれまで広く用いられた訓令式が引き続き活用されることも考慮いたしまして、学校現場で混乱が生じないよう、現行の学習指導要領解説を、今後、適切に更新をしてまいります。なお、現行の小学校学習指導要領の解説におきましては、例えば高学年の外国語科におきまして国際的な共通語として英語を使用する観点から、いわゆる「ヘボン式ローマ字」で表記することを指導することとしていることから、英語のテストで先ほどもおっしゃってくださった富士を「huzi」のように訓令式で回答した場合は間違いや減点になるものと考えます。以上です。
記者)
北海道の釧路市教育委員会は、釧路湿原の周辺で進められている舗装路の建設計画について、文化庁に対して国の国立天然記念物「タンチョウ」などの生息への影響を危惧していると意見書を提示したそうなのですけれども、今後の対応と大臣の所感をお願いします。
大臣)
北海道の釧路市におきまして、メガソーラー開発事業の工事の一部が着工されておりまして、この当該事業の予定地に国の特別天然記念物の「タンチョウ」、また天然記念物の「オジロワシ」の生息地が含まれていることは承知をしているところでございます。お尋ねの釧路市の教育委員会の意見書につきましては、8月21日付で北海道を通じまして文化庁に進達があったものでございまして、釧路市としてメガソーラーの開発事業者に対しまして専門家への意見聴取を通じて天然記念物への影響を確認することを求めることが文化財保護法の趣旨を踏まえた対応かどうかについて見解を求められたものでございます。文化庁からは、文化財保護法の規定におきましては騒音また振動等を伴う天然記念物への「保存に影響を及ぼす行為」をしようとするときは、影響が軽微でない場合は文化庁長官の許可が必要であることから、釧路市の意見のとおり影響の確認を求めることが適当である旨を22日付の文書で北海道を通じて回答しているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き開発が天然記念物の滅失や既存につながることがないように釧路市教育委員会におきまして適切に指導していただきたいというふうに考えているところです。以上です。
記者)
冒頭のTICADに関連して伺います。石破総理大臣は、TICADの中で今後3年間に教育を含む幅広い分野で30万人の人材を育成するとともに、AIの分野では3万人を育成する方針を表明しました。文科省の関わる分野で今後どのように取り組む考えなのかを教えてください。
大臣)
アフリカ諸国とは2024年時点で、留学生については2,741名の留学生を受け入れている他、科学技術分野におきましては、例えばJSPSによる「外国人研究者招へい事業」、これらによりまして57名、またJSTの「さくらサイエンスプログラム」によりまして203名の人的交流を行うとともに、2025年時点で環境、防災、感染症などの33課題の国際共同研究を実施するなど交流を行っているところでございます。文部科学省といたしましては、「TICAD9横浜宣言」を踏まえまして、アフリカにおける教育課題の解決、また人材育成に向けまして日本型教育の好事例のモデル化と拡大、また大学間の連携・学生交流の促進、研究者交流や国際共同研究の推進、スポーツ及びまた文化交流の促進など、「人材育成」、「若者の相互交流」を中心に取り組むことというふうにしているところでございまして、引き続きまして関係省庁の他、JICA、また世界銀行等の関係機関とも連携していきながら協力を進めてまいりたいというふうに思っています。
記者)
全国各地で熊の被害が相次ぐ中、学校敷地内にも熊が出没するような事案が発生している他、中学生が学校に向かう途中に熊に追いかけられる事案が発生するなど、子供が差し迫った危険にさらされつつあります。また、学校敷地内で猟友会が発泡を行うような事案が発生しています。新学期が始まる中、学校現場や子供の安全確保という観点から文科省としての受け止めと今後の対応についてお伺いいたします。
大臣)
今月23日土曜日でございますが、北海道の初山別村の中学校敷地内で地元の猟友会の方が熊に向けて発砲したということでございますが、当日は土曜日でございまして、熊の出没情報を受けて部活動等も中止していたなど、学校敷地内に生徒、教職員がいない状況の中でのことでございまして、特段の被害は生じていないものというふうに承知をしているところでございます。昨今、学校敷地内における熊の出没など、児童生徒等の安全を脅かす事案が発生しているものと認識をしているところでございます。学校におきましては、児童生徒等の安全を確保するため、保護者等と連携を図るとともに必要な措置を講ずるよう努めることが求められているところでございます。文部科学省といたしましても、まずは学校現場や学校設置者における対応を注視していきながら、また適切な対応が図られるよう必要に応じて指導・助言を行ってまいりたいというふうに思います。また、熊対策でございますが、現時点で熊対策に特化した対策は考えてはいないところではございますが、必要に応じて教育委員会等に対し周知や注意喚起を行うことも検討してまいりたいというふうに思っています。以上です。
記者)
事前の通告がなくて大変恐縮なのですが、夏休み明けに子供の自殺が多くなるという傾向がある中で、もう既に学校が始まっている場所もありますが、改めて今後の文科省としての対応と、学校に行きたくないとか学校に行くことを迷っている子供たちに向けて大臣からメッセージがあればよろしくお願いします。
大臣)
本当に児童生徒の自殺者数でございますが、令和6年に529名と過去最多となりまして、児童生徒の自殺予防に向けた取組を一層充実していく必要があるというふうに私どもも考えているところでございます。文科省としては、これまでも1人1台端末等を活用いたしました子供の自殺リスク等の早期把握と早期対応に取り組んできたとともに、また命の大切さ、更には尊さを実感できる教育、またSOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の推進等の取組を進めてきたところでございます。加えまして今後、学校が医療機関等と連携をしながら自殺のリスクを抱えた児童生徒への対応を組織的かつ速やかに実施するためのガイドライン等の作成を今、検討しているところでございます。未来を担う子供たちの命を守るためには、やはりこども家庭庁等の関係省庁ともしっかり文部科学省が連携をしていきながら自殺予防の取組に全力を尽くしてまいりたいというふうに思います。
記者)
先ほどの熊の件で1個だけ追加でお伺いさせてください。NHKが取材したところ、東北地方の県教委のこれまでの事案の発生件数と数字で把握しているのは秋田県教委のみだったのですけれども、新たな被害者への対策には実態把握等も必要になってくるのかなというのは考えられるのですけれども、今後、国として事案の発生状況や現場へのマニュアル設置状況について調査や通知等を行う予定はありますでしょうか。
大臣)
現時点で熊対策に特化した対策は、先ほど申し上げましたが、考えておりませんけれども、必要に応じまして教育委員会等に対しまして周知、注意喚起を行うこともしっかり検討してまいります。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室