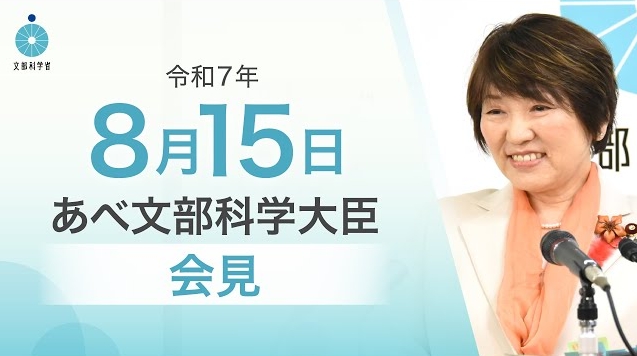- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月15日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月15日)
令和7年8月15日(金曜日)
教育、科学技術・学術、スポーツ
キーワード
私立大学の定員・定員充足率及び大学の規模の適正化に対する見解、広陵高校の甲子園2回戦辞退及び本事案におけるSNSでの誹謗中傷に対する見解、学校教育における歴史教育の果たす役割や課題について、科学研究のベンチマーキング2025の結果を踏まえた我が国の研究力強化について
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年8月15日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年8月15日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
記者)
私学事業団の調査で、私立大学の定員が22年ぶりに減少に転じたことが分かりました。一方、定員充足率が80%を下回った大学が2割あることも分かりました。大臣の受け止めと、今後、18歳人口の減少が見込まれる中、大学の適性化が課題となってきますが、文科省としての施策の方針をお聞かせください。
大臣)
ご指摘のとおり、定員充足率が80%を下回る大学が2割以上に上るなど、私立大学の経営環境、依然として厳しい状況にあると認識をしています。こうした中でございますが、今般の調査結果につきましては各学校法人がそれぞれの経営状況を踏まえ、規模の縮小また撤退など早期の経営判断を行った結果、全体の入学定員が減少したものと考えられます。改めまして、今後の高等教育全体の「規模」の適正化は喫緊の課題であると受け止めているところでございまして、また私立の設置者の枠を超えた形で高等教育機関の間の連携と再編と、更には統合、縮小、更には撤退の議論を含め、地域の状況を踏まえていきながら、また高等教育全体の適正な規模の見直しを進めていくことがまさに必要だというふうに考えているところでございます。文部科学省といたしましては、本年2月に中教審でとりまとめられました「知の総和」答申、これを踏まえまして速やかに具体的方策の実行に取り組んでまいります。以上です。
記者)
広陵高校の関係で2点ほどお尋ねします。先週のこちらの会見で暴力行為があったことに対して大臣は遺憾であるというご回答をされました。その後、2回戦出場を辞退するということになっておりますけれども、そのことに関する大臣の受け止めをまず教えてください。続きまして、今回のSNS上を含めたインターネット上での誹謗中傷みたいなものも問題視されているということなのですけれども、学校の教育現場とか児童生徒を守るという立場から大臣のお考えがあればお願いします。
大臣)
まず、先般の会見でも申し上げましたけれども、広陵高等学校の硬式野球部におきまして暴力行為があったことについては大変遺憾に思っているところでございます。暴力行為は決して許される行為ではございませんでして、広陵高等学校におきまして今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努めていただきたいというふうに考えています。また、その上で甲子園への出場を辞退されたことにつきましては、広陵高等学校におきまして判断されたものでございまして、個別のコメントは差し控えさせていただきます。いずれにいたしましても、広陵高等学校におきまして生徒のケアなどに適切に対応していただくことをお願いしたいというふうに思っているところでございます。
また、本事業(注)に関しましてインターネット上で様々な意見が飛び交っているということは承知しているところでございます。ただ、先ほど申し上げましたように暴力行為があってはならないことももちろんでございますが、無関係の生徒また関係者の方々が誹謗中傷に晒されることも決してあってはいけません。先般の会見でもお願いをしたところでございますが、SNS等に関しまして発言がエスカレートすると誹謗中傷として新たな人権侵害を生むことにつながりますので、改めまして冷静な対応をお願いしたいというふうに思います。以上です。
(注)「事業」は、正しくは「事案」です
記者)
本日は終戦の日ということで、戦後80年に関係してお伺いします。戦争を直接知る世代というのが非常に少なくなっていて、歴史的事実を伝えていくことが難しさに直面していると思います。また、歴史的事実を非常に根拠のないままに、なかったかのように発言する政治家がいたりとか、あとSNS上で全く根拠のないデマと言いますか、フェイクも飛び交っている状態です。その上で、学校教育において戦争の歴史をどういうふうに教えていくかというのは非常に重要だというふうに考えますけれども、教育の果たす役割と、一方で今現在における課題というのは何だというふうにお考えなのか、ご意見をお聞かせください。
大臣)
戦後80年の節目を迎える中にございまして、二度と悲惨な戦争を繰り返さないようにするため改めて平和で民主的な社会の実現に努めることの大切さ、教えることが極めて重要でございます。我が国の学校教育におきましては、学習指導要領や教科書に基づきまして、例えば社会科で第二次世界大戦を扱い、国民が大きな被害を受けたことや、また我が国が多くの国々に多大な損害を与えたことなどを教えています。こうしたことも含めまして、歴史教育(注)、客観的かつ公正な資料に基づきまして、子供たちが歴史的事実、これをしっかりと正確に理解をしていきながら多面的・多角的に考察をしていき公正に判断する能力、育成する役割があると私どもは考えております。昨今、戦争体験者の減少が進みまして、いかに若い世代へ戦争の記憶を継承していくかという課題もございますが、戦争体験者の声を盛り込んだ例えばデジタル教材の活用などを推進していきながらも、また歴史教育の更なる充実に文部科学省としてもしっかり努めてまいりたいというふうに思います。以上です。
(注)「歴史教育」は、正しくは「歴史教育は」です。
記者)
先日、科学技術・学術政策研究所が科学研究のベンチマーク2025を発表しました。その中で、日本の大学のトップ10%論文の割合がこのところ低下しているという傾向が表れています。その要因として、国立大学の運営費交付金といった経常的経費が、基盤的経費が抑制されてきたことにあるのではないかという指摘もありますけれども、大臣としては来年度概算要求に向けてこれから基盤的経費を確保するための反転攻勢をかけていくのか、そういったお考えについて教えてください。
大臣)
先週公表されました科学研究のベンチマーキング2025でございますが、我が国におきましては注目度の高い、論文数、Top10%補正論文数の順位におきまして、昨年に引き続きまして13位にとどまっているところでございまして、論文の定量的な指標だけでは研究力を測定できるものではございませんけれども、研究力の相対的な低下の課題が改めて確認されたというふうに私どもも認識しているところでございます。次期の「科学技術・イノベーション基本計画」におきまして、この検討に関しましては研究力の抜本的強化による「科学の再興」という実現と(注)、最重要課題の一つというふうに私どもも考えておりまして、このために御指摘の基盤的経費、この確保はもとよりでございますが、まずは科学技術の人材への投資の拡大、更には新興・融合領域研究への挑戦、またAI for Scienceの実現、更には国際プレゼンスの強化など、総合的に推進していくことがまさに重要で必要だというふうに考えているところでございます。文部科学省といたしましては、これらの総体的な取組を通じまして我が国の研究力強化に向けまして概算要求の準備をしっかりと進めてまいりたいというふうに思います。
(注)「「科学の再興」という実現と」は、正しくは「「科学の再興」の実現を」です
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室