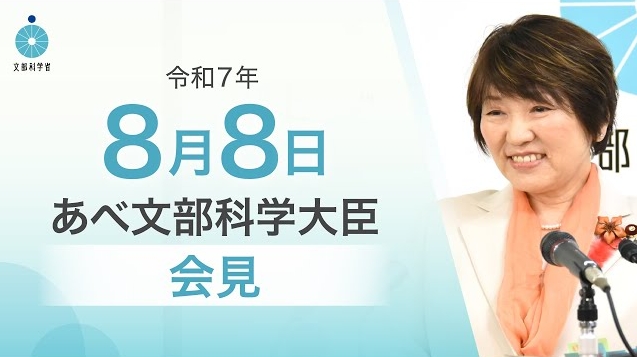- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月8日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月8日)
令和7年8月8日(金曜日)
教育、科学技術・学術、スポーツ、その他
キーワード
JAXA種子島宇宙センターの視察について、教員性暴力等防止法に基づくデータベースの活用状況の調査について、いわゆる東京「君が代」裁判5次訴訟の判決について、終戦の日に合わせた靖国神社参拝の有無、今後の平和教育の展開における課題、広陵高校野球部の暴力事件に対する見解
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年8月8日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年8月8日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは2件でございます。昨日7日でございますが、宇宙航空研究開発機構、JAXAでございますが、種子島宇宙センターを視察いたしましたので御報告をいたします。JAXA種子島宇宙センターでございますが、ロケット打上げまでの指揮、また作業を行う総合司令塔、大型ロケットを組み上げるための組立棟、ロケットの打上げが行われる射点などを、視察をさせていただきました。H3ロケットを安全かつ着実に打ち上げるための技術力の高さを実感させていただくとともに、企業との連携を深めるための意見交換を行うなどの貴重な機会となりました。今回の視察を踏まえまして、引き続き我が国の宇宙開発利用、また宇宙産業の育成を積極的に文部科学省としても推進してまいります。
もう一つ、2件目でございますが、子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはならず、児童生徒性暴力の未然防止に向けまして教員性暴力等防止法に基づくデータベースの活用が大変重要でございます。しかしながら、教員採用にあたってデータベースへのユーザー登録、また適切な活用ができていない事例が確認されたところでございます。文部科学省といたしましては、今回の事案を重く受け止めさせていただきまして、本日、全国の国公私立学校でのユーザー登録の徹底を周知するとともに、実際に適切に活用されているかの調査を、発出をいたしました。今後、年内を目処にこの調査結果を取りまとめまして公表することとしておりまして、今回の調査結果も踏まえまして引き続きデータベースの活用徹底に向けまして全力を挙げて取り組んでまいります。なお、この後、事務方によってブリーフィングを行いますので詳細につきましては事務方にお尋ねください。以上でございます。
記者:日本経済新聞)
今、冒頭発言にありました教員による児童生徒性暴力防止法に基づくデータベースの登録活用状況に関しての調査について伺います。あらためてですけれども、調査の実施方法や実施対象、また狙いについて教えてください。
大臣)
今回の調査につきましては、教員採用にあたりましてデータベースへのユーザー登録、また適切な活用ができていない事例が確認されましたことを踏まえまして、登録状況と活用状況の把握を行いましてデータベースの活用徹底を促すということを目的としているところでございます。調査の内容につきましては、データベースのユーザー登録状況と活用状況、データベースに登録、活用できていなかった場合はその理由などを中心に確認することとしているところでございます。なお、9月下旬をめどに全国の国公私立学校から回答いただくことにしておりまして、その後、調査結果を踏まえたデータベースの活用徹底に向けた周知などに取り組んでまいります。さらに、具体的な御質問に関しましてはこの後、事務方によるブリーフィングを行いますので事務方にお尋ねいただきたいというふうに思います。以上です。
記者:フリー)
先週、いわゆる東京君が代裁判5次訴訟の判決が出されたのですけれども、それに関連して伺えればと思っております。都立学校の卒業式などで国旗に向かって起立し国歌を斉唱するように命じられた教員がこれに従わずに処分された件について、先週7月31日の東京地裁判決はこれまでの最高裁判決の枠組みの中での判決でありまして、思想信条の自由などに関しては憲法違反とまでは認めませんでしたけれども、東京都教育委員会の裁量権の濫用を認定して減給処分を全て取り消すという判決を出しました。この争いは20年以上続いておりまして、最高裁も補足意見ではあるのですけれども、教育現場にこのような争いはふさわしくないでありますとか、教育行政には寛容の精神が求められるなどの補足意見を述べています。それで、国際機関のILOとかユネスコの合同委員会も日本政府に対して教員側と話し合いの機会を持つよう環境整備をしなさいというような勧告をこれまで4回も出しています。あべ大臣は性的少数者などを含めて共生社会の大切さということを説いていらっしゃるかと思うのですけれども、最近、教育現場には外国からの児童生徒が増えておりまして、特にアジアなどにルーツを持つような児童生徒は起立斉唱をしたくないという子供たちもおりまして、教員の中にはそういう子供たちの他のみんなとは考え方を思想的な少数者の子供たちの側に立って寄り添って教育、同調圧力がかかってしまうので起立斉唱できないという、そういう教員もいるのですね。それで、こうした背景を踏まえて教育行政の最高責任者としてあべ大臣は東京委と教員側の対話を促すでありますとか、和解を勧告するでありますとか、そういう具体的な解決策をお示しされるような、そういうおつもりはありますでしょうか。
大臣)
ありがとうございます。お尋ねの判決がなされたという報道は承知をしているところでございます。一般論として申し上げますと、懲戒処分でございますが、事案に応じまして任命権者である各教育委員会の権限と責任において行われるものでございます。また、御指摘の判決の内容についてでございますが、司法の場で判断されたものでございまして、文部科学省としてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
記者:共同通信)
15日の終戦の日が近づいてきておりますけれども、大臣は15日に合わせて靖国神社を参拝する御意向があるかどうかお尋ねできればと思います。
大臣)
靖国神社を参拝する予定はございません。
記者:教育新聞)
平和教育に関してです。今年で戦後80年を迎えて戦争体験者の減少、高齢化が進む中、証言を引き取って語り継いでいくことや、あらためて平和教育をどのように展開していくかが課題となっています。今後の平和教育のあり方について大臣のお考えをお聞かせください。
大臣)
戦後80年の節目となります年を迎える中でございまして、2度と悲惨な戦争を繰り返さないようにするため、改めて戦争が未曾有の惨禍をもたらしたことを理解をしてもらい、平和で民主的な社会の実現と国際協調・国際平和の実現に努めることの重要性を改めてしっかりと教えていくことがまさに重要だというふうに考えています。現行の学習指導要領におきましては、例えば社会科などにおきまして日本国憲法の平和主義の原則、さらには国際貢献を含む国際社会における我が国の役割、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの大切さなどを教えることとしているところでございます。また、厚生労働省と連携をしていきながら「平和の語り部事業」を推進しているところでございますが、戦争体験者の減少と、また高齢化が進む中にございまして、例えば戦争体験者の声を盛り込んだデジタル教材を活用するなど、持続可能な形で平和教育の充実を進めていく必要があるというふうに私どもも考えているところでございます。文部科学省といたしましては、こうした取組を通じていきながら平和に関する教育の更なる充実にしっかりと努めてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者:毎日新聞)
現在行われている夏の甲子園に出場している広陵高校について、暴行事案が報道された件で2点お尋ねします。被害生徒は転校をよぎなくされた一方で、加害を加えたとされる生徒らは処分を受けたということでありますが、広陵高校が出場していることに対してSNS上では批判的な意見が出ています。この件に関する受け止めと、高校、高野連の判断に対する大臣の所感をお願いします。また、関与したとみられる生徒を、実名を晒して中傷するかのようなネット上の書き込みもみられますが、こちらについてはどのようにお考えでしょうか。
大臣)
広陵高等学校硬式野球部にありまして(注)、上級生から下級生に対しまして暴力行為があったことにつきましては大変遺憾に思っております。暴力行為は決して許される行為ではありませんでして、部活動を含めまして学校教育活動を通じて人の痛みを想像し、他者への思いやり、また助け合いの心を育むことがまさに重要だというふうに考えているところでございます。広陵高等学校におきまして、被害を受けた生徒のケアと、また暴力行為に及んだ生徒への指導など、適切に対応していただき、今後このようなことが決して起こらないよう再発防止に努めていただきたいというふうに考えているところでございます。
なお、甲子園の出場につきましては大会主催者である日本高等学校野球連盟において適切に判断されるものと承知をしておるところでございますので、個別のコメントは控えさせていただきたいと思います。
また、本件に関しましてインターネット上で様々な意見が飛び交っているということは承知をしているところでございます。先ほど申し上げたように、広陵高等学校におきましては被害を受けた生徒のケアなど、適切な対応と再発防止に努めていただきたいと考えております。他方で、特に匿名性が高いSNS等におきましては発言がエスカレートしていきまして、ややもすると誹謗中傷として新たな人権侵害を生むことにつながってまいりますので、ぜひ冷静な対応をお願いしたいというふうに思っております。以上です。
(注)「ありまして」は、正しくは「おきまして」です。
記者:フリー)
先ほどの件で、裁判とはなれていわばそういう少数派の子供たちに教育的な配慮をしようとしている教員が今、処罰の対象になっているという現状自体は、大臣はどう御覧になってどういうふうに解決したいと思っていらっしゃるでしょうか。
大臣)
例えば、大臣の立場で語れることとそうでないことがあるわけでございますが、例えば国旗国歌法でございますが、過去の説明によりますと国民生活一般に対して述べたものではございませんでして(注)、内心に立ち入って強制しようというものではなく、御指摘の当時の発言でございますが、教育指導上の課題として国歌の斉唱を指導したり、儀礼的な所作として起立斉唱の職務命令を行うことまでを否定するという趣旨のものではないというふうに考えているところでございます。具体的には入学式、また卒業式等におきまして国歌の斉唱や、また起立を求める職務命令を発するかどうかでございますが、これは教育委員会、また校長が適切に判断するものだというふうに私ども考えておりまして、公立学校の教職員、こうした職務命令を受けた場合でございますが、地方公務員法上これに従う職務上の責務があるというふうには考えているところでございます。この責務を果たすというふうに考えているところでございます。以上です。
(注)「述べたものではございませんでして」は、正しくは「述べたものであり」です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室