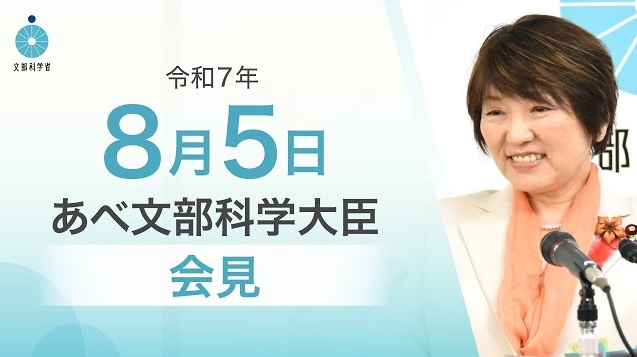- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月5日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年8月5日)
令和7年8月5日(火曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
油井亀美也宇宙飛行士のISS長期滞在を踏まえた今後の日本の宇宙活動への期待、地域における医師の確保のための施策、初等中等教育段階における主権者教育の課題及び改善方策、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)への期待
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年8月5日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年8月5日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭はございません。よろしくお願いいたします。
記者)
油井宇宙飛行士が先日、ISSに到着しました。大西宇宙飛行士と共同で記者会見するなど、日本人宇宙飛行士の活躍が目覚ましいです。また、宇宙開発利用部会の国際宇宙ステーション国際宇宙探査小委員会でもISS退役後の日本としての方向性が決まるなど、議論が進んでいます。今後の日本の宇宙活動への期待と国際社会での存在感について、大臣のご所見を伺います。
大臣)
日本時間8月2日、JAXAの油井亀美也宇宙飛行士が搭乗します米国クルードラゴン宇宙船運航(注)11号機が打ち上げられまして、ISSに無事到着したことを大変嬉しく思います。油井飛行士が着実にミッションを遂行し、またISS及び「きぼう」日本実験棟における成果が最大化されることを心から期待申し上げるところでございます。また、2030年頃、民間主体で運用いたします宇宙ステーションを見据えまして、これまでのISSで培いました我が国の知見や技術を民間企業等に適切に継承していきながら、民間が一体となって宇宙開発利用の発展に取り組むこととしているところでございます。今後とも、宇宙分野の国際協力等を含めた、着実に私ども進めさせていただきながら、国際社会における我が国の存在感、これをしっかり高めていくとともに、民間企業などとともに連携をしながら、我が国の宇宙開発利用に引き続き、取り組んでまいりたいと思います。以上です。
(注)「運航」は、正しくは「運用」です。
記者)
昨日4日、「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」が増子事務次官を訪問し、医師不足や地域間偏在の解消についての提言書を提出されました。医師が少ない地域での医学部の臨時定員増を恒久的なものにすることや医科大学への財政支援なども求めていました。大臣のこの提言に関する受け止めと、医師不足や地域間偏在の解消に向けて文部科学省が今後取り組み、実施を検討している取り組みなどについて教えてください。
大臣)
御指摘の提言書の内容に関しましては私も拝見させていただきました。改めて、地域における医師の確保、喫緊の課題であると感じたところでございます。医学部の定員に関しましては、将来の医師の需給、この観点から原則、抑制するということをしているところでございますが、厚生労働省の検討会における議論も踏まえまして、医師不足地域における勤務、これを条件とする地域枠等を中心に臨時的な増員を認めてきたところでございます。今後とも、厚生労働省との連携を図りつつ、文部科学省といたしましては、地域に必要な医師の確保に向けて、現場の御意見を伺いながら、地域のニーズに応えようと努力することをしっかりと評価をしていきながら取り組んでまいりたいと思っているところでございます。また、各大学が継続的・安定的に教育研究活動を実施できるように、国立大学法人運営費交付金、また私学助成などの基盤的経費の確保にも全力で取り組んでまいりたいと思います。以上です。
記者)
主権者教育についてお伺いします。先日の参院選含めて、選挙では、18歳、19歳の投票率が全体の平均よりも低い傾向が続いているという総務省の結果が出たかと思います。選挙権年齢の引き下げが法律で定められてから10年経ったわけですけれども、現状、このような現状にとどまっていることの受け止めと背景と、今後、どういう風に投票率の向上に取り組んでいくかの考えを教えてください。
大臣)主権者教育に関しましては、学習指導要領に基づきまして、政治参加の重要性や選挙の意義について指導するとともに、大学に対しましても、住民票異動の必要性、また不在者投票制度についても周知を促しているところでございます。一方で、初等中等教育段階におきましては、子どもの意見表明の機会、また、対話や協働を通じました参画の機会が十分に整備されていない、子どもの意見を受け止め、政策や社会の仕組みづくりに生かす地域社会の受け皿が不足しているなどの課題があると私どもも認識をしているところでございます。投票率に関しましては、様々な事情が総合的に影響するものと考えているところでございますが、次期学習指導要領に関する検討の中におきましても、主体的に社会参画するための教育の改善について議論を今、しているところでございまして、引き続き、総務省とも連携しながら、この主権者教育を積極的に推進してまいりたいと思います。また、投票率の向上に向けて、ということの取り組みでございますが、初等中等教育段階におきましては、学習指導要領に基づきまして、政治参加の重要性、また選挙の意義などについて指導を行っているところでございます。特に高等学校におきましては、「公共」などでこの政治的中立性の確保に留意をしながら、指導の一層の充実を図っているところでございまして、また、大学におきましては、住民票異動の必要性、また不在者投票制度等について周知をしながら、入学時におけるオリエンテーションなどを通じまして、学生への啓発活動を促しているところでもございます。文部科学省といたしましては、今後とも、若者の投票率の向上に向けまして、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思います。
記者)
大臣、J-PEAKSのシンポジウムに出席されたかと思うんですけども、実際に現場での取り組みの状況を聞いたりですね、あるいはその感想とですね。今後への期待について教えてください。
大臣)
昨日、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)でございますが、このシンポジウムに出席させていただきまして、採択大学の学長などから、各大学のこの戦略の実現に向けた今後の計画、現在進められている取組などにつきましてお伺いすることができまして、大変感銘を受けました。特に、本当に皆さん頑張ってくださってというところ、さらには資金繰りで大変なところに関してもそれぞれ、いろんなアイデアがございまして、勉強になりました。また、社会が複雑化する中でございますが、大学にはビジョンをしっかりと提唱していきながら、様々な課題解決、牽引していくことが今求められているところだと感じていいます。とりわけ、今回の本事業に採択されました25の大学におきましては、今後の日本の研究力の一翼をしっかりと担っていただくということを期待申し上げているところでございます。文部科学省といたしましても、この事業の伴走支援を通じまして、各採択大学の取組をしっかりと後押しをさせていただきながら、我が国全体の研究力の強化に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思います。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室