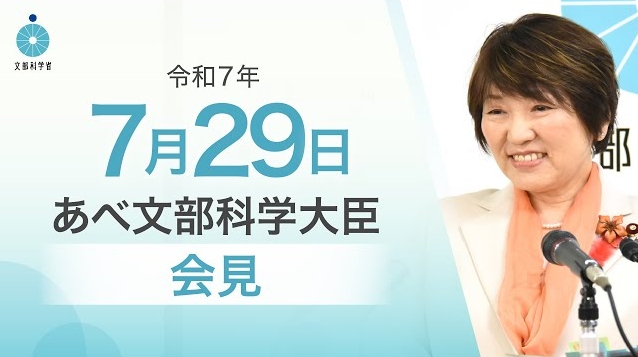- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月29日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月29日)
令和7年7月29日(火曜日)
教育、その他
キーワード
光の子どもクリスチャン・スクール及び同志社大学の視察、優秀な留学生の受け入れ拡大のための大学設置基準等の改定案に関するパブリック・コメントの開始、いじめの未然防止のための取組、自民党における両院議員総会の開催及び石破総理の責任、日本語指導者のうち半数以上をボランティアが占めている実態、日本語指導が必要な児童生徒に対する学校における指導体制の確保・充実
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年7月29日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年7月22日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございます。先週25日でございますが、兵庫県の川辺郡の猪名川町におきまして光の子どもクリスチャン・スクールを、また京都府京都市におきまして同志社大学「今出川校地」を視察してまいりました。光の子どもクリスチャン・スクールにおきましては、児童生徒の皆さんお一人お一人が熱心に学んでいる姿を実際に拝見することができました。学校外の機関における不登校児童生徒に関わる取組状況を把握することができました。引き続き、不登校児童生徒の学びの継続に資する取組を進めてまいります。また、同志社大学「今出川校地」でございますが、キャリアセンター、またラーニングコモンズなどを拝見いたしまして、学生一人ひとりの成長を支えるサポート体制、大学の魅力の一つになると改めて実感をいたしました。今後とも、私立大学の教育研究環境の整備にしっかりと努めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
文部科学省は、優秀な留学生の獲得を促すために25日に定員規制の弾力化を盛り込んだいわゆる大学設置基準等の改正案に関するパブリック・コメントを行ったと承知しておりますが、本件に関する狙いを教えていただきたいです。
大臣)
多様な国及び地域からより多くの優秀な外国人留学生を日本の大学が受け入れ、また大学の学習環境が国際化していくということは我が国のグローバル人材育成を進めていく上でまさに重要だというふうに私ども考えております。これを促進するために、優秀な留学生の受け入れ拡大を計画する大学の学部を文部科学大臣が認定をいたしまして、認定した学部つきましては特例として収容定員の超過を一定程度認めることにいたしまして、パブリック・コメントを開始したところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き優秀な外国人留学生の受け入れを通じました大学の国際化の推進にしっかりと努めてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
何回か伺っていたのですけれども、いじめ要項についてなのですが、大臣は5月13日の会見でいじめの未然防止のためには「安全安心な学校づくりや学級づくり、児童生徒自身が主体的に実施できるようになることが重要」だとおっしゃっていましたけれども、そのためには何が必要で現状何が不十分だと思われますか。昨今、一気に表明した感のある教員の質の低下というのを思うとなかなか難しいのではないかなと思わざるを得ないところもあるのですがいかがでしょうか。よろしくお願いします。
大臣)
御指摘の会見で述べましたとおり、いじめの未然防止につきましては安全で安心な学校づくり、学級づくり、これを児童生徒自身が主体的に実施できるようになることが重要でございますが、これらは何か一つの取組だけで実現されるものではございませんでして、学校教育全体におきまして実現されていくものというふうに考えているところでございます。例えば、これまでも進めてまいりました道徳教育、また人権教育に加えまして生徒指導提要でも示しているところでございますが、様々な意見を出し合える自由な雰囲気を確保すること、また異学年の交流等の機会を通じまして他者の役に立っているという実感、さらには児童生徒の自己信頼感、これを育むことなどに教育活動全体を通じて取り組んでいくことはいじめの未然防止につながるものであるというふうに私ども考えているところでございます。こうした考え方を踏まえまして、今年度、全国で4カ所でいじめの未然防止教育のモデル構築推進事業を実施しているところでございます。来年度以降におきましても、これらの成果を教育委員会等にしっかりと周知をしていきながら生徒指導提要に示されました考え方の更なる周知徹底を図ることによってベテラン・中堅・若手、この教師の格層におきましていじめの未然防止の取組が一層推進するよう、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
記者)
石破総理大臣の進退について、閣内から責任を求める声が上がっていて、両院議員総会の開催を求める署名集めが行われています。まず大臣がこちらに署名されたのか、もしくはされていないのかを教えてください。また、参院選の選挙結果も含めた石破総理の責任についてどう考えているのか、改めて大臣の受け止めをお聞かせください。
大臣)
お尋ねのございました両院議員総会や石破総理の責任につきましてでございますが、文部科学大臣としてお答えするこの場におきましてコメントをするものではないというふうに考えているところでございます。その上で、敢えて申し上げるところでございますが両院議員総会の開催を求める署名につきましては私は関わっておりません。また、私といたしましては石破内閣の一員である文部科学大臣といたしまして、文部科学行政が停滞することがないように引き続き今ある課題に対して一つ一つ着実に取り組んでまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
外国人の日本語学習の指導体制についてお伺ねします。2点お伺いします。日本語学習者が増加する中で日本語教師などの指導者が4万人前後にとどまっており、うち半数以上をボランティアが占めています。これについて大臣の見解をお聞かせください。また、日本語指導が必要な児童生徒数が増加の一途をたどっていますが、7月25日に開かれた有識者会議では教員免許と登録日本語教員の両方の資格を取得できる制度ですとか、採用促進の施策などの何らかのインセンティブをつけるべきではないかという意見が委員から上がっています。日本語指導の人材確保や質の向上、指導体制の拡充に向けて国として必要な予算や施策をどのように考えているのかお聞かせください。
大臣)
令和5年度の「日本語教育実態調査」によりますと、いわゆる御指摘のように国内の日本語教師等の数は46,257人でございまして、そのうち約半数はボランティアとなっているところでございます。ボランティアの方々の多くでございますが、地方公共団体等が実施をいたします地域の日本語教室におきまして指導を行っているところでございまして、地域の日本語教育を支える重要な役割を果たしているものと認識をしているところでございます。このため、文部科学省におきましてはボランティアを含む地域の日本語教育人材の養成・研修など支援に取り組んでいるところでございます。また、ボランティアだけではなくて令和6年度から始まりました日本語教育機関の認定制度、また国家資格としての登録日本語教員制度も活用させていただきまして、日本語教育の水準の維持向上に努めてまいりたいというふうに思っております。また、御指摘のところの過去最高のいわゆる日本語指導が必要な児童生徒のところでございますが、文部科学省といたしましては外国人児童生徒等の日本語習得に関しまして、これまでも日本語指導のための「特別な教育課程」の制度化、また日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、更には日本語指導補助者や、また母国語の支援員の配置など、外国人児童生徒等への支援に取り組む自治体に対する支援などを行ってまいりましたところでございます。他方、日本語指導が必要な児童生徒数は令和5年度に約6.9万人と、約10年間で2倍に増加しているところでございまして、更なる支援の充実が求められているところでございます。このため、本年3月、有識者会議を、設置をいたしまして今後の取り組むべき施策等について御議論いただいているところでございます。先日の会議におきましては、御指摘のありましたように学校における指導体制の確保、また充実に向けまして様々な議論が行われたところでございまして、文部科学省といたしましては有識者会議で議論等も踏まえまして、子供たちに質の高い学び、これを提供できるよう、引き続きしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室