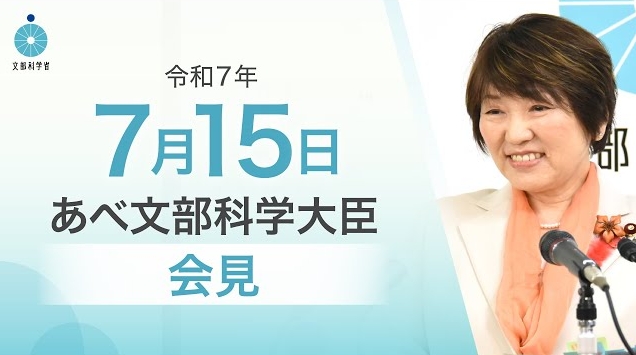- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月15日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月15日)
令和7年7月15日(火曜日)
教育
キーワード
沖縄工業高等専門学校、沖縄科学技術大学院大学及びN高等学校沖縄伊計本校の視察、令和7年度全国学力・学習状況調査の結果公表、令和6年度文部科学白書の閣議配布、教員による子供への性暴力事件を受けたオンライン教育長会議の開催、グラス駐日米国大使との面会、私立学校や名古屋市教委における教員性暴力等防止法のデータベース活用、茨城大学附属小学校におけるいじめ重大事態の調査、SNS上での中国人留学生に関する投稿
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年7月15日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年7月15日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは3件でございます。7月9日に沖縄県に出張いたしまして、関係の教育機関を視察させていただきました。沖縄工業高等専門学校におきましては、高専生による研究活動、また同校の特色ある教育につきまして説明を伺うとともに、沖縄科学技術大学院大学、OISTでございますが、のほうも交えまして高専とOIST、この連携について意見交換を行いました。また、高専生による研究活動の紹介といたしまして災害時に活用できる通信機器機能付きヘルメット、またAIを活用いたしまして海難事故を防止する海流のモニタリングシステムの開発について、事業化も見据えた取組を紹介していただきました。同校が航空関係企業と連携をして取り組んでいる航空技術者育成プログラムについてもお伺いをいたしまして、高専が担っている社会課題解決、また産業人材育成の役割の重要性を改めて認識をいたしました。また、OISTにおきましてはマルキデス学長を始めといたしましたOISTの方々より、外国人教員を日本に引きつけ引き留めるための取組、またOISTと産業界との連携の状況についてお話を伺うことができました。N高等学校におきましては、校内施設、また沖縄伊計本校での面接指導の様子を、視察をさせていただくとともに、進路決定率の向上に関する取組、また実社会に結びつく経験の提供など、特色ある取組についてお話を伺うことができました。今回の視察、また意見交換などを踏まえまして、引き続き関係施策の充実に取り組んでまいりたいというふうに思います。
2件目でございます。昨日、令和7年度全国学力・学習状況調査の結果、学校に提供するとともに、正答率などの全国平均、また今回初めてデータを収集した不登校児童生徒の参加状況などを公表いたしました。本年度調査におきましては、平成19年度の調査開始以来初めて学校現場からの要望に応えまして、夏休み前に結果を提供させていただきました。早速、昨日、子供たちに結果を返却した学校もあるというふうに伺っているところでございます。また、今回の中学校理科の結果でございますが、従来の正答数と正答率ではなく、IRTに基づきますスコア、また5段階の理解度で示しております新しい結果の見方、また活用方法につきまして説明動画やリーフレットを先日公開しましたところでもございます。各学校におかれては、返却した結果を早速御確認いただければというふうに思っております。また、来週には教育委員会にも結果を提供するとともに、今後、国からも細かな分析結果を順次公表いたしまして、学習指導の改善の取組をしっかり支援してまいりたいというふうに思います。
3件目でございます。本日の閣議で令和6年度文部科学白書を配布いたしました。今回の白書におきましては、第1部の特集で2つのテーマを取り上げています。1つ目でございますが、本年2月に中央教育審議会で取りまとめられました答申でございます我が国の「知の総和」向上の未来像について紹介をいたします。2つ目でございますが、昨年7月から9月にかけて開催されましたパリのオリンピック、またパラリンピック競技大会につきまして、大会の概要また結果をまとめるとともに、選手の活躍を支えた文部科学省の取組などを紹介しています。文部科学省といたしましては、引き続き国民に活用される白書を目指すとともに、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化芸術分野の各施策の更なる充実を図ってまいります。以上でございます。
記者)
教員による盗撮など子供への性暴力事件が相次いでいることを受け先週、文部科学省は都道府県などの教育長を集めたオンライン会議を開催し、未然防止に向けた具体策の徹底を求めました。今後、実効性を確保するために例えば全国の教育委員会からの報告を求めるといった対応を検討されているのか、大臣としてどのように対策を徹底されるお考えか、お聞かせください。
大臣)
お尋ねの件につきましては、今月1日に通知を発出するとともに、先週10日木曜日でございますが、「緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議」を開きまして、児童生徒性暴力等の防止など、教師の服務規律の確保の徹底につきまして初等中等教育局長より直接指導を行いました。「児童生徒等に対する性犯罪・性暴力等は絶対に許さない」という姿勢を明確にし、また今一度、取組を徹底するよう強くお願いしたところでございます。今後とも様々な機会を捉えて、教育委員会に対しまして繰り返し指導を行ってまいりたいというふうに考えておりまして、例えば各教育委員会の人事管理担当者向けの研修会などの機会、これも活用するなど、各教育委員会の取組の徹底を促してまいります。以上でございます。
記者)
児童生徒への性暴力で処分された教育情報をまとめたデータベースの関係で、資格法人の75%は確認していなかったことに加え、名古屋市教委でも活用を怠っていたことが分かりました。大臣の受け止めをお聞かせください。また、今回の事態を受け実態を把握するため国公立を含めた全国調査を行う考えはありますでしょうか。
大臣)
今般、名古屋市教育委員会におきまして教育採用に当たって教員性暴力等防止法に基づくデータベースが活用されていなかったとの報告があったところでございます。法律で義務付けられた手続きを実行できていなかったという事実は誠に遺憾でございまして、二度とこのようなことがないよう名古屋市教育委員会に猛省していただきたいというふうに思います。名古屋市教育委員会としては、今後、教員採用にあたって官報の情報検索ツール(注)とともにデータベースを活用していくとのことでございますが、法律上の義務の履行を徹底していただきまして失った信頼を取り戻していただきたいというふうに思います。文部科学省といたしましては、今回の事案を重く受け止めまして全国の国公私立学校でのユーザー登録を改めて徹底するとともに、実際に適切に活用されているかということを調査するよう事務方に指示をしたところでございまして、速やかに実行に移してまいります。子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはならず、児童生徒性暴力の未然防止に向けまして引き続き全力を挙げて私ども取り組んでまいります。以上でございます。
(注)「官報の情報検索ツール」は、正しくは「官報情報検索ツール」です
記者)
大臣は今日この後、アメリカのグラス駐日大使と面会される予定ということなのですが、この場でどういったお話しをされる予定なのか伺います。また、トランプ政権は学生ビザについてSNSの投稿内容の審査を強化する方針を打ち出しました。このことによる日本人学生への影響をどう見られているのかという受け止めと、この件についてグラス大使に何か要望されるお考えがあれば合わせてお願いします。
大臣)
米国は我が国にとりまして唯一の同盟国でございまして、人的交流また学術交流、日米同盟を支える重要な基盤となっているところでございます。本日は日米間の教育、また科学技術協力の強化につきましてグラス大使と率直な意見交換ができればというふうに思っております。また、学生ビザの件でございますが米国政府による学生ビザの問題に関しましても、これまでも累次にわたりまして米国に申入れを実施をしているところでございます。本日、グラス大使にも日本人留学生等に不利益を生じさせないよう柔軟な対応を求めてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
茨城大学教育学部附属小学校で2021年に起きたいじめ重大事態についてお尋ねします。この件をめぐっては、文科省側への重大事態の報告をめぐり大学が被害女児側に事実と異なる情報を伝えており、大学学長が3度にわたり保護者に謝罪する異例の事態となっております。このことについてと、第三者委員会が立ち上がってから間もなく2年を迎えるのですがまだ調査結果が出ていないことについての大臣としての受け止めをお聞かせください。
大臣)
御指摘の事案につきましては、現在、第三者委員会におきましていじめ重大事態の調査が行われているものと承知をしているところでございます。そういう中で、調査に要する期間は事案によって異なっておりまして、一概に調査期間の妥当性について見解を述べることは困難だというふうに考えています。その上で、一般論として申し上げればこの重大事態の対応にあたりましては法や国の基本方針、またガイドラインに基づきまして被害児童生徒やその保護者のいじめの事実関係を明らかにしたいという切実な思いがありますので、それに私どもしっかりと寄り添いながら対応していくことが重要だというふうに考えているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き大学の対応を注視するとともに、必要な指導と助言に関して行ってまいりたいというふうに思います。
記者)
学力調査関係で2点お尋ねします。今回初めて不登校や障害がある児童生徒の参加状況をアンケート調査をして小学校で約4万人、中学校で約2万5,000人が参加したことが把握できました。この結果の受け止めと、今後どう活かされるかをお話いただきたいのが1点と、もう一つ、今回、児童生徒質問の速報値で小学校の算数、中学校の数学で授業の内容がよく分かると回答した児童生徒の割合が減っていることや学校以外の過ごし方で平日の勉強時間が減少傾向にあるということが明らかになりました。この結果の受け止めと今後の対応についてのお考えをお話しください。
大臣)
長期欠席児童生徒、特別な教育的支援を必要とする児童生徒、外国人児童生徒等の本調査への参加状況を把握するため、5月から6月にかけて、今年でございますが、各学校にアンケートを実施いたしました。回答くださった学校に感謝を申し上げます。各学校の御協力によりまして、支援を必要とする児童生徒の本調査の参加状況を初めて把握できたことは大変意義深いというふうに考えておりまして、今後、このアンケート結果を活用させていただきながらこれらの児童生徒の学力、学習状況の分析を進めまして支援策の検討・充実につなげてまいりたいというふうに思っているところでございます。また、今回の児童生徒の質問におきましては国語、算数・数学、理科、全ての教科において授業の内容がよく分かると回答した児童生徒の割合が減少をいたしました。また、学校の授業以外の勉強時間の減少傾向が続いているということも分かりました。いずれも例年、各教科の正答率とスコアとの正の相関が見られる項目でございまして、分析を深める必要があるのだと考えているところでございます。質問調査の結果、詳細、それを受けた対応につきましては7月31日に2段階目の結果公表をお示ししてまいりますので、またいろいろ御質問などをいただければというふうに思っているところでございます。
記者)
参院選の投開票を前に、SNS上では外国人留学生の誤情報と思われる投稿が拡散されています。その点について2点質問させてください。中国人留学生だけを優遇しているといったSNSの投稿が拡散されていますが、現状の留学制度において国籍の差異によって優遇実態はあるのでしょうか。また、こうした外国人に関する根拠に基づかない偽情報が広がっている現状について大臣の受け止めをお教えください。
大臣)
外国人留学生の受入れに関しましては、大学等における多様性また流動性を高めるものでございまして、日本人学生と外国人留学生が共に学ぶ環境は我が国のグローバル人材育成を進める上でまさに重要だというふうに考えています。文部科学省におきましては、多様な国及び地域から優秀な外国人留学生を受け入れるための各種支援制度を設けておりますけれども、特定の国籍を優遇した支援は行っておりません。文部科学省といたしまして、引き続き支援制度の趣旨また内容等について正確な情報発信に努めてまいります。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室