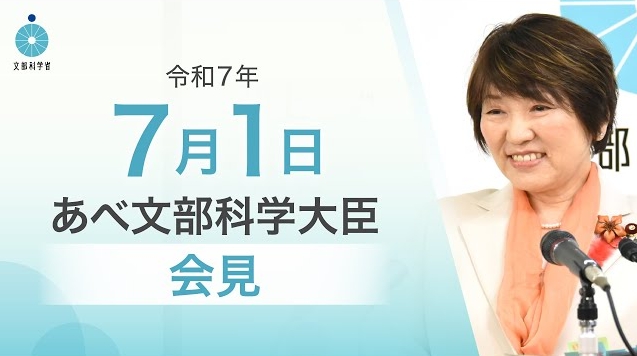- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月1日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年7月1日)
令和7年7月1日(火曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
H-ⅡAロケット50号機の打上げ成功、鹿児島大学及び市来農芸高校の視察、大学入学共通テストの電子出願「マイページ」の開始、大学ファンドを活用した海外の優秀な若手研究者等の緊急支援の決定、教室内の防犯カメラ設置の是非、教師による児童生徒性暴力等の根絶、博士課程学生向け支援事業制度における留学生への支援の見直しについて、郷土に関する学習の充実、小田原短期大学の幼稚園教諭要養成課程における不適切試験、メンタルヘルスに問題を抱える大学生の増加について、高校教育改革に関する検討について
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年7月1日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年7月1日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは4件でございます。6月29日午前1時33分でございますが、「温室効果ガス・水循環観測技術衛星」(いぶきGW)を搭載いたしましたH-ⅡAロケット50号機の打上げを実施いたしまして、衛星の軌道投入に成功したという報告を受けました。いぶきGWでございますが、JAXAと環境省が共同で開発いたしました衛星でございまして、これを温室効果ガスや海面水温等の高度な測定を可能とするものでございます。気候変動、また防災、更には減災、水産業などの幅広い分野におきまして貢献することを期待しているところでございます。また、今回のH-ⅡAロケット50号機でございますが、最終号機でございまして、2001年の運用開始以降、50機中49機が打上げ成功となるなど、高い信頼性を示すことができたところでございます。有終の美を飾れましたこと、大変喜ばしく思っておりまして、関係者の皆様に心から敬意を表したいというふうに思います。今後は、後継となりますH3ロケットの打上げや高度化を着実に進めまして、引き続き宇宙開発利用を積極的に推進してまいりたいというふうに思います。
2点目でございます。昨日6月30日でございますが、鹿児島大学と鹿児島県立市来農芸高等学校の視察をしてまいりました。鹿児島大学におきましては、新日本科学、鹿児島大学、熊本大学の産業人材育成に係る今後の連携方策、また少子化が進む中においての国立大学の在り方について意見交換を行うとともに、大学と企業が連携するに当たりまして必要となります双方向遠隔講義システムを視察をさせていただきました。鹿児島県立市来農芸高等学校におきましては、「コオロギをタンパク源として養鶏に活用する研究」について生徒さんたちから発表していただきまして、改めて農業教育の重要性を認識するとともに、鹿児島県におきましては農業高校の振興にしっかりと取り組んでいただいているということを実感いたしました。今回の視察を通して得たことを踏まえまして、引き続き関連施策の充実にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
3件目でございます。令和8年1月実施の大学入学共通テストから志願者の利便性向上、また高等学校の負担軽減のため、電子出願システムが導入されます。これに伴いまして、本日から「マイページ」の作成が開始されます。出願受付に関しましては9月16日から開始となるところでございますが、出願に先立ちまして志願者自身が出願サイトでアカウントを登録しマイページを作成する必要があります。大学入試センターが発行する受験案内に操作方法などを記載しておりますので、志願者は焦らずに安心して対応いただくようお願い申し上げます。文部科学省といたしましては、大学入試センターと連携をしながら高校関係者等への複数回の説明会を実施するなど、引き続き丁寧な情報発信を進めてまいりたいというふうに思います。
4件目でございます。先日公表いたしました「J-RISE Initiative」に基づきまして、海外研究者等の受け入れに向けまして緊急的に大学ファンドを活用することとしていましたが、昨日付で国際卓越研究大学法に基づく基本方針につきまして必要な改訂を行いまして、当該改訂を踏まえた緊急支援の概要を決定いたしましたので御報告をさせていただきます。具体的には、海外から優秀な若手研究者・博士課程の学生の受け入れを進める日本トップレベルの大学に対しまして、大学ファンドを活用いたしまして今年度からの3年間で総額33億円を助成することにいたしました。今後、準備が整い次第でございますが当該支援に関する公募を開始いたしまして、本年9月中を目途に支援大学を決定する予定でございます。また、応募状況、J-RISE Initiativeに関わる施策の実施状況を見ながら必要に応じまして追加的措置をしっかりと検討してまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
名古屋市の教員による盗撮事件に続いて、広島市でも教室で教員がわいせつ行為をしようとしたとして監禁や不同意わいせつ未遂などの容疑で逮捕されるという事件が起きました。また、福岡県でも高校での盗撮事案が判明していて、ちょっと続きすぎていて異常なのではないかなという印象も受けます。昨日、こども家庭庁の有識者会議とかでは防犯カメラの設置も有効なのではないかという議論も出ていたようですけれども、防カメの設置についてメリット、デメリットであるとか賛否、必要性についてどう考えているかというのを教えていただけますか。
大臣)
教師によるわいせつ事案が立て続けに報道されておりまして、極めて遺憾でございます。改めて強く申し上げますが、教師から児童生徒への性暴力は決してあってはならないことでございまして、断じて許されるものではありません。事実が確認され次第、任命権者におきまして厳正に対処していただきたいと考えているところでございます。その上で、ご指摘の教室への防犯カメラの設置につきましては、一般論といたしまして複数の人の目が届く状況で性被害の発生は想定しがたいということや、また子供たちの日常の活動が全て録画されているという状況の是非などを踏まえますと、一般の教室への設置を広く推奨することは様々な議論があるものと私ども思っております。他方、例えば一対一または少人数となる場面など、複数の人の目が届きにくい限定的な場面でのカメラの活用は考えられるところでございまして、その場合におきましても保護者や児童生徒等にカメラの設置につきましてしっかりと御理解を得ながら実施することが必要だというふうに考えているところでございます。いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては今般の事案を踏まえて、まずは児童生徒に対する性暴力等の防止など、教師の服務規律の確保の徹底を図ることが重要であるというふうに考えているところでございまして、本日にも全国の教育委員会に対しまして文書を発出いたしまして指導をしっかりしていくとともに、近く都道府県等の教育長を集めてオンライン会議を開きまして直接説明を行うなど、引き続きあらゆる機会を捉えて教師による児童生徒性暴力等の根絶に向けまして厳正な対応の更なる徹底をしっかり図ってまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
私、先週金曜日の会見にいなかったので朝日さんの質疑の続きみたいなところなのですけれども、SPRINGの生活相当額の支給を日本人に限定する変更について、朝日さんの質疑の中で大臣は事業の趣旨が日本人の支援で趣旨に沿った見直しということをおっしゃっていたと思いまして、実際にそれを事業趣旨だとして切実である博士人材確保の観点から言いますと本来、国籍に関係なく多様で優秀な人材に1人でも多く日本の博士課程に進学してもらうことが重要だと思うので、事業趣旨やそれに沿った見直しとして生活相当額の支給を国籍で区切る必要性、意味があるのか、そのほうが国益の面で大きなアウトカムにつながるという根拠があるのかを教えてください。あと、合わせて日本人の支援が事業趣旨というのがちょっと公文書上の根拠でよく分からなかったのでその根拠も教えていただけますでしょうか。
大臣)
御指摘のとおり、先日26日でございますが、開催されました審議会におきまして次世代研究者挑戦的研究支援プログラム(注)(SPRING)についてでございますが、支援の見直しのあり方を示している議論がなされたというふうに承知をしているところでございます。具体的には、日本人学生の博士後期課程への進学の支援、また学生が安心して研究活動に専念できるようにするための支援、また大学による学生に対するキャリア支援、環境整備の事業趣旨を改めて明確化をした上で、留学生への研究の奨励費に関して、これは生活費相当額の部分でございますが、この支援は行わないということや、社会人学生に対しまして研究費を支援すること、また優秀な学生に対して研究費支援を重点化することを盛り込んだ見直しを示しました。日本人学生が博士後期課程に進学しない要因といたしましては、特に在学中の経済的不安等があるのに対しまして、留学生は日本の大学の博士後期課程進学を目的に来日をしておりまして、かつ私費留学の学生も多いことに鑑みまして、留学生への研究奨励金の生活費相当額の支援を行わない方向が示されたところでございます。なお、大学の研究活動の活性化、また学生の質の向上の観点から引き続き留学生に対しても研究費を支援する方向ではございます。文部科学省としては、引き続き博士人材の確保に努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
(注)「次世代研究者挑戦的研究支援プログラム」は、正しくは「次世代研究者挑戦的研究プログラム」です。
記者)
今のお話あった留学生の方が私費で留学していて支援が不要というお話なのですけれども、従来、自費が多かったのは留学生に限らず日本人も同じで、留学生だからお金をもらわなくても生活費に困らないというのがちょっといささか危惧に感じたのですけれども、そもそもSPRINGの公募要領の事業概要の書き出しにある博士課程に進学すると生活の経済的見通しが立たないので、今、大臣もおっしゃっていたお話、このボトルネックがある背景については大臣はなぜだと認識されていらっしゃるのか。その背景は日本人に限ったものなのか、それとも日本への進学を検討している外国人を含めて共通するものなのか。もし外国人にも経済的見通し、日本の博士に進んだら経済的に見通しが立たないというボトルネックが共通するものであれば、これは外国人に対しても生活費支援相当額の支給が必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
大臣)
詳細につきましては事務方にまたお尋ねいただければと思います。
記者)
幼稚園教員免許取得を巡る小田原短大の試験で模範回答を丸写しできる状態だったことが判明しました。この問題に関する大臣の受け止めと、文科省として全国の短大や大学、専門学校などに指導を行う考えがあるかどうかをお聞かせください。
大臣)
幼稚園教諭免許状の取得に対する部分のお話でございますが、本件につきましては2月の報道を受けまして小田原短期大学の聞き取りを行ったところでございまして、単位の認定試験におきまして、試験に持ち込むことが認められた学習の手引き等に試験問題と同一の問題、模範解答が含まれるなど、不適切な運用が確認されたところでございます。そのため、文部科学省といたしましては当該短期大学への指導及び助言を行いましたところでございまして、文部科学省におきましては今般の事例を踏まえまして単位の認定と成績評価等の適切な運用について改めて周知をしっかりしてまいりたいというふうに思います。
記者)
民間の会社による調査で、メンタルヘルスの問題を抱える大学生がコロナ禍以前と比べて現在かなり増加傾向にあることが分かっております。自殺件数も高止まりの傾向にありまして、学生の相談によって非常に対応に追われてパンク状態になっている大学がある現状もあります。こういった状況につきまして、文科省としてはどのように捉えられているのかというのを教えてください。また、今後、実態調査などを行う予定はあるのか、また文科省として取り組む対策などにつきましてお考えがあればお聞かせください。
大臣)
御指摘の調査についてでございますが、その詳細は把握しておらず個別にコメントすることは控えたいというふうに思うところでございますが、日本学生支援機構が実施した調査によりますと一大学当たりの学生からの相談件数につきましては、コロナ禍前の令和元年でございますが1,084件であったところ、令和4年におきましては1,238件と増加傾向にあるということは承知をしているところでございます。こうした中におきまして、各大学におきましては学生の悩みや不安に寄り添ったきめの細かい対応を図ることがまさに重要でございまして、文部科学省におきましても大学の取組事例を収集していくとともに、また大学等の教職員を対象といたしました研修などの機会を活用いたしまして好事例の周知を図るなど、各大学における取組の充実を努めているところではございます。引き続き、日本学生支援機構におきましては調査等を通じまして学生の実態また大学の取組状況の把握にしっかり努めていくとともに、学生が安心して学びに打ち込めるような各大学の取組を促してまいります。また、調査などに関してでございますが、更なる調査でございますが、繰り返しになりますが文部科学省といたしましては、引き続き日本学生支援機構による調査等を通じまして学生の実態また大学の取組状況も把握に努めていきながら、大学等の現場の声もしっかり聞かせていただきながら学生が安心して学びに打ち込めことができるように必要な対策は取り組んでまいりたいというふうに思います。
記者)
名古屋、福岡の教員による盗撮事件の関連で、追加でお尋ねします。盗撮した画像などは、SNSのグループチャットで共有されていたとされており、小中学校の教員と見られる約10人が参加されていたと見られています。現状ではそのうち逮捕に至ったのが3人にとどまっており、その他については今も教壇に立っている可能性があると考えられることから、全国の児童生徒や保護者の方は非常に不安な思いを抱えているかと思いますが、こうした状況についての大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
お尋ねの一連の件につきましては、現在、警察等による捜査が行われているというふうに私ども承知しているところでございますが、おっしゃるように報道では10人近くの教員がSNS上のグループで画像を共有していたというふうにされているところでございます。当該教員がいれば、子供たちの前からすぐに離れて一刻も早く名乗り出ていただきたいと私ども考えています。また、先ほど申し上げましたように文部科学省におきましては再発防止に向けまして、全国の教育委員会に対しまして本日にも文書を、発出をいたしまして指導いたします。加えて、近く文書だけではなく都道府県等の教育長を集めたオンライン会議を開きまして直接説明をする予定でございます。国及び各教育委員会等、取組の徹底を通じまして教師による児童生徒性暴力等の根絶に向けまして厳正な対応の更なる徹底を図ってまいります。
記者)
先ごろ、新しい地方経済生活環境創生本部の閣僚会議で閣議決定されました「地方創生2.0」、こちらの基本構想に今後10年間に取り組む目標施策として地域に愛着を持ち地域で活躍する人材の育成が盛り込まれています。具体的には、次期学習指導要領で郷土学習を充実するとしたほか、現行の学習指導要領でも郷土学習の先進事例の普及や加速といったことを明記しています。これに対して、教員から負担増を危惧する声が上がっているほか、外国につながる児童生徒に対してはプレッシャーになるのではないかといった懸念も聞かれます。文科省としての見解をお聞かせください。
大臣)
「地方創生2.0基本構想」でございますが、おっしゃるように学習指導要領を改訂いたしまして、郷土学習、これを充実すること、また改訂をまたずに郷土学習の先進事例を普及加速することが盛り込まれたところでございます。いずれにいたしましても、詳細は今後の検討となるところでございますが、教育内容の充実は働き方改革と両立させる必要があると私どもも考えておりまして、過度な負担が生じないよう十分配慮してまいりたいというふうに思います。また、学校が所在する地域に関する学習の充実が外国にルーツを持つ児童生徒にプレッシャーをかけるとは必ずしも考えていないところでございますが、具体の教育活動を行う上で多様な背景を持つ子供たちに必要な配慮を行うことは当然というふうに考えているところでございまして、今後の検討にあたりまして御懸念のようなことがないようにしっかり対応してまいりたいというふうに思います。
記者)
高校教育改革のことについてお尋ねします。国会のほうで、自公維で高校教育改革のグランドデザインについて議論されてきましたが、こちらについて文科省が8月中に中間まとめを行う方向で調整に入ったという報道がありました。こちらの事実確認をさせてください。また、もし事実であるならば今後どのように取りまとめを行っていくのかという流れと、どのような内容をその中に取り込んでいきたいというお考えなのかも合わせて教えてください。
大臣)
公立高校の将来的な在り方を示すグランドデザインにつきまして、8月中に中間まとめが行われる旨の報道は承知しておりますが、そういった事実はございません。いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては先日、3党の検討チームで取りまとめられました大枠の整理、また骨太方針等を踏まえまして高校教育改革、また高校教育の質の向上につながりますよう、引き続き検討は進めてまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室