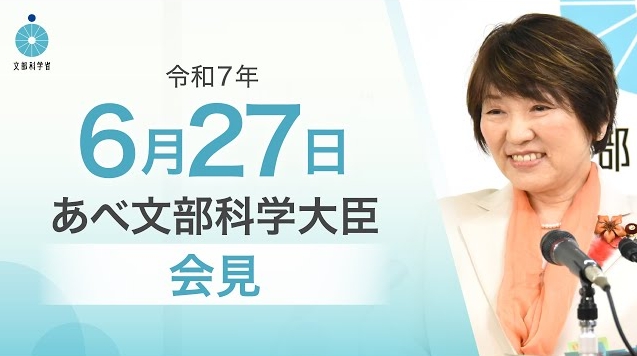- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月27日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月27日)
令和7年6月27日(金曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
福島県立ふたば未来学園及び大熊町立学び舎ゆめの森の視察、小学校教員らによる児童盗撮事件を受けた教員による性暴力等防止への対応、博士課程学生向け支援事業制度における留学生への支給の見直し、入学しない私立大学への入学料の納付に対する対応、国立大学協会の新会長への期待と今後の方針
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年6月27日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年6月27日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から1件でございます。昨日26日でございますが、福島県双葉郡で福島県立ふたば未来学園と大熊町立学び舎ゆめの森を、視察させていただきました。ふたば未来学園でございますが、復興のシンボルとなる学校でございまして、同校の教育活動、また、NPO法人カタリバと連携をしていきながら、校内のフリースペースで生徒をサポートする取組を視察するとともに、同校の先進的なカリキュラムによる人材育成について意見交換を行わせていただきました。ここで学んだ子どもたち、1度福島を出た後に戻ってきてくれているとのお話も伺っておりまして、復興が着実に進んでいることを実感をさせていただきました。また、学び舎ゆめの森でございますが、令和5年8月に大熊町に帰還した学校でございまして、0歳から15歳までシームレスな学びや子ども自身で学びを進める自由進度学習などの先進的な教育活動を視察させていただきまして意見交換を行いました。この学校が核となりまして、移住者の呼び込みにつながっているというお話も伺いました。今回の視察を踏まえまして、福島の復興・創生に向けまして引き続き全力で取り組むとともに、教育政策の充実をしっかりと活かしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
記者)
名古屋市の小学校の教員らが女子児童を盗撮し、画像などをSNS上のグループチャットで共有したとして逮捕された事件についてお尋ねします。この事件では、勤務中に撮影したとみられる写真があったことや小中学校の教員ら10人近くがグループに参加していたとみられることが報道されています。事件についての大臣の受け止めと、文科省として現時点での再発防止策などの検討がありましたらよろしくお願いします。また、2026年12月から運用開始予定の日本版DBSでは、教員採用時などに性犯罪歴を照会することになりますが、事件化されていないわいせつ行為は対象外で初犯の抑止効果は限定的とも言われています。こうした課題を踏まえて、今後どのような対策が必要と考えているかお尋ねします。
大臣)
お尋ねの名古屋の小学校教員らのいわゆる女子児童らの盗撮の件でございますが、いずれにつきましては現在、警察等による捜査が行われていると承知しているところでございますが、容疑者も容疑を認めているという報道もございまして、こうしたことにより教師への信頼、これが損なわれるような状況が生じていることにつきまして極めて遺憾に思います。また、被害を受けた子どもたち、日々頑張っている多くの教師の皆さんのことを思うと本当に怒りを覚えるところでございます。断じて許せません。また現在、名古屋市教育委員会及び横浜市教育委員会からは「事実関係を確認しているところであり、事実確認の上、厳正に対処する」という旨の報告を受けているところではございますが、教師から児童生徒への性暴力は決してあってはならないことでございまして、事実確認次第、任命権者において厳正に対処していただきたいと考えているところでございます。本事案を受けまして、文部科学省といたしましては児童生徒に対する性暴力等の防止など、教師の服務規律の確保の徹底につきまして全国の教育委員会に対しまして文書を発出して指導をいたします。併せて、文書だけではなく都道府県等の教育長を集めてオンライン会議を開きまして、直接説明をさせていただきます。詳細につきましては、急ぎ事務方に検討を指示したところでございますが、あらゆる機会を捉えて教師による児童生徒性暴力等の根絶に向け、厳正な対応の更なる徹底を図ってまいります。また、今後施行予定でございますこども性暴力防止法の適切な運用に向けまして、こども家庭庁とも密接に連携しながら対応を進め、こうした仕組みも含めまして引き続き必要な取組を徹底してまいりたいというふうに思います。
また、もう一つお尋ねの日本版DBSでございますが、いわゆる日本版DBS法、こども性暴力防止法におきましては、御指摘いただいたように採用時に性犯罪歴を確認することとなっているところでございますが、このほかにも学校設置者等に対しまして、子どもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置として子どもと接する職員に対する研修の義務付け、さらには性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として児童等への面談等の措置の実施、また児童等が容易に相談を行うことができるようにするための相談体制の整備等の措置などを講じるよう義務付けているところでございます。また、既に施行されている教員性暴力等防止法におきましても、教育職員への研修の実施等、事案の防止などのために必要な措置を学校設置者に義務付けているところでございまして、これらの法に基づく取組を引き続き徹底してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
記者)
大学院の博士課程の学生向けの支援制度SPRINGについて、最大240万円減額にあたる生活費部分の支給を留学生に対して2027年度以降取りやめる方針を26日、昨日、文部科学省が示しました。3年間では700万円近い支援が0になるという意味で、今後40万人の受け入れを目指す留学生の招致に向けてネガティブな政策変更になるのではないでしょうか。また、米トランプ政権の政策で世界的に留学生や研究者が不安を感じているタイミングでもあり、日本のアカデミアが内向きなイメージを持たれるのではないでしょうかという懸念が出ています。大臣の所感を聞かせてください。
大臣)
昨日、審議会が開催されまして、次世代研究者挑戦的研究プログラム、いわゆるSPRINGでございますが、につきまして支援の見直しの在り方を示して議論がなされたというふうに承知をしております。具体的には、日本人学生の博士後期課程の進学の支援、また学生が安心して研究活動に専念できるようにするための支援、また大学による学生に対するキャリア支援や環境整備の事業趣旨を明確化した上で、留学生への研究の奨励費に関しましては生活費相当額でございますが、その支援は行わないこと、また社会人学生に対して研究費を支援すること、優秀な学生に対して研究支援を重点化することなどを盛り込んだ見直しを示したところでございます。文科省といたしましては、審議会におけるこの議論を踏まえながら、引き続き博士後期課程学生に対する支援に努めてまいりたいというふうに思っておりまして、事業趣旨は、元々は日本人学生の博士後期課程学生の進学を支援すること等を明確化した上で、留学生には研究奨励費としての生活費相当の支援は行わないことでございまして、これは事業趣旨にのっとりました見直しでございまして、政策変更には私たちは当たらないというふうに考えておりまして、引き続き留学生に対する研究費を支援する方向であることから日本のアカデミアが内向きであるという指摘には当たらないというふうに私どもは考えています。以上です。
記者)
昨日26日、私学のほうから入学しない大学への入学金の納付につきまして学生の負担軽減策を求めるような通知を発出されました。この問題を巡っては、長年にわたっていろいろな指摘や議論があったものというふうに思っております。こういった通知をこのタイミングで出すことになったのはどうしてなのか、このタイミングで出すことの意義についてお聞かせください。また、入学金を巡っては2006年の最高裁判決によって大学側が合格者に入学できる地位を与える対価というふうな判断を示して、原則返還の必要はないという判決を出しております。今、私立大の入学金の平均は約24万円ですけれども、この24万円という額は入学できる地位を与える対価として妥当な金額だというふうに思われますでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
大臣)
大学における入学料の額、また納付期限等の取り扱いにつきましては各大学において判断されるものでございますが、入学しない大学に納付する入学料、また学生や保護者にとって負担となっている現状、また入学者選抜の機会が多様化をいたしまして入学料を複数の大学に納付する機会が拡大している状況、さらには昨今の高等教育の負担軽減の観点、これを踏まえた上で昨日6月26日付で入学しない学生の納付する入学料に関わる負担軽減のための方策を講じるよう努めることなどについて通知を発出し、要請を行ったところでございます。また、私立大学の入学料の平均額でございますが、減少傾向には実はございますが、入学料について最高裁の判決によりまして学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質ということを有し、学生を受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられていることが予定されているものというふうにされておりまして、当該判決も踏まえつつ各大学の設置者におきまして適切に設定いただくものと私ども考えているところでございます。各大学におきまして、学生の進路選択の幅が狭まることがないよう、大学の実情に応じまして経済的負担軽減等に取り組んでいただきたいというふうに私ども考えておりまして、文部科学省といたしましては大学の取組がしっかりと進むよう、趣旨の徹底等に努めてまいりたいというふうに思います。
記者)
教員による盗撮共有事件について、関連でお尋ねします。名古屋市では、関連事案がないか独自調査をするとしていますが、服務規律の徹底や教育委員会の指導とともに必要な対応を今後検討されるのでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
大臣)
繰り返しになるところでございますが、全国の教育委員会に対しまして文書の発出による指導、また教育長を集めましたオンライン会議の場、先ほど申し上げましたが、直接説明することによりまして児童生徒に対する性暴力等の防止など、教師の服務規律の確保の徹底をしっかりと求めていく予定でございまして、文部科学省が全国的な調査を実施するということに関しましては現時点では考えてはおりませんが、教育委員会と連携しながら教師による児童生徒の性暴力等の根絶に向けて必要な取組はしっかりと徹底してまいります。
記者)
国大協が先日行った総会で、東京大学の藤井学長が新会長に選任されました。全国の国立大学を知の拠点として知の総和の向上や世界のウェルビーイングにつなげるよう取り組みたいという要望を述べましたが、文科省として新会長に期待することや今後、国大協との連携の方針について教えてください。
大臣)
国立大学協会の新たな会長に就任されました東京大学の藤井輝夫総長におきましては、今後の国立大学の更なる発展に向けまして大いに尽力いただけるものと期待をしているところでございます。文部科学省といたしましては、国内における少子化、この急速な進展と複雑化する国際社会におきまして大学の教育研究活動の発展に向けまして必要な改革、しっかり取り組んでいただくことが必要であるというふうに私ども考えておりまして、引き続き国立大学協会と連携をしながら教育の質の向上、更には研究・イノベーション力の強化と、更にはこれを支える経営基盤、ここの強化など、国立大学の機能強化に向けて取り組んでまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室