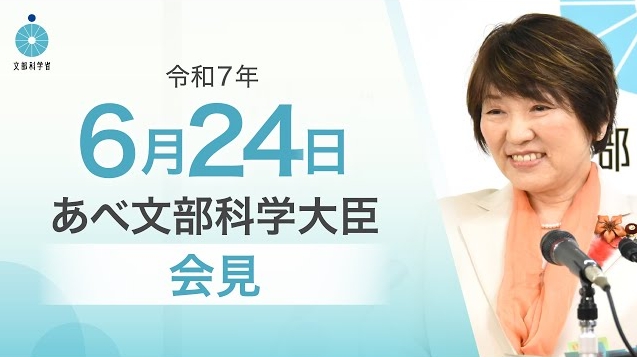- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月24日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月24日)
令和7年6月24日(火曜日)
教育、科学技術・学術、その他
キーワード
日本原燃及び東北大学の視察、令和7年「こども霞が関見学デー」プログラムについて、令和6年度「英語教育実施状況調査」の結果に対する見解と今後の取組、「国際原子力人材育成イニシアティブ」をはじめとする原子力人材の育成について
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年6月24日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年6月24日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から2件でございます。昨日23日でございますが、青森県の日本原燃と東北大学を訪問してまいりました。日本原燃におきましては、竣工に向けまして準備を進めていますところの再処理工場、またMOXの燃料工場といった原子力の関係施設を視察をさせていただきました。東北大学におきましては、若手研究者との意見交換に加えまして大学執行部と、特に優れた業績を挙げた際の特例的な給与のあり方、またプロボストのもとで人事戦略の司令塔となる専門部署の設置、さらには海外研究機関での経験を積んだ他国出身の国際化担当役員の着任など、先進的な取組状況等について意見交換をいたしました。また、大学の敷地内に量子科学技術研究開発機構が地域パートナーと連携をして整備をしておりまして、本年の3月から共用利用を開始したNanoTerasuの視察を行わせていただきました。今回の視察を踏まえまして、引き続き原子力分野における人材育成、さらには最先端の大学研究施設(注1)の整備・共用や世界最高水準の研究大学の実現の取組をしっかり進めてまいります。
2件目でございますが、今年度も各府省庁等に(注2)「こども霞が関見学デー」を実施することといたしましたのでお知らせをいたします。今年度は、子どもたちの夏休み期間中であります8月6日水曜日、7日木曜日、これを中心に開催いたしまして、過去最多の29府省庁等がそれぞれの特色を生かしたプログラムの実施を予定しているところでございます。文部科学省におきましては、大臣と子供たちの懇談をはじめとして69の体験型プログラム・オンラインプログラムを実施いたしまして、親子の触れ合いを深めつつ子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会を提供することとしているところでございます。できるだけ多くの親子に参加していただき、また子どもたちの夏休みを有意義なものにしていただきたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。
(注1)「最先端の大学研究施設」は、正しくは「最先端の大型研究施設」です
(注2)「各府省庁等に」は、正しくは「各府省庁等と共に」です
記者)
昨日23日に英語教育実施状況調査の結果が公表されました。一定レベルの英語力を持つ生徒の割合が増えている一方で、地域差が大きいという課題も改めて浮かんだかと思います。結果の受け止めと、この格差の解消に向けてどう取り組んでいくか、お考えを教えてください。
大臣)
今回の調査におきましてでございますが、一定の英語力を有する中高生及び教師の割合は前年度より増加いたしました。教育委員会や現場の先生、子どもたちの努力に敬意を表したいというふうに考えているところでございます。また、御指摘のとおり、生徒の英語力等には地域差がございますが、生徒の英語力に関する政府目標を達成した自治体数はここ数年増加する傾向にございまして、例えば中学校でございますが令和3年20であったのが令和6年度は37、高等学校におきましては全47自治体中でございますが、令和3年8であったのが令和6年で21となりました。文部科学省といたしまして、全ての都道府県・指定都市が目標を達成することが重要というふうに考えておりまして、調査結果を各教育委員会に丁寧にフィードバックをし主体的な検討を促すとともに、AIを活用した英語教育の実証事業の拡充や、また英語教育の好事例の周知と、また普及に努めるなど、自治体の取組を積極的に支援してまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
今の質問に関連しまして、最近AIを使った翻訳ツールなどが相当発達していまして、子どもたちに英語を学ぶ意義をどう伝えていくかも課題となっていると思います。大臣は、アメリカへの留学の御経験もある立場を踏まえまして、大臣としてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
大臣)
現行の英語の学習指導要領では、単に日本語を英語に置き換えるのではなくて、文化の理解、また相手への配慮をしていきながら気持ちや考えを伝え合う力、また態度を育成することを重視しているところでございまして、こうした考え方は今後とも大切だというふうに私ども考えているところでございます。一方で、御指摘の生成AIなどの技術が飛躍的に発展し、また手軽に質の高い翻訳、通訳も可能となる中にありまして、子どもたちに一層意欲を持って英語を学んでもらうためにも英語教育のあり方を改めて検討し直す必要があるものと考えているところでございます。このため、次期学習指導要領に向けまして中央教育審議会への諮問でございますが、AIの活用を含めた英語教育の改善、またさらには英語教育の意義の再整理も含めた検討を要請しているところでございまして、今後、専門の部会を設けまして集中的な議論を行ってまいります。以上でございます。
記者)
行政事業レビューを対象に「国際原子力人材育成イニシアティブ」が選ばれました。そこで、改めて原子力人材育成の重要性についての大臣の御認識と文科省の取組について教えてください。
大臣)
本当にまさに原子力人材育成は重要でございまして、原子力、これは発電をはじめとするエネルギー利用等の観点から重要な分野でございまして、国家としても、また科学技術といたしましても原子力分野の人材育成を安定的に行っていくことが大変重要だと私ども考えております。このため、文部科学省におきましては国際原子力人材育成イニシアティブ事業、これを通じまして産学官、これが連携をした人材育成コンソーシアム(ANEC)を構築いたしまして、原子力人材育成の体系的な教育と研究基盤の整備を今進めているところでございます。一方で、国際原子力人材育成イニシアティブ事業でございますが、令和8年度の終了が予定されているところでございまして、行政事業レビュー公開プロセスにおきまして原子力人材育成を、効果的に展開をしていくための今後の方針、さらには在り方について議論をしていきたいというふうに考えているところでございます。文科省といたしましても、行政事業レビューで頂く御指摘を踏まえつつ、関係府省と原子力関係機関とも密接に連携をさせていただきながら原子力の利用と、さらには安全を支える幅広い分野におきまして人材育成をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室