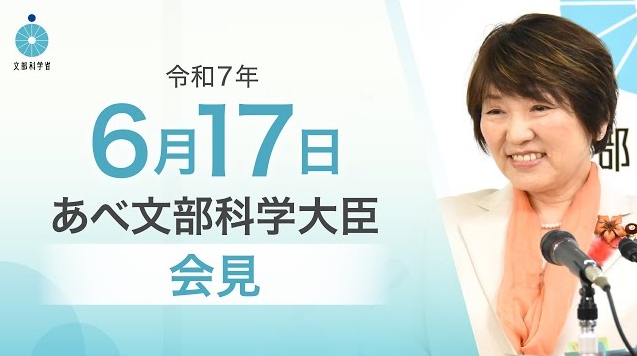- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月17日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月17日)
令和7年6月17日(火曜日)
教育
キーワード
三重県の愛農学園農業高等学校の視察、中学校の35人学級の導入にむけた検討状況、給食費の無償化に向けた検討のスケジュール、学用品の学校備品化に向けた検討、学校給食の地場産物の使用状況に関する調査、地方自治体の日本語教室に対する支援
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年6月17日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年6月17日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございまして、昨日6月16日でございますが、三重県にございます愛農学園農業高等学校の視察をしてまいりました。愛農学園農業高等学校におきましては、生徒さんたちが学校で作られた、自分たちで作った作物を使用した昼食をご一緒にいただいたところでございます。実習等におきましては、生徒さんたちが一生懸命取り組む様子を拝見いたしまして、農業教育の重要性を改めて感じました。今回の視察を通じて得たことを踏まえまして、引き続き農業高校をはじめとする専門高校の教育内容の充実にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
13日に閣議決定された骨太の方針についてお伺いします。2026年度からの中学35人学級導入に言及されていますが、3年間で何人くらいの定数改善を見込んでいるか、また財源としてどれくらいの予算が必要かを教えてください。また、財源については省の予算規模自体は変えずにメリハリをつけることで捻出をするのか、それとも省の予算自体を拡充する考えか教えてください。
大臣)
御指摘の中学校におけます35人学級に必要な定数改善数におきましては、今後、より精緻な試算を行う予定でございますが、規模感といたしましてはおおむね1.7万人程度の基礎定数の改善を見込んでいるところでございます。また、必要な予算額といたしましては400億円程度を見込んでいるところでございますが、少子化の影響なども踏まえつつ、必要な財源をしっかり確保してまいります。以上でございます。
記者)
給食無償化についてなのですけれども、先日、自公維のほうで大枠整理をまとめたのですけれども、こちらには給食無償化については盛り込まれませんでした。文科省は、昨年末にまとめた課題の整理で児童生徒間の交流などについて課題を指摘していましたが、こちらに対しては来年度の実現に向けてこれから議論をしていく必要があるかなと思います。文科省としては、今後どういうふうにこちらの詳細の制度設計について課題を整理していくなどのスケジュール感で考えているのか教えてください。
大臣)
先週13日に閣議決定いたしました骨太の方針2025でございますが、いわゆる給食無償化等について三党合意や昨年12月に公表いたしました「給食無償化に関する課題の整理」などに基づきまして具体化を行い、令和8年度予算の編成過程におきまして成案を経て実現することとされているところでございます。当該三党合意におきましては、「合意後も引き続き3党の枠組みの中で合意事項の実現に責任と誠意を持って取り組む」というふうにされているところでございまして、現在は3党における検討チームにおきまして教育無償化について順次議論されるものと私ども承知をしているところでございまして、現時点で文部科学省として詳細なスケジュール感をお示しできる状況では実はございません。いずれにいたしましても、今後十分な検討を行いまして安定的な財源の確保と併せまして、いわゆる給食の無償化が意義あるものとなるように取り組んでまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
骨太の方針に関してまた質問させていただきます。骨太の方針の中に今回、学用品の学校備品化の取組周知を推進するという文言が盛り込まれたかと思います。先日、文科省などに対して子どもの貧困対策推進議員連盟のワーキンググループが提言をまとめまして、そちらでも同様の指摘があったかと思うのですけれども、具体的に学用品と一言で言っても多種多様なものですから、どのようなものを学校の備品とすることを想定しているのか、または周知の方法ですとか時期、あるいは狙いなども合わせて教えていただきたいと思います。また、学校備品にするということになれば学校のほうでも予算を増やさなければならないということも考えられると思うのですけれども、この点について文科省としてはどのように考えていらっしゃるのかというところも合わせて教えてください。
大臣)
学用品の備品化のところでよろしいですか。各学校で使用する教材につきましてでございますが、その費用負担の在り方を含めまして、学校の設置者である自治体が適切に判断することになるところでございます。そうした中で、保護者負担の軽減の観点から自治体の工夫によりまして、例えば算数セット、さらには彫刻刀、裁縫セットなどを学校の共用の備品として整備する事例があるということを私ども承知しているところでございます。また、国におきまして各教科等におきましての使用する教材のうち学校に備えるべき品目、また数量の目安を示しまして、それを自治体が整備できるよう所要の地方財政措置を講じているところでございます。保護者負担が過重なものとならないように留意をしながら適切に教材の整備を図ること、これはまさに私どもも重要だというふうに考えているところでございまして、文部科学省といたしましてはこうした国における対応、また自治体の取組事例をしっかりと周知をさせていただきながら、各自治体の取組を促すべく速やかにその方法を検討して実施をしてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
学校給食の地産地消についてお聞きします。文科省は、2024年度の地場産食材の割合数を先週公表されました。しかし、日本農業新聞が調査を実施したところ、文科省調査の実態と大きく乖離していて実態を把握できないとして31道府県が独自に調査を実施しています。文科省の調査では、7施設のみの調査で19道府県は調査は全学校給食センターによる全数調査などです。自治体専門家からは、文科省の調査は自治体から乖離しているので改善すべきだと厳しい指摘が出ています。これについて大臣の御見解をお願いいたします。
大臣)
文部科学省におきましては、学校給食におけるいわゆる地場産物の活用状況でございますが、学校現場の調査に関わる負担等も配慮しながら全数調査ではなくて、各都道府県のいわゆる調理場を対象といたしました抽出調査を実施をいたしまして、その概況を把握しているところでございます。御指摘の各都道府県における独自の調査でございますが、詳細を私ども把握していないためにコメントは控えさせていただきますが、現在の学校現場におきます教職員の勤務状況等を踏まえれば、調査対象を広げることを踏まえ、調査方法を変更することについては慎重であるべきだというふうに考えているところでございます。
記者)
金額ベース、若干、数値のところ、物価高騰の中で地産地消の割合は自然と高まっている、高まるということで調査の改善の必要性はないという認識でよろしいでしょうか。
大臣)
詳細は事務方から説明をさせていただきます。後ほどだそうです。
記者)
地方自治体などが運営する外国人向けの対面日本語教室についてお尋ねします。文科省の調査では、この教室の教師に占める8割がボランティアであるとされていて、文科省としてもボランティア依存の解消を含めて自治体への支援を進めているところだと思いますが、支援を申請するためには3年から5年の事業計画を国に提出する必要があるため、これが負担となってなかなか申請に至らないとの指摘も出ているようです。こうした指摘や国の支援がなかなか広がっていないと考えられる状況について、大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
外国人向けの日本語教室でございますが、ボランティアによるものも含めまして広く意欲のある方に地域の日本語教育を支えていただくこと、非常に重要だというふうに考えているところでございます。このため、文部科学省といたしましては地域における日本語教育の充実に向けましてボランティアを含む日本語教育人材の養成・研修、また地方公共団体に対する日本語教室の開設などの支援に取り組んでいるところでございます。本支援事業の申請にあたりましては、中長期的な事業展開を見据えた上で段階的に支援を行うという観点でございまして、そこから見込みを含めた計画の提出を今お願いをしているところでございます。今後も、事業の趣旨等を丁寧に説明しながら、また必要な改善を図っていきながら地域の日本語教育の環境整備をしっかり進めてまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室