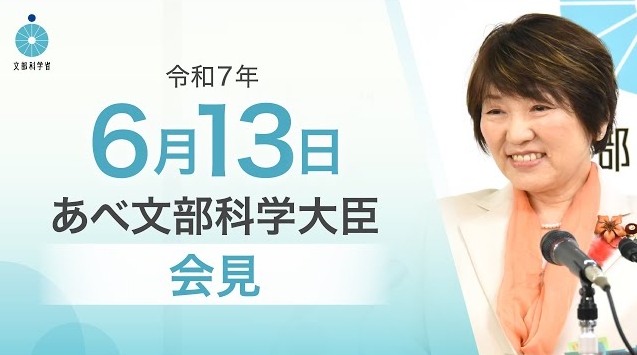- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月13日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年6月13日)
令和7年6月13日(金曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
給特法改正案の成立と今後の取組及びスケジュールについて、令和7年版科学技術・イノベーション白書の閣議決定、海外研究者等の招へいによる国際頭脳循環の取組強化、学習指導要領における性教育に関する規定について、3党による高校無償化に関する論点の大枠整理、学校給食の質の向上や地場産物の活用、大学ファンドの活用による既存事業への影響
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年6月13日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年6月13日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
おはようございます。
記者)
それでは、会見を始めます。大臣から何か発言をお願いします。
大臣)
冒頭、私から、3件ございます。今国会に提出をしておりました「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」、11日の参議院本会議において可決をされまして、成立をいたしました。法案の検討段階におきましては、中央教育審議会において一年以上にわたり御議論をいただきました。また、国会におきましては、重要広範議案といたしまして、衆参両院において合計約50時間のご審議を積み重ねていただきました。多くの方々のご協力・ご支援によりまして今回の成立に至ったものでございまして、すべての関係者の皆様に対し、心より御礼を申し上げます。改めて申し上げますと、この法律でございますが、学校教育の質の向上に向けまして、教師に優れた人材を確保するため、教育委員会に対する学校における働き方改革に関する計画の策定、また実施状況の公表の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の10%への引き上げなどの措置を一体的に講ずるものでございます。今後、国会審議などを通じて、いただきました御指摘を踏まえまして、速やかに文部科学大臣が定める働き方改革に関する「指針」の策定などを行うとともに、広く国民の皆様に対しまして、法律の趣旨また内容を注視いたしまして、教師を取り巻く環境整備を強力に進めてまいります。また、法律の成立を受けまして、11日に私から、国民の皆様に学校における働き方改革への御理解と御協力をお願いするメッセージを発表いたしました。メッセージの中にございますように、今後、教育委員会や学校関係の皆様はもちろんのこと、地方公共団体の首長の皆様、地域や保護者の皆様と力を合わせて取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。この場をお借りいたしまして、改めて皆様の御理解とご協力をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
2点目でございます。本日、「令和6年度科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告」、いわゆる令和7年版科学技術・イノベーション白書が閣議決定されました。今回の特集テーマでございますが、「白書とともに振り返る科学技術・イノベーション政策の歩み~科学技術基本法30年とこれからの科学技術イノベーション~」です。具体的には、戦後から現在までの科学技術・イノベーションの歩みを振り返った後、今後の政策の推進に向けたこの展望を紹介しているところでございます。また、本年度は、例年の広報に加えまして、「科学の力」をテーマといたしましたテレビアニメの「Dr.STONE」とタイアップをいたしましたポスターを作成いたしまして、全国の学校等に配布をいたします。本白書が、国民の皆様にとって科学技術・イノベーションのあり方や理解を深めるその一助になることを期待しているところでございます。
3件目でございます。「国際頭脳循環」の取り組み強化のための対応策をとりまとめましたので、ご報告をいたします。文部科学省といたしましては、国益に資する観点から、戦略分野を中心に、研究力が高く、受け入れ環境が整った大学等が優秀な研究者を呼び込めるよう、必要な支援を実施していくことが重要というふうに考えているところでございます。このような観点から、今般のこの対応策におきまして、国際卓越研究大学への支援等、既存の大学等への支援を着実に実施することに加えまして、新たに、大学が優秀な若手研究者等を秋の新学期も見据え、可能な限り早期に招へいすることを支援するため、緊急的に大学ファンドの運用益を活用することといたしました。また、国際頭脳循環の強化に向けましては、研究者への直接的な支援だけではなく、生活環境等の充実など、日本の魅力を高めるための取り組みも重要であるというふうに考えておりまして、引き続きさらなる検討を進めてまいりたいというふうに思います。私からは以上でございます。
記者)
先ほど冒頭でも大臣が発言された給特法の改正の関係で、今後、働き方改革に関する指針を速やかに策定されるとおっしゃってたんですけれども、速やかにっていうのはいつぐらいなのかっていうことと、具体的な内容はどんなことになりそうか、教えてください。
大臣)
大臣メッセージにも書かせていただきましたように、教育の要でございます教師の皆様、日々活き活きと子どもたちに向き合い、その意欲と専門性を最大限に発揮できるよう、改革を加速して進める必要があると私ども考えております。このため、文部科学省におきましては、「学校・教師が担う業務に関わる3分類」の徹底のほか、標準を大きく上回る授業時数の見直し、また、部活動の地域展開、小学校における教科担任制の拡充など教職員定数の改善など、様々な施策を総動員して取り組んでまいります。また、教育委員会におきましては、法律に基づく計画の策定などを速やかに進めていただく必要がありますので、今後、今回の法律に関連した国における制度改正、また予算の全体像を工程表として整理をしてお示しをしてまいります。指針の具体的な改定の時期について決まってるところはございませんけれども、各教育委員会におきまして、改定後の「指針」に即した働き方改革に関する計画の策定などの整備を円滑に進めることができるよう、秋頃までにはお示しをしたいというふうに考えております。内容に関しては、詳細は検討中でございますが、各教育委員会におきまして、教師の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例、業務の精選・適正化に関する観点、ストレスチェックや面接指導の実施を始めとする健康確保措置に関する観点、また「学校・教師が担う業務に関わる3分類」の位置付けなどを盛り込みまして、国としての取り組みの方向性を示してまいります。
記者)
性教育のことについてお聞きします。朝日新聞が全国の教育委員会に対して性教育についてのアンケートを実施しました。その中で、性教育を拡充する上で障壁と考えられるものについて尋ねたところ、学習指導要領上のいわゆるはどめ規定というのをあげた教育委員会が11に及びました。またあのはどめ規定に抵触しうる可能性がある性交や避妊方法、人工妊娠中絶について教えたいという学校があった場合の対応について尋ねたところ、積極的に認めたい、ある程度は認めたいと答えた教育委員会が半数程度に上りました。そもそもですけれども、はどめ規定というものはどうして導入されたのか、教えてください。また、こういったはどめ規定が性交や妊娠中絶について教えたいっていう学校に対しての事実上の障壁となっていることについてどのようにお考えなのか、はどめ規定は必要だという風にお考えなのか、お答えください。
大臣)
性教育に関してでございますが、中学校保健体育の学習指導要領におきまして「妊娠の経過は取り扱わない」としている規定は、平成10年の改正(注)時に設けられたものでございます。この改訂文により、それまで高等学校の内容でございました「受精・妊娠」を中学校で指導することになった際、性に関しては、中学生の段階では特に生徒間の発達の差異が大きく、また保護者の理解を得ながら実施する必要があることなどを踏まえ、個々の児童生徒の状況等に応じた個別指導により対応するということを趣旨としているところでございます。この「はどめ規定」のところで事実上の障壁になっているのではないかという御指摘でございますが、そのような御意見もあるということは私ども承知をしているところでございますが、御指摘の学習指導要領の規定におきましては、当該事項を教えてはならないという趣旨ではなく、個々の児童生徒の状況等に応じた個別指導により対応するという趣旨でございますことを指導に当たる関係者が共通に認識できるようにすることが重要であるというふうに考えているところでございます。また、指導にあたりましては、「性に関する指導」として、発達の段階を踏まえ、学校全体で共通の理解を図り、また保護者の理解を得ながら実施するようにすることにつきましても認識のこの共有を図る必要がございます。文部科学省としては、こうした趣旨等について関係者の理解が深まるよう、引き続き周知に努めてまいります。
(注)「改正」は、正しくは「改訂」です
記者)
大臣ご自身は、看護師としてのご知見ですとか人工妊娠中絶についての問題を取り上げた上で、国会でも性とリプロダクティブヘルスの教育が必要だという風に訴えられてきたと思います。そういう中で、やっぱりこういったはどめ規定によって事実上そういった教育がやっぱり難しくなっているという状況については、大臣個人としてはどのようにお考えなのか、ご見解いただけますか。
大臣)
この会見の場におきましては、文部科学大臣として立たせていただいておりますので、個人的な見解を申し上げることは控えさせていただきたいというふうに思いますが、性に関する指導に関しては、私を含め様々な意見をお持ちの方がいらっしゃることは事実でございまして、今後、中央教育審議会におきまして専門的かつ総合的な議論を経ながら、広く関係者のご理解をいただくことがまずは重要であるという風に考えています。
記者)
先日、高校無償化をめぐる3党協議が、大枠整備について正式合意しましたと。高校教育改革に関するブランドデザインを国が作成し、都道府県が実行計画を作った上で、交付金など新たな財政支援をすることが盛り込まれています。文科省としての見解を改めてお聞かせください。
大臣)
11日の3党の検討チームにおきまして、「三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理」が取りまとめられて、その中におきまして、国が示す「高校教育改革に関するグラウンドデザイン」を踏まえ、都道府県が作成する実行計画に基づく取組みをこの交付金等による支援する仕組みづくりが必要であることなどについて盛り込まれていると承知はしております。文科省といたし、文部科学省といたしましては、3党合意後の国会審議をはじめとする様々な議論を踏まえつつ、またこの大枠整理をしっかりと受け止めて、高校教育改革、また高校教育の質の向上につながるよう、引き続き検討に取り組んでまいりたいという風に思います。
記者)
冒頭、幹事社さんから給特法のことで、ちょっと追加でお尋ねしたいと思います。給特法に関しまして、時間外在校等について教員の間でも実効性を疑うような声も多く上がっておりますけれども文科省とされまして、その実効性を担保していく取り組みについては、具体的にはどのようにお考えでしょうか。
大臣)
今回の改正でございますが、処遇の改善のみならず、自治体・学校・地域・保護者が協力しながら、この働き方改革を推進する仕組みを構築しているほかに、令和11年度までに1か月あたりの平均の時間外在校等時間を月30時間程度まで削減することを目標にすることが附則に盛り込まれるなど、この給特法の働き方改革推進法としての性質を強化する「抜本的な改正」であると考えております。文科省としては、この法改正の趣旨を丁寧に説明しながら、教師を取り巻く環境整備をさらに進めてまいりたいと思いますし、また、学校における働き方改革でございますが、国、教育委員会、学校の各主体、それぞれの権限と責任に基づき取組みを進める必要があるものでございまして、文科省としても率先して責任を果たしてまいりたいというふうに思います。今回の法改正におきまして、全ての教育委員会が、文科大臣が定める「指針」に即しまして計画を策定する仕組みが設けられましたところでございまして、教育委員会や学校が取り組むべき働き方改革の方向性を文部科学省が「指針」で明確に示してまいります。また、時間外在校等の時間の削減のためでございますが、教職員定数の改善など指導・運営体制の充実も必要でございまして、文科省といたしましては、令和8年度から中学校35人学級を実施するため、この義務標準法の改正案の提出に向けましてしっかりと準備を進めてまいりたいというふうに思います。
記者)
学校給食無償化予算で、今まで通り給食の確保やこれまで以上の地場産品目の活用というのは可能でしょうか。また、給食の質を担保する制度設計を求める声もあります。給食の質・意義に向け、大臣の思いを聞かせてください。
大臣)
学校給食の質の確保でございますが、地場産物(注1)を活用することにおきましては(注2)、適切な栄養の摂取による健康の保持増進のほか、また、地域の食文化・産業への理解、生産者への感謝の気持ちを育んでいくなど、子供たちの食に関する理解を深めるために大変有効であると私ども考えております。いわゆる給食無償化につきましては、本年2月の3党合意におきまして、地方の実情等を踏まえ実現することとされておりまして、地産地消の推進を含む給食の質の向上など様々な論点が示されているところでございまして、今後、安定的な財源の確保と併せまして十分な検討を行いまして、完全、給食の(注3)この無償化が意義あるものとなりますように取り組んでまいりたいというふうに思います。以上です。
(注1)「地場産物」は、正しくは「地場産物等」です
(注2)「ことにおきましては」は、正しくは「ことは」です。
(注3)「完全、給食の」は、正しくは「給食の」です。
記者)
国際頭脳循環の件で伺います。大学ファンドの運用益を積極的に活用する方針を示されましたが、大学ファンドを活用した国際卓越大や家庭支援など既存事業への影響はないか、大臣の認識をお聞かせください。
大臣)
冒頭でもお伝えいたしましたが、大学ファンドの緊急的な活用による支援等につきましては、現在詳細を検討しておりまして、追って公表を予定しているところでございます。大学ファンドの支援対象でございます国際卓越研究大学への支援、また博士課程の学生への支援に影響を及ぼさないように、この大学ファンドの財務状況等を勘案させていただきながら、支援策の検討をしっかり行ってまいりたいという風に思います。
記者)
科学技術・イノベーション白書の関連でお尋ねをさせてください。内容にですね、掲げられていたような研究人材の支援であるとかですね、若手支援の目的が達成されたとは言い難いという風に言及があるようなんですけれども、それについて、今後の科技政策の中でのその人材の支援についてですね、大臣のご認識と、あと期待について教えていただければと思います。
大臣)
科学技術・イノベーション政策におきましては、時代の変化、要請を踏まえまして様々な施策を講じてきたものの、基本法制定時に課題として認識されておりました基礎研究力の低下とこの若手研究者の雇用環境、さらには研究支援、人材不足は実は未解決の状況でございます。この十分な研究開発投資の確保に努めていくということに加えまして、国際卓越研究大学、またJ-PEAKS採択大学などを中心にいたしまして、この大学マネジメント改革、さらには研究環境の整備、若手人材や高度専門人材育成にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室