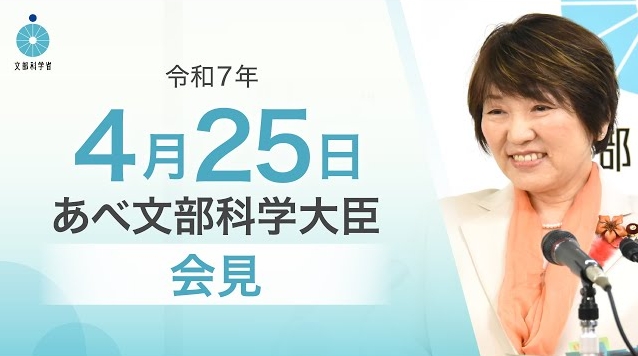- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月25日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月25日)
令和7年4月25日(金曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
H-ⅡAロケット50号機の打上げ日決定と次期基幹ロケットへの期待、2025年大船渡市山林火災の総合調査研究への助成、福島第一原子力発電所2号機における2回目の燃料デブリの試験的取り出し成功、デジタル技術を活用した公立高校入試の併願制の検討、地方大学振興に関する有識者会議における大学・大学院学生である特別委員への期待、日本国籍の子供がインターナショナルスクールに通う実態
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年4月25日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年4月25日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは3件でございます。本日、JAXAから公表されますけれども、H-ⅡAロケット50号機におきまして(注)、「温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)が6月24日に打上げ予定でございます。GOSAT-GWでございますが、JAXAと環境省が共同で開発した衛星でございまして、温室効果ガス濃度、また海面水温等の高度な測定を可能とするものでございます。気候変動、また水産などの幅広い分野におきまして貢献することを期待しているところでございます。H-ⅡAロケットは、今回の50号機で最終号機を迎えます。2001年から現在まで49機中48機の打上げに成功しておりまして、国内外・官民の多様な衛星を打ち上げ、国民の皆様に親しまれるとともに、地球上の様々な課題の解決、より豊かな経済・社会活動の実現に着実に貢献したものと考えています。また、最終号機が打ち上がり、GOSAT-GWが様々な分野で貢献できるよう、引き続き、JAXAにおかれましては着実に準備作業を進めて頂きたいと考えております。
2件目でございます。本年の2月に岩手県大船渡市で発生いたしました大規模な山林火災に関しまして、今後の防災対策に生かすため、火災の自然要因の解明等に向けた調査研究を実施いたします。このため、東京理科大学火災科学研究所の桑名一徳教授を研究代表者とする研究提案に科学研究費の助成事業、科研費でございますが、特別研究促進費によりまして助成することといたしました。本研究の成果におきましては、国の機関また地方自治体等に提供することとしておりまして、激甚化が懸念される火災への対応、この対応力の向上に活用されることが期待されるところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き、我が国の防災機能の強化に向けまして、基礎研究の推進及び研究成果の活用を図ってまいりたいというふうに思います。
3件目でございます。23日、東京電力が福島第一原子力発電所2号機におけます2回目の燃料デブリの試験的取り出しを完了したとの発表がございました。ご尽力いただいている関係者の皆様方に本当に心から敬意を表したいというふうに思います。今回、取り出された燃料デブリも経済産業省の補助事業におきまして、JAEAが分析を実施する予定と聞いています。JAEAが燃料デブリの分析を通じまして、今後の燃料デブリ取り出しの方策検討のために貢献することによりまして、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組が進展することを期待しているところでございます。以上でございます。
(注)「におきまして」は、正しくは「で」です
記者)
公立高校のデジタル併願制について伺います。現在、多くの都道府県の公立高受験で採用されている単願制を見直し、デジタル併願制の導入を検討するよう石破首相から指示があったかと思いますが、文部科学省の大臣としてはどうするのか、スケジュールも含め、今後の対応と実施にあたっての課題について教えてください。
大臣)
22日に開催されました「デジタル行財政改革会議」では、公立高校入試におきまして一人の生徒が一つの公立高校に出願をするいわゆる「単願制」、この課題とこの解消策の提案を踏まえまして石破総理より、平デジタル担当大臣とともに「生徒の希望する進学につながることのメリット、また現場の課題を丁寧に考慮し、希望する自治体での事例の創出の具体化を図」るよう御指示がございました。公立高校の入学者選抜の実施方法等は、実施者であるところの各都道府県教育委員会等が決定するものでございますが、デジタル技術を活用した併願制につきましてもメリットが考えられる一方で、生徒の多様な個性と能力が十分に評価されるか、また学校の特色・魅力が損なわれないか、地域人材を育成する専門高校に影響がないかなどの課題も想定されるところでございます。文部科学省としては、メリットや課題について整理をしつつ、高校教育の質向上につながりますよう、自治体・高校関係者の意見もよくお伺いして、また関係省庁とも十分に連携の上、丁寧に検討してまいります。以上でございます。
記者)
21日に開催された急激な少子化時代の地方大学振興に関する有識者会議では、群馬、山梨、愛媛県内の大学、大学院生6人が特別委員として参加しました。文科省の設置する有識者会議で学生が委員を務めることは珍しいかと思いますが、学生の委員に対してどのような議論を期待していますでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
大臣)
本有識者会議におきましては、本年2月の中教審の答申の提言を踏まえまして、地域の高等教育へのアクセス確保、また地方創生など、地域の大学振興のあり方について総合的に議論するものでございまして、学生を含め 産 官 学 金 労 言 から幅広く参画いただくとともに、地域大学振興に関連する関係省庁にもオブザーバー参加をいただいているところでございます。特に、学生の委員に対しましては、地域の高等教育機関がどのような場であるべきなのか、また大学、地方公共団体、産業界等に期待することなどを率直にお話しいただきたいと考えているところでございます。文部科学省といたしましても、この有識者会議における議論を踏まえながら、関係省庁とも連携を図りながら各地域におけます大学振興の取組に関する検討を進めてまいりたいというふうに思っています。以上です。
記者)
インターナショナルスクールに通う子供についてお尋ねします。東京23区でこうした施設に通う日本国籍の子供が少なくとも4,800人余りいることがNHKの調査で分かりました。インターナショナルスクールは、多くの場合は義務教育の学校認められていませんが、こうした実態をどのようにお考えでしょうか。また、こうした施設がどの程度広がっているのか分かっていませんけれども、文科省として実態調査を行うのか、方針についてお聞かせください。
大臣)
義務教育でございますが、憲法に規定する教育を受ける権利を保障するものでございまして、学校教育法におきましては保護者に子女を小学校、中学校等に就学させる義務を課しているところでございます。また、市町村教育委員会は保護者が就学義務を怠っていると認められるときは、保護者に対して児童生徒の出席を督促しなければいけないというふうにされているところでございます。一方で、例えば帰国児童生徒の日本語能力がいわゆる養われるまでの一定の期間、適切な機関で日本語の教育を受ける等の措置が講じられている場合など、市町村教育委員会から就学義務の猶予または免除を受けてインターナショナルスクールに通学している場合もございまして、個別の事情に応じた判断が子供の利益につながると考えているところでございます。こうした制度を踏まえまして、各市町村教育委員会において適切に対応していくべきものと考えておりまして、文部科学省として現時点で調査を行うことは考えていないところでございます。以上です。
記者)
冒頭でありましたH-ⅡA最終50号機の打上げに関して伺います。H-ⅡAはご存じのとおり、世界トップレベルの打上成功率を誇りまして20年以上にわたって日本の基幹ロケットとして活躍してきました。今現在、次のさらなる新しい基幹ロケットの検討も始まっていますけれども、その上でこの数十年のH-ⅡAロケットが日本の宇宙開発利用に与えてきた影響ですとか貢献、あと今後この経験をどのように繋げていくか、所感を伺えますでしょうか。
大臣)
H-ⅡAロケットにおきましては、これまで災害時の緊急観測等で貢献する「ALOS-2」、また気象衛星「ひまわり9号」、小惑星のサンプルリターンを行う「はやぶさ2」など多様な衛星を打ち上げているところでございまして、これらの活躍により地球規模の課題の解決、またより豊かな経済・社会活動の実現などに貢献してきたというふうに考えているところでございます。また、H-ⅡAロケットで培われました知見でございますが、これはH3ロケットの開発・運用にも着実に引き継がれているところでございまして、今後、次期の基幹ロケットに向けた検討におきましても重要な知見として活用されるものと私ども承知しているところでございます。文部科学省としては、我が国の自立性確保と、また国際競争力強化のための重要な基幹ロケットの開発・運用を引き続き着実に進めてまいりたいというふうに思っております。
記者)
冒頭でもデジタル併願制の話が出ていましたけれども、大臣御自身はデジタル併願制についてどのようにお考えか、お聞かせください。
大臣)
先ほども申し上げましたように、公立高校の入学者選抜のデジタル化と単願制の二つの観点が私はあるというふうに考えておりまして、個人的な見解でございますが、デジタル化につきましては入学志願者の利便性の向上、また実施者、教職員の負担軽減に資する観点から、入学者選抜の出願方法等のデジタル化を積極的に進めていくことが必要というふうに考えています。その上で、いわゆる単願制につきましてもこれまでも受験の機会の複数化、選抜方法の多様化の配慮を各教育委員会に求めてきたところでございますが、地域の実情等に応じて様々なメリットや課題があるというふうに考えているところでございます。このため、今回の総理からの御指示も受けまして希望する自治体での事例創出に向けまして、デジタル庁と連携しながら各自治体、また高校関係者の方々とも意思疎通を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室