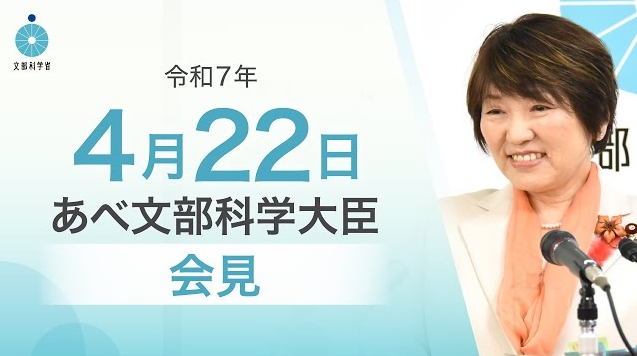- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月22日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月22日)
令和7年4月22日(火曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
川崎市殿町にあるナノ医療イノベーション施設等への視察、大田区にある「みらい学園中等部(学びの多様化学校)」の視察、学校図書館の活用と公共図書館との連携、PTAの在り方について、大西宇宙飛行士の日本人3人目となるISS船長の就任、米などの物価高騰による学校給食の負担増への対応
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年4月22日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年4月22日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございます。昨日21日でございますが、神奈川県川崎市の殿町にあります国際戦略拠点キングスカイフロントと東京都大田区にございます学びの多様化学校「大田区立御園中学校文教室 みらい学園中等部」を視察してまいりました。キングスカイフロントにおきましては、ナノ医療イノベーション施設と実中研を訪問させていただきました。ライフサイエンス分野における先端的なオープンイノベーション拠点の取組、医療・創薬の基盤に関わります(注)最先端の研究につきましてお話を伺いまして、持続的に産学官が連携していくための仕組みをつくることがまさに重要であると改めて認識をいたしました。引き続き、イノベーション創出のための環境整備を進めてまいります。また、学びの多様化学校でございます「みらい学園中等部」では、生徒の皆さん一人一人が笑顔を交えながら教室で生き生きと学んでいる姿を実際に拝見することができまして、私といたしましても学びの多様化学校の意義、さらには重要性を改めて認識することができました。引き続き不登校児童生徒の多様な学びの場の確保に向けた取組を進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
(注)「基盤に関わります」は、正しくは「基盤である実験動物に係る」です
記者:読売新聞)
学校図書館の運営充実についてお伺いします。公共図書館の数が年々増加している一方で、拠点の数が減少したり子供たちの付属率が高まったりと課題も見受けられます。読書環境の充実化をめぐっては、昨年より文科省で有識者会議が設置され、今まさに議論されています。学校図書館の活用、学校図書館と公共図書館の連携が重要かと思いますが、大臣のお考えや読書環境充実に向けた今後の対策があればお聞かせください。
大臣)
文部科学省におきましては、読書環境の充実に向けまして第5次「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画」、また第6次の「学校図書館図書整備等5か年計画」を踏まえまして、読書活動の推進に取り組んでおります。今年からは、新たに、図書館・学校図書館と、書店を含む地域の様々な関係機関の連携協働による読書活動の促進を通じました「読書のまちづくり」を推進する事業を実施する予定でございます。また、昨年12月より「図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議」を開催いたしまして、デジタル社会に対応した図書館・学校図書館の運営充実の在り方、また多様な人々のための読書環境の整備などについて検討を進めているところでございます。文部科学省といたしましても、この御指摘のございました学校図書館の活用、また学校図書館と地域の公共図書館の連携は重要な課題と認識しているところでございまして、今後、この有識者会議の中で今後の推進方策のあり方について議論を深めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者:日本経済新聞)
公立小中学校PTAの全国組織日本PTA全国協議会の会員数が2024年度の1年間で100万人以上減少していると一部の報道がありました。法人運営の不祥事などの原因ともされていますが、改めてPTAのあり方について大臣の見解を伺えますでしょうか。
大臣)
公益社団法人日本PTA全国協議会におきましては、ご指摘のように様々な要因によりまして会員数が減少しているところでございます。信頼回復に向けた運営健全化の取組を今進めているというふうに承知をしているところでございまして、PTA(注)、学校・家庭・地域、この連携・協働を推進する上におきまして重要な役割を果たしている社会教育関係団体でございます。そうした中で、文部科学省といたしましては、公益社団法人日本PTA全国協議会がPTA関係者の理解をしっかりと得ながら、ガバナンス構築に向けて引き続き努力をされながら、各地域においてPTA本来の役割が活発に行われることを期待しているところでございます。以上でございます。
(注)「PTA」は、正しくは「PTAは」です
記者:共同通信)
国際宇宙ステーションに長期滞在中のJAXAの大西宇宙飛行士が昨日、ISSのコマンダーに着任しました。改めて船長としての大西飛行士、あるいは日本がこれからISSで果たしていく役割について大臣の期待をお聞かせください。
大臣)
日本時間の4月19日未明頃でございますが、大西卓哉宇宙飛行士がロシアのアレクセイ・オブチニン宇宙飛行士から国際宇宙ステーションの船長職を引き継ぎまして、日本人として3人目となる船長に就任したと承知しているところでございます。この度の船長の就任におきましては、日本のこれまでのISS計画への貢献等に加えまして、また大西宇宙飛行士の能力、さらには実績が高く評価されたものと認識をしているところでございます。大西宇宙飛行士がISSの船長として他の搭乗員をまとめ、様々なミッションを遂行していくことで世界に期待される我が国の地球低軌道の活動の充実、さらには発展に貢献していただくことを心から期待申し上げるところでございます。以上です。
記者:教育新聞)
先ごろ総務省が発表した全国消費者物価指数で、米類が前年同月比90%以上上昇し、過去最高の上昇率となっています。これに加え野菜など生鮮食品の高騰も目立つ状況です。こうした中で、学校給食について様々な点から影響が出ることが懸念されています。米の高騰や不足によって米飯給食の数を減らしたり給食費の値上げに踏み切った、そういった自治体がどれぐらいあるか文科省としてお調べになっているのかという点と、もう一つ、食材費高騰のコストを抑えるために学校給食で使用する食材を絞ることで食事の質が低下するのではないかという懸念がされています。物価高騰に伴う給食費値上げなどの負担増を防いで給食の質も担保するためにどういった対策が必要だとお考えなのか、合わせて伺えればと思います。
大臣)
文部科学省におきましては、昨今の物価高騰を踏まえまして、いくつかの自治体に対して対応状況の聞き取りなどを行っているところでございまして、御指摘のように米飯給食の回数を減らすなど、予定していた献立また食材の変更を行っていると回答した自治体もあったところでございます。また、物価高騰による給食費の負担増を防ぐために、まずは主食の米につきましては年間使用料を契約しているところでございまして、値上げをある程度見越した価格で調達している、また保護者負担額との差額の部分でございますが、これを市で負担しているなどの方法で対応している自治体もあるというふうに聞いているところでございまして、私ども文部科学省といたしましても、こうした状況を踏まえていきながら、学校給食の質の確保、ここが本当に重要でございまして、また保護者の負担の軽減でございますが、この両立を図るために、昨年12月に教育委員会に対しまして、重点支援地方交付金を活用した形で事業者負担の軽減と及び保護者支援について通知をさせていただいたところでございます。引き続き、この活用を促してまいりたいというふうに思っているところでございまして、また詳細に関しては担当課にお尋ねいただければというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室