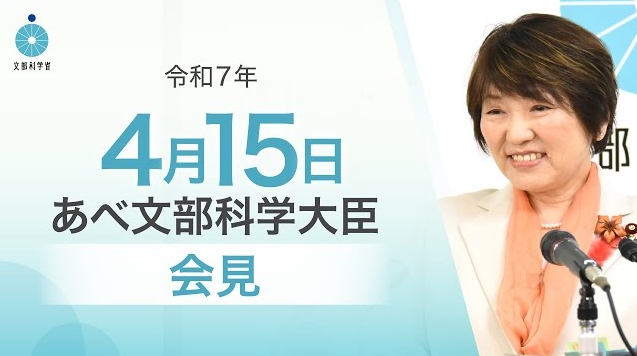- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月15日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月15日)
令和7年4月15日(火曜日)
教育、科学技術・学術、スポーツ、その他
キーワード
大阪・関西万博開会式の出席、大阪大学量子情報・量子生命研究センター視察,令和7年度全国学力・学習状況調査の実施,部活動等における落雷事故防止対策,特別支援学級等の教師に支給される調整額の見直し,修学旅行等で大阪・関西万博を訪れる際の安全確保,特異な才能を持つ児童生徒への特別課程の検討,優秀な博士後期学生に支援する「SPRING」の在り方,本日の石垣市議会との面会
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年4月15日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年4月15日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは2件でございます。4月12日土曜日でございますが、大阪大学量子情報・量子生命研究センターを視察させていただきまして、その後、大阪・関西万博の開会式に出席をいたしました。大阪大学におきましては、量子コンピューターが実際に稼働している様子を見学させていただきながら、この研究成果がベンチャー設立につながった点、また人材育成について意見交換をさせていただきました。大阪・関西万博におきましては、開会式に出席をさせていただいた他、見どころの一つでございます大屋根リングの見学を行いまして、実際にその上を歩かせていただきました。いよいよ開幕を迎えました大阪・関西万博でございます。科学技術分野の最先端の技術や成果、また我が国の文化芸術の魅力、先端技術の活用などスポーツの新たな可能性等を内外に発信できる貴重な機会でございまして、引き続き関係省庁とも協力をさせていただきながら、万博の成功に向けたさまざまな取組をしっかりと進めてまいります。
2件目でございます。毎年、小学校6年生、中学校3年生を対象に実施しております「令和7年度全国学力・学習状況調査」が、昨日から始まりました。本調査の実施に御協力くださっている全国の学校・教育委員会等の皆様に感謝を申し上げる次第でございます。今回の調査におきましては、教科調査に初めてCBTを導入いたしました。今年度は中学校理科をオンライン方式で、17日までの4日間で実施をいたします。その他教科は従来どおり紙の冊子を用いて17日に実施をするところでございます。また、CBTの導入によりまして、動画の利用など多様な出題が可能になりました。また、CBTで実施する調査におきましては、18日以降は、自宅など学校外での実施も可能といたしまして、長期欠席の生徒等も調査に参加できるようになりました。また、我が国の調査がCBTも含めて円滑かつ確実に実施されるよう、対応に万全を期してまいります。以上でございます。
記者:読売新聞)
奈良市の帝塚山学園で10日、サッカー部の練習中に落雷で6人が緊急搬送される事故がありました。文科省は11日に天候の急変時には直ちに活動を中止するよう各教育委員会などに通知を出しています。昨年の4月には宮崎市でも高校サッカー部の試合中に18人が搬送される落雷事故が発生し、同様の通知を出しています。通知から1年で似たような事故が再び起こってしまったわけですが、文科省として今後の対策や対応について考えていることがあれば教えてください。
大臣)
部活動の現場でこのような事故が発生しましたことは大変痛ましく、事故に遭った生徒さんの1日も早い回復を願っているところでございます。落雷事故を防ぐためには、天候の急変など雷の兆候があるときは、ためらうことなく活動中止等の措置を講ずること、また子供にも、危険を感じた際には、大人に申し出ることについて指導をすることなどが重要でございまして、文部科学省におきましては、11日に、改めて、全国の教育委員会等に事故防止の徹底を依頼する事務連絡を発出したところであります。新年度となりまして、指導体制が変わった学校もあると思いますので、各学校においては、こうした留意点も踏まえながら今一度、事故防止の徹底をお願いしたいというふうに思います。以上です。
記者:毎日新聞)
二つのテーマに渡ってしまって恐縮なのですが、お伺いさせてください。一つ目が教員の処遇に関して、特別支援に従事されている先生方の調整額が段階的に引き下げられることになっていると思いますけれども、これに対して批判の声が上がっているようです。受け止めと引き下げの目的及び当初は処遇改善というところを積極的にアピールされていたと思うのですけれども、引き下げに関して説明がなかったという指摘に対するお考えを教えてください。
もう一つが、万博に関して大臣も出席されたということでしたけれども、一部の中学校で修学旅行の行き先を万博から変更するということが発生しているようです。こうした状況の受け止めと会場の安全、安心の確保について運営元の博覧会協会だとか地元の自治体だとかに求めたいということがあれば教えてください。
大臣)
今般のいわゆる特別支援の件でございますが、教師の処遇改善にあたりましては教職調整額の改善を図るだけではなく、教師の職責、また業務負担に応じた給与とする観点から給与全体に関しての検討を行いました。御指摘の給料の調整額に関してでございますが、特別支援学校や特別支援学級に関わる教師に支給されるものでございますが、近年、通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加するなど、全ての教師が特別支教育に関わることが必要となっておりまして、こうした背景を踏まえて中教審答申におきましても見直しの必要性が提言されたところでございます。このため、教師の給与全体を検討する中において、教職調整額の10%への引上げ等を踏まえつつ、引き続き、他の教師と比較し一定の特殊性を有していることから廃止ではなく、半減とするものとしたものでございまして、財源捻出を目的としたものではございません。なお、この見直しに関しましては一度に行うのではなくて、令和8年度から2年かけて行うこととしておりまして、教職調整額の引上げと合わせますと、毎年度、教師個人の給与水準は上がることとなります。更に、御指摘の給与(注1)の調整額の見直しに関しましては、令和8年度以降の予算に係るものでございますが、都道府県教育委員会などへは説明を行ってきているところでございまして、今後も、丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに思います。
2点目の御質問でございますが、一部の中学校が修学旅行の行き先を大阪・関西万博から変えた旨の報道は承知をしているところでございます。大阪・関西万博におきましては、次世代(注2)を担う子供たちにとって学びの多い場であるというふうに私ども考えておりまして、その上で文部科学省といたしましては、修学旅行等における事故防止、また安全確保の徹底は来場にあたっての不可欠の前提と考えておりますが、あわせまして、都道府県教育委員会等を通じまして、必要な情報を提供していくこともまさに重要だというふうに考えているところでございます。特に4月6日に基準値を超えるメタンガスが検知された事案を受けた対策も含めまして、会期中の安全対策は博覧会協会において講じていると承知をしているところでございますが、文部科学省といたしまして多くの子供たちが安心して万博に来場できるよう、引き続き安全確保の徹底について関係省庁を通じまして要請するとともに、関係省庁と連携しながら都道府県教育委員会等を通じて必要な情報を提供するなど、対応に努めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
(注1)「給与」は、正しくは「給料」です
(注2)「次世代」は、正しくは「次代」です
記者:教育新聞)
特異な才能のある児童生徒に関してお伺いします。4月10日に開かれた中教審の特別部会で、特異な才能のある児童生徒への特別の教育課程を新設するという提案がなされましたが、「特異な才能」とは具体的にどのようなものなのか、そうした児童生徒が国内にどれくらいいるのでしょうか。今後、実態調査を行う予定がありましたら教えてください。また、特別部会では必要な学校に教育課程の特例を設けるともしていました。例えば、海外のように特例校などとして特異な才能のある児童生徒のための学校を作るといった、そういったお考えはありますでしょうか。こちらも合わせてお聞かせください。
大臣)
1点目でございますが、先日の部会におきまして、小学生で大学生レベルの学習・研究を行うなど、特定の分野で突出した才能を有していたり、才能がゆえに学校生活上の困難を抱えていたりする子供を取り上げて、そうした子どもたちを包摂する特別の教育課程のあり方についての検討が行われました。こうした児童生徒については、才能を示す領域や程度が多様であることから、一律の定義を設けて人数等を網羅的に調査することは難しいところでございますが、今後、実態把握の適否も踏まえて(注1)特別の教育課程の仕組み、また関連施策について中央教育審議会で、引き続き検討してまいりたいと思います。
お尋ねの2点目でございますが、先日の部会における事務局からの提案におきましては、困難の解消を図りつつ、特異な才能を伸ばすためには、特異等(注2)に応じた高度な内容に関わる部分以外は、基本的に通常の学級の中で学習することを想定しています。このため、特異な才能のある児童生徒のための特別の学校を作ることは想定しておりませんが、今回提案した特別の教育課程の枠組みが、学ぶ権利を保障し、多様な才能を開花させることができる適切な制度になりますよう、引き続き中央教育審議会で検討を行ってまいります。以上です。
(注1)「踏まえて」は、正しくは「含め」です
(注2)「特異等」は、正しくは「特性等」です
記者:朝日新聞)
博士課程で学ぶ研究者に経済支援を行ういわゆるSPRING制度につきまして、2024年度の実績で受給生の約4割が留学生であり、また一部の国籍の方が突出していることについて3月、疑問視する立場での国会での議論がありました。優れた研究人材を招いて日本で育てる観点からも、多様な国の留学生を受け入れることが重要かと思いますけれども、文部科学省の答弁では日本人学生の支援強化など、制度改正を近く審議会で議論を始めるということでした。国籍や地域で支援内容や基準に差を設けるかなど、制度のあり方について現時点で大臣の考えを聞かせてください。
大臣)
SPRINGでございますが、我が国の科学技術・イノベーションの将来を担う、博士後期課程学生の経済的支援と、及びキャリアパス支援を、一体として行う大学を対象とする事業でございます。我が国の研究力強化に向けましては、優秀な日本人博士後期課程学生に対する支援の充実を基本とした上で多様な国、また地域の優秀な留学生の受入れを行っていくことも重要と今は考えているところでございます。文部科学省としては、優秀な日本人学生に対する支援強化、また留学生に対する支援の在り方など、SPRINGにおける博士後期課程学生への支援の在り方について、本年の夏頃までには中間取りまとめを行うべく今後、審議会で検討を進めてまいります。以上でございます。
記者:NHK)
高校授業料の無償化についてお尋ねします。今日午後に面会を予定されている石垣市議会は先月、外国人学校の授業料の支援に日本人の税金が使われることは税負担の本来の目的から逸脱しているなどとして外国人学校やインターナショナルスクールに通う外国籍の子どもへの支援のあり方を見直すよう求める意見書を可決しています。このことについての大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
沖縄県の石垣市議会におきまして、お尋ねのような意見書が可決されたことは承知をしておりまして、本日夕刻、私のところにも意見書をお持ちいただく予定となっているところでございます。ただ、意見書でございますのでまずは御意見をよく伺ってみたいと考えておりまして、この場でのコメントは控えたいと思います。その上で申し上げますと、いわゆる現行の就学支援金制度におきましては高校教育の効果は広く社会に還元されるものでございまして、教育費については社会全体で負担するという考え方のもと、我が国に適法に在住をし、また社会を構成する者については国籍を問わず対象とすることとしているところでございまして、まず今後につきましては今般の3党合意におきまして支援対象者の範囲の考え方など様々な論点について十分な検討を行うこととしているところでございまして、引き続きその枠組みの中で合意内容の実現に取り組まれるものと認識しておりますので、文部科学省としてもその状況を踏まえつつ対応を検討していくことになりますが、現時点におきましては個別の論点について何らか申し上げる段階にはないものというふうに考えております。以上です。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室