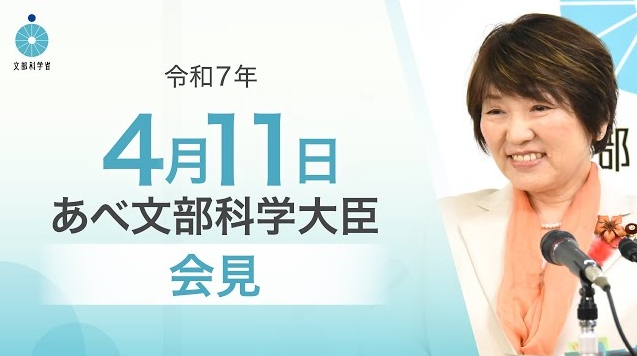- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月11日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月11日)
令和7年4月11日(金曜日)
教育、科学技術・学術、スポーツ、その他
キーワード
高校生等の修学支援に関するリーフレット公表,ハイパフォーマンススポーツセンター視察,給特法改正案の審議について,文科省職員も任命された地方創生支援官への期待,広島市長が職員研修で教育勅語を引用したことへの見解,大阪・関西万博の教育的意義と懸念への対応,米国をはじめ海外の優秀な研究者の獲得競争、研究者の処遇
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年4月11日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年4月11日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
まず、ここに公式キャラクターを置かせて頂いているところでございます。明後日でございますが、4月13日日曜日から「2025年 日本国際博覧会」、通称「大阪・関西万博」が開幕をいたします。私も開会式に参加する方向で今検討させていただいているところでございますが、万博が「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマのもとで成功裏に進むことを祈念しますとともに、文部科学省といたしましても引き続き関係省庁とも協力しながら万博の成功に向けまして様々な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
私から冒頭で2件でございますが、本日、高校生等のための修学支援に関します新しいリーフレットを公表いたします。本リーフレットは、いわゆる「高校無償化」につきまして、3党合意に基づいて、令和7年度から実施される先行措置に関しまして、都道府県・学校・保護者等に分かりやすく周知をすることを目的としているものでございます。具体的には、高等学校等就学支援金の所得制限の一部を事実上撤廃をし、また所得制限を受けている年収910万円以上の世帯の高校生等に対して、「高校生等臨時支援金」として、年間11万8,800円を支援する予定でございます。また、授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金も拡充予定でございます。対象となる生徒に漏れなく支援が行き渡るよう、SNSなどを活用いたしまして積極的な情報発信に取り組んでまいります。皆様におかれましても、広報への協力をお願いできましたら幸いでございます。
2件目でございます。先日9日でございますが、我が国のトップアスリートの活動拠点でございますハイパフォーマンス スポーツセンターを訪問させていただきまして、各競技の練習場、実際に選手の動きのデータを取得・分析している様子を、視察をさせていただきました。視察の中におきまして、アスリートの方々から競技生活の中においての課題として、遠征費、また競技用具の費用負担についてのお話を伺いました。また、ハイパフォーマンス スポーツセンターのスタッフと保有するデータの活用方法等について意見交換を行いました。アスリートが活躍する姿は国民に勇気、また感動を与えるものでございます。今回の視察も踏まえまして、引き続き、競技団体と連携を図りながら競技力向上に必要な予算の確保に努めながら、我が国における国際競技力の一層の向上に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。私からは以上でございます。
記者)
昨日、給特法の審議がありましたけれども、野党のほうから法案修正を求める声もあったと思うのですが、この点について大臣はどのようにお考えか教えてください。
大臣)
現在、国会でご審議いただいています「給特法等の改正案」につきましては、現時点で他の各党から修正案が提出されているわけではございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。いずれにいたしましても、改正案の内容、必要性については今後の国会審議において丁寧に説明をさせていただきながら、成立に向けて御理解をいただけるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。
記者)
地方創生についてお伺いいたします。石破総理は9日、地方創生2.0を進めるために中央省庁の職員180人に地方創生支援官を任命しました。その中には文部科学省の職員も含まれていますが、大臣としてこの地方創生支援官に期待することがあれば教えてください。
大臣)
文部科学省からも、実は係長級から課長級から計14名の職員が任命されたところでございまして、顔が見え、また熱が伝わる実効性のある支援に取り組んでぜひ課題を抱えている地方自治体に寄り添った伴走支援に取り組んでもらいたいというふうに考えているところでございます。
記者)
広島市の松井一実市長が2025年度の新規採用職員研修で講話に用いた資料の中で戦前の教育勅語の抜粋を掲載していたとのことで、地元の市民団体から抗議の声も出ているようですが大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
お尋ねの件に関しましては、報道により承知をしているところでございますが、広島市の職員研修に関することでございまして、文部科学大臣としてのコメントをする立場にございません。その上で申し上げれば、教育勅語、日本国憲法及びまた教育基本法の制定等を持って法制上の効力を喪失しているものというふうに承知しているところでございます。以上です。
記者)
大阪・関西万博についてお尋ねします。万博をめぐっては、予行演習で滞留が発生し、雑踏事故のリスクが指摘されています。また昨年3月、会場設備の工事中にメタンガスが原因の爆発事故が起きたりですとか、4月3日にも基準値を超えるメタンガスが検知されている状況にあるのですけれども、こうした懸念から保護者や教員から校外学習に反対する署名も起きているところです。文科省、修学旅行での大阪・関西万博の活用について各都道府県の教育委員会に通知を行ってきていらっしゃるかと思うのですけれども、大臣がお考えになる大阪・関西万博の教育的意義、こちらについてお伺いできればというのと、合わせてこういった指摘されている懸念点について、安全性の基準についてはどう思われるかについてもお聞かせいただければと思います。
大臣)
大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもとで、子供たちが「いのち」、またSDGs達成への取組、また世界の多様な文化・価値観、次世代の技術、社会システム等の未来社会などをそれぞれ体感できる、次世代(注)を担う子供たちにとって学びの多い場であるというふうに考えているところでございます。その上で、文部科学省といたしましては修学旅行等における事故防止、安全確保の徹底は来場にあたっての不可欠の前提でございまして、そのように考えている中で経済産業省からは今回のメタンガスの事案を受けまして、いわゆる博覧会の協会がメタンガス対策にかかる追加対策を講ずることを含めまして、会期中の安全対策に万全を期すと伺っているところでございます。そうした中で、文部科学省としては、引き続き、安全確保の徹底について関係省庁を通じて要請をしていきながら、それとともに関係省庁と連携をしながら、都道府県教育委員会等を通じまして情報の提供等、対応にしっかり努めてまいりたいというふうに思っています。
(注)「次世代」は、正しくは「次代」です
記者)
米国のトランプ政権が進める政府機関人員の予算削減によって、科学研究にも影響が出ておりまして、科学誌「ネイチャー」が米国在住の研究者1,600人に調査した結果、そのうち1,200人が研究拠点を米国外に移すことを検討している旨の結果が発表されています。このような動きから、フランスなど諸外国では人材獲得に乗り出すべく措置を講じる、既に募集等をしているところもあります。文部科学省としても具体的に獲得方策を講じていく考えがありますでしょうか。教えていただければと思います。
大臣)
我が国の研究力の強化に向けまして、アメリカからの研究者の受け入れに限らず、優れた人材の育成と獲得がまさに不可欠でございます。そうした中、文部科学省といたしましては現在、先端分野での欧米等の先進国との国際共同研究を通じまして、海外の研究者との交流・関係構築の強化をしているという中と、また海外の優秀な研究者を惹きつけるための世界トップレベルの研究拠点の整備などの取組を今進めているまさに最中でございまして、こうした取組を引き続きしっかり進めていくことが重要と考えておりまして、諸外国の状況も勘案した上で第7期科学技術・イノベーション基本計画の策定に向けた議論と合わせながら、我が国の研究力強化に向けた検討をしっかり行ってまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
今の質問に関連して、アメリカの研究者が研究拠点を移すときに欧州とかカナダが移す場所になっている、有力候補になっているのですけれども、日本が移転先の有力候補にならない理由の一つに給与水準がシンガポールより低いという現実があると思います。大臣としては、日本の研究者の処遇についてはどのようにお考えでしょうか。
大臣)
おっしゃるように、文部科学省においては国内外問わずに優秀な研究者が、我が国で研究したいと思えるような、そういう研究環境が重要だというふうに考えておりまして、為替の関係もありかなりいろいろな形で日本が選択肢に入りにくいというお話は様々なところで聞かれるところでございますが、大学等における基盤的経費、また充実・確保によって研究者の安定ポスト、その安定ポストを確保し、また研究活動を支援するための多様な競争的研究費の充実と強化に取り組んでおりまして、今まさに4月7日に始めました地方創生のための人材育成のところでもクロスアポイントメントをもっと増やしていきながら、一つはポジションの問題とまた給与の問題、様々なところがやはり日本がまだまだ体制整備が重要だというふうに私どもも認識しているところでございまして、今後とも審議会の検討も踏まえていきながら科学技術・イノベーションの担う優秀な研究者の確保、また同時に活躍促進に向けた取組を強化していかなければいけないというふうに考えておりますので、しっかり努力してまいります。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室