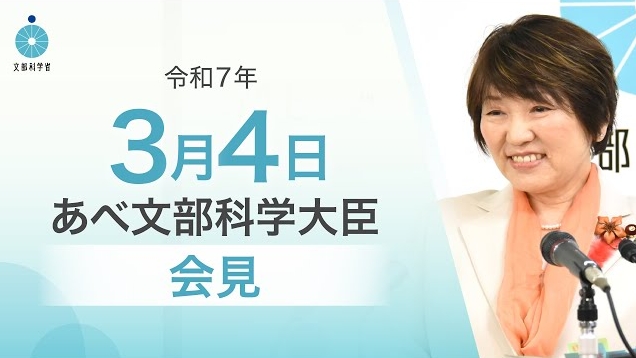- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年3月4日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年3月4日)
令和7年3月4日(火曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)の共用利用開始、月や火星探査をめぐる今後の宇宙政策、高等教育機関の修学支援制度の要件見直し、小中学校の指導体制に見合った授業時数の計画へ見直す通知
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年3月4日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年3月4日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございます。官民地域パートナーシップによる役割分担に基づきまして、宮城県仙台市で運用しておりますNanoTerasuにつきまして、令和7年3月3日より「特定の先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」(注1)に基づく共同利用(注2)を開始いたしました。共同利用(注2)が開始されるのは、世界最高性能を達成したビームラインをはじめとする国が整備いたしました世界最先端の性能を持つ3本のビームラインでございます。今回の利用に際しまして、38件が採択されました。文部科学省といたしましては、地域パートナーとも連携しつつ、NanoTerasuが持つ世界最高峰のビームラインを活用・高度化することで質の高い研究成果が創出されることを期待しているところでございます。以上でございます。
(注1)「特定の先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」は、正しくは「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」です
(注2)「共同利用」は、正しくは「共用利用」です
記者)
宇宙関連でぜひお話を伺いたいのですが、今、米国のイーロン・マスク氏が人類を月に送るアルテミス計画を批判していて、月ではなく火星探査に展望すべきと言及していますが、アルテミス計画にも参加する日本における今後の宇宙政策の影響についてまず教えていただきたいのと、日本も同様に火星を目指していくことに支援を向けていくのかどうかということについて、合わせてお伺いできればと思います。
大臣)
「アルテミス計画」、米国主導の有人宇宙探査プログラムでございます。日米の宇宙協力の重要な柱でもございまして、先月の初めの日米首脳共同声明におきましても、アルテミス計画での月面有人探査を始めとする日米宇宙協力を継続する方針が確認されたところでございます。文科省といたしましては、これまでと同様、アルテミス計画を含む日米宇宙協力の着実な推進に取り組んでまいります。また、我が国におきましては、現在、火星への有人探査を行う計画を有しておりませんが、惑星探査の分野の取組といたしまして、世界初の火星の衛星からサンプルリターンを目指す火星衛星探査計画(MMX)を進めているところではございます。以上です。
記者)
大学などへの修学支援制度の件についてお伺いします。修学支援制度については、2024年度から基準以上に定員割れが続いた大学などに対して支援制度の対象外とする制度の要件として厳格化してきたと思います。ただ、厳格化したことによって対象校が非常に多くなったということもあり、緩和する方針を示されたと思います。改めて、まず24年度に要件を厳格化したことについての目的を教えてください。また、これがわずか1年で実質的に緩和する方向になったことへの大臣の受け止め、そして最後に今後どういった基準にしていくかという緩和の要件について具体化していくと思いますけれども、この間ありました高等教育の答申を踏まえまして大臣としてはどのような基準にしていくことが望ましいとお考えなのか教えてください。
大臣)
お尋ねのございました高等教育の修学支援新制度、大学等の経営が継続、いわゆる継続的かつ安定的に行われることを確認するために一定の教育や経営に関する要件、機関要件でございますが、を満たす大学等を対象機関としているところでございます。機関要件におきましては、大学等の経営困難から学生等を保護する観点から、令和6年4月より収容定員の充足率の要件を満たさない学校については、これはあくまで先ほど申し上げたように学生の、いわゆる学生を保護するという観点でございましたが、制度の対象外とする見直しを行ったところでございます。一方、この枠組みは維持をさせていただきながら、中教審における高等教育のアクセス確保という観点の議論も踏まえさせていただき、地域の経済社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学等への配慮する観点から、いわゆる機関要件の見直しを行うこととしておりまして、現在、この省令の改正の準備を進めさせていただいております。改正内容におきましては、現在、意見公募に付しているところでおります省令案についてもお示しをしているところでございまして、そこでいただいた御意見を踏まえ、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。
記者)
標準授業時間数の関係でお尋ねします。文科省は先日、2024年度に公立の各小中学校が立てた年間授業計画で授業時間数が標準を大幅に超えていた学校について、都道府県と政令指定都市別の割合を公表されていました。これを見直すようにという通知を出されたかと思いますが、この割合には地域でかなり差が見られることが調査結果から読み取れることになっていたと思いますが、結果についての大臣の受け止めや文科省として今後現場に求めたいことなどがありましたらお願いします。
大臣)
この度公表させていただきましたデータによりますと、令和6年度計画におきましては、1,086単位時間以上の教育課程を編成している学校は大きく減少はしたものの、実は多い県では5割以上である一方、既に0となっている県もあるなど、都道府県間で大変大きな差があるところであります。また、こうした学校のうち標準授業時数を上回る部分の具体的な使い道を想定していない学校も4分の1程度ございます。これを踏まえまして、文部科学省といたしましては、今般、改めて指導通知を発出いたしまして、標準を上回った時数が真に必要な時間かどうかの精査、指導体制に見合った改善を図るように求めてきたところでございまして、引き続き、あらゆる機会を捉えまして、指導助言を行うとともに、適切なタイミングで改善状況をしっかりとフォローアップもしてまいります。以上です。
記者)
先ほど衆議院予算委員会のほうで新年度予算案と自公維の教育無償化などに関する合意を踏まえた修正案が可決されました。この後、本会議でも可決される見通しですが、このことに関する大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
まだ本会議を待っている段階でございますが、教育の無償化に関しましては自民党、公明党、日本維新の会の3党での合意文書が取り交わされたところでございまして、自民、公明の両党からこれを踏まえた修正案が提案されまして、先ほどおっしゃってくださったように衆議院の予算委員会においても可決をされたばかりでございます。文科省といたしましては、引き続き国会における予算案の審議に真摯に対応をしていきます。国会における審議結果に基づき迅速に対応できるよう、合意内容を踏まえた令和7年度における具体的な制度設計について速やかに検討をしてまいりたいというふうに思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室