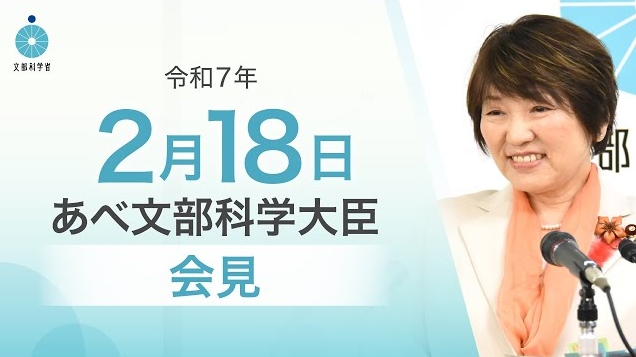- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年2月18日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年2月18日)
令和7年2月18日(火曜日)
教育、科学技術・学術、文化
キーワード
大阪関西万博プレイベント「わたしとみらい、つながるサイエンス展」の視察,日本遺産10周年記念式典の出席・日本遺産マルシェと京都国際マンガミュージアムの視察,デジタル教科書に関する懸念への対応と子供の意見を聞くことについて,エジプトなどの学校で日本の「特別活動」の広がりについて,教育無償化による地方専門高校等への進学者減少の懸念について
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年2月18日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年2月18日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私から2件ございます。2月14日金曜日、東京・有楽町で開催されました、文部科学省主催の大阪・関西万博のプレイベント「わたしとみらい、つながるサイエンス展」を視察をさせていただきました。プレイベントにおきましては、15大学等による体験型コンテンツを始めといたしました展示、その他に学生団体、高校生によるステージイベント等が開催されておりまして、4日間で1,000人を超える方々がご来場いただきました。私も8つの展示を中心に視察させていただきました。創意工夫を凝らした展示物の体験、また研究者や高校生の方々とのコミュニケーションを通じまして、様々な分野の研究の持つ素晴らしい可能性に触れることができました。文部科学省といたしましては、万博本番に向けまして、研究成果がより明確でわかりやすく伝わるよう、更なる磨き上げを進めるとともに、引き続き関係省庁とも協力をしながら、万博本番に向けた準備や機運の醸成を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
2点目でございます。先週15日の土曜日でございますが、赤松大臣政務官とともに京都市の二条城で行われました日本遺産10周年記念式典に出席をさせていただきまして、主催者として御挨拶を申し上げるとともに、新たに日本遺産に認定されました北海道・小樽市長に認定証を授与させていただきました。式典におきましては、日本遺産認定地域としてこれまで御尽力いただいてまいりました各市長・町長の皆様にお目にかかることができまして、その熱意を改めて肌で感じたところでございます。また、これに伴って日本遺産の各地域が出展する「日本遺産マルシェ」に伺わせていただきまして、地域の特色あるブースを拝見させていただいたほか、またわが国が誇る漫画資料の保存・活用を行う京都国際マンガミュージアムを視察をさせていただきまして、原画の保存、またコンテンツ人材育成について意見を交わさせていただきました。今回の式典や視察を通じまして得た知見を踏まえまして、引き続き魅力のある文化資源を生かした地域の活性化、コンテンツ分野の文化の振興など、重要な文化政策の推進にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
デジタル教科書の取り扱いについてお尋ねいたします。先週の中教審のワークキンググループでデジタル教科書に関する中間案が取りまとめられ、導入時期であったり各教育委員会による選択制などの方向性が示されました。仮に正式な教科書となった場合には、指導する教員側の能力などの課題や教育の格差の拡大なども懸念されますが、正式な教科書とすることについての現時点での大臣のお考えをお聞かせください。また、「ランドセルが重い」といった子どもたちの率直の意見も聞かれますが、学習指導要領の改訂のように子供たちの声に耳を傾けることなどは検討されますでしょうか。
大臣)
先般14日でございますが、中教審のワーキンググループの中間まとめ案におきまして、教科書の形態として、紙だけではなくデジタルによるものも認め、採択を通じて選択できるなどの方向性が示されたということは承知をしているところでございます。今般示された方向性につきましては、学力など教育格差が出ないようにするためにも、全国一律対応ではなく、現場の関係者が自分事として納得感のある形での主体的取組を促し、また現場の実態を踏まえた様々な対応を可能とするための選択肢を設けようとする方向であるというふうに理解をしております。その際、教員の指導力の向上は極めて重要でございまして、ワーキンググループとしても、今後更に検討を進めるものと聞いているところでございます。御指摘の点も踏まえまして、デジタル教科書の在り方をめぐっては、様々な御意見があるものと承知をしているところでございますが、文部科学省といたしましては、今後、パブリックコメントなどを通じ、子供たちを含めて様々な声にしっかりと耳を傾けつつ、ワーキンググループにおいて引き続き活発な議論が行われることを期待しているところでございます。以上です。
記者)
昨日、大臣を表敬訪問されたエジプトの教育大臣がエジプトにおける日本の「特別活動」、「特活」を取り入れたいわゆる日本学校の取組について話しておられたと承知しています。日本の学校独自のものである「特活」をよその国の学校が取り入れていることへの受け止めをお聞かせください。また、翻って日本の学校での今後の「特活」のあり方についてお考えがあれば伺いたいと思います。
大臣)
昨日、エジプトの教育大臣と会談をさせていただきまして、御質問の特活、特別活動についても意見交換をさせていただいたところでございます。エジプトにおきましては、JICAの支援によりまして、特別活動などを行うエジプト日本学校(EJS)が55校今設置をされておりまして、成果を大変あげております。将来的には100校・200校と開校したいというふうに昨日もお話がございまして、大変嬉しく思いましたところでございます。文部科学省といたしましても、アフリカ開発会議のTICAD9、横浜で開催されるところでございますが、この夏の機会を活用いたしまして日本型教育の代表例として特別活動をさらに発信していきたいというふうに思っているところでございます。特に、この特別活動の意義につきましては学校や学級、自分の自己の生活上の課題を、他者と協働していきながら、児童生徒自らが自主的、実践的に解決することを目指す取組でございまして、我が国の教育課程の大きな特徴の一つでございます。ご存じかと思いますが、映画で「The Making of a Japanese」といういわゆるドキュメンタリーが2年前の多分東京国際映画祭で取り上げられまして、その後、世界中が大変日本の教育というのに焦点を当てているところでございます。私の知識では、多分今は有楽町でもやっているのではないかと思いますが、非常に日本の教育がなぜこのように日本人がこんなに真面目で素晴らしいのかということは世界中が見ているところでございまして、この特別活動に関しましては、例えば、生徒会を中心として校則の見直しについて議論する等きまりをつくって守る活動等も行われているところでございまして、社会参画意識の醸成、また人間関係の形成と自己実現等の観点から大変大きな意義があるものだというふうに考えております。以上でございます。
記者)
私立高校を含む高校の就学支援金制度の拡充が進んだ際に、農業や水産など公立の専門高校の人気が低迷するのではないかという懸念があると思います。この懸念についての大臣の受け止めと、専門高校の魅力向上について考えている政策などがありましたら教えてください。
大臣)
私立高校の授業料支援の拡充につきましては、これに伴って私立高校の進学を希望する生徒が増加する、また公立高校の進学者数が減少する可能性があるなど、その多くが公立として設置されているいわゆる専門高校、おっしゃっていただいたように一定の影響があるものと考えられるところでございます。私立高校におきましては、その建学の精神に基づき、特色のある豊かな教育を提供する役割を担っている一方で、いわゆる専門高校は地域産業の発展を支える大変重要な役割を担っているものというふうに認識をしているところでございまして、このため文部科学省といたしましてはデジタルを活用した高度な専門教科の指導等を支援する「DXハイスクール事業」において、専門高校が産業界と連携する取組を重点的に支援する「プロフェッショナル型」の創設、また先週の会見で御紹介させていただきました「専門高校生による魅力発信動画」などの展開の取組を進めるほか、また「地方創生2.0」に向けまして、産業界の伴走支援を受けさせていただきながら、農業高校をはじめとする「専門高校を拠点とした地方創生支援・地域人材の育成」に取り組むなど、専門高校への支援と魅力発信を強力に進めてまいりたいというふうに思っているところでございまして、しっかりと私ども情報発信をさせていただきながら、地域の産業と伴走する専門高校の重要性をしっかりと皆様にお伝えしていきながら、どのように支援体制をしていくかも含めて今検討させていただいているところでございます。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室