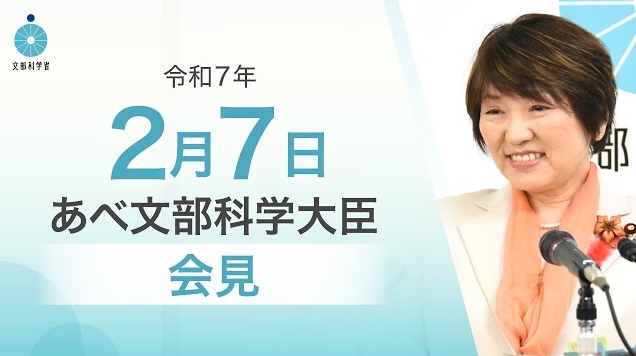- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年2月7日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年2月7日)
令和7年2月7日(金曜日)
教育、科学技術・学術、文化、その他
キーワード
文部科学省から提出する通常国会提出法案の閣議決定、大洗原子力工学研究所の視察、政党間による高校無償化に関する議論、書店振興と活字文化の振興について、私立大学の安易な公立化について、法案の成立に向けた意気込み
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年2月7日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年2月7日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは2件ございます。先ほどの閣議におきまして、文部科学省から今国会に提出する2本の法律案が閣議決定をされました。1本目は、「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案」でございます。本法律案は、「こども未来戦略」に基づきまして、令和7年度から、多子世帯の学生等につきまして、所得制限なく、一定の額まで、大学等の授業料・入学金を無償とするものでございます。2本目でございますが、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与(注)に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」でございます。この法律案に関しましては、学校教育の質の向上に向けまして、教師の優れた人材を確保するため、教職調整額の引き上げ、また学校における働き方改革の推進など、教師を取り巻く環境整備を行うものでございます。国会の審議を通じまして、この法律案の内容、必要性を丁寧に説明をさせていただきながら、速やかな成立を目指してまいりたいというふうに思っているところでございます。
2件目でございます。今週5日水曜日でございますが、茨城県の大洗町にあります日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」、高温ガス炉HTTRなどを訪問いたしましたのでご報告をさせてください。視察におきましては、令和8年度半ばの運転再開を目指す「常陽」、また900℃を超える熱供給による水素製造、期待される高温ガス炉の開発状況など、また福島第一原子力発電所から取り出されました燃料のデブリの分析の状況などを拝見いたしまして、この原子力機構の高い技術力を改めて認識をさせていただくとともに、これを支える人材育成の重要性についても実感をいたしました。今回の視察を通じまして得られたことを踏まえまして、引き続き関連施策の充実にしっかりと取り組んでまいります。以上です。
(注)「給与」は、正しくは「給与等」です
記者)
高校無償化の件をお尋ねします。昨日、日本維新の会の前原共同代表は、公立は今年4月から、私立は来年4月から所得制限を撤廃する案を自民党から示されたと記者会見で話しました。私立だとなぜ来年度からの開始が難しいのか、文科省の見解をお尋ねします。また、教育無償化について国会での議論が活発化していることへの大臣の受け止めをお願いします。
大臣)
御指摘の報道の件に関しましては、自民党、公明党、日本維新の会の協議の内容にかかるものでございますため、この場での言及は控えさせていただきます。いずれにしても、政府の立場といたしましては、まずは自民党、公明党、さらには日本維新の会の三党による協議の状況をしっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。
記者)
書店活性化や活字文化の推進について伺います。近年、全国での書店減少や「読書離れ」が進む中、読売新聞社と講談社は「書店活性化に向けた共同提言」を発表し、書店と図書館の連携や読書教育の充実などが盛り込まれました。書店の活性化や活字文化の振興にも貢献するものと思われますが、大臣の受け止めと書店活性化を今後どのように進めていくことをお考えかを教えてください。また、合わせてこれから政府が作成予定の書店活性化プランに文部科学省としてどのように対応するかをお聞かせください。
大臣)
出版文化産業振興財団の調べによりますと、全市町村のうち書店が存在しない市町村の割合、令和7年11月現在で約28%であるということは承知をしているところでございまして、書店、地域における文字と活字の文化の発信の拠点でありまして、人々が本に親しみながら、触れる身近な場となっているため、書店数の減少は文字・活字文化の振興を図る上でも少なからず影響があるものというふうに認識をしております。このため、来年度予算案につきまして、書店等が地域にゆかりのある例えば文芸作品等を題材にいたしました読書会などを行うことによって、地域における文字・活字文化の振興モデルの構築に向けた取組を新たに行うこととしております。今後とも、経済産業省など関連省庁とも連携させていただきながら、書店の活性化を含む文字・活字文化の進行に努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。また、書店活性化プランということでございますが、経済産業省におきましては、今年の1月に、書店活性化に向けました「関係者から指摘された書店活性化のための課題」を整理しているところでございまして、この書店の収益構造の改善、ここに資するデジタル技術を活用いたしました対応方策等を検討中であるというふうに承知をしているところでございます。文部科学省といたしましても、経済産業省とも連携をさせていただきながら、読書活動の推進、また文字・活字文化の振興の観点から書店の活性化プランの策定にしっかりと協力をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。ごめんなさい。先ほど申し上げた市町村の割合が28%は令和7年ではなくて令和6年ということで訂正をお願いいたします。
記者)
高等教育についてお伺いします。中教審の大学分科会が先日数字で公表した高度教育に関する答申案の件なのですけれども、私立大学の公立化について安易な設置は避ける必要があるとして、具体的方策で留意すべき事項の明確化を行うとの記載があるのですけれども、大臣が私立大の公立化について感じていることですとか、文科省としてどのようなことに留意すべきと現時点で考えているか教えていただけますでしょうか。
大臣)
大学進学者数が今後大幅に減少することを踏まえますと、私どものいわゆる推計でございますが、2040年には46万人となって今よりも27%減っていくということを考えたときに、高等教育機関の再編・統合、縮小、撤退などを進めていくことも求められているところでございます。このような状況の中にあって、私立大学の公立大学化については地方公共団体の御判断ではございますが、安易な設置は避ける必要があるというふうに思っております。したがって、真に地域に貢献するようなものとなりますように、特に地域の人材の需要の課題、また定員充足の見込み、さらにはそれに見合った学部・学科の編成、財政負担と将来の運営の見通し等も十分に吟味するなど、慎重に検討した上で、地方公共団体におきましては、公立大学としての設置、この是非を判断していく必要があるというふうに考えています。以上です。
記者)
冒頭発言にあった二つの法案の閣議決定に関連しまして、今回は少数与党の中で審議に臨むことになります。昨日の省庁別審査でも相当、野党から様々な要求が出されていましたが、改めて法案にかかる野党との質疑及び法案成立に向けた大臣の意気込みを聞かせていただけますか。
大臣)
今回、文部科学省から提出する2本の法律案に関する野党の賛否は現時点で不明でございますが、高等教育費の負担軽減、またこれを推進するという方向性、また学校における働き方改革、教師の処遇改善を行う必要性については、各党とも御賛同いただいているものと考えておりますので、私どもしっかり丁寧に御説明をさせていただいて、法律案の成立に向け御理解をいただけるよう、全力を尽くしてまいります。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室