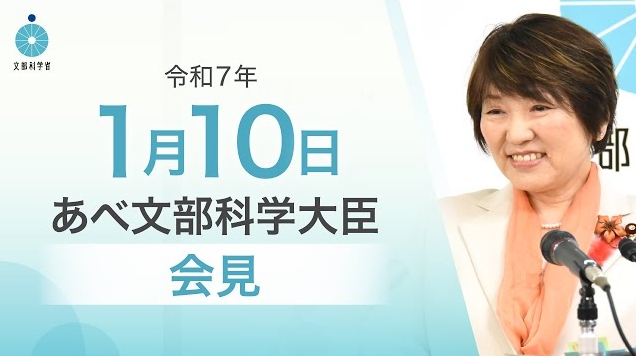- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年1月10日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年1月10日)
令和7年1月10日(金曜日)
教育、科学技術・学術、文化、その他
キーワード
年末年始の海外出張(中国・米国)、大田区立糀谷中学校夜間学級の視察、新しい時代における文化庁の役割等について、夫婦別姓に関する小中学生へのアンケート結果や教育現場への影響、新年の抱負、国際卓越研究大学制度の支援開始と東北大学への期待、東北大学の医学イノベーション研究所(SiRIUS)への期待
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年1月10日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年1月10日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは2件ございます。昨年末、12月25日水曜日から26日木曜まで、日中のハイレベル人的・文化交流対話等に出席するために、中華人民共和国を訪問いたしました。日中ハイレベルの人的・文化交流対話におきましては、岩屋外務大臣、王毅外交部長、また孫業礼文化旅遊部長等と両国間における青少年交流などについて議論をさせていただきました。また、懐進鵬教育部長との会談におきましては、日中教育交流5か年計画を着実に実施すべく、大学間の交流、教職員交流などの日中間のこの交流事業について意見交換を行いました。
次に、1月2日木曜日から8日にかけまして、アメリカ合衆国を訪問いたしました。まず、サンフランシスコ・シリコンバレーを訪問させていただきまして、iPS細胞技術の実用化を目指したスタートアップの現状の視察、また現地日本人研究者コミュニティのネットワーク化の取組、また研究環境整備等に関する意見交換、更には現地美術館を訪問いたしまして、館長より、寄付税制の在り方、また美術品の保存修復に関する取組について伺いました。
次に、ワシントンD.C.におきましては、NSFの長官やNASAの長官との意見交換のほか、本年8月に横浜で行われますTICADアフリカ開発会議も見据えた上で、国際機関と民間財団などと連携いたしましたアフリカ支援の方向性に関して、関係者との意見交換を行いました。これらの会談を通じまして、今後とも科学技術や学術・文化交流の分野での日米協力を維持・強化していくことの重要性を関係者と共有いたしました。文部科学省といたしましては、今回の中国・米国の訪問で得た知見を活用いたしまして、引き続き、関連施策の充実に積極的に取り組んでまいります。以上でございます。
2件目でございます。昨日1月9日に、昨日でございますが、大田区の糀谷中学校夜間学級を視察をいたしました。糀谷中学校では、かつて不登校だった生徒が夜間中学でもう1度学び直したいと頑張る姿や、家庭科の授業で、慣れないながらも懸命にエプロンに針で刺繍を刺し作品を完成させる場面、すごろくを活用して楽しみながら日本語の学びを深める場面などを拝見いたしました。夜間中学は、誰一人取り残さず、社会で生きていくために必要なことを身につける場となっている、学ぶことは生きることだということは改めて実感をさせていただきました。そして、先生方が本当に一生懸命工夫を凝らして指導されている姿、また本当に素晴らしいと感銘を受けました。文部科学省としては、引き続き、夜間中学の設置促進・充実に向けまして、各地域の取組を支援してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
記者)
文化庁に関係する省庁、もしくは組織の再編について伺いたいと思います。昨今、文化庁の役割は幅広くなっておりまして、例えば新たなクールジャパン戦略では、基幹産業としてコンテンツ産業が位置付けられています。そのコンテンツ産業の中ではアニメ、漫画、映画という文化庁の知見というのが多いに活用されることが期待されております。また、インバウンド観光につなげるというところでは、文化庁の持っている資産、これをいかに使っていくかというところも期待されております。その中で昨年、経団連さんはコンテンツ省の設置の提言、これはずっとしていますし、あとは文化省、もしくは文化芸術省、こういったものの設置を求める声というのも未だに根強いかなと思っております。文化庁の役割というのは、かつては文化財の保護というのがまず大きな役割だったとは思うのですけれども、今の新しい時代において文化庁の役割はどういったものを考えるか、また役割に合わせて省庁や組織というのを柔軟に変えていく可能性というのが今後あるのかどうか、その可能性についてもしあればお考えを伺わせてください。
大臣)
文化芸術、まさに人類に必要不可欠でございまして、コンテンツを含む文化芸術の振興、我が国の社会の持続的な発展に欠かせないものだと思っておりまして、実は先日、アメリカ出張で訪問した美術館では、10月に日本の漫画展を開催する予定というお話を伺いまして、私も日本文化の持つ力を改めて実感をしました。大英博物館でいわゆる同じことをやったキュレーターの方が企画をしておりまして、日本からも漫画家の方が数名行くということも聞いているところでございます。文化芸術施策の推進にあたりましては、文化庁の京都移転を契機といたしまして、文化芸術のグローバルな展開と、更には文化芸術のDX化、更には観光・地方創生に向けた文化財の保存・活用などをはじめとした新たな文化行政の展開を進めてまいりたいというふうに思っております。御指摘のコンテンツ省また文化省・文化芸術省の設置につきましては、国の行政組織の在り方全体を議論の中で検討する必要があるものと考えているところでございます。いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、引き続き、文化芸術立国の実現に向けまして、文化芸術の振興に全力を尽くしてまいります。
記者)
選択的夫婦別姓について、弊社のほうで昨年の11月から12月にかけて小中学生約2,000人にアンケートを取りまして、その結果、親子別姓だとか兄弟別姓といった家族内での名字が違うことに反対という声が約半数に上りました。こうした小中学生の意見について大臣としてどのように受け止めますでしょうか。そして、夫婦別姓が導入されることになれば兄弟間で姓が異なったり、また選択する家庭とそうでない家庭の子供の間で意見が食い違うこともあると考えられます。学校現場でこうしたことに対する対応はどのようなことが必要だと考えられますでしょうか。
大臣)
夫婦別姓に関しましては、文部科学省の所掌を超えるものでございまして、御指摘のアンケート結果に対する見解も含め、ここでは述べることを差し控えさせていただきます。また、仮に夫婦別姓が導入された場合の教育現場における対応につきましては、具体的にどのような制度が導入されるかという議論が深まる中において私ども検討していくべきだというふうに考えております。以上でございます。
記者)
2025年初めての記者会見が、今年初めての記者会見ということですね、新年の抱負などをお聞かせください。
大臣)
新年の抱負ということでございまして、まずは「人づくりこそ国づくり」ということでございまして、文部科学行政、国民が、「今日より明日は良くなる」、このように実感をし、自分の夢に挑戦しながら、自己実現を図っていくためにまさに重要だというふうに考えています。今年も、繰り返しになりますが、教師を取り巻く環境の整備、また教育費の負担の軽減の推進、また研究力の向上に向けた取組、地方創生にも資するスポーツや文化の振興をはじめ、文部科学行政を一つ一つ着実に前に進めてまいりたいというふうに思っております。また、通常国会におきましては、令和7年度予算案の成立にまずは全力を挙げてまいりたいというふうに思います。以上です。
記者)
今年はいよいよ国際研究卓越大学制度において東北大への支援が始まります。昨年末の会見でも御回答がありましたけれども、改めてという形なのですが、卓越大の制度による支援開始や、東北大にはどのような大学になってほしいですとか、2回目の公募ではどんな計画を期待しているのか、そういった点について教えてください。
大臣)
国際卓越研究大学、世界トップクラスの研究者が集まり相互に触発し活躍すること、また、特に次世代の一流の研究者集団、この育成と若手研究者に独立して存分に研究できる環境を提供すること、などを通じまして世界最高水準の研究大学を目指すこととされております。また、次の国際卓越研究大学(注)に認定された東北大学につきましては、昨年12月に体制強化計画を認可させていただいたところでございまして、今年度中に速やかに大学ファンドからの支援開始を予定しているところでございます。今後、東北大学におかれましては、若手研究者が、何度も言いますが、独立した環境で自由な発想による多様な研究活動を行うための研究体制の確立など、体制の強化計画に盛り込まれた内容の着実な実行を通じまして、我が国全体の研究力をけん引していただきたいことを期待しているところでございます。また、次の応募に関しても同じようなことでございまして、しっかり私ども応援していく体制を強化してまいりたいというふうに思っております。
(注)「次の国際卓越研究大学」は、正しくは「初の国際卓越研究大学」です。
記者)
今のに関連してなのですけれども、東北大では医学研究者も研究時間が非常に少ない中で、新しい医学研究所「SiRIUS」を開設します。これについての大臣の期待などがありましたら教えてください。
大臣)
東北大学において、今年の4月に「SiRIUS」を開設しまして、若手の臨床医である研究者が独立して研究に専念できる環境に取り組む予定と承知をしているところでございます。医学系研究、国民の健康また医療に直接的に貢献するとともに、いわゆる創薬力の向上を通じまして我が国の産業競争力にも直結する重要な研究領域です。本研究の活動を通じまして、医学研究をけん引するトップレベルの人材の育成、また医療のイノベーションが創出されることを心から期待しているところであります。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室