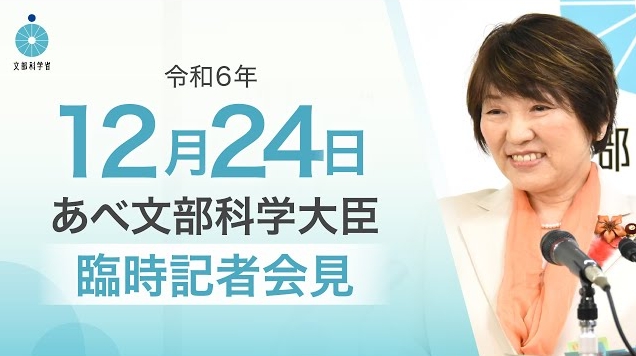- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録-予算-(令和6年12月24日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録-予算-(令和6年12月24日)
令和6年12月24日(火曜日)
教育
キーワード
教師を取り巻く環境整備の充実
あべ俊子文部科学大臣臨時記者会見映像版
令和6年12月24日(火曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和6年12月24日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
令和7年度予算をはじめといたしました、教師を取り巻く環境整備につきまして、本日、財務大臣と折衝を行いまして、以下の内容について御了承いただきました。教師の処遇改善について、給特法を改正し、教職調整額を令和12年度までに確実に10%へ引き上げるとともに、学級担任への手当の加算など、職責と業務負担に応じた給与とすること、なお、来年度の制度改正後の初任者の給与は、人事院勧告の影響も合わせると年収ベースで15%の増となります。教職員定数について、今後4年間で計画的に改善することとし、令和7年度予算においては、小学校教科担任制や中学校生徒指導担任教師の拡充等のための2,190人の改善を行うこと、なお小学校35人学級の推進に伴う定数改善等々合わせると5,827人の改善となり、これは直近20年間で最大の改善数となります。さらに、令和8年度から中学校35人学級への定数改善を行うこと、また働き方改革について教師の平均の時間外在校等時間を月20時間程度とすることを目指して、まずは今後5年間で約3割縮減し、月30時間程度とすることを目標として取組を加速化していきます。詳細は配布資料を御覧ください。今回の両大臣合意は、我が国の未来を担う子供たちのために教師への優れた人材の確保に向けた大変意義深いものになりました。これにより、公教育の再生に向けて教師を取り巻く環境が抜本的に変わってまいります。教職調整額の引上げは約50年ぶり、中学校の35人学級は約40年ぶりの改革になります。教育関係者の皆様とともに、子供たちのために一生懸命取り組んでまいりたいと思います。改めて、合意いただいた加藤財務大臣に感謝申し上げます。以上です。
記者)
教職調整額の率のほうなのですけれども、13%ということで文科省としては要求していたと思いますが、10%ということの数字になった、このことについての理由と大臣の受け止めをまず伺いたいと思います。
大臣)
教師の処遇につきましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないとされ、人材確保法に伴う改善が完結した昭和55年にはその優遇分は約7%、これは月収ベースでございますが、が確保されていました。中教審の答申におきましては、この昭和55年当時の優遇分の水準以上を確保するため、教職調整額を少なくとも10%以上とすることが必要とされました。予算編成過程では、教師の職務・勤務状況に応じた処遇となるよう、教職調整額を含む処遇全体について議論を重ね、結果として教職調整額は10%に引き上げることとなりました。今般の教職調整額の10%への引上げやその他手当の改善等が完成する際、教師の優遇分は昭和55年当時と同水準、約7%でございますが、が確保できることとなります。このような教員給与の大幅な引上げについては約45年ぶりとなります。
記者)
今回の大臣折衝の合意について、文科省として当初、概算要求で示していて実現に至ったものと至らなかったものがあると思います。例えば、一気に13%まで教職調整額を引き上げるといったことであったり、教科担任制の導入が小学校4年生にとどまってしまったりというところが実現に至らなかったこととして挙げられるかなと思いますけれども、このことについて大臣の評価をお願いします。
大臣)
教師を取り巻く環境を整備するために、学校における働き方改革のさらなる加速化と、また学校の指導・運営体制の充実、さらには教師の処遇改善、一体的・総合的に推進することが必要でございます。このため、処遇改善の他、中学校の35人学級の実現など教職員定数の改善、支援スタッフの充実、また働き方改革の取組への支援など、様々な施策を総動員させていただきまして、今後、取組を進めることというふうにさせていただいておりまして、こうした取組をバランスよく一体的かつ着実に進めていくため、段階的に推進していくこととさせていただいています。また、小学校は第四学年の拡大に、担任制をしたということに関してでございますが、低学年には設けられていない理科、また外国語活動等が始まるなど、実は各教科等の特質に応じた学びにつなげていく時期であることに加えて、特に4年生につきましては、年間の標準授業時数が高学年や中学校と同じ1,015単位時間となっているところであります。これを踏まえまして、子供たちへの学びの質の向上、さらには教師の持ち授業の時間の軽減の観点から、まずは小学校4年生に教科担任制を拡充するための定数改善、令和7年度予算案に計上することといたしました。なお、各地域、学校の実情に応じた取組が見通しを持って可能となるように、令和7年度から4年間で計画的に推進することとしています。
記者)
評価の部分で、全体としては大臣としては一定の満足できるものになったというような受け止めでしょうか。
大臣)
冒頭に申し上げましたように、今回の両大臣合意は我が国の未来を担う子供たちのために教師への優れた人材確保に向けた大変意義深いものになったというふうに感じておりまして、これにより公教育の再生に向けて教師を取り巻く環境が抜本的に変わっていく、先ほども申し上げましたが、教職調整額の引き上げは50年ぶり、また中学校の35人学級は約40年ぶりの改革となります。教育関係者の皆様とともに、子供たちのために一緒に取り組んでまいりたいというふうに思っています。
記者)
中学校の35人学級についてお伺いします。このスケジュール感というか、いつまでに中学1年から中3までが35人学級が完成するのかというようなことと、それにあたってどのくらい定数が改善されるのかということを教えてください。
事務方)
中学校の35人学級でございますけれども、今後、中学校の35人学級を導入することによって必要な教職員定数の改善数ですが、約1.7万人というところでございます。令和8年度からこういった中学校の学級編成の引下げについて着手するということで今回、合意されたものでございまして、令和8年度から着実に学年進行で進めていきたいというふうに考えているところでございます。
記者)
令和10年度に中3まで終わるということでよろしいですか。
事務方)
はい。
記者)
合意書にある1番と2番の文言に関連してお尋ねしたいのですが、先ほど冒頭にも令和12年度までに教職調整額の率を確実に10%への引き上げを行うとしている一方で、2番目の中間段階で状況を確認しながらその後の教職調整額引き上げ方やメリハリ付けなども検討するとあるのですが、これは令和12年度までの10%への引き上げ、13年度以降のやり方などについて検討していくという意味なのでしょうか。
大臣)
合意事項でございます令和9年度以降の確認・検証につきましては、両省におきまして学校における働き方改革と財源確保の状況を確保することとしておりまして、詳細は今後、両省で相談してまいりますが、具体的には、例えば教職調整額の引上げをいわゆる前倒すこと、さらには時間外在校時間等の縮減をさらに進めるために必要な施策を講じることが考えられるところでございまして、教職調整額の引上げにつきましては、令和12年度までに10%への引上げを行い、時間外在校等時間の削減を条件付けすることなく確実に引上げを行うことで合意しているところでございまして、このため、給特法改正案を来年の通常国会に提出をさせていただきます。したがいまして、自主的な条件付けとの御指摘は当たらないというふうに思います。
記者)
2問になってしまうかもしれないのですけれども、今回、管理職手当についての改善はどうなっているのかというのと、あともう1問、今回の予算折衝を総合的に、合意内容を大臣としては何点をつけられますか。
大臣)
1点目のところでございますが、管理職手当の部分でございますが、今回の教師の処遇改善にあたりましては、教職調整額の引上げと合わせまして、教職調整額が支給されない管理職につきましても同水準の本給の改善を図ることとさせていただいています。なお、こうした改善も踏まえまして、管理職手当は見送ることになりました。
今回の合意内容の自己採点でございますが、50年ぶりとなる処遇改善、また直近20年間で最大となる定数改善を盛り込むことができたことを鑑みると、私としては文部科学省全体でみんなで頑張ってきて80点ぐらいかなとは思っています。一方、厳しい勤務実態を学校の先生方がしている学校現場の状況を見て考えてみれば、及第点ギリギリ61点ぐらいではないかと。本当に皆さんにしてみればまだまだ足りないという状況だというふうに思っておりまして、教師や児童生徒に学校の環境が変わっていくことをいわゆる実感してもらえるように、法案の提出に向けた準備を進め始め、また教師を取り巻く環境整備の充実に向けた取組をさらに加速させていきたいというふうに思っています。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室